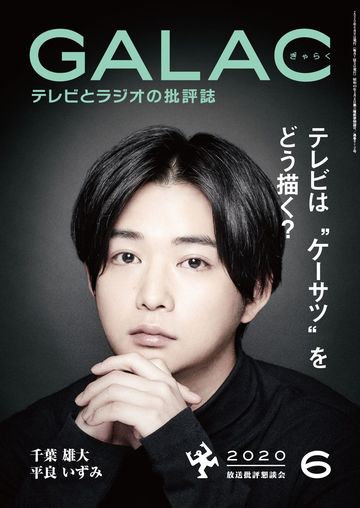「刑事ドラマ」歴代の名作が映し出す社会の変化
2020.05.08
東洋経済オンライン

「刑事ドラマ」は、時流に合わせて変化し続けています(写真:xiangtao / PIXTA)
黎明期から現在に至るまで、ドラマの主たるジャンルを形作ってきた「刑事」ドラマは、時代の潮流を敏感に捉えつつ、その表現領域を拡張してきた。近年のトレンドは定番の「刑事」から、警察組織のさまざまな構成員に至る登場人物の多様化だ。
今、刑事ドラマがテレビドラマ屈指の人気ジャンルであることは間違いない。いつもどこかのチャンネルで新作が放送されていると言ってもいいほどで、刑事ドラマがない状態を想像することなどもはや難しいくらいだ。その人気の理由として、まずは物語としてのわかりやすさがあるだろう。なんらかの事件が起こり、それを刑事が地道な捜査や華麗な推理の末に解決し、最後には犯人が逮捕される。そんな勧善懲悪を柱とする肩の凝らない娯楽作品として愛されてきた面は大きいはずだ。
だが刑事ドラマの歴史を紐解いてみると、実はそれほど話は単純ではない。勧善懲悪的な面はもちろんずっとあるにせよ、複雑な陰影を帯びた作品も少なくない。そして今やその複雑さの度合いはいっそう深まり、ひと括りにするのが難しく思えるほど刑事ドラマは多岐にわたるものになっている。ここではそうした変化の大筋を“「刑事」ドラマから「警察」ドラマへ”として捉えてみたい。以下、いくつかの作品をピックアップし、その時々のテレビや社会の状況にも目を配りながら、変遷をたどってみることにする。
1960年代という原点に登場したドラマ
1959年の皇太子ご成婚などを機に、テレビが普及・発展期に入ろうとしていた61年10月、二つの刑事ドラマがほぼ同時に始まった。ひとつは、TBS「七人の刑事」。警視庁捜査一課に所属する7人の個性豊かな刑事たちが殺人や強盗などの事件を解決する。部長刑事役の芦田伸介のトレードマークだったハンチングによれよれのコート姿、また警視庁の庁舎をとらえるところから始まるオープニングなどは、後の刑事ドラマの定番にもなった。
また〈このドラマに登場する人物、団体は実在のものではありません〉という断り書きを番組の最後に入れたのもこのドラマが最初だったとされる(読売新聞芸能部編『テレビ番組の40年』NHK出版、208頁)。それは、この作品の社会派的作風と無関係ではないだろう。まだドラマも生放送の時代。スタジオ収録が中心だったこともあり、派手なアクションよりも室内での刑事と犯人の緊迫したやり取りが見せ場になった。それに伴い、犯人の動機がクローズアップされ、掘り下げられることになる。そしてその結果、犯罪の背景として世の中の歪みも浮き彫りにされた。
当時の日本社会は高度経済成長期。敗戦からの復興が進み、生活も豊かになる一方で、その急激な変化の波についていけず取り残される社会的弱者や孤立する人々もいた。「七人の刑事」には、そうした人々がしばしば登場する。例えば「夢千代日記」(NHK)で有名な脚本家・早坂暁はまだ新進の頃、このドラマで被爆二世の少女が世間の冷たい視線に耐えかねて殺人に走る話を書いた(同書、208頁)。
もう一つの作品が、NET(現テレビ朝日)の「特別機動捜査隊」である。同作は、事件発生から解決までのプロセスをきめ細かく描くことに重きを置いた。そうしたドラマ作りを支えたのが、警視庁の協力である。その点は初の刑事ドラマとされる「ダイヤル110番」(日本テレビ・読売テレビ、57年放送開始)とも共通するが、「特別機動捜査隊」の場合は実際に起こった事件についての警視庁からの資料提供をもとに、殺人事件の場面や捜査の様子などをよりリアルに描いた。そうしたリアリズム志向は、大枠として「七人の刑事」とも重なる。