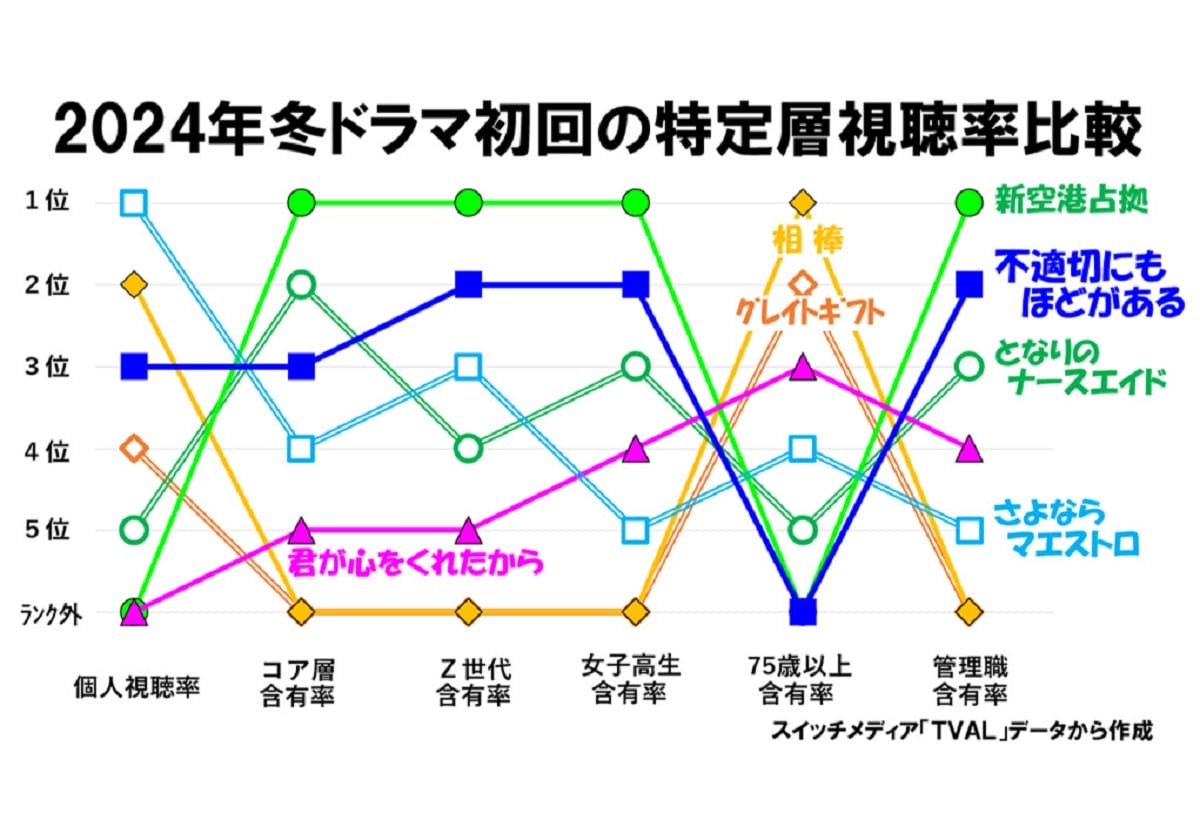「刑事ドラマ」歴代の名作が映し出す社会の変化
2020.05.08
東洋経済オンライン
さらに「相棒」には社会派の一面もある。「七人の刑事」が犯罪の背景にある世の中のひずみを描いたように、「相棒」にもそんなエピソードが時折登場する。あるひとりの男性が現代の過酷な雇用状況を背景に死へと追い込まれていく様子を克明に描いたシーズン9の第8話「ボーダーライン」などはその好例である。
「相棒」のこうした多様性は、脚本家の複数制によって支えられている面も大きい。現在の日本の連続ドラマでは、全話をひとりの脚本家が担当する場合が多い。それに対し、「相棒」の場合は基本1話完結で複数の脚本家が分担して執筆する。
それぞれの脚本家には得意分野や作風があるので、それがそのまま「相棒」の多様性になる。むろんプロデューサーなど統括的立場にあるスタッフによって、ストーリーや役柄の一貫性は保たれる。そうした制作体制のあり方は、海外ドラマにも近い。
このように、刑事ドラマとしての多彩な魅力がある一方で、「相棒」全体を貫く柱になっているのが、警察ドラマとしての側面である。ただこの場合、現実の警察組織をその通りに描くのではなく、ドラマとしての仕掛けがある。それが「特命係」という部署の設定である。
杉下右京とその相棒が属する特命係は、実際の警察には存在しない架空の部署である。「警視庁内の陸の孤島」「人材の墓場」などと揶揄される窓際部署で、本来捜査権限もない。だがことあるごとに独自の捜査を行い、難事件を解決してしまう。この構図自体がバディものとしての純度の高さにつながり、さらに特命係と絡む捜査一課の刑事や鑑識係など脇役たちを引き立たせていると言える。つまり、特命係の設定には、より娯楽性を高める効果がある。
だがもう一方で、特命係の設定は、警察ドラマとしての「相棒」に作品の深みをもたらすうえでも重要な役割を果たしている。杉下右京は東大卒のキャリア組だが、上の命令に従わず嫌われた結果、特命係に“島流し”された。それもあり、特命係は独自に捜査を進めるなかでしばしば警察組織、さらにはその背後にある政官界の思惑と対立することになる。
当然劇中にも警察幹部や大物政治家などが多数登場するが、なかでも印象的なのが岸部一徳の演じた小野田官房長だろう。特命係の誕生にもかかわりのある小野田は、杉下右京と阿吽の呼吸で通じ合っているところもあるが、対立することも少なくない。それは両者の正義観の違いから来るものである。
小野田は警察組織、ひいては国家の秩序を維持するためならば時に取引をし、罪を見逃すことも大きな意味での正義と考える。一方、杉下右京は誰であろうと相手の素性にかかわりなく法の支配のもと正義が平等に遂行されるべきという信念を絶対に曲げない。「杉下の正義は、時に暴走するよ」という小野田の有名なセリフは、そんな両者の違いを端的に表現している。
刑事ドラマの現在、さらなる拡張を求めて
2000年代以降、この「相棒」の登場もあって、刑事ドラマはその幅を格段に広げ、物語としても複雑さを増した。その傾向は近年ますます強まっているように見える。例えば、金城一紀脚本のテレビ朝日「BORDER 警視庁捜査一課殺人犯捜査第4係」(14年放送)では、主演の小栗旬演じる刑事・石川安吾が正義と悪、生と死の境界で揺れ動く様が実に濃密に描かれる。苦悩する石川の姿には、一種の哲学的な雰囲気さえ漂う。
単なる推理ものではない、人間ドラマとして見応えのある刑事ドラマも目につく。安達奈緒子脚本による振り込め詐欺を扱ったNHK「サギデカ」(19年放送)は、社会派の伝統を受け継ぎつつ、主演の木村文乃が演じる刑事の苦悩にも焦点があてられる。
また野木亜紀子脚本で石原さとみが法医解剖医役を演じたTBS「アンナチュラル」(18年放送)は、狭義の刑事ドラマではないが、やはり事件を起点に人間ドラマが展開されていく点で、刑事ドラマの一つの拡張した形と見ることができる。
そして今年放送されたフジテレビ「教場」は、「踊る大捜査線」の君塚良一脚本による警察学校が舞台のドラマ。木村拓哉演じる教官を中心に、教え子の生徒たちの卒業までが描かれる。ミステリー要素を交えつつ、すぐれた青春ドラマでもあるその内容は、警察ドラマの新たな可能性を示したと言えるだろう。