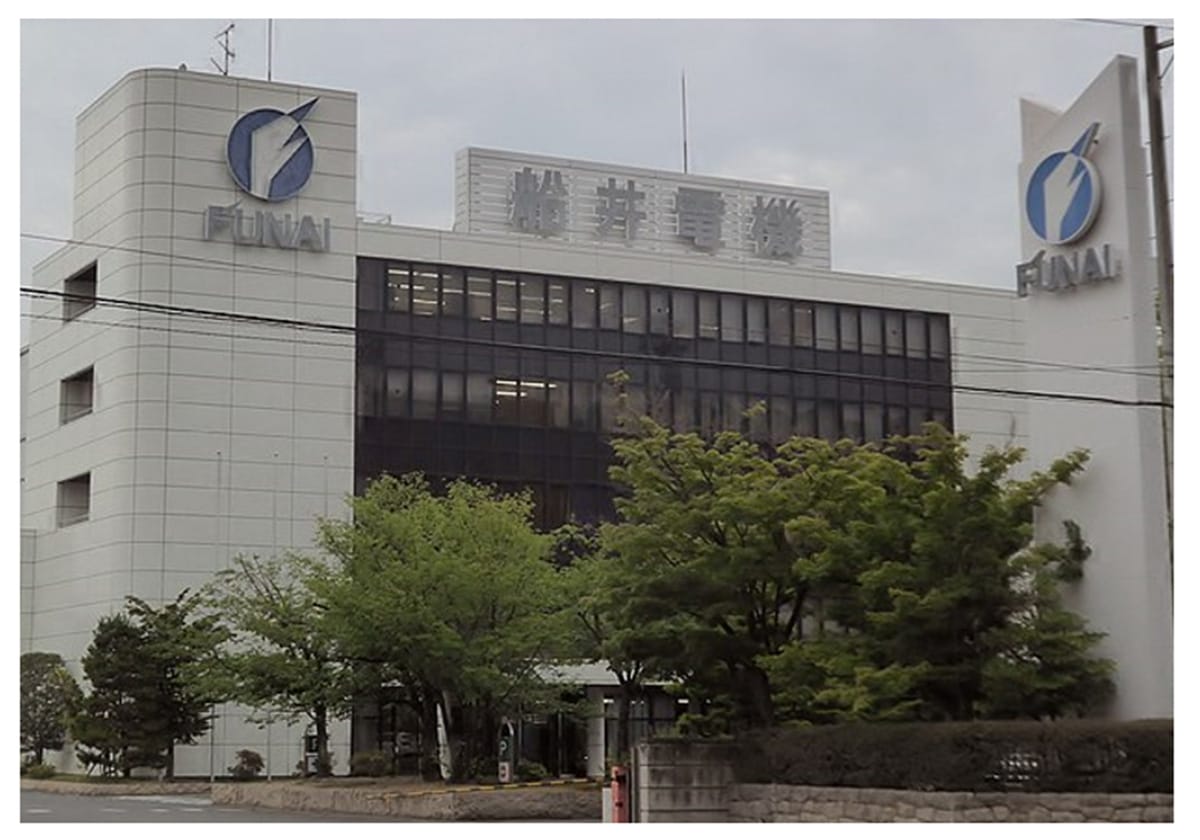「伯方の塩」シェアトップの奇跡…厳しい制約条件乗り越え誕生、低価格競争は回避
2023.07.05
ビジネスジャーナル

少子化の影響などにより、日本においては多くの商品の市場規模が縮小している。今回取り上げる家庭用塩の市場も、過去10年の間に4割減少している。
家庭用塩の場合は、健康ブームによる減塩の影響を受けているため、ことさら深刻ではあるものの、このように完全に成熟化してしまった市場における企業間競争の熾烈さは容易に想像できる。こうした競争に勝ち抜くために、低価格販売を行うことは常套手段といえるだろう。しかしながら、伯方塩業株式会社は適正な価格での販売を維持しつつもシェアトップを堅持している。
伯方塩業の主力商品である「伯方の塩」は、テレビCMにおける「は・か・た・の・しお」のジングルで一世を風靡し、高い認知度を獲得している。よって、こうした広告効果により、偶発的に大きな成功を収めることができた、平たくいえば「たまたま上手くいった」と思われる人も多いのではないかと予想されるが、実際には緻密なマーケティングを実行し、大変な逆境を乗り越えてビジネスを軌道に乗せている。
本稿では、塩ビジネスの特殊性を踏まえ、「伯方の塩」成功までの道のりを辿ってみたい。なお、情報収集においては伯方塩業取締役社長・石丸一三氏にインタビューを行った。
消えてしまった日本の塩田
1905年に塩は国の専売品となり、以後、長きにわたり国が管理を担うことになった。塩は国民にとって必需品であるため、安定的かつ安価に供給する必要があり、また国の財政収入の確保という事情もあった。
国の管理の下、1971年までは瀬戸内海を中心に日本中の塩田で塩がつくられていた。こうした塩田でつくられた塩には、主成分である塩化ナトリウムに加え、マグネシウム、カルシウム、カリウムというミネラルの三大要素を含む“にがり”が含まれている。
しかし、1971年、塩業近代化臨時措置法の成立により、塩の製造はイオン交換膜製塩法という近代的な製法に限定され、塩田での塩づくりは許可されず、結果、日本から塩田は消えてしまった。高度成長期という時代において、塩田での塩づくりは効率が悪く、時代遅れと判断されてしまったわけである。
一方、世界に先駆けて導入されたイオン交換膜製塩法は、海水をイオン交換膜がセットされたタンクにため、通電させることにより濃い塩水をつくり、煮詰める製法である。イオン交換膜を用いてつくる塩は圧倒的にコストが低いというメリットがあるが、塩化ナトリウム99%以上の均一な成分となり、従来の塩田を用いてつくられた塩とは全く異なっている。
日本の製塩の歴史は、“にがり”をいかに除くかとともに、いかに程よく残すかという苦闘の歴史でもあった。その“にがり”成分がなくなる、また世界初となる製法の安全性を不安視する声も当時は強かった。
自然塩(塩田塩)存続運動
こうした状況に対して、愛媛県在住の菅本フジ子氏をはじめとした5人の有志が、従来の塩田製法による塩を食する選択肢が必要だと立ち上がり、自然塩(塩田塩)存続運動を開始した。こうした運動は全国に広まり、各地の消費者・団体の協力によって短期間に5万人の署名を集めた結果、1973年に“厳しい生産上の制約”のもと、国から生産販売委託の認可が下りることになった。
厳しい生産上の制約の詳細については後述するが、いずれにせよ、イオン交換膜製塩法以外の塩を日本で製造・販売できる条件が整ったわけである。同年、伯方塩業が愛媛県伯方島に設立され、塩田の塩を手本に、“にがり”をほどよく残した「伯方の塩」が誕生した。名前の由来は、「伯方島の塩田を復活させたい」という多くの人の願いを象徴したものとなっている。設立に際して、1口10万円の無担保、無保証、無期限の「塩による出世払い」で出資を募り、たちまち数百万円が寄せられた。