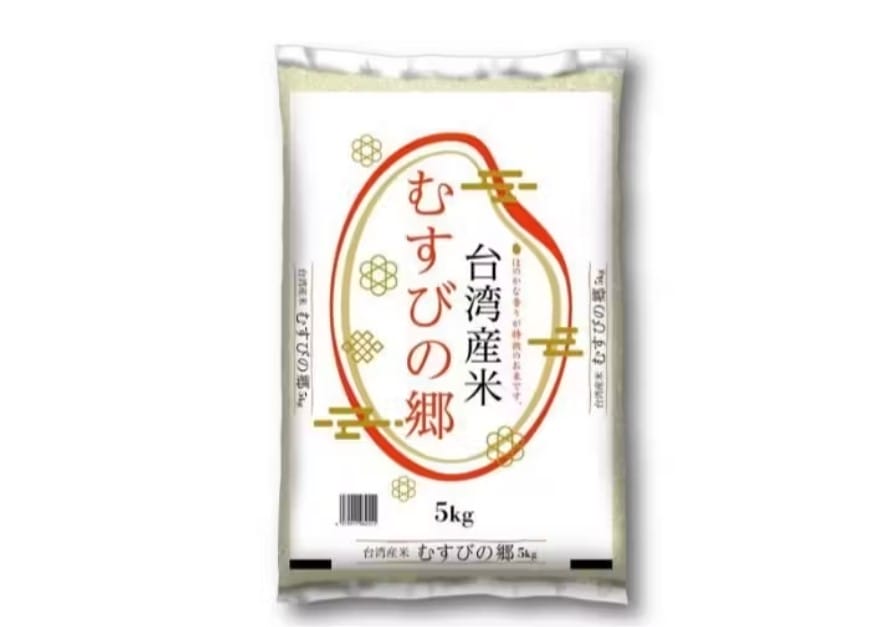「伯方の塩」シェアトップの奇跡…厳しい制約条件乗り越え誕生、低価格競争は回避
2023.07.05
ビジネスジャーナル
軌道に乗った現在の取り組み
このようにして、伯方塩業は厳しい制約条件を乗り越え、ビジネスを軌道に乗せていったわけである。「価格に頼らず、価値を売り込むことに成功した」と言ってもよいだろう。こうした価値の持続・発展に向け、現在は以下のような取り組みに注力している。
主力商品である「伯方の塩」に加え、新商品の開発にも精力的に取り組んでいる。例えば、創業の目的であった“自然塩(塩田塩)存続”を具現化するために、自社工場内に伝統的な塩田である“流下式枝条架併用塩田”を再現しており、ここでつくられた塩を「されど塩」という商品名で販売している。そのほか、大粒の「フルール・ド・セル」など、数多くの商品を展開している。
しかしながら、新商品の発売による商品数の増加は、自社商品間のカニバリゼーション(共食い)という深刻な事態を生じさせる。よって、比較的こうした問題が生じにくい“抹茶塩”といったフレーバー塩などに、とりわけ注力している現状である。
インパクトの強いテレビCMにより高い認知度を得ているものの、認知=購入となっていない場合も多い。塩の購入頻度は世帯平均で年2回程度しかなく、認知度の向上・維持に向けたテレビCMは今後も継続していくものの、自社商品の購入に直結するキャンペーンなどのプロモーションにも注力している。
また、伯方塩業の現在のロイヤルカスタマーは概ね50代以上となっており、20~30代の顧客をつくることは将来に向けた重要な課題であり、SNSやYouTubeなども積極的に活用した情報発信を行っている。現時点において、明確な成果が出ているかの判断は難しいが、“これからの消費者”をつくるためには重要な取り組みとなる。
一方、業務用(BtoB)にも注力している。伯方塩業の売り上げは、家庭:業務=7:3の比率となっており、業務用市場の拡販は重要な課題である。よって、例えば食品メーカーなどに対しては、高い認知度を誇る「『伯方の塩』使用」などを相手先の商品パッケージに表示することを推奨するなど、強い自社ブランドを生かし、単なる取引を超え、顧客の商品の付加価値が高まるコラボレーションのような関係構築にも精力的に取り組んでいる。
塩業界には、公益財団法人塩事業センター(旧専売公社)や味の素株式会社といった大企業に加え、2002年に塩の生産・流通が完全自由化されて以降、多くの小規模事業者が参入してきている。
まず、主としてイオン交換膜製塩法を採用する大企業に対しては、自社製法による塩の品質の良さ、美味しさなどの優位性を訴求している。また、販売促進にかけることができる予算は大手に比べれば見劣りするものの、「塩といえば『伯方の塩』」と初めに想起されるブランドとなり続けるように取り組んでいる。
一方、2002年以降に参入してきた小規模事業者の多くは、近場の海水を用いた家内工業的な製法を採用している者が多い。当時はこうした事業者に顧客が流れる傾向が見られたものの、毎日使用するにはあまりに価格が高すぎるといった要因により、程なくして多くの顧客が戻ってきたようである。
このように、伯方塩業は“おいしい塩を適正な価格で”というポジショニングのもと、大企業と小規模事業者に対する差別化に成功しているわけである。
(文=大﨑孝徳/香川大学大学院地域マネジメント研究科(ビジネススクール)教授)