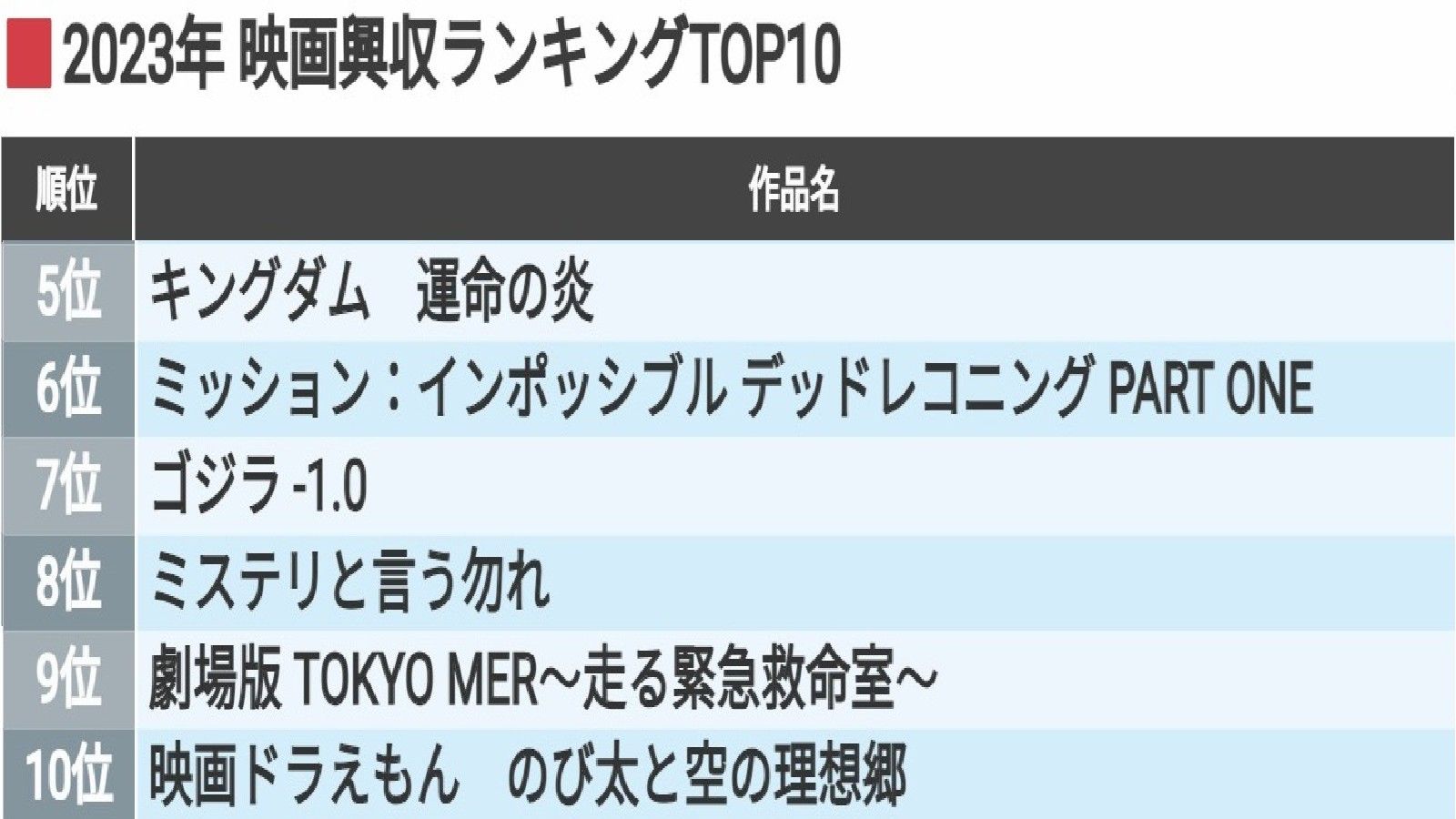
40歳「なりゆきで小説家になった男」の波瀾曲折
2020.01.17
東洋経済オンライン
上京するときに頼りにした、小学校時代からの友達とはまだつながっていた。その友達は業界紙の編集者で、アルバイトの仕事をくれることもあった。
ある日、その友達から相談を受けた。
「『知人が小説教室に通っていて、小説を書いたんだ。もしヒマだったら読んで感想をくれないか?』と頼まれました。実際、ヒマでしたので『いいよ』と引き受けました」
さっそくその小説を読んでみたが、面白いとは思わなかった。
「つまらなかった!!」
と言ってやろうと考えたが、ふと「32歳で仕事もないやつが、そんな偉そうなことは言えないんじゃないか?」と思った。
「僕も、同じ枚数の小説を書こうと思いました。そうすれば、堂々と批判できるんじゃないかな?と思ったんです」
澤村さんは小説を書くことにした。これまでに小説は、会社に泊まり込んでいるときに暇つぶしでショートショートを書いたことがあるくらいだった。その小説も誰にも見せたことはない。
ストーリーや枚数は送られてきた小説に合わせた。OLの日常と震災を絡めた純文学で、原稿用紙140枚の中編だった。
「小説家になろうとは全然思ってなかった」
「小説を書き終えて、3人で飲みながらお互いの小説の品評会をすることになりました。それが友達にはとても面白かったらしく、彼は『この会を続けよう』と言い出しました。30歳を過ぎた、おじさんたちの趣味の会です。もちろん、このときには将来的に小説家になろうとは全然思っていませんでした」
澤村さんはフリーランスの仕事の間に、時間を見つけて小説を書いた。
そして会は続き、合計10本の小説を書いた。
「10本書いたことだし、一念発起して長編小説を書くことにしました。どうせなら好きなホラー小説を書こうと思いました」
そうして執筆されたのが『ぼぎわん』だった。『ぼぎわん』のアイデアは大学時代の思い出から生まれたという。
「大学時代、祖母の家にいたら、訪問販売の人が来たんです。それをおばあちゃんが剣呑な態度で追い返していました。それがなぜか強く記憶に残っていました。もしも訪問販売員がお化けだったら面白いだろうな……と考えました」
そして『ぼぎわん』を書き終え、せっかくなので賞に応募することにした。ちょうど応募期日が間に合う日本ホラー小説大賞に応募することにした。
「大賞を受賞できるとは夢にも思っていませんでした。『ぼぎわん』は加筆して『ぼぎわんが、来る』として発売されました。すぐに新作の執筆依頼も来ました」
1作目『ぼぎわんが、来る』は世に発表する予定のない、いわば趣味の作品だった。

2017年に上梓された『ぼぎわんが、来る』(筆者撮影)
2作目は出版社から依頼をされて書く仕事の作品だ。澤村さんはプロとして、初めて小説を書くことになった。
「どうにか2作目である『ずうのめ人形』を書き下ろすことができました。この作品は自分に対する試練でした。なにもアイデアがないところから、絞り出して書くことができました。この作品を仕上げられたことで、今後プロの小説家としてやっていけるという自信を持つことができました」
たまたまだが、澤村さんは大賞をとった1カ月後にお付き合いしていた女性と結婚していた。そしてお子さんも生まれた。
澤村さんは、小説家の収入で家族を支えなければならなくなった。
「執筆依頼はたくさん来ました。ざっくりですが、依頼を消化するだけで5年以上はかかります。ただ、もちろん出版が確定している数冊の本が売れなければ、未来の約束はなくなってしまうと思います。とにかく今は、一生懸命書かなければならない、と思っています。
『ぼぎわんが、来る』が映画化されたことで知名度が上がり書籍も売れました。また映像化権、ソフト化権などまとまったお金も入ってくるようになりました。『家族を養うことができている』という実感があります」


























