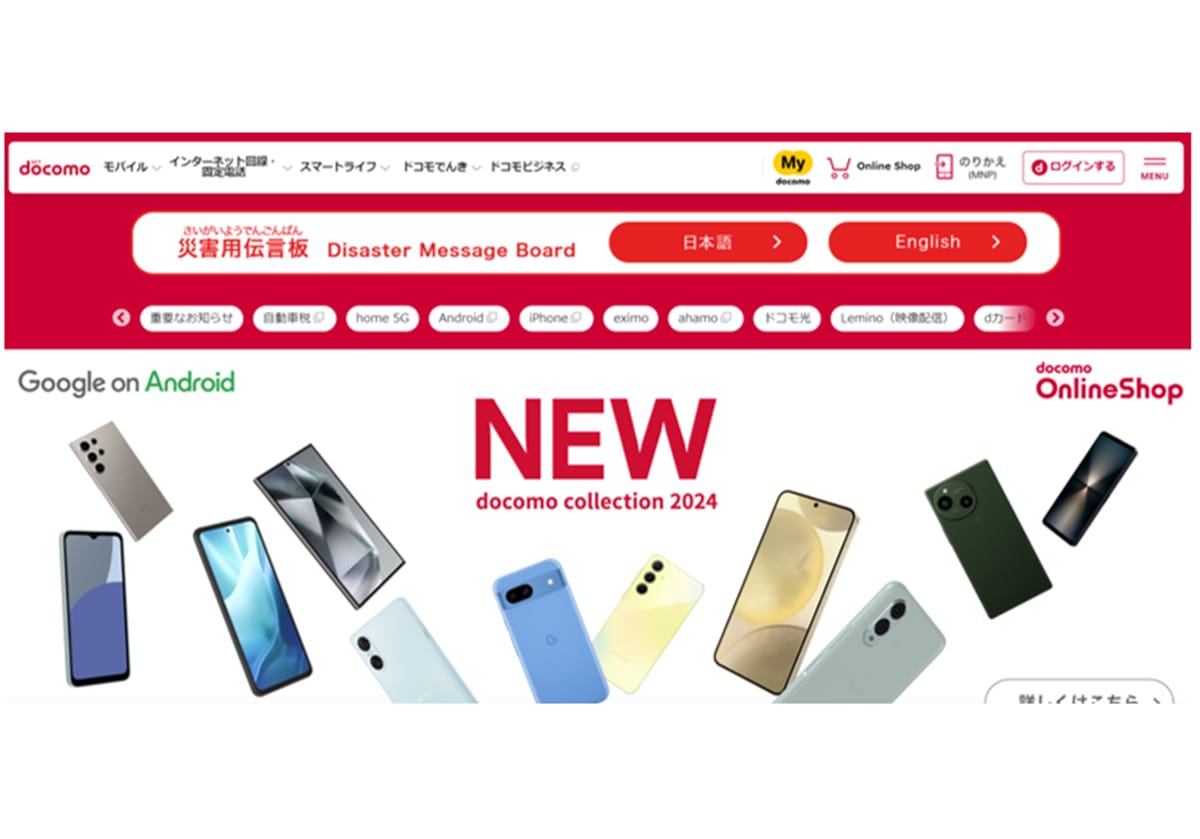「枯れたシステム」メインフレームが今も大量に稼働している理由…根強い需要
2024.12.23
ビジネスジャーナル

システムの領域でオープン化やクラウド化の波が強まるなか、日本IBMと三菱UFJ銀行がレガシーシステムといわれるメインフレーム(大型汎用機)に関する新たなサービスを立ち上げた。「時代遅れ」「枯れたシステム」というイメージがつきまとうメインフレームだが、いまだに底堅い需要が存在するとの声もある。そんなメインフレームの今とこれからを追ってみたい。
かつては大企業などの基幹系・業務系システムで広く使用されていたメインフレームだが、日本では1990年代頃からより小型かつ安価なサーバを複数接続してシステムを構築するオープン化の動きが拡大。加えて、現セールスフォース・ジャパンのセールスフォース・ドットコム、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)、日本マイクロソフトのマイクロソフト・クラウド、グーグル・クラウドなどの外資系クラウドが相次いで日本市場に参入して普及し、高額なメインフレームの利用は縮小してきた。
堅牢性によるミッションクリティカルを重視してメインフレームを使ってきた銀行でも、オープン化の動きが加速。ITベンダーが構築したシステムを地方銀行が共同で使う地銀共同システムが普及。メインフレームの開発から撤退する日立、富士通に加え、開発を継続する日本IBMとNEC、システム開発会社のNTTデータはそれぞれ地銀共同システムを運用し、複数の地銀が参加している。
「日立製作所や富士通などメインフレームを製造する国内ベンダにとって、銀行や保険会社など大手金融機関が大口の納入先だったが、1990年代に始まった金融再編のなかで、金融機関同士の経営統合で規模が大きい側が日本IBM製のメインフレームを利用しているケースが多かったため、そちらのシステムをメインに残していく流れができ、結果的に国産メインフレームの販売が減退していくことにつながった。加えて2000年代に入ると外資系クラウドの波が一気に押し寄せ、メインフレームに限らずサーバをはじめとするハードウェアを扱う国内メーカー、SIerは転換期を迎えることになった。
メインフレームは非常に高価で、かつ製造できるメーカーが少ないため利幅が大きい一方、メーカーは開発・製造・サポートのために多くのハード・ソフト技術者と生産設備を抱える必要がある。そのため、一定以上の販売量がないと採算が合わないので、日立や富士通など国内勢は開発終了に追い込まれた。
それを機に各社が抱えていたメインフレームに使われるプログラム言語であるCOBOLのエンジニアが余剰となり、他の領域への人員転換が進められたが、以前より減ったとはいえCOBOLシステムは現在でも数多く残っており、かつ新たにCOBOLのエンジニアになる人はいないため、扱えるエンジニアが今後足りなくなる問題が生じるのではないかともいわれている」(大手SIer社員)
サーバ系システムへの置き換えには大規模な作業が必要
そんな利用が減少傾向にあるメインフレームだが、日本IBMと三菱UFJ銀行が連携して新たなサービスを立ち上げた。地銀が共同でメインフレームの機能を共用できる「金融ハイブリッドクラウド・プラットフォーム」を提供する。
メインフレームの特徴や用途について、データアナリストで鶴見教育工学研究所の田中健太氏はいう。
「大規模かつ絶対にダウンしてはいけないシステムを動かすための専用コンピュータという言い方が実態に近いでしょう。大半の部品は専用につくられたもので、耐障害性・可用性の高い堅牢な設計になっており、同じコンピュータでもPCやサーバとは大きく異なります。オープン系システムが多数のサーバをつないで構築するのに対し、メインフレームは1台で高い性能を実現できます。その堅牢性から、現在でも銀行をはじめとする大企業の基幹システムで利用されています。たとえば2030年度にメインフレームの製造を終了することを発表している富士通ですが、同社のメインフレームは現在も約700台稼働しているということです(4月23日付「日経クロステック」記事より)」