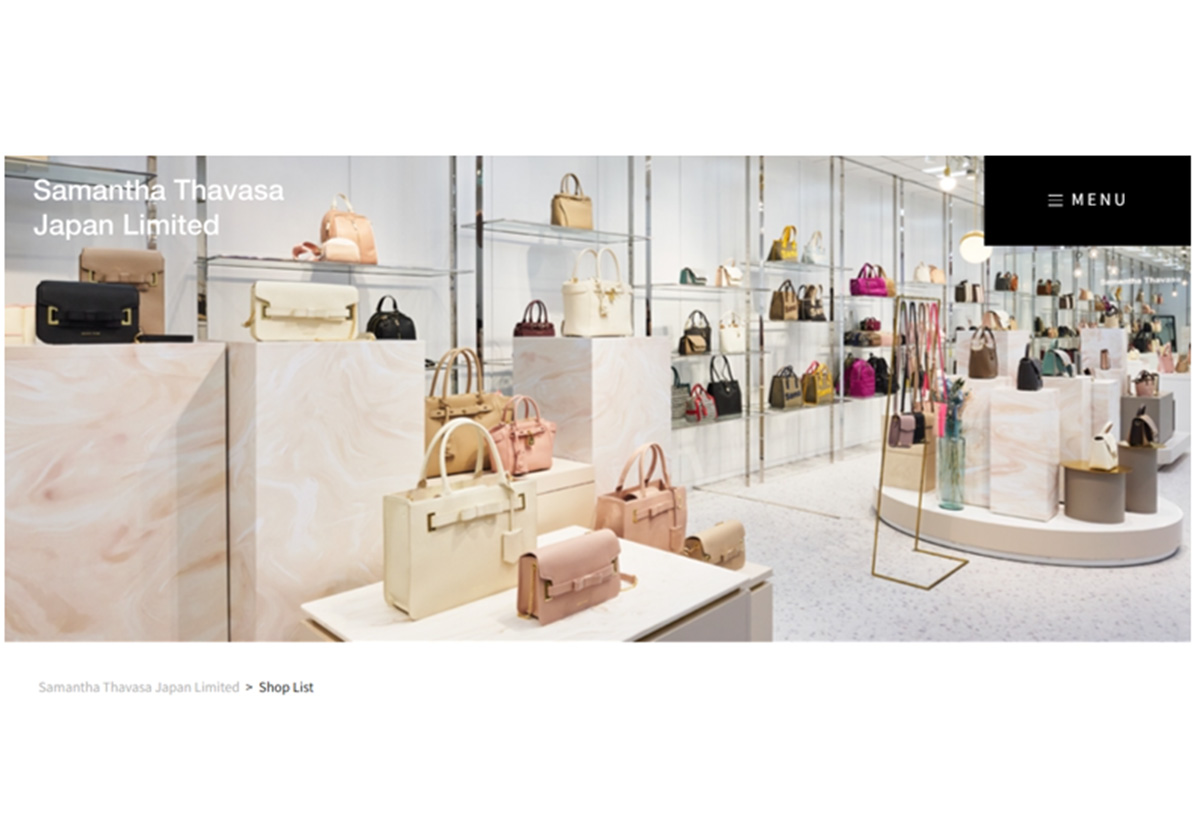損失隠し事件から10年、なぜオリンパスは完全復活を遂げられたのか?祖業も売却
2022.09.12
ビジネスジャーナル

つい最近、オリンパスは祖業である顕微鏡など科学事業の売却を発表した。それによってオリンパスは「真のグローバルなメディカル・テクノロジーカンパニー」を目指すとしている。当社の狙いは、医療分野での急速な成長期待を捕らえることだろう。世界全体で健康に関する人々の意識は急速に高まっている。がんなどの治療や検査のために内視鏡需要が増えている。それに加えて、より高性能な画像処理センサの利用による診断精度の向上や人工知能(AI)を用いた画像診断など、医療分野におけるデジタル技術の利用も増えるだろう。
祖業売却によってオリンパスは過去の発想にとらわれず、企業価値を高める決意を内外に示した。1990年初頭に日本で資産バブルが崩壊したのち、オリンパスは損失を隠した。過去10年間で経営陣は事業運営体制の変革を加速し、内視鏡事業を中心に事業運営体制は再建された。それでも、世界トップの医療機器メーカーとの売上規模の差は大きい。当面、オリンパスは内視鏡事業などの売上高増加を急がなければならない。その上で、経営陣が迅速に資金をデジタル関連事業の運営強化によりダイナミックに再配分することが同社の成長に決定的なインパクトを与えるだろう。
かつて内向き志向に陥ったオリンパス
現在、オリンパスは光学機器メーカーから、世界最先端の医療関連企業への飛躍を目指して、事業運営体制の変革を加速している。特にリーマンショック後は世界経済全体でデジタル化が加速した。本来、オリンパスは早期に事業ポートフォリオの入れ替えなどを進めるべきだったが、それには想定された以上に時間がかかった。
その根底には、組織全体での内向き志向の強まりがあっただろう。特に1990年代以降は同社の組織全体に新しい取り組みを増やすよりも、すでに進められてきたことを続けたほうが良い、あるいは続けなければならないという固定観念が一段と強まったと考えられる。創業から2011年ごろまでのオリンパスのヒストリーを確認し、いかに内向き志向が強まったからを考察したい。
1919年、オリンパスの前身企業である高千穂製作所が設立された。高千穂製作所は「オリンパス」ブランドの顕微鏡やカメラ(フィルムカメラ)の生産を行い、成長した。それが今日のオリンパスの事業運営体制の基礎を形作った。1950年代以降、オリンパスは顕微鏡などの事業で磨いた光学機器の製造技術を他の分野に生かすようになる。まず、1950年には胃カメラが開発された。また、小型のカメラであるオリンパスペンも発売され、オリンパスの成長が加速した。オリンパスペンのブランドはデジタルカメラにも継承された。
その一方で、1990年代初頭に日本の資産バブル(株式と不動産の価格が理論的に説明が難しい水準まで高騰する経済環境)が崩壊した。株式や不動産などの価格は急速に下落した。オリンパスは有価証券投資の失敗によって損失に直面した。それに加えて、一部の経営陣が主導した高値でのM&Aからも損失が発生した。歴代経営陣は海外の投資ファンドなどを活用して一連の損失を隠しつづけた。
その結果として、オリンパスは顕微鏡やカメラなどすでに運営体制が確立された事業に対する依存を深めたと考えられる。2011年に損失隠しが明らかになって以降、同社は経営体制の刷新などを進め、新しい経営風土の醸成に努めた。その上で2020年9月に映像事業の売却が、2022年8月29日には祖業である顕微鏡など科学事業の売却が発表された。
加速するオリンパスの事業運営体制の変革
2012年に経営体制が刷新された直後、当時の経営陣はより迅速に事業ポートフォリオを入替え、事業運営体制を再建しなければならないと危機感を強めたはずだ。しかし、事業ポートフォリオ入替が加速し始めるには、約8年の時間を要した。過去の損失隠し発覚の負のインパクトは非常に大きかった。その状況下で資産売却などを進めると、組織全体に雇用などに関する動揺が広がり、個々人の集中力を高めることは難しくなる。経営陣がリスクをとって新しい取り組みを進めることはさらに難しくなる。そうした展開を避けるために、オリンパスの経営陣は時間をかけて変革を進めざるを得なかったと考えられる。その間、世界経済は大きく変化した。その一つとして、スマホの普及によってオリンパスのデジタルカメラ需要は減少した。