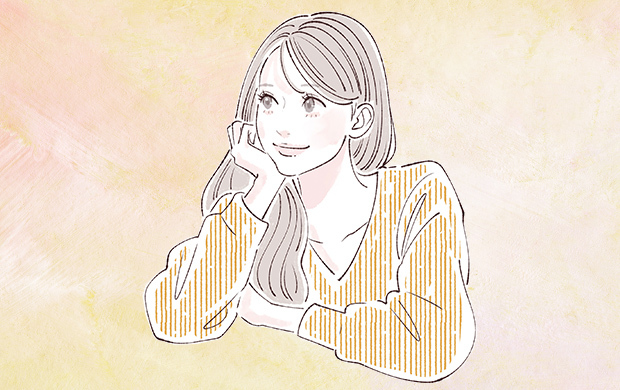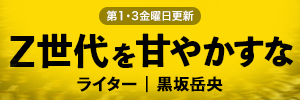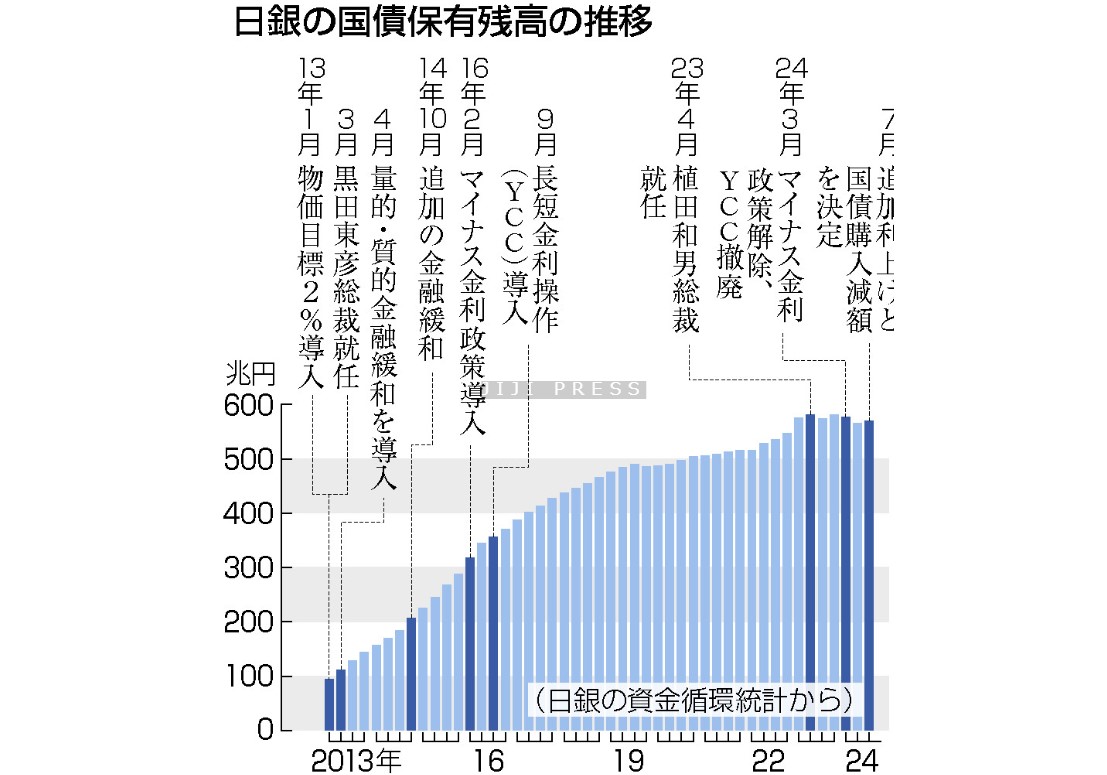
「コンビニは通える引きこもりたち」の知られざる実態…理解や支援を難しくする“思い込み”
2021.09.29
ビジネスジャーナル
引きこもりは日本人にとって身近な社会問題だが、正しい知識や情報が共有されていないために、偏ったイメージが広まっているようだ。
今、自分が何歳なのかもわからない…
久世さんが執筆した『コンビニは通える引きこもりたち』には、ニュースタートが携わったさまざまな事例が登場する。その一部を紹介しよう。
「ノリオ君(仮名)は、現在35歳です。都心で一人暮らしをしながらデザイン系の専門学校を卒業し、広告会社に入社。ですが入社して10年が経った頃、『何のために働いているのか分からない』『何のために生きているんだろう』と話すようになりました。終電でばかり帰るようなきつい仕事で、うつの傾向も見られたため、親も『疲れたのだろう』と判断。しばらく休職し、家にいさせることにしました」(同書より)
その後、彼は仕事を退職。失業保険が切れた後もなかなか重い腰が上がらず、短期のアルバイトも「合わない」とすぐ辞めてしまったという。
「普段はパソコンに向かい、たまに買い物などに出かけ、以前の貯金があるので小遣いの要求もありません。そんな生活を5年も続けています」(同書より)
この事例のように一度就職し、さまざまな理由で退職した後に引きこもりになるケースは少なくないという。そのほかにも、大学受験に失敗して浪人中から引きこもりになった20代の男性や、派遣法が変わった影響で雇い止めに遭って以来、5年間仕事をしていない50歳の男性など、その経緯はまさに千差万別だ。
「最近では、子どもが40代、50代の家庭からの相談も増えていますね。年齢の幅が広がった分だけ内容も多様化していて、“誰しも引きこもりになる可能性がある”と考えるようになりました。18年間引きこもりをしていたある男性に家にいた頃の話を聞いたところ、『はじめの3年ほどは葛藤があったが、それ以降は時が止まったような感覚になった』と話していました。もちろん苦しみはあったと思いますが、自分は引きこもって何年経ったのか、今自分が何歳なのかもわからなくなり、時間の感覚が薄れていた、という言葉が印象的でしたね」(久世さん)
「レンタルお姉さん」と「共同生活寮」
ニュースタート事務局では、1994年の活動開始以降、さまざまな形で引きこもり支援を行ってきた。代表的なのが、スタッフが家を訪問して本人と交流する「レンタルお姉さん」と、家を出た人たちが暮らす「共同生活寮」の運営だ。
「レンタルお姉さん・お兄さんは、はじめに何通か手紙を送ってから電話をかけ、自宅に訪問する支援方法です。訪問と電話を交互に織り交ぜながら、週に1回交流をしていきます。支援を始める前には、子どもに就労してほしいのか、共同寮への入寮なのか、スタッフと親で目標を立ててから“次のステップ”を目指します。入寮を切り出すタイミングも、スタッフが本人の様子を見ながら外に引っ張る力と、彼らの背中を押す親御さんの力がうまく合致したときに、前に踏み出すケースが多いですね」(同)
レンタルお姉さんの支援は半年~1年を目処に行われる。会話の主な内容は“雑談”。相手が興味を持ちそうな内容を投げつつ、こちらからアプローチを続けて少しずつ距離を縮めるという。久世さんは「家族ではない第三者だからこそできる支援を心がけている」と語る。
「家を出た人が入る『共同生活寮』では、卒業後の一人暮らしを想定して、寮生による自主運営を基本にしています。一人ひとりに個室があり、食事は当番制で洗濯は各自で行い、共用部の掃除は分担制です。同時に、週4日はニュースタートが運営するパン屋などで仕事体験をしてもらい、残り3日はお休み。寮生同士の交流で仲間ができるのも、自活への第一歩です」(同)