
授乳室や子どもが遊べる空間も…ユニクロ、新3店舗にみる革新的進化と難点
2020.08.24
ビジネスジャーナル

コロナ禍による人々の活動自粛のため明るい話題の少ないアパレル業界だが、ファーストリテイリング傘下のユニクロが実験的な新コンセプトの大型3店舗を戦略店舗として相次ぎオープンさせた。4月13日に「ユニクロの店舗が公園になっている」ユニクロパーク横浜ベイサイド店が三井アウトレットパーク隣接地にオープンした。6月5日には、新装されたJR原宿駅前のWITH HARAJUKUの1階と地下1階に新しいファッションやカルチャーを発信するユニクロ原宿店をオープン。同月19日には、有楽町駅前の元プランタン百貨店のマロニエゲート銀座2を1階から4階までぶち抜いたグローバル旗艦店、ユニクロ トウキョウをオープンした。
そこで今回は、各店舗からみえるユニクロの可能性と課題を探ってみたい。
1.3世代を取り込む公園一体型「ユニクロパーク 横浜ベイサイド店」
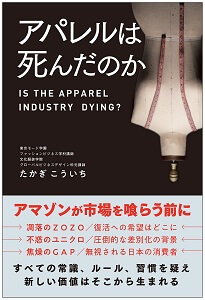
筆者が最も評価するユニクロの社会貢献は、日常に着る服を親子3世代で選べる楽しさを根付かせたことである。かつて服選びは、母親が買ってきたものを家族が着る、あるいは孫の服を祖母や祖父が選んでも子ども夫婦の趣味に合わなかったりした。家族で服をお互いに選び合いながら購入する楽しさは、ユニクロの売場面積の広さによって実現した。そこには、世代を超えた品揃え、気にする必要のない価格帯、接客のなさで大切な人の服選びをする楽しさがある。
これは、アパレルの実店舗が消費者に提供する最大のワクワク感のひとつである。実験的なコンセプトの横浜ベイサイド店は、まさにこの延長線上にある。1階はユニクロ、2階はGU、3階はユニクロとGUのベビー・キッズの融合売場。教育知育玩具のボーネルンドと連携して、公園には子どもが楽しく安心して遊べる遊具が多数設置されている。ファミリー層の来店用にナーシングルーム(授乳室)、オムツ替え台、調乳専用浄水給湯機なども設置されている。小売店が地域社会の重要なメンバーとして求められる今の時代、店舗の建築自体も半パブリックな地域社会に開放的なつくりになっている。
「わざわざ行きたくなる店」を目指すユニクロの世界戦略のクリエイティブ・ディレクターの佐藤可士和氏がグランドプロデューサーを務め、建築家の藤本壮介氏が基本構想とデザイン監修を行った。コト発信で消費者が参加しやすいコミュニティが形成されていくのが楽しみである。
2.リアルとバーチャルの融合体験を目指す「ユニクロ原宿店」
1998年にユニクロ初の首都圏都心型店舗を出店しフリースの大ブームを生んだ原宿地区で、新店舗がオープンした。場所柄、若者を強く意識したコンセプトとなっている。全面ガラス張りで店内の様子が外からもよく見える演出となっている。店内奥の大型ディスプレイの映像、ティッカー(メッセージが表示される赤の電光掲示板)、メタル調のマネキン、ガラス張りの天井など、ハイテク感満載で未来型店舗の印象に溢れている。
シンボル的な存在として、現代美術家の村上隆氏がポップアイコン、ビリー・アイリッシュの3メートル級の像を製作。ユニクロ、村上、ビリーのトリプルコラボTシャツを着用している。ファンにとっては聖地となる。美術館のようなガラスケースのTシャツだけでなく、ステーショナリー、バンダナ、ステッカーなど、若者が気軽に買える記念グッズも揃う。
地下には、自分だけのTシャツがつくれる「UTme!」などのサービスも充実。VMDもストリートテイストのオーバーサイズでコーディネイトされている。音楽配信のスポティファイと協業したスペシャルブースも展開。カルチャー発信にも挑戦している。地下1階の正面スペースには240台のモニターが壁面に埋められ、消費者がアプリ「スタイルヒント」に投稿した着こなしが次々とアップされる。もちろんモニターをタッチすると在庫情報が表示される。大型の古着回収ボックスの設置もあり、アイデアいっぱいの新店舗である。これらの先進的なアイデアが実売にどう影響するのかが注目される。




























