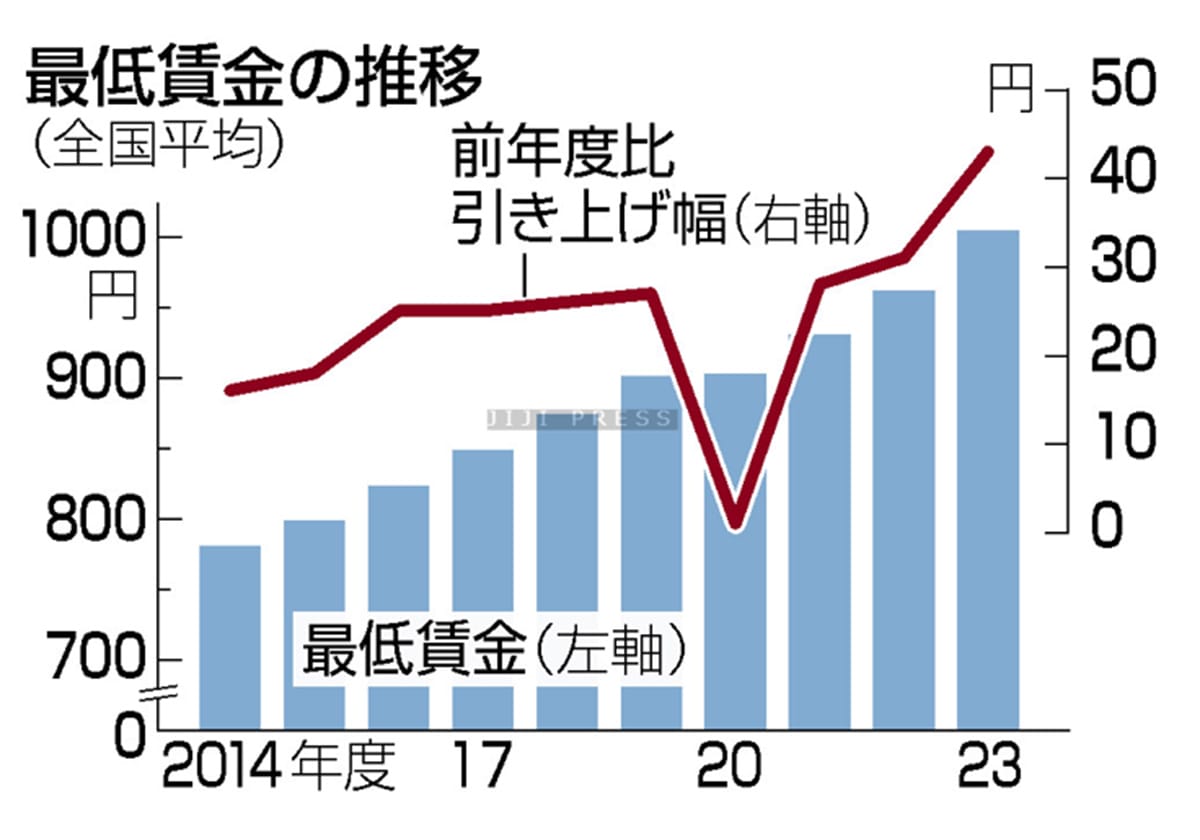
「田舎/夏/恋人消える物語」なぜTikTokでバズる?
2024.03.12
東洋経済オンライン

たしかに、「君」や「僕」がつくタイトルが多い(編集部撮影)
SNSが生活を覆う時代、個人は、いくつかのアカウントによって、常にスイッチングが可能になってきた。いわゆる「別垢」でまったく異なる人間関係とつながることも可能になった。

『キミスイ』こと『君の膵臓をたべたい』では、主人公の名前が最後まで明かされず、本編のほとんどで『僕』で通されている(amazonより)
さらに、SNSを見れば、まばゆい活躍をしている、特別な同世代はいくらでも目にすることができる。
ある意味では、自分自身が一人の人間という固有の存在ではなく、切り替えも代替も可能な一人であるに過ぎない……。
その意味でブルーライト文芸に登場する、無個性かつ匿名性の高いキャラクターは、SNS時代に適合したキャラクター像だともいえるだろう。
また、ぺシミ氏は元々中高生が読んでいたライトノベルの衰退も挙げる。
「今のライトノベルは、中高生に売ることを諦めているように感じます。タイトルもセンシティブで、学校では読めないものも多い。また、女性向けのラノベでも悪役令嬢とか婚約破棄みたいなものが多くて、はたして、そんな人間関係にドロドロしたストーリーを中高生が読みたいかというと疑問です。
なので、今の高校生にとってリアリティがあるのは、ブルーライト文芸的な描かれ方の青春小説なのではないでしょうか。ライトノベルが吸収できない層をライト文芸が吸収している側面はあって、中高生が自分に共感できるものを求めていった結果、ライト文芸が盛り上がりつつあるのではないかと思います」
そのうえで、ペシミ氏はこう指摘する。
「以前は子どもが本を読む順番として、児童書から青い鳥文庫に移動して、それと近いライトノベルを読みあさり、次第に大衆文学へ移行していくという流れがあったと思います。
しかし、今は児童書と大衆文学の間にライトノベルを挟まず、ブルーライト文芸から直に接続しているのではないでしょうか」
ブルーライト文芸が、文学作品への一つの間口になっているともいえるのだ。
TikTokとブルーライト文芸はなぜ親和性が高いのか
また、ブルーライト文芸が中高生に人気の理由としては、TikTokとのコラボレーションが挙げられる。
ブルーライト文芸はTikTokでバズることも多く、特にスターツ出版の『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら』(汐見夏衛)は出版から4年後に、TikTokで大きな反響を呼び、大ヒットした。TikTokとブルーライト文芸はどうして相性がいいのだろうか。

映画化もされた通称『あの花』。福原遥と水上恒司のW主演で話題となった(amazonより)
「メディア的な特徴として、縦画面の動画と、縦の本の表紙が合致したことがありますよね。また、青くてエモい表紙に音楽を掛け合わせるだけで、“エモさ”が増して、TikTokウケしやすい。
また、そもそも、ブルーライト文芸は実写化されることが多くて、そこで起用される俳優がスマイルアップの俳優だったりする。そのファン層の若い女性が使っているのはTIkTokの場合が多いので、そうした意味での親和性もありますね」
『残像に口紅を』がTikTokでバズったのも納得だ
TikTokと文芸作品で言えば、近年、筒井康隆の『残像に口紅を』がTikTokで大きくバズったことが話題にもなった。

TikTokでバズったことが、書店でも紹介されている『残像に口紅を』(編集部撮影)
考えてみると、この作品も、言葉が一つ一つ「消失」していくものであり、ヒロインが<消失>するブルーライト文芸の構成に近いものがある。また、エンタメ作品も多い筒井作品の中でも、実験的な作品であり、文学を楽しむ入門編としても最適だろう。


























