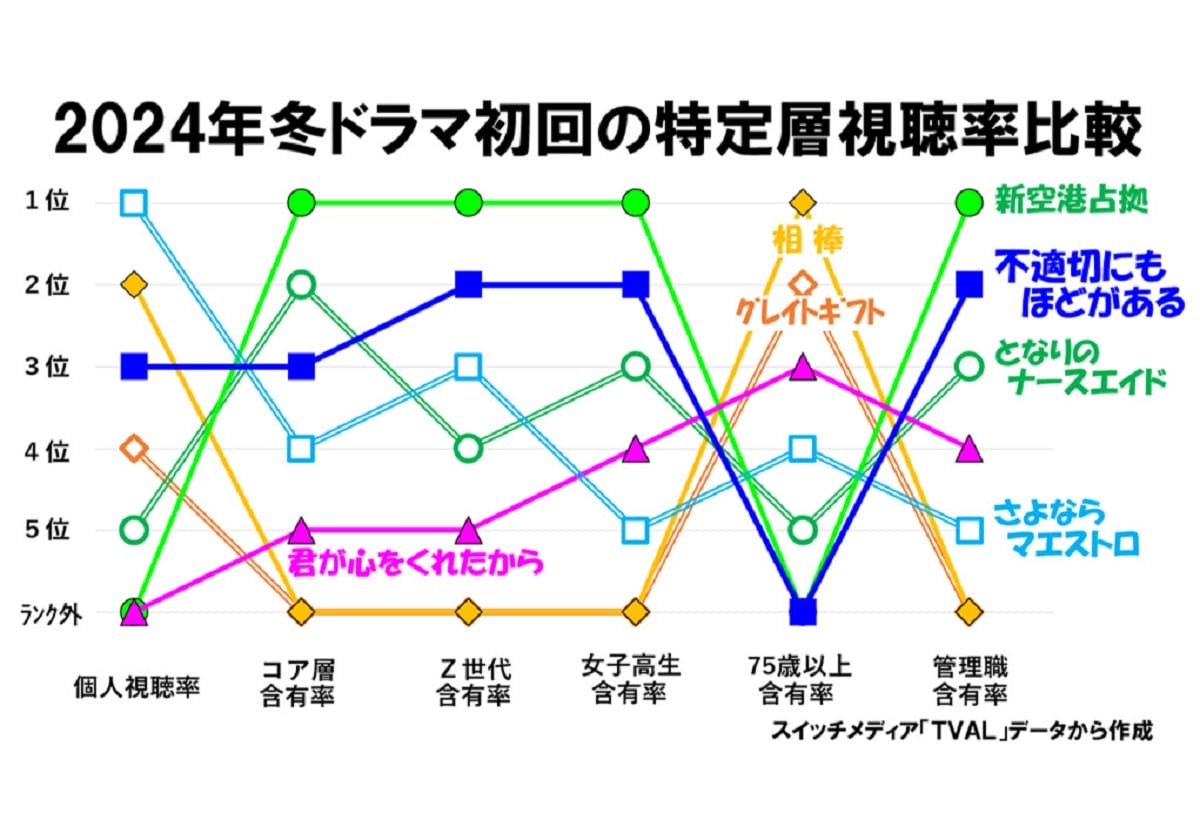22年映画興収「100億超え4本」も喜べない複雑事情
2022.12.07
東洋経済オンライン
シリーズ続編の興行力の低下とテレビドラマの映画化作品の低調ぶりは近年の課題であったが、コロナを経て中クラスヒット層の下降傾向がより顕著になった。
まず洋画を見ていこう。洋画が戻った今年は、前述の『トップガン マーヴェリック』のほか、『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』(64億円)『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(45.8億円)『ミニオンズ フィーバー』(45億円)『スパイダーマン: ノー・ウェイ・ホーム』(42億円)『SING/シング ネクストステージ』(33億円)などが映画館をにぎわせ、幸先の良い洋画シーンのリスタートになったように見える。
たしかにコロナ禍の2年間と比べれば、大作がシネコンに戻ったことで3年ぶりに洋画興行を大きく底上げした。しかし、見方を変えるとその実情は異なる。コロナで洋画が止まった時期を経て、これだけ知名度も人気も大きなシリーズ続編の公開が続いているにもかかわらず、ほとんどがシリーズ前作から興収を大きく落としているのだ。
シリーズ続編が前作より興収が下がるのはいまにはじまったことではない。もちろん上がる作品もあるが、下がる作品のほうが圧倒的に多い。だが、今年は一部を除きその落ち幅が従来以上に大きくなった。
その流れに抗い、圧倒的な作品力で観客を惹きつけたのが『トップガン マーヴェリック』や『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』だ。とくに前者の爆発的ヒットばかりが今年の洋画シーンの景気のいい話題として際立っているが、そのほか多くの続編が、シリーズのタイトルの大きさに対して思うように興収を上げられない苦境にさらされているのが実情だ。
ディズニープラスへの配信シフト
それでも先に挙げたシリーズ続編は健闘しているほうだ。さらに厳しい結果になっているのがディズニー作品。作品数はあるものの、2022年は『ドクター・ストレンジ マルチバース・オブ・マッドネス』(21.6億円)が同社の興収トップとなり、期待されていた『バズ・ライトイヤー』(12.2億円)や『ソー:ラブ&サンダー』(13.5億円)を含め、15億円を超えるヒットがほぼないまま終わりそうだ。
かつてディズニーと言えば、毎年50億円から70億円のヒットを連発し、100億円を超える作品も少なくなかった。100億円超えが3本、60億円台が2本となった2019年が象徴的で、近年の洋画市場はディズニーが大きく牽引していた。そんな洋画の雄から大ヒットが生まれなくなっている。
その背景には、ディズニープラスへの配信シフトがあるだろう。コロナ禍でディズニーは新作の配信独占公開や劇場と配信の同時公開に踏み切るなど、試行錯誤を繰り返してきた。
現状では、基本的に劇場公開から配信まで45日間を設ける「45日ルール」がデフォルトになっているが、配信でドラマや映画を見ることに慣れたファミリー層や若年層のディズニーファンがそちらに移っていることは想像に難くない。
ただ、ディズニーは劇場公開から生まれる社会的ヒットがコンテンツ価値を高める重要性を理解している。ディズニープラス(配信)を主軸に構える姿勢はコロナ以降変わっていないが、劇場と配信の両方をどううまく事業として成り立たせ、利益を最大化していくかがこれからの大きな課題だろう。
今年はディズニー以外の洋画配給は健闘した。日本映画市場の規模として見た場合の洋画復興は、ひとえにディズニーにかかっている。
では邦画はどうか。今年もコロナ前からの傾向がそのまま現れており、アニメは好調だが実写が苦戦している。アニメは100億円超えが3本あった一方、実写のトップは『キングダム2 遥かなる大地へ』(52億円)。そのあとに『シン・ウルトラマン』(45億円)が続き、『余命10年』や『沈黙のパレード』『コンフィデンスマンJP 英雄編』は30億円にとどかなそうだ。