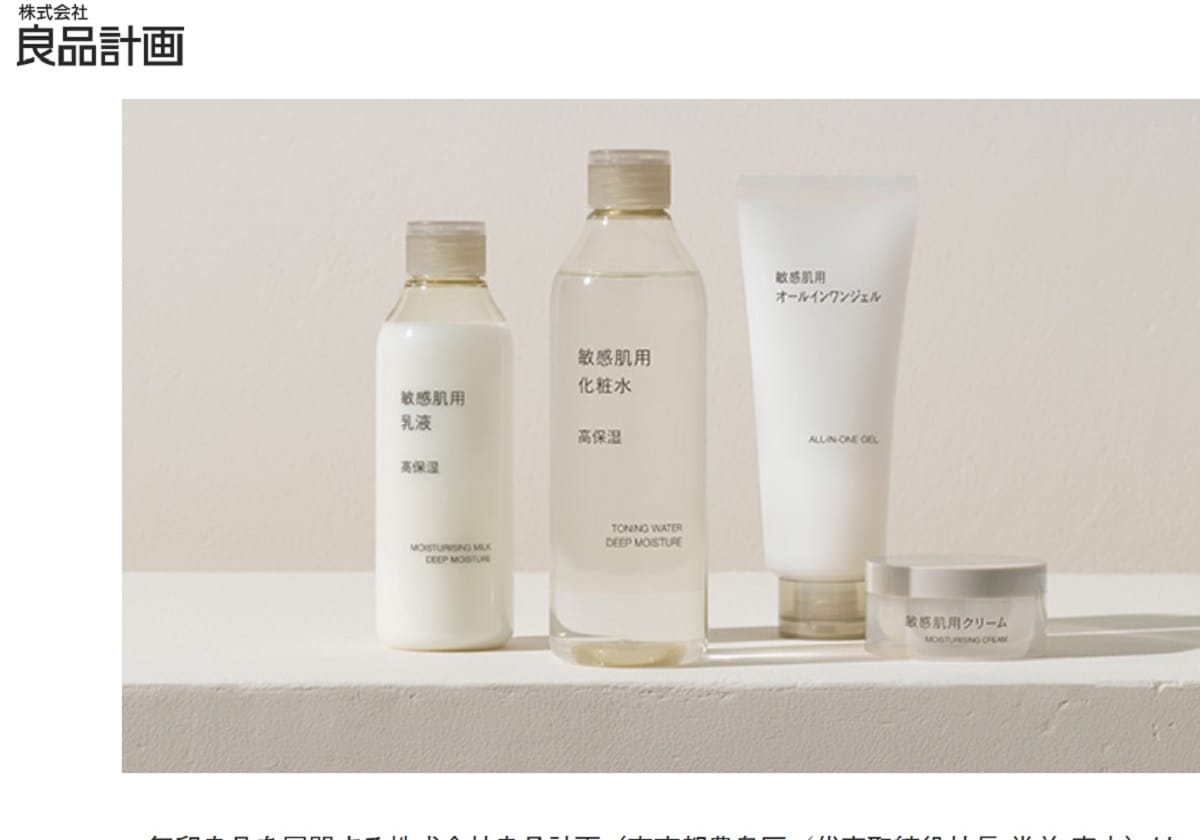トップの度量が試される「リスクをとる力」

リスクをとらずして、大きな成果は得られない
勝負には常に勝敗があり、敗れることを恐れてばかりいては、勝負の場にさえ出ることができず、結果、いつまでも不戦敗が続くことになる。勝ちを得るためには、失敗のリスクをとる勇気と覚悟が必要だ。それが将たるトップにとっての必要条件である。
定年を迎えたサラリーマンが、送別会のときに口にする常套句(じょうとうく)が「おかげさまで定年まで大過なく勤めることができました」である。私は正直この言葉にひっかかりを覚えてならない。大過なくとは、大功もなかったということである。大失敗はしなかったものの、大成功もなかったということを告白しているようなものだ。
大失敗する者だけが大成功を収めるという。リスクをとってでも、勝負に出るときには出ることで、勝機をつかむことができるのだ。
“The greatest risk is not to take a risk.(最大のリスクとはリスクをとらないことである)”という。しかし、リスクをとる勇気と覚悟を蛮勇と同一視してはならない。暴虎馮河(ぼうこひょうが・素手で虎と戦い、歩いて揚子江を渡る)の類は、自暴自棄の無茶、あるいは自殺行為であって、トップのとるべきリスクとは違う。単なる無鉄砲であり蛮勇である。トップのとるべきリスクとは、計算されたリスクでなければならない。
リスクマネジメントは70点主義
私はリスクマネジメントの要諦は「70点主義」と考えている。完璧主義はビジネスではあり得ない。リスクをとるといっても、成功すれば1億円の利益、失敗したら1億円の負債というオール・オア・ナッシングでなく、失敗したときに全てを失うことのないようにダメージをコントロールすることが肝心である。
そこで、あわよくば100点などとはじめから過剰な期待などせずに、私はリスクを抑えたうえでの70点主義で勝負に出ることが、「計算されたリスク」のとり方だとしている。ハイリスク・ハイリターンという賭けではなく、ミドルリスク・ミドルリターンである。それでも読みを誤ればリスクは増大する。
リスクを抑えるために、まず必要なのが情報である。情報は量、質ともに十分か。情報不足では、リスクは増大するばかりだ。情報の量と質を計算するときに、勘違いしてはならないのが情報の質である。伝聞情報や2次情報ばかりをいかに大量に集めても、それでは十分とは言えない。自分の目や耳で確かめた確度の高い情報があるか否かが、リスクを計算するうえで最重要といえる。
人から聞いた情報を2次情報というのに対し、自分の目や耳で集めた情報を1次情報という。2次情報は加工品だが、1次情報は生ものだ。伝聞や2次情報だけで、リスクを判断してはならない。伝聞や2次情報に頼って判断するときには、往々にしてリスクを見誤る可能性が高くなる。
現地・現場に赴き、現実と現物、すなわち“FACT(ファクト)”を自分の目で確かめること、これがリスクをとるときに行うべき基本動作である。MBWA(Management By Walking Around)(歩き回ることによる経営)が求められる。
総合商社の伊藤忠商事で社長・会長を務め、その後、中国駐在大使を務めた丹羽宇一郎さんは、若い頃に同社の役員だった瀬島龍三氏から次のような薫陶(くんとう)を授けられたと、著書の中で述べている。
「何か問題が起こったらすぐに飛行機に乗って現地に行きなさい。お金なんか気にしなくていい。それで会社から文句を言われるなら、私に言いなさい」
リスクの原因はすべて現場や現地にある。それを確かめないまま判断することは極めて危うい。
新聞記事だけで判断し大失敗
丹羽氏さんは、やはり著書の中でご自身の苦い経験についても記している。伊藤忠商事に入社して間もない頃、丹羽さんはニューヨーク駐在となり、主に穀物などの食糧の売買を担当した。あるとき「ニューヨークタイムス」で「今年は大干ばつになる」という気象予測が報じられた。大豆を扱っていた丹羽さんは、この予測記事を見て「今年の大豆は干ばつで不作となり値段が高騰する」と判断し、値段が上がる前に購入しておこうと大量の買い付けを行った。
まだ気象予測の精度が低かった時代である。しかし、丹羽さんの判断とは裏腹に、アメリカの大豆産地の天気は、日照り続きから一転、雨が降り出し大豆は大豊作となった。そのため大豆の値段は暴落、高値で大量に大豆を買っていた丹羽さんは会社に大損害を与えることになる。
損害額は、当時の金額で500万ドル近かった。この数字は「当時の会社の税引き後利益に匹敵するものでした」(丹羽宇一郎『死ぬほど読書』幻冬舎)という。丹羽さんはこのとき本気で会社を辞めようかと考えたそうだ。
何とか思いとどまった丹羽さんは、「2次情報ではだめだ、自分の目で確かめなければいけない」ということを肝に銘じた。そこでMBWAを行った。どんなに多くの人々に支持された権威ある新聞でも、専門家の予測であっても、信用できるとは限らない。瀬島龍三氏に受けた薫陶のように、自ら現地に飛んで、自分の目で確かめなければいけない。これが後年の丹羽さんのビジネス哲学となる。
この話には後日談がある。丹羽さんが大豆で大失敗した翌年、やはり「ニューヨークタイムス」が今度は小麦の生産地帯で「大干ばつが来る」と報じた。その記事を見た丹羽さんはただちに飛行機の乗り、さらに空港からはレンタカーを借り、何時間も運転して小麦の産地へと向かった。
現地に着くとレンタカーで広大な小麦畑を見て回った。至るところに青々とした小麦が生育しているばかりで、どこにも干ばつで枯れた小麦など見当たらない。現地の人に話を聞いても、干ばつに悩んでいる人はいなかった。丹羽さんは「これは買ってはだめだと思い、自慢めきますが、周囲がみな買っている中、冷静に対応して損をまぬがれた」と、今度は会社に大きな貢献をしたのである。
オススメ記事
「トップの力 ジョンソン・エンド・ジョンソンで学んだ経営の極意」 記事一覧
- 第23回 計画する力
- 第24回 学ぶ力
- 第16回 トップの度量が試される「リスクをとる力」
- 第6回 「理念の力」
- 第5回 「目標の力」