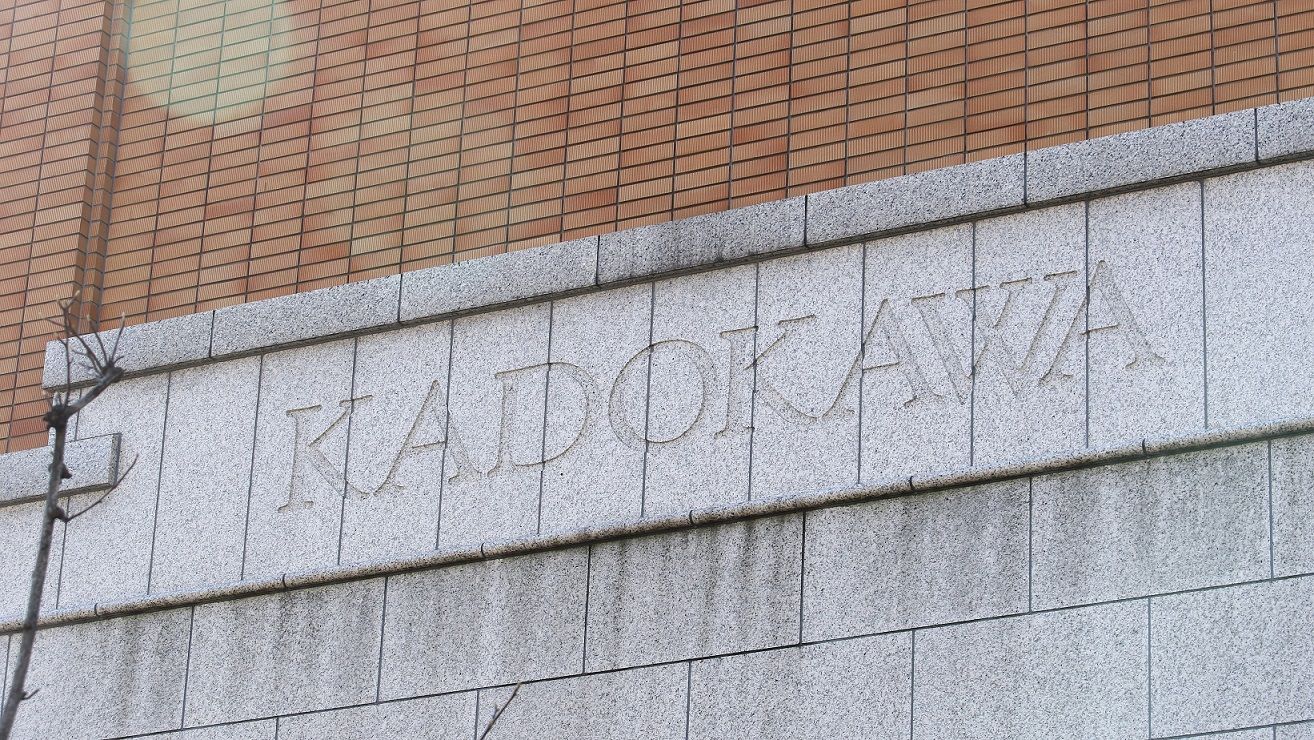トップの度量が試される「リスクをとる力」

リスクを見抜く決め手は胆識にあり
丹羽さんは現地で青々と繁った小麦を見て、リスクを回避することができたが、同じ光景を見ても、なお「ニューヨークタイムス」を信じる人もいるだろう。今は青々として繁っているが、これから大干ばつになって全滅するかもしれないと判断した人もいたはずだ。自分の目よりも権威ある新聞や専門家の意見のほうに頼る人は、今日でも少なくない。
こういう人は知識偏重タイプである。知識偏重タイプは、往々にして権威や知名度に弱い。以前にも述べたとおりトップに必要なのは、知識、見識、胆識の3つである。特に重要となるのが胆識である。知識はなくてはならないが、知識だけではNATO(ノー・アクション、トーク・オンリー)となる。
対して胆識はWTT(Walk The Talk=言行一致・知行合一)である。「ニューヨークタイムス」の記事は知識だが、知識に過去の経験が加わり見識となり、さらに現地に飛び、現実の状況を確かめるとう行動が加わることで胆識に昇華する。丹羽さんの場合、1年前の失敗によって高い胆識を得たといえる。大失敗を、大成功を生む力(胆識)としたのである。
だが、どんなにリスクを計算しても、神ではない人間はやはり間違える。トップのリスクをとる力には、間違った時、最後の最後は「さあ殺せ」と腹をくくる覚悟も必要だ。トップにとって必要な勇気と覚悟とは、恐れずにリスクをとる勇気と、失敗したときに「さあ殺せ」腹をくくる覚悟のことである。
ダメージコントロールの最大の敵は「隠しごと」
もうひとつリスクをとるために必要なのが、期待したとおりにことが進まなかった場合のダメージコントロールと是正措置である。
いくら覚悟を決めてリスクをとっても、すべてが上手くいくとは限らない。もし失敗した時には、適切な対処によってダメージを最小限に抑える必要がある。その時に最も重要なことは、損害を明らかにすること、そのために全社的な損害を隠さないということである。正しくダメージ(損害)を把握することなしには、適切な是正措置をとることはできない。損害を明らかにするためには、各部署からの報告が必要だ。しかし、損害を明らかにすれば自分の失敗を報告しなければならない。
人は自分の失敗を隠したがるものである。人の集団である組織全体で、包み隠さずすべてを明らかにすることは容易ではない。失敗や損害を隠さない、これは一見すると簡単なことのように思えるが、実はひと筋縄ではいかないことなのだ。
再び丹羽さんの話だが、丹羽さんがニューヨークで大豆の買い付けで大損害を出したとき、当時の伊藤忠商事本社の上司からこう言われたそうだ。
「一切隠しごとはするな。すべて会社に報告しろ。お前が首になるなら、オレが先に首になる」
丹羽さんは上司のこのひと言でふっきれ、会社を辞めずに失敗の全てを会社に報告することができた。丹羽さんは、その後、伊藤忠商事の社長となり、約4000億円という不良資産、不良債権を思い切って処理し、同社のV字回復を達成することとなる。
各部門に隠れている不良資産、不良債権を明らかにする時、部長たちに「これ以上赤字を隠していたら、君たちの給料をストップせざるを得ない」と告げるとともに、「君たちに責任はない。社長である私が最後の責任をとるから出しなさい」と現場を説得した。隠しごとをするなと言うだけでは、人は隠しごとをやめない。
丹羽さんは自身の体験から、すべての失敗を自ら会社に報告することは、とてもつらいことだとわかっていたのである。
トップは「失敗を隠さない組織風土」を創れ
会社の存亡の危機という最大のリスクを生む原因は、組織の隠ぺい体質である。東芝の不祥事は、現場の社員が目標の辻褄合わせのために行った不正会計から始まっている。目標のために行った不正会計というのは、すなわち隠しごとであり、捏造(ねつぞう)であり、ごまかしである。
東芝の現場で、辻褄合わせのための不正会計が行われていたのは、昨日今日のことではなく、相当以前からだったと聞く。長く続いていた不正会計、すなわち隠しごと、捏造、ごまかしは、時間の経過とともに習慣化し、組織の体質となっていた可能性は高い。東芝は不正会計が致命傷だったのではなく、隠しごと、捏造、ごまかしを許す組織体質が大問題だったのである。
不正会計だけなら、富士フイルムグループのニュージーランドの子会社とオーストラリアの子会社も、やはり不正会計による不祥事を起こしている。しかし、富士フイルムと東芝を比べた時、そのダメージは次元が異なる。そこには体質の差が大きく影響していると私は見ている。隠しごとをしない組織の体質を、丹羽さんは「清く、正しく、美しく」と言った。
「清く、正しく、美しく」という風土を創るには、修道僧のように清廉な生活しても実現できない。人は自分の失敗を隠したがる、一度の失敗で将来が断たれるような職場では、誰も自分の失敗を明らかにしようとはしないだろう。
信賞必罰(しんしょうひつばつ)は組織の鉄則であるから、失敗を不問に付すような規律の乱れは許されない。しかし、失敗した者にも積極的にリカバリーのチャンスを与えることはできる。一度や二度の失敗をしても社長になれるという生きた見本があって、人は「安心して」失敗を報告するようになれるというものだ。
次回に続く
オススメ記事
「トップの力 ジョンソン・エンド・ジョンソンで学んだ経営の極意」 記事一覧
- 第23回 計画する力
- 第24回 学ぶ力
- 第16回 トップの度量が試される「リスクをとる力」
- 第6回 「理念の力」
- 第5回 「目標の力」