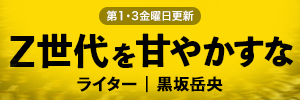「納品した」「されてない」日通・アクセンチュア、開発頓挫の訴訟がエグ過ぎる
2024.10.11
ビジネスジャーナル
日本企業の場合、メーカーだと製造部門や物流部門、銀行であれば支店や営業部門、物流企業であれば物流部門など、本業の現場の声や力が強いため、システム部門は力関係的に下になりがちなので、社内に言うことを聞かせにくいという点も、システム開発プロジェクトの障害としては結構大きかったりします。システム部門が本体から外出しされてシステム子会社になっていれば、なおさらです」(9月27日付当サイト記事より)
裁判所はどのように判断するのか
過去には大規模システムの開発中止をめぐって発注元企業とベンダが訴訟に発展するケースもあった。野村ホールディングス(HD)と証券子会社・野村證券は10年、社内業務にパッケージソフトを導入するシステム開発業務を日本IBMに委託したが、作業が大幅に遅延したことから野村は開発を中止すると判断し、13年にIBMに契約解除を伝達。そして同年には野村がIBMを相手取り損害賠償を求めて提訴した一方、IBMも野村に未払い分の報酬が存在するとして約5億6000万円を請求する訴訟を起こし、控訴審判決で野村は約1億1000万円の支払いが命じられた。
テルモは物流管理システム刷新プロジェクトが中止となり、14年に委託先ベンダのアクセンチュアを相手取り38億円の損害賠償を求めて提訴。また、12年に基幹系システムの全面刷新を中止した特許庁は、開発委託先の東芝ソリューション(現・東芝デジタルソリューションズ)とアクセンチュアから開発費と利子あわせて約56億円の返納金の支払いを受けることで合意している。
システム開発が頓挫する場合、原因が発注元、ベンダのどちらにあるのかは判断が難しいが、損害賠償の金額というのは、裁判所はどのように判断するのか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。
「システム開発やソフトウェア開発を業とするクライアントを持つ弁護士にとっては、開発が頓挫した場合の法的紛争について、長年、苦労しています。なぜなら、このような開発は、契約『時』には、“だいたいこんな感じのものを作ろう”という合意しかなく、契約『後』に、要件定義といった“何をつくるか”を少しずつ明らかにしていく作業が行われるという性質があるからです。これに対し、裁判の世界は、あくまでも契約『時』に遡り、当事者は契約『時』において、はたして“何を作る合意があったのか”“当事者は何をしたかったのか”を確定する作業であり、なかなか開発の現場の実態と合致しないところがあるからです。
こういった紛争が長く続いてきたため、経済産業省や(独)情報処理推進機構は『システム開発等の標準契約書』を作るなどして、法的紛争を未然に防ぐ努力をしています。しかし、上記のとおり、どんなに契約書をしっかり作っても、法務部や顧問弁護士がしっかりしている大手の会社同士の契約であっても、今回のような法的紛争が避けられないのが、システム・ソフトウェア開発業界の特徴です。そして、たいていの場合、カネを出す発注者は、なるべく自分の要望を強く押し出してきますし、時に最初に希望していたモノと違うモノを欲したりもするので、仕事をもらうという弱い立場の開発側は、苦労することになるわけです。
今回、日本通運は125億円の損害賠償を請求したとのことですが、今後、当事者間は裁判内で、契約『時』に“何を作る合意があったのか”“当事者は何をしたかったのか”“実際には、何が完成したのか”を確定する作業をしていくこととなります。その上で損害額を確定していくのですが、おそらくですが、『委託料』に相当する金額(システム開発として支払った金額)を損害賠償としたのでしょう。
確かに、大金を支払って、ろくでもないモノが納められたなら、カネ返せと言いたくなるのは当然です。特に、システム開発は『ある用途』のために使えないことがわかれば無用の長物となるので(ほかに転用ができない)、払ったカネを返せという訴訟が定番となるわけです」
(協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表、田中健太/データアナリスト、鶴見教育工学研究所)
●田中健太/データアナリスト、鶴見教育工学研究所
東京工業大学大学院 博士課程単位取得退学。ITベンダー系人材育成サービス企業で、研修開発、実施に従事。クラウド、IoT、データサイエンスなどトレンド領域で多数の教材作成、登壇。リサーチ会社でデジタルマーケティング領域のデータ分析に従事。アンケート、アクセスログ、位置情報、SNS等を組み合わせた広告効果の分析を行った。現在は、フリーランスとして教育の領域で活動。
鶴見教育工学研究所