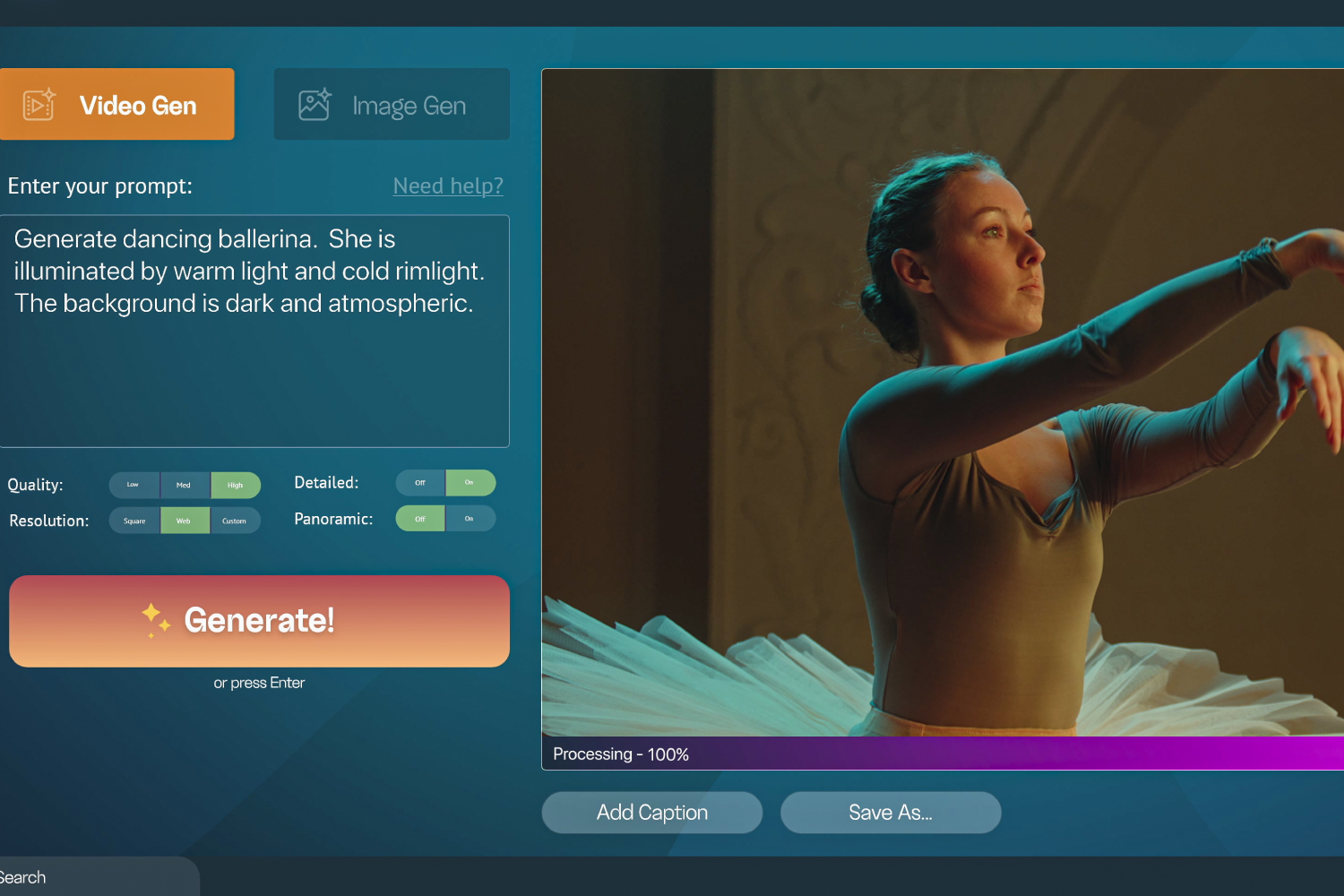労基法違反が横行する意外な理由…時間外割増賃金、固定残業代、管理職は●●
2024.07.02
ビジネスジャーナル

サービス残業や長時間労働の強制など、企業による不当な労働強要がなくならない。なかには労働者本人が気が付かないまま適正な賃金を得られていないといった事例もあるが、経営者が意図的に不当行為を行っているわけではなく、そもそも労働基準法を読んでいないため内容を知らないことが原因となっているケースもあるようだ。具体的にはどのようなケースがあるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
働き方改革関連法によって、今年4月からトラックドライバーやバス運転手など自動車運転者、建設業従事者にも年間960時間未満などの「時間外労働の上限規制」が適用され、中小企業を含めたほぼすべての企業に同規制が適用された。だが、一部企業ではいまだに不当な条件で労働者が働かされている実態があるという。社会保険労務士法人ALLROUND渋谷代表の中健次氏はいう。
「経営者の方が労基法などの労働関連法規の内容を詳しく把握していないことが原因で、従業員が不適切な労働条件で働いているというケースは、肌感覚としては少なくないと感じます。典型的な例としては、月60時間を超える法定時間外労働に対する時間外割増賃金率は50%と定められているにもかかわらず、それを下回る割増率になっていたり、今年4月から労働条件明示事項が追加されたにもかかわらず、必須な事項が雇用契約書に明記されていないといった事例です。36協定で定める時間外労働時間は会社が労働基準監督署に届け出をして初めて効力を持ちますが、会社がきちんと届け出をしないままに、従業員に残業をさせているという事例もあります」
会社と従業員が合意した給与額が、実は法律に違反していることもあるという。
「現在の東京都の最低賃金は1113円ですが、これはアルバイト・パートだけではなく常用含めすべての労働者に適用されます。基本給・固定残業代・通勤手当の合計で給与を設定している場合、最低賃金には固定残業代や通勤手当は含まれないため、時給に換算すると事実上、最低賃金を下回っていることがあります。
『課長は管理職なので残業代の支給対象外』という会社もありますが、『課長だから』『部長だから』という肩書で判断されるべきではなく、労働基準法第41条に規定された『管理監督者』に該当するかが基準となります。なので、『肩書は課長だが、労務管理において経営者と一体的な立場にあるとはいえない』ような“名ばかり管理職”の場合は、会社は残業代を支払わなくてはなりません。このほか、残業代は分単位で計算して支給しなければなりませんが、30分単位で丸めて計算していることもあります」(中氏)
固定残業代分の残業時間を“見込み過ぎている”
この残業代の扱いについては、正しく運用されていないケースが散見されるという。
「当たり前ですが、固定残業代は雇用契約書に『●時間分の残業代が含まれていますよ』と明記し、かつ本当に残業時間が上限時間内に収まっているのかを集計する必要がありますが、それらの基本的なルールが守られていないことがあります。このほか、固定残業代分の残業時間を“見込み過ぎている”というケースもあります。それを超えるとただちに違法になるというわけではありませんが、固定残業代は原則として45時間が上限と考えるのが妥当となっており、それにもかかわらず60時間分の残業が見込まれていたりというケースはたまにあります」(中氏)
会社の業績悪化に伴い賞与の支給がなくなり、支払われるものだと認識していた従業員と会社が揉めることもある。
「賞与は会社の業績に連動する性格のものなので、雇用契約書に『必ず払いますよ』という定めがない限りは、払われないこともあり得ます。なので一般的には『原則、支給あり。ただし支払わない場合もある』という旨が記載されています。そのあたりを会社側がきちんと従業員に対し説明していないとトラブルのもとになります」(中氏)
もし勤務する会社で不当な労働強要があったら?
では、もし勤務する会社で不当な労働強要があった場合、どのような行動をとるべきなのか。
「いきなり労基署に事実を訴えるという方法が必ずしも得策とは限りません。たとえば今の会社に今後も勤務する考えである場合、労基署の調査が入ると会社内で通報者は誰なのかという“犯人捜し”が始まり、自分が会社にいづらくなってしまうという展開も考えられます。経営者に対して『労基署に行きますよ』と強硬な姿勢で問題を指摘して、会社と戦うようなかたちになってしまうのも大変です。単に会社側が法律を勘違いしていたという可能性もあるので、まずは総務部の担当者に棘のない範囲で質問してみるというのも、一つの賢明な方法ではないでしょうか。そのために、普段から総務部と風通しの良い関係を構築しておくことが大切だと考えます」
(文=Business Journal編集部、協力=中健次/社会保険労務士法人ALLROUND渋谷代表)