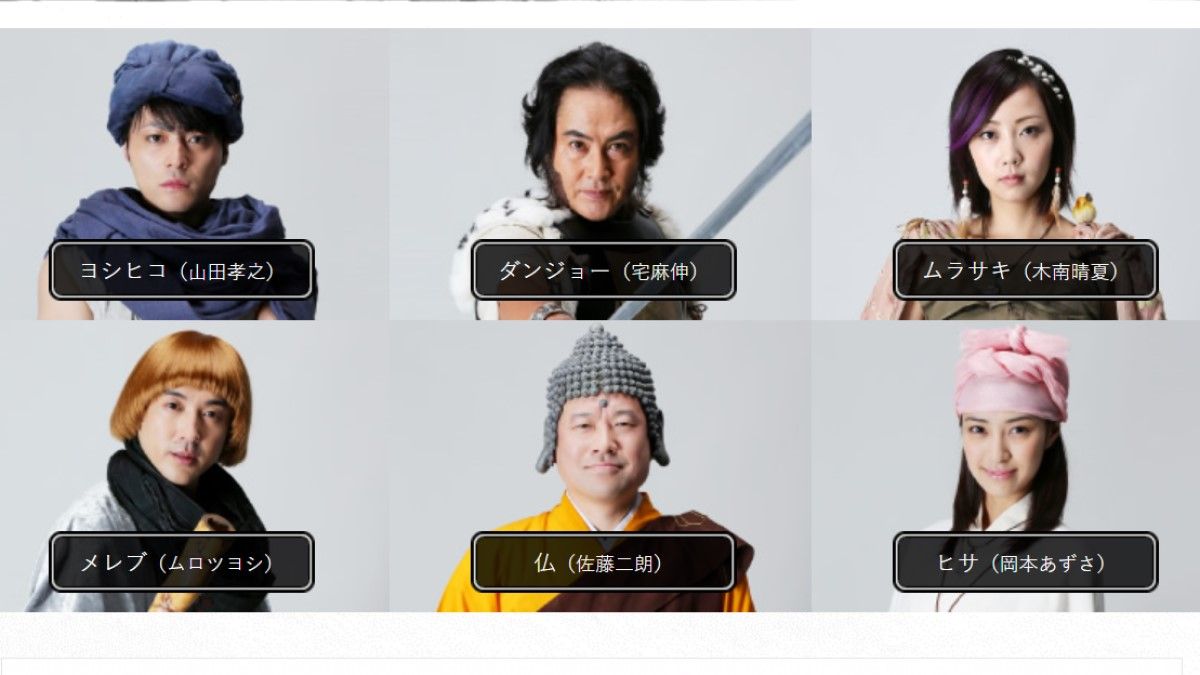
【水島新司先生追悼企画】『ドカベン』2大死闘試合!山田太郎の両親不在の秘密も
2022.02.02
ビジネスジャーナル
「なぜ山田の両親がいないのか?」「なぜ里中はアンダースローなのか?」、そして「なぜ神奈川県生まれの岩鬼は関西弁をしゃべるのか?」――。4人の過去を明かしつつ、最後に殿馬がサヨナラホームランを放ち明訓に勝利をもたらすことで、4人全員が背負った過去の忌まわしき記憶に別れを告げたという構成だ。
それぞれの悲しい過去と、それを乗り越えた4人の衝撃のエピソードが試合の白熱度に拍車をかけ、すべて重なり合って引き出された熱戦。その上で劇的な幕切れで優勝するストーリーに感動した読者も多かったのではないだろうか。
高校野球史上初、3季連続優勝の前に立ちはだかる弁慶
もうひとつは、山田たち明訓四天王の高2の夏の甲子園、2回戦の弁慶(岩手)戦である。高1の夏、高2の春と甲子園を連覇した明訓は、高校野球史上初となる夏・春・夏の3連覇を狙って甲子園に乗り込んできた(ちなみに現実の高校野球でも3季連続優勝は達成されていない)。
その明訓の前に立ちはだかったのが、エース・義経光と主砲の武蔵坊数馬を擁する弁慶だった。特に武蔵坊は病に倒れた岩鬼の母や、左肩の故障で苦しんだ江川学院(栃木)のエース・中を気功のような不思議な力で治すなどしており、ただならぬ雰囲気を漂わせている。
試合の数日前、弁慶のエース義経はテレビのインタビューで明訓戦での「初球ど真ん中ストレート」を予告。それを観た明訓の土井垣将監督は悪球打ちの1番・岩鬼と4番・山田の打順を入れ替えたのである。その目論見どおり、山田はプレーボール・ホームランを放ち、1点を先制した。
ところが、これが弁慶のワナだった。“塁に出る”岩鬼と“走者を返す”山田が逆になったため、攻撃のリズムが崩れてしまったのである。追加点が取れない明訓だったが、エース里中の好投でこのまま逃げ切るものと思われた。だが、迎えた7回裏の弁慶の攻撃、ランナー1塁で打席には武蔵坊。明訓ベンチは敬遠を選択したが、このボール球を武蔵坊のバットが捉える。打球はライトへの逆転2ランとなり、一転して明訓が追う展開となってしまった。
追い詰められた明訓の最後の攻撃は8番から。幸運な打順の巡り合わせで3人目の打者は山田であった。期待通り、2死無走者から山田はライトを守る武蔵坊の頭上を遥かに越えるソロホームランを放ち、明訓が同点に追いつく。
追いつかれた弁慶は9回裏、1死から3番・義経と4番・武蔵坊が連打で1・2塁と、一打サヨナラのチャンスをつくる。それでも義経と武蔵坊以外にはほぼ打たれていない里中だけに、延長戦突入が濃厚と思われた。
続く5番の安宅の打球はセンター前へと抜けようかという当たりであったが、これをセカンドの殿馬が横っ飛びで好捕、二塁ベースカバーに入ったショートの石毛幸一にトスして一塁走者だった武蔵坊を封殺。さらに石毛は一塁でダブルプレーを狙うが、その送球を武蔵坊が自らの額で受けて阻止。
この併殺崩れの間に二塁走者の義経はサヨナラのホームを狙うが、こぼれ球を拾った殿馬が渾身のバックホーム。タイミングは完全にアウトだったが、義経が大ジャンプ“八艘飛び”を繰り出し、捕手・山田の頭上を抜きホームイン。弁慶高校の劇的サヨナラ勝ちで、無敗の明訓がついに敗れることとなった。
額に送球を受けた武蔵坊はグラウンドに倒れ、再起不能になる。この後、二度と野球をすることはなかった。この“弁慶の立ち往生”が試合を決めるポイントとなったワケだが、実は明訓は負けるべくして負けている。
それは前述した1番・岩鬼と4番・山田の打順入れ替えである。山田が1番として出塁しても、鈍足すぎて塁を進めることができず、逆に4番の岩鬼は悪球打ちの弱点を抱えており、ランナーが溜まっても真ん中直球勝負さえしておけば安全だからだ。
“勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし”という言葉がある。明訓も実際に不思議な形で勝ちを拾った試合もあったが、唯一の敗戦を喫したこの試合は“あるべき姿”を崩してしまったことが敗戦につながってしまった。常勝・明訓にして負けに不思議の負けなし、を体現した一戦となったワケである。
今回取り上げた試合は甲子園大会限定だったが、県大会や関東大会でも数々の名勝負が描かれている。山田が記憶喪失のまま、途中出場した1年秋のクリーンハイスクール(千葉)戦、“ルールブックの盲点の1点”が描かれた2年夏の白新(神奈川)戦などは特に忘れがたい。その激闘は今もなお、色褪せずに多くの野球ファンの脳裏に刻まれている。
(文=上杉純也/フリーライター)


























