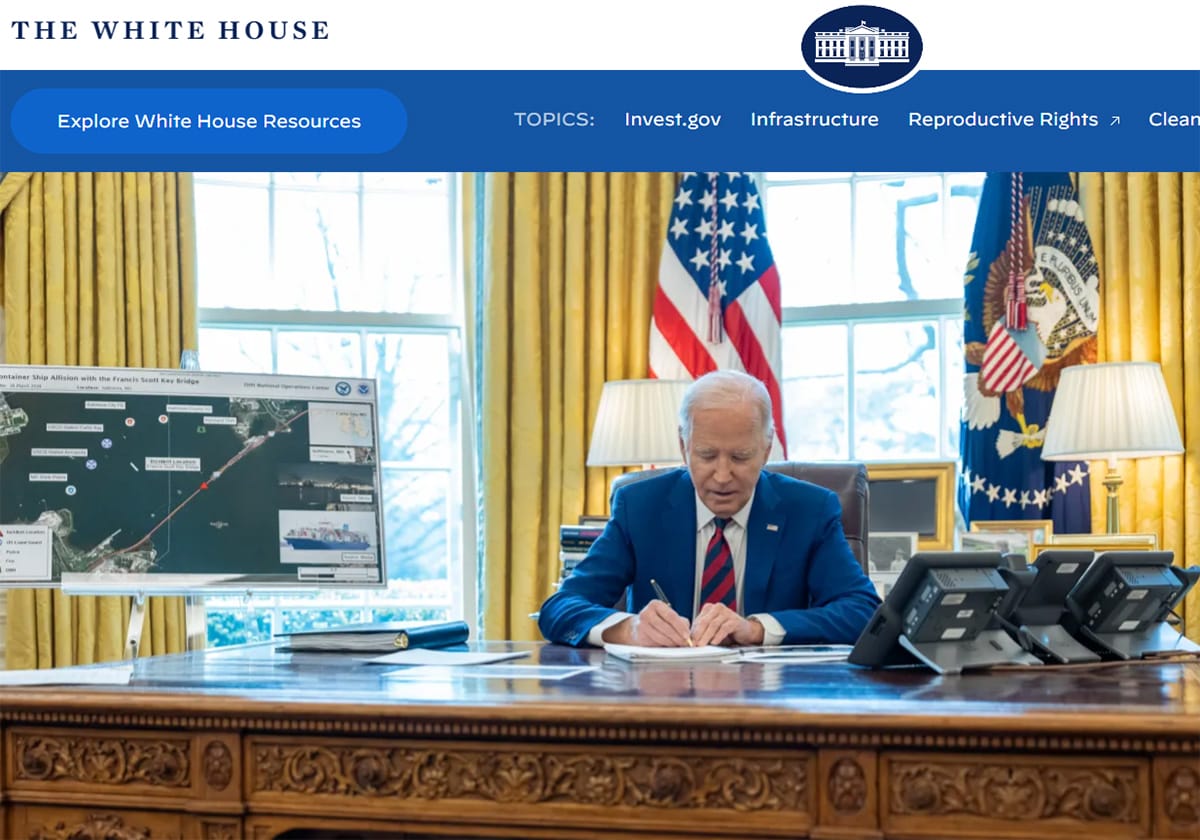
ロシア、よぎるソ連崩壊の悪夢…原油埋蔵量「枯渇」シナリオが現実味、寿命20年説も
2021.05.08
ビジネスジャーナル

4月末の原油価格は堅調に推移している(1バレル=60ドル台半ば)。インドやブラジルでの新型コロナウイルス感染拡大をめぐる懸念はあるものの、堅調な米経済指標をはじめとする原油需要の回復期待などが支援材料となっている。
コロナ禍で低迷するリスクを抱える原油価格を下支えしてきたのは、OPECとロシアなどの大産油国で構成される「OPECプラス」である。OPECプラスは4月27日、共同閣僚監視委員会の会合を開催、「世界の原油需要の回復見通しに変わりはない」と判断して、5月から7月にかけて協調減産を段階的に縮小していく方針を確認した。
OPECプラスは現在、サウジアラビアの自主減産(日量100万バレル)を含めて日量約800万バレルの減産を実施している。今回の決定により、OPECプラスの減産幅は5月、6月それぞれ日量35万バレル、7月は約44万バレル縮小し、サウジアラビアの自主減産幅は5月に25万バレル、6月に35万バレル、7月に40万バレル縮小することになる。これにより7月までにOPECプラスの減産規模は日量580万バレルとなる計算である。
OPECプラスの今回の増産は、「原油価格の上昇が国内経済に悪影響をもたらす」と懸念する米国の意向を踏まえ、サウジアラビア主導で決定されたが、4月初めにこの方針が打ち出された際には原油価格の下落が懸念されていた。
OPECプラスは、「今年の世界の原油需要は日量約600万バレル増加する」との強気の見通しを維持しているが、次回の閣僚級会合は6月1日に開催し、7月と8月の生産水準を検討するとしている。
OPECプラスの協調減産は2022年4月まで続くことになっているが、ロシア第2位の石油会社ルクオイルの幹部は26日、「OPECプラスが目指す石油市場の均衡化は長期的な取り組みになる。気候変動をめぐる新たな現実を踏まえれば、恒久的なものになるかもしれない」との見解を示した。
ロシアの原油生産、開発条件が急速に悪化
新型コロナウイルスのパンデミックは、脱炭素社会への流れを加速している。4月20日付本コラムで「世界の投資家は原油などの化石燃料は今後『座礁資産(社会の環境が激変することにより、価値が大きく毀損する資産)』となる可能性が高いとみている」ことを紹介したが、世界の石油会社も未来のエネルギー候補と目される「水素」の開発を真剣に検討し始めている。
その中でもっとも意欲的なのは、イタリアの石油大手Eniである。同社は昨年、再生可能エネルギーへの移行と石油・ガス生産の段階的な縮小に向けての大規模な事業改革案を発表した。その内容は267億ユーロに上る負債をバランスシートから切り離し、その上で資本を調達し、将来の会社の基盤となる再生可能エネルギーと低炭素事業を構築するというものである。その一環として今年4月には西アフリカと中東の石油・ガス事業を分離させ、新たな合弁会社を設立することを明らかにしている(4月21日付ロイター)。
原油が今後「座礁資産」とみなされるようになれば、中長期的に価格が下落することは避けられない。「価格が下がれば収入を確保するために増産しなければならない」という悪循環が起き、世界の石油会社は今後「冬の時代」を迎えることになる可能性が高いが、なかでも深刻な問題を抱えているのはロシアの石油産業のようである。
ロシア天然資源・環境省のキセリョフ次官は4月、政府機関紙であるロシア新聞のインタビューで「ロシア産原油の可採埋蔵量は58年分あるとされているが、そのうち現在の条件下で利益が出るのは19年分のみである」と発言し、話題を呼んでいる。


























