
「全部嫌になった」角田光代、34年目の働き方改革
2024.06.27
東洋経済オンライン
依頼してくれた会社はどこか。出版社なら、載せるのが週刊誌なのか、文芸誌なのか。書いてほしいのはどんなジャンル、テーマの小説なのか。そういう側面から決めていくケースが多く、ときには「興味が湧かないな」と思うテーマを扱うこともありました。
――そういった不本意な状況は今後なくなるわけですが、では逆に、今後もご自身のスタイルとして変えないであろうことは?
どこに目をつけるかを考える際、毎日暮らしている中で社会に対してなんとなく抱く”違和感”みたいなものを大事にしていて、その感じは今後も変わらないだろうと思います。
――近年ではドラマ化、映画化をめぐって原作者と制作者がトラブルになる事例が出ています。角田さんの作品にも映像化されているものは多数ありますが、どう感じますか。
作品の二次使用については本当に人それぞれ考え方が違うので、そこは原作者の考えを尊重しなきゃいけないと思っています。
私の場合は二次使用にまったく関わっていないんですね。預けたら預けっぱなし。でも、関わりたい人もいるし、どちらが正解というものではない。作った人の気持ちが尊重されるべきでしょう。
――作家にとって、自分の作品は子どものようなものだとも聞きます。角田さんはどう折り合いをつけていますか。
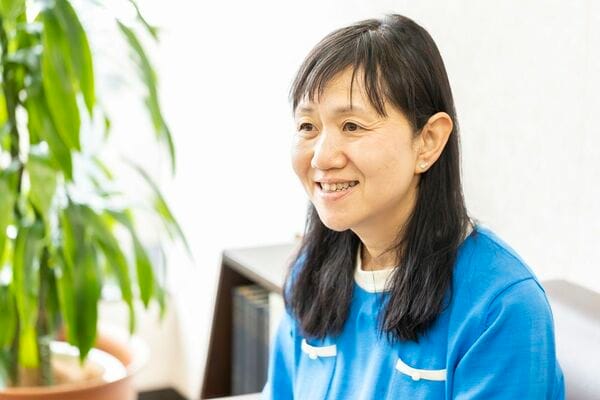
角田光代(かくた・みつよ)/1967年生まれ。1990年「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。著書に『対岸の彼女』(直木賞)、『八日目の蝉』(中央公論文芸賞)など。2015年から5年をかけて取り組んだ『源氏物語』の現代訳では読売文学賞受賞(撮影:今井康一)
子どものような感覚は、私にはないかもしれない。小説を書いて世に出したとき、「メッセージは何ですか?」とよく聞かれますが、私にはとくにない。ただ書いただけなんですね。読み手が10人いれば受け取るメッセージは10通りあるのが当然と思っています。
読み手が「つまらない」「クソみたいな本だ」と言うのも、自由だと思う。せっかく書いた私の本を「クソ」と言われたらそれは傷つきますけど、「クソじゃないよ」と私が訂正して回ることはできない。そこに関してはしょうがないというか。
映像化についても、例えば映画と小説って、まったく別物だと思っています。原作ありきで映画を見た人、あるいは映画を先に見て原作を読んだ人が「がっかりした」みたいな感想を漏らすことがよくありますが、たぶんその観念が、私には欠けているんだと思います。
書いているときにまったく絵が浮かばない
――『八日目の蟬』の映画版を見た角田さんが号泣されていたというエピソードを聞きました。書いたのは角田さんじゃないか、展開もすべて把握しているじゃないか(笑)と思いました。
作家によって、書いているときに絵が浮かんでいる人と、そうでない人がいるんです。前者の人は、主人公は女優さんだとこの人、みたいに、ぱっと名前が出てきたりする。でも私は真逆で、書いているときにまったく絵が浮かばないタイプなんです。
なので映像として見たときに、本当にびっくりするというか、「生きてる!」と感動してしまいます。主人公を誰が演じていても「ぴったりだ!」と思っちゃう(笑)。
『八日目の蟬』でいうと、冒頭、主人公は赤ちゃんを抱いて逃げています。映像で見ると初めて、赤ちゃんに重さがあることを感じる。それを抱いて、自分の体を駅まで運んで、逃げているところを見ると、もうわーっと泣けてきちゃって。こんなに大変なことなんだなって。
でももちろん、私と違う人もいて、映像化するならキャスティングなどまでしっかり関わるという人もいる。どちらがいいという話ではないです。


























