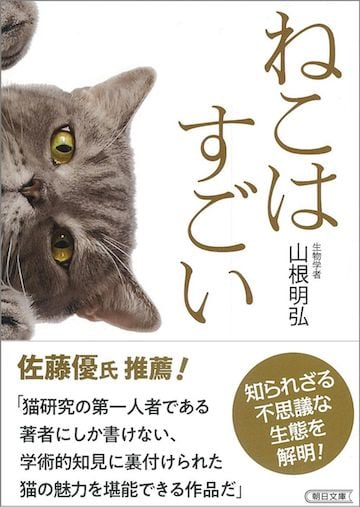江戸時代に今をはるかにしのぐ猫ブームがあった
2022.03.08
東洋経済オンライン

江戸・明治の猫の浮世絵200点(於七尾美術館)(写真提供:朝日新聞社)
このような面白すぎるねこの浮世絵を次々と世に出すことができたのは、もちろん作者である国芳自身が無類のねこ好きだったことにもよりますが、何よりも、たくさんの江戸の庶民たちが、これらのねこの浮世絵を喜んで買ったからです。いつの時代も、売れないものはつくられません。このことからも、当時の人々は、現在のわたしたちが想像する以上にねこ好きで、ねこブームの真っただ中にいたことがうかがい知れます。
さらに、国芳の作品のなかには、当時の人気歌舞伎役者たちの顔を、ねこの顔に模した絵を、うちわにしたものまであります。当時の歌舞伎役者といえば、現在のアイドルのようなもの。人気グループのコンサートなどでは、そのアイドルの写真を貼ったうちわをつくって、会場に持っていくそうです(うちの娘も、コンサート前にせっせとつくっていました)。
しかし、そのファンがいくらねこ好きであったとしても、アイドルの顔をねこの顔にしたうちわを持っていくことなどはありえません。当時は天保の改革などにより贅沢が禁じられ、歌舞伎役者の浮世絵は禁止されていたそうです。それならその代わりとして、なぜ身近な存在であった「いぬ」の顔や、顔形が人間に近い「さる」の顔にはせずに、「ねこ」の顔にしたのでしょうか。
江戸時代の歌舞伎役者のファンの間で、ねこ顔にした役者のうちわが出回っていたところに、現在の「ねこブーム」とはとても比べることができない当時の熱狂ぶりを、わたしたちは垣間みることができます。
幕末前後に日本のねこ文化が本格化した
幕末から明治の初めにかけても、このねこブームは続きます。この時代になると、子ども向けの「玩具絵(おもちゃえ)」といった、すごろくや、切り抜いて遊ぶメンコやカルタ、紙模型、それに着せ替えというものもありました。いまのようにゲームなどない時代、子どもたちは手先と想像力を最大限に使って、工夫しながら楽しく遊んでいました。
その玩具絵のなかには、ねこを擬人化したものも多く見られます。なかでも、ねこの全身姿とさまざまな衣装を切り抜いて遊ぶ着せ替えは、現代のわたしたちには「なぜ、人の人形ではなく、ねこなんだろう?」とも思えます。当時の人々にとって、ねこの着せ替えは、まったく違和感がなかったのかもしれません。それほど、ねこは当時の人々にとって、身近で特別に愛すべき動物だったのでしょう。
幕末前後の空前のねこブームによって、ねこは日本の文化のなかにさらに深く刻み込まれ、現在に至っているものと思われます。海外からの旅行者が、日本のねこ文化に引かれるのは、これが単なる一過性のブームなどではなく、時間をかけて熟成された本物の文化であることを、鋭く見抜いているからなのだと思います。
わたしたちは誇るべきこの日本のねこ文化を、もっと自信をもって海外に向けて発信してもいいのかもしれません。