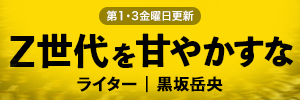翻訳から始まったビジネス書誕生秘話

なぜ翻訳から始まったのか
日本にも井原西鶴の「算用・始末・才覚・信用」や近江商人の「三方よし」などの立派なマネジメントの教科書はあったのだが、当時の日本人はそちらにはあまり注目せず、もっぱらアメリカ産マネジメントのほうをありがたがった。
その理由のひとつには、当時、日本のビジネスパーソンに商人出身者が少なかったことがあろう。戦前は日本人のほとんどが農民だった。戦後になってもしばらくこの構造は変わらない。農業に化学、生物学は必要だが、マネジメントは要らなかった。こう書くと些か語弊があるが、まあそうだ。
「算用・始末・才覚・信用」は古典であるし、「三方よし」も一部の老舗の商人に伝わる家訓だったため、農民から経済発展に伴ってビジネスパーソンにスライドしていった当時の日本人に縁はなかった。したがって、ほとんどのビジネスパーソンは西鶴も近江商人も知らなかったのである。しかし、ここでもう一つの疑問が浮かぶ。
戦前の日本には、マネジメントの原理主義組織である軍隊があったではないか。軍隊のマネジメントを企業に移すことは可能だ。事実、欧米の組織も軍隊組織の応用である。確かにそうだ。だが、日本の軍隊は負けた軍隊である。しかもかなりイメージが悪い。かたやアメリカは戦勝国であり、経済でも輝く世界ナンバーワンの国である。マネをするならアメリカ式のほうがよいとなるのは当然だろう。当時といえども、もし社長が「我が社は日本軍式のマネジメントを行う」と宣言したら、たちまち社員の半分はいなくなってしまいかねない。
初期ビジネス書はワーカーのための本ではなかった
1960年代はビジネス書の誕生から成長へと向かう時代である。企業がもっと儲かるための教科書として、アメリカ式マネジメントの翻訳が出版されたのが、ビジネス書のスタートだった。企業がもっと儲かることに一番熱心なのは経営者だ。初期ビジネス書の読者は経営者である。この段階では、まだ今日のビジネス書のような幅広い読者層を獲得できていない。
しかし、経営者だけが読者ではビジネス書に成長はない。では、なぜビジネス書が成長できたのだろうか。経営者がマネジメントの本を読むと、そこには企業が儲かるためには社長ひとりが指揮を執るワンマン経営では成長に限界があると書いてあった。経営者は、自分だけがマネジメントを学んでマネしても効果は薄く、工場長や支店長、課長にもマネジメントを学ばせなければならない。彼ら幹部のマネジメント能力こそ、企業がもっと儲かるために重要なのだということを知ったのだ。
そこで経営者は、管理者、幹部にマネジメントを学ぶように働きかけることになる。企業経営者が自分のところの社員を読者にしてくれたのである。企業がもっと儲かるようになるために管理者、幹部に読ませるよいマネジメントの本はないか。そして登場するのが『こんな幹部は辞表を書け』(畠山芳雄 日本能率協会 1968年)である。
工場長、支店長は役職に就任したからといって安閑とはしていられなくなったのだ。企業がもっと儲かるためにセミナーに行って勉強し、この本を読めと与えられる。企業幹部にとっては受難の時代の始まりである。この頃からいろいろと締め付けが厳しくなる。この時代のビジネス書はワーカーのための本ではない。部下を持つ人の部下を動かすための本である。個人の自己啓発という切口はなく、すべての結果は企業の成果に帰納していくことが基本だった。
この点では微妙に戦前の滅私奉公的色が付け加えられている。恐らく彩色したのは日本人作家だろう。アメリカ人に滅私奉公の思想はない。すべて結果は企業の成果に帰納していく以上、本の購入費は企業持ちが多かった。企業はもっと儲かるために社員教育に予算を惜しまなかったのである。この傾向は1973年の第一次オイルショックまで続く。
組織にトップはひとりだが、中間マネジメント層は何人もいる。それらの企業幹部を読者に取り込んでいったことは、ビジネス書の成長に大きく貢献したことは疑いない。出版社も中間マネジメント層を取り込んだところは成長し、経営書にこだわったところは出遅れた。ビジネス書は組織の中間層に浸透したことで、ビジネス書らしい性格を帯びてくるようになる。それは、より便利に、よりわかりやすく、というビジネス書の基本的な性格である。
1970年代になると、60年代にマネジメントを学んだ人が徐々に作家となって現れ始める。この辺が「ビジネス書の青春時代」の始まりだろう。作家が増えるに従い、この頃からビジネス書も少しずつテーマが細分化してくるとともに、表現方法も多様化する。まだ印刷技術の制限があったため、今日ほどのバリエーションは出せなかったが、当時の書籍を見るとそれなりに工夫の跡がうかがえる。
日本人作家が増えたとはいえ、この時代のビジネス書の作家は需要のわりに数が多くはなく、大ヒットは出なくても安定的に本を出せる環境だった。いまから思えば作家にとってけっこう恵まれた時代だったといえる。
次回に続く
オススメ記事
まだ記事はありません。「ビジネス書業界の裏話」 記事一覧
- 第50回 出版界の再編と作家の未来
- 第51回 ビジネス書作家の在り方とは
- 第32回 翻訳から始まったビジネス書誕生秘話
- 第31回 実績ある作家と新人作家、出版に有利なのは?
- 第30回 意外に奥深いビジネス書作家と講演会の関係