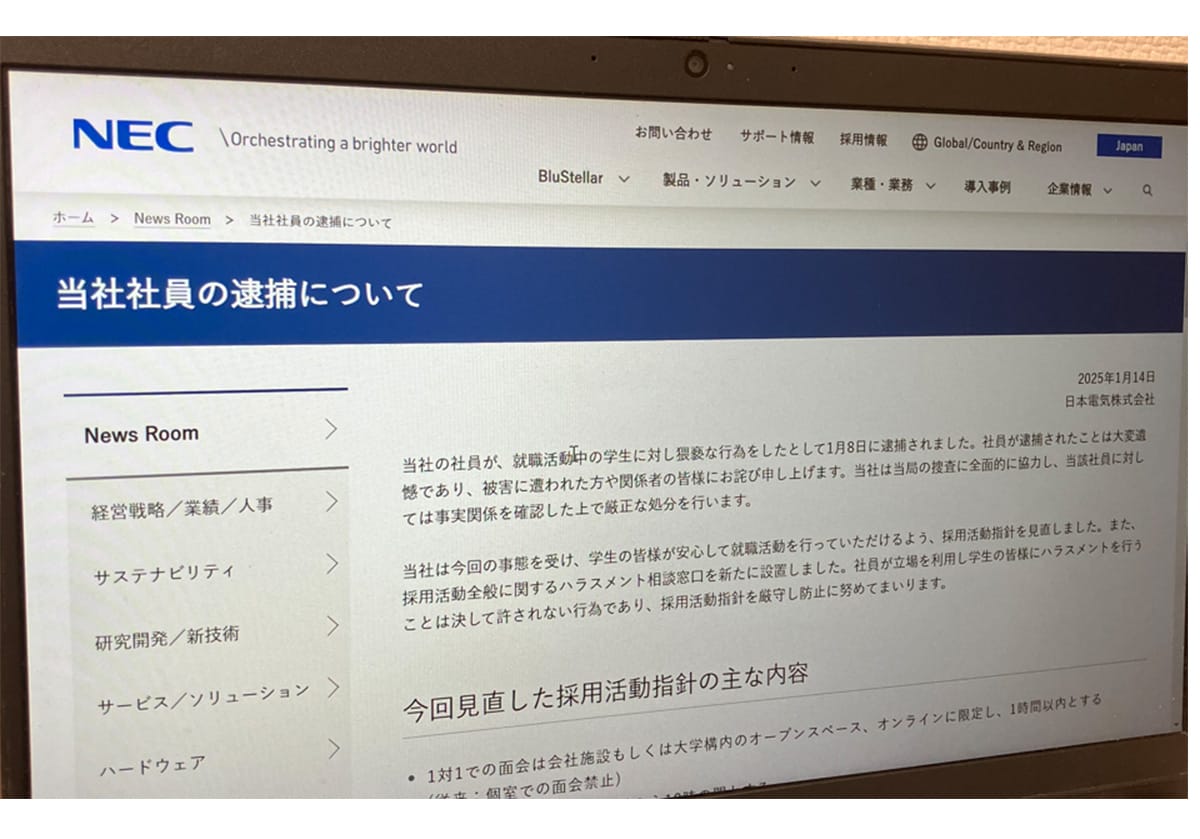世界の大富豪たちを唸らせた名執事の極上サーヴィス哲学

世界の名だたるセレブ、大富豪たちに最高の満足を提供する、日本バトラー&コンシェルジュ代表、執事の新井直之さん。エグゼクティブを唸らせる「執事によるフルオーダーメイド」の極上サーヴィスは、どのようにして生まれたのか。「お客さまの感情に飛び込み、提案し、満足していただくことが執事の仕事」という新井さんの、サーヴィス哲学の原点と、仕事にかける想いを伺ってきました。
(インタビュー・文/沖中幸太郎)
無茶振りは日常茶飯事!?
大富豪を満足させる極上のサーヴィス
 |
| 新井直之(あらい・なおゆき) 執事(バトラー) 日本バトラー&コンシェルジュ株式会社代表取締役社長 東京都出身。大学卒業後、米国企業日本法人勤務を経て、日本バトラー&コンシェルジュ株式会社を設立。国内外の大富豪、超富裕層を顧客に持つ同社の代表を務める傍ら、おもてなし、富裕層ビジネス、顧客満足度向上に関する講演・研修、コンサルティング、実用書の執筆、数々のドラマや映画の執事監修、所作指導をおこなうなど、執事による独自の「サーヴィス哲学」の普及につとめている。 |
――(スーツ姿を見て)いつも、その格好でお仕事されるのですか。
新井直之氏(以下、新井氏):今日は執事を一番イメージしていただきやすい服装で参りましたが、いつもこうした格好をしているわけではございません。執事というと、マナーや所作の方に目が向かれがちですが、お子様の送り迎えなど、場合によっては、シャツにジーンズというTPOに合わせた姿でお仕事をすることもあります。
私どもは日常生活から冠婚葬祭、旅行、留学の同行、プライベートな催しまで、お客さまになり代わり、あるいは補佐役として、あらゆる事柄に対してご要望にお応えしております。しかし一番大切なのは姿や形ではなく、ご主人さまと、そのご家族に満足していただくことです。そしてそれが、どんなご要望であってもお応えするのが、執事の仕事であり喜びでもあります。
ある時、外国のご主人さまが本国へ帰る直前のお土産に「お気に入りの飲料500本とフーセンガム1000個」をご要望されました。そのオーダーを受けたのが、成田出発の2時間前。スタッフをフル動員し、途中にあるお店というお店に片っ端から連絡し、どうにか確保してお渡しすることができました。さすがに想定外でしたが、こうした「想定外のご要望」にも、ご満足頂ける対応をするのが執事の務めです。
このようにフルオーダーメイドのサーヴィスとは、単にご要望をお受けするのではなく、どのようなことがあっても対応できるよう、常にご主人さまの行動に気を配り、仮説を立て準備をしておくことです。この時は、なんとか間に合わせることができましたが、どうしても難しい場合は、それに代わる提案をしなければなりません。ご主人さまの真意を汲み取り、潜在的な満足につながる提案が必要不可欠です。そういった意味も込めて、私どもは無料の響きがある「サービス」ではなく、すべてのご要望に高いレベルでお応えするという意味で「サーヴィス」と表記して区別しています。
人に貢献する喜びを仕事にしたいと始め、まもなく10年になります。こうしたお仕事をさせていただくまでに、さまざまな経験を通じて貢献することの喜びを学んで参りました。
コンビニのレジと出版社のクレーム処理で学んだ
人に喜ばれる幸せ
新井氏:私は東京都北区の王子出身で、両親はガラス工事の商売をやっておりました。控えめで、いつも脇役。裏方で支えるというのが、幼い頃からの私の性格でした。中学生の頃はバドミントン部のキャプテンもやっていたのですが、キャプテンとは名ばかりで、サボり気味の生徒に声をかけたり、試合をおこなうために他校と調整したりと、そこでも裏方的存在でした。けれど、それが嫌というわけではなく、むしろその役割を楽しんでいました。高校は定時制も備えた所に通っていたので、夕方五時半には部活も終え、それからはコンビニエンスストアでアルバイトをしていました。
働くという経験は新鮮でした。最初はただレジを打つだけでしたが、次第に顔を覚えていただけるようになり、その人たちから「ありがとう」という言葉をかけられるうちに、「もっと人の応えたい」と思うようになりました。コンビニのような、ある種画一的な商品、サービスが求められているような場所では、アルバイト店員はレジ係以上のことは求められていないかもしれません。しかし、できる範囲内で相手が喜ぶことをしたいと、積極的にお客さまとコミュニケーションをとるようになりました。
私がいる時にしかおでんを買っていかないおばあさんや、買った商品の中からジュースの差し入れをくださるおじさん、バレンタインデーにはチョコレートをくださるお姉さまなど、そうした馴染みになっていただいたお客様さまからかけていただく優しい言葉。そこで働くことの喜びを教えていただきましたね。
コンビニは売っているモノでは差がつきにくい業態ですが、高校生なりに、人と人のふれあいという「見えないものの価値」「コミュニケーションの大切さ」を、実感しました。この時の経験は、その後の私の働き方に大きく影響を与えました。
――執事を目指すにはぴったりのキャリアですね(笑)。
新井氏:実は私、スーツを着て大きな会社でバリバリ仕事をする、当時流行っていたヤンエグ(ヤングエグゼクティブ)に漠然とした憧れを持っていたくらいで、それ以上の、将来への明確な目標は持っていませんでした。当然、執事という仕事は考えてもいませんでしたし、むしろそうした職業があることすら知りませんでした。
明治大学の政治経済学部へ進みましたが、大学時代ももっぱらアルバイトでした。求人情報誌に載っていた大手出版社の「編集補助」という仕事でしたが、入ってみると実際はクレーム処理の部署でした。付録の不備、書籍の乱丁・落丁への対応がおもな仕事で、電話やお手紙で、読者からのさまざまな苦情をお受けしていました。
「付録の部品が足りない」「落丁があった」などというご連絡があれば、午前中に処理をして郵便でお送りしていましたが、特にお急ぎの場合はバイク便を手配して当日中に届けていました。中には、苦情というよりお願いに近いものもあり、「付録の組み立て方が難しくてわからない」という読者のために、付録を昼休みに作って送るということもやっていました。
――どうして、そこまでできたのでしょうか。
新井氏:お客さまからいただく言葉の裏にある「想い」が見えてしまったのです。お小遣いを貯めて本を買ってくれた子どもたち、孫が喜ぶ顔を見たくて本をプレゼントしたお祖父さま、お祖母さま、子どもの成長を願って買われたご両親。そんな思いをを電話越しに聞いているうちに、心に火がついてしまって。それでコンビニのときと同じように、言われたこと以上にやり過ぎてしまいました。朝から晩まで働いて、帰宅する頃にはクタクタでしたが、不思議なことにそこに疲労感はなく、むしろ幸福感でいっぱいでした。
「人はもしかすると、誰かに喜んでもらいたくて働いているのではないか」と、薄々感じるようになりました。社会人になる前に、このアルバイトで「誠実に対応すること」と、「その喜び」を学べたのは、とても幸運なことだったと思います。