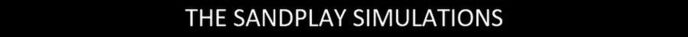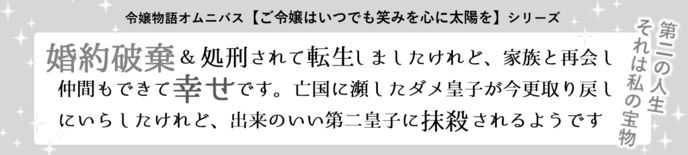18 / 35
Simulation Main thread
一、松の高官
しおりを挟むユタの胸を支配したのは、どす黒い憎しみだった。
(ふざけるなっ……、ふざけるな!)
目に、手に、そして口にも布をあてがわれ、脚はそれぞれの別の女が押さえている。全く身動きができない。うなり声を上げ左右にもがくと、馬乗りの女から平手で殴られた。
「黙ってりゃあ、気持ちよくしてやるよ。大人しくしてな」
(やめろ、離せ!)
頭の中は怒りと恐怖でまだらに染まった。
なぜ、自分がこんな目にあわなくてはならないのか、男というだけでどうしてこのような理不尽と暴力にさらされるのか。悔しさと悲しさに支配されないためには、怒り、そして耐えるしかなかった。
「あたしたちはずっとお前に狙いをつけていたんだ。思った通りちょうど良さそうな育ち具合だ。どれ、勃たせてみようか」
くすくす笑いにぞっとする。
(くそ、死ね、死ね、死ね……!)
いちもつを握られ、恐れとくやしさで奥歯がきしむ。
避けられない暴力に屈服するしかない現実をかみしめたとき、奥の戸が開き、天の助けのように光が差し込んだ。
「なにをしている」
とたん、三人の女たちがしどろもどろになり、青年を解放した。
「調べも済まぬ子どもに手をつけるとは何事だ」
布越しに感じる光の先に、凛と響く女の声。
(だ、誰……?)
「行け、さっさと仕事に戻れ」
バタバタと足音が去った後、静かな気配が傍らに立った。目隠しを外されると、見たことのない官吏がいた。
赤や緑の飾り襟のついた領巾、艶やかな宝髻に結い上げられた黒髪。五色に輝く首飾りと耳飾りは、高貴な官吏の証。齢は二十代中ごろだろうか、目元の涼しく口元の引き締まった、美しい女だった。
口輪と手をほどくと、官吏はあたりを見わたした。
「衣は?」
「……」
ユタが答えずにいると、官吏が領巾を脱ぎ、自分に着せようとする。ありえない。慌てて後ずさって膝を折り、頭を床に押しつけた。
「その格好で宿まで戻る気か?」
「……」
「うん?」
「……」
「どうした、口が利けぬのか?」
頭を床につけたまま、喉から震える声を絞り出す。
「お、恐れながら……、三たび聞かれるまでは、口を利くなと……」
「ああ……そうだったな。ひとりで帰れるか? 衣はあるのか?」
「……」
「おい、三度も同じことを聞かせる気か」
びくりと体がこわばった。指先がじっとりと床を濡らすのを凝視しながら、慎重に口を開く。
「……お、お心づかい、か、感謝いたします……」
しばし沈黙が流れたかと思うと、官吏が近づいてきた。
(しまった、機嫌を損ねた……!)
腕を掴まれ身体を引き上げられた瞬間、殴られる覚悟で目をつぶった。
振ってきたのは、柔らかな薄い綿布の感触と、布に染みこんだ香りだった。
(え……っ?)
「ほら、行け」
出口に向かって顎で指す。
(な、なにが起こっているんだ……)
混乱した。位の高い官吏が、なんの得てもない滓に、このような温情をかけるなどあってはならない。滓とは、淘汰された男たちの呼び名である。種をふるいにかけて落ちたもの、すなわち滓だ。
(官吏様のお袖に泥を跳ねて殺された男がいたじゃないか。まさか、僕はここを出たら処刑される……!)
よぎった不吉な予感に、ただひれ伏すしかなかった。
「お、お許しください……」
「……」
青年は悟った。
なんと短い人生……! 生まれて十七年余り。思えばいいことなんてひとつもなかった。いや、ある。マナホ。つがいにすると約束してくれた。ああ、マナホ……!
鼻をすすりながら涙をぬぐうのを、官吏が見つめている。
「なにを泣いている?」
(ああ、もうこれで僕は終わりだ。マナホに会いたい。もうきっと会えないのだ……)
「また同じことを尋ねさせる気か」
「お、おゆ、るしください……」
「別に怒っていない」
「……で、でも、お召し物が穢れて……」
「お前は今湯に入ってきたばかりなのだろう? 別に汚れていない」
(……ええ……?)
涙目を見開くと、官吏はいたって静かに見返してきた。
女の中には男というだけで汚らわしいと厳しく当たる者もいるというのに、この人は、本気で言っているのだろうか。信じられないことはさらに起こった。
官吏の手が領巾を引き寄せると、包むようにユタの首元で重ねた。その布の端で濡れた目と鼻を拭いたのだ。
「お前、ちゃんと仲間のもとに帰れるか?」
(……か、帰れます)
驚きのあまりに、心の内では答えたが、声にはならず、こくんと首を縦に振った。
「では行け」
立ち上がり、言われるがままに部屋を出た。振り返ると、未だ戸口の前の官吏と目が合った。木造りの湯屋の角を曲がる前にもう一度振り向くと、官吏はまだそこに立っていた。
官吏がそこからが立ち去ったのは、青年が角の先に消えるのを見届けたあとだった。
角を曲がると、湯屋の入り口の前でマナホが待っていた。
「ユタ、探したんだぞ! それ……、どうしたんだ?」
ふたり分の湯あみ道具を下に置くと、ユタを抱えるようにしてその領巾を見つめる。
「か、官吏様に助けられたんだ……! 役人に捕まって、犯されるところだった」
さっと顔色を変えたが、改めてユタの無事を確かめると、ほっと息をついた。
「そ、そうか、無事でよかった……!」
齢四十を過ぎたあたり。やや小柄だが均整の取れた体格に、優しそうな顔。長い下げ髪を後ろで束ねている。清潔だが、飾り気のない麻の貫頭衣の胸の高さで、ユタの黒い短髪が安らぎを求めて猫のようにすり寄った。
「早く帰ろうよ。僕、着替えてくる」
「いや、いいんだ……。このまま帰ろう」
「でも、目立つよ。またあいつらが襲ってきたら……」
「いや、大丈夫だ。さあ、帰ろう」
湯屋はちょうど入れ替えの時間で、同じ区の者は去り、平野区の男たちがやって来た。
滓に相応しからぬ領巾を見るや、驚きと好奇のまなざしが遠慮なく投げつけられた。顔見知りのムラネが目を丸くして駆け寄って来る。
「お、おい、マナホ、ユタ……。その、衣、まさか……」
「ああ、ムラネ……。わたしたちは急がねばならん。またいずれ」
マナホはユタを急がせた。
「ねぇ、マナホ。ムラネはなにを言いかけたの?」
「その話は宿に帰ってからだ」
区に戻ると、ちょうど夕食が始まっていた。
男たちは共同生活をしている。二階建ての掘立柱の建物は宿と呼ばれ、この方羽区では現在およそ二十人余りの男たちが、ここを根城に暮らしている。宿の外では薪が焚かれ、その赤々とした火の上には、大きな鉄鍋がたっぷりと雑炊を蓄えていた。
「このにおい、今日は鹿粥だ!」
駆け出そうするユタの腕を引き留めた。
「それは後だ。先にお前に話さなければならんことがある」
宿に入る間も、男たちはユタを包む領巾に目を丸くし、口々になにか言いかけたが、保護者が背中を押すので最後までは聞き取れなかった。
入り口をくぐると、長と呼ばれる三人の男たちが食事をしていた。真ん中を一の長ケムタ、左が二の長マツカ、右が三の長クマリ。それぞれ歳はマナホとそう変わらない。いつものようにいろりを囲んで板間に座っている。
「ユタが衣を頂きました」
「なんと……」
いろりの前に座するや否や、マツカが側へ寄ってきて領巾の柄を調べた。
「これは、ただの官吏様ではあるまい。梅や竹の模様なら時に目にするが、これは松。国司様に近い御人に違いない」
(確かに、一度も見かけたことがない官吏様だった……。そんなに位の高いお人だったのか)
静かなあの目と、きりりと結ばれた唇を思い出した。
「ユタよ、これはどなたからどのように頂いたのだ?」
(マナホにならともかく、言いたくないな……)
察したマナホが代わりに口を割った。
「湯屋で下っ端の役人に乱暴されそうになったところを、その官吏様が救ってくださったようです」
「そうだったか……。それで、お前はその官吏様のお手つきになったのか?」
「な、なってません……! 僕、なにもされてません」
慌てて言い返した。マナホに弁明するように顔を向けたが、視線を返してはくれなかった。
長たちは声を低くして、なにかを示し合わせるように目配せした。
「いずれ沙汰があるだろう。マナホ、それまでユタを頼むぞ。ユタ、お前は方羽宿の誉だ、よくやった」
(よくやったって……、別になにもしていないけど……。それに沙汰って、なんのことだろう……)
「二階をしばらく借りてもいいですか?」
「ああ、しばらく人払いしよう」
マナホの指図で、宿の二階に上がった。二階は子どもや若い者が使うことになっていて、茅葺の天井は手が届くほどの高さにある。
「ユタ、そっちの窓を開けてくれるか」
「うん」
棒をつがえて戸板窓を押し上げると、そこから山に沈む夕日が見えた。輝くような赤が胸に刺さって、しばらく見とれた。
「ユタ、ここへ」
「僕、本当になにもされてないよ、本当だよ」
「それはいいんだ」
「よくない。僕、マナホのつがいになるんだよ。もう十八だ」
「わたしたちは、もうつがいになれない」
「どうして」
「お前は、これから宮にお仕えするからだよ」
「僕が? そんなわけない。御調べも受けてないのに」
「ああ、そうだ、普通はな。だが、こういうことは例がないわけじゃない」
「こういうこと?」
「力のある官吏様が個人的に御用郎を望んだ場合、それには従わなければならないんだ」
「……えっ、この衣……」
「お前はもうその方のものだという証だよ。これは拒めない。近々お達しがあるだろう」
「マナホ……」
「そんな顔をするんじゃない。これは方羽宿にとっても誉なことなんだよ。この宿からひとりでも多くの御用郎を出せるのだから。それに、望まれて行くならば、自分の子を世に残せる見込みははるかに多いだろう」
「そんなの嫌だよ、マナホのつがいになるって約束じゃないか!」
跳ねるように身を乗り出したユタを、マナホが突き出した掌が退けた。
「その衣をはおったまま、わたしに近寄ってはならない。お前はもう、その松のお方のものなのだ」
「嫌だ、そんなの嫌だよ……」
黒めがちな目にたちまち涙を浮かんだ。保護者には儚そうな笑みを浮かぶ。
「ユタ、こんな機会は二度とない。わかるね?」
(それは、わかる……)
「男が子を残すには、宮に上がらなければならない」
「……」
「男たちはみな十六になれば御調べを受ける。選ばれた者だけが、御用郎として宮の女たちと交わることが許される。そうでない者は、一生子を残す機会すら与えられず、時が来れば滓穴に葬られる、それが定めだ」
「……」
「わたしは四十を過ぎた。いつ穴に送られてもおかしくない」
「マナホ……」
「小さく生まれたせいで滓児とされ、お前はすぐにこの宿に捨てられた。一度淘汰された者は、御調べには呼ばれない。わたしもそうだった。だが、今日までお前を大事に育ててきてよかった。このような幸運がユタに訪れるとは」
「でも、僕、マナホとの約束を……」
「ユタも知っているだろう。御調べで一度でも男と交わったことがあると知れたら、すぐに淘汰されてしまうことを。お前は歳のわりに体も小さく、幼な顔だし髭も生えていない。十六と言ってもまだ通るだろうと思っていた。お前が幼く見えるうちはなんとしても、宮仕えの道を探してあげようと思っていたのだ。お前を抱かずにいて本当によかった」
「僕はずっと待ってたのに……! 十五のときからずっと」
「お前は選ばれたんだよ。十人並みの容姿のお前が、まさか官吏様に見初められるとは思わなかったが……」
「う、う……、嫌だよ。僕、行きたくない。マナホとここで暮らしたいんだ」
ユタの背に手を廻し、優しくなでた。
「お前はわたしの人生の中で一番の輝きだよ」
「マナホが好きだ。一番好きなんだ」
「これまではわたしが保護者だったが、これからは松の官吏様がお前を守ってくださる。どんな方だった? お姿を覚えているだろう?」
黒髪の美しい女人の姿を目に浮かべた。
「……きれいで強そうな人だったよ……。今まで見たどの役人よりも」
「そうだ、その方がお前を守ってくださるよ」
「ああ、でも、マナホがいいんだ!」
乱暴にマナホの唇に自分の唇を押し付けた。
目を開けると、マナホは怒ったような、それでいて悲しいような顔をしていた。拒絶されるのは怖かったが、焦った。今を逃したら、きっとマナホとつがいになる機会は二度とない。
ユタの手は腰ひもの下のマナホのいちもつをそっと探し当てていた。
「僕、やり方わかるよ……」
「やめなさい」
ユタがそこへ顔をうずめようとするのを、強く止めた。
「だって……」
「聞きなさい、ユタ」
ぐずぐずとするユタをマナホがちからで起こした。
「引退した御用郎から聞いたことがある。御調べのあと、女と交ぐわるための御指南というものを受けるそうだ。男同士のむつごとと女相手のそれはずいぶんと勝手が異なるらしい。だから、この宿で見聞きしたことは忘れなさい。下手な行いをしたり、余計な口を出してしまうと、すぐに殺されてしまう」
マナホの親指がぬぐうようにユタの唇を撫でた。
(僕はこの感触を絶対に忘れない……。一生忘れないんだ……)
「どうしてわたしが、お前を宮に上げたかったかわかるか?」
「子孫を残せるから……」
「それもある」
「他にもあるの?」
「ある。歴史、というものだ」
「れきし?」
「その御用郎はこうも言っていた。宮では女と交ぐわるやり方のほかにも、文字なるものも習うらしい」
「そ、そうなの……?」
「そして、歴史というものを学ぶそうのだ」
「なんなのその、れきしって」
「この国の成り立ちだ。宮にはこの国ができたそのときから今日までの、すべての記しが残っているそうだ」
「しるし……?」
「わたしはそれを聞いたとき驚いた」
「どうして?」
「男たちはこの国の成り立ちや昔あった出来事など、なんにも知らずに死んでいく。だが、女たちはそれを知っているんだよ」
「それが、なんなの……?」
「わからないかい? 知っている者は強い」
「よくわからないよ……」
「目安星(北極星)を知ってるだろう? これを知っていれば家に帰れたのに、知らずに帰れなかった子どもがいたのを覚えているだろう。つまりそういうことだ」
「……れきしがわかると、なにかの役に立つってこと?」
「そうだよ」
「なんの役に立つんだよ……」
「わからない。わからないが、なぜ女が強くて男が弱いのか、わたしはそれが知りたい」
「マナホ……」
「けものや草花を見ていると不思議なのだ」
「え……」
「どうやら種によって、雄と雌とのあり方は、さまざまらしく……」
「そんなの、知ったところで、どうにもならないよ」
「そうかなあ」
「一ぺん死んで、女に生まれ変わって来れば違うかもしれないけど……」
「でも、歴史がわかれば、腑に落ちるんじゃないかと思うんだよ」
「……」
「目安星みたいに、ああそうか、あそこに帰ればいいんだなって」
マナホの双眸は窓のむこうの初夏を見ていた。倣うと、小さな粗末な垂木に縁どられた紺の中に、光の粒がきらめいている。
「れきしを習えっていうこと……?」
「そうだよ。歴史を知って、お前によりよく生きてほしい」
「……わかった……」
涙のうちに、マナホの願いを自分の心の確かな場所にとどめた。
翌朝、宿に迎えの馬が来た。それがユタとマナホの今生の別れになった――。
こちらもぜひお楽しみください
0
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる