4 / 10
第4章 不可能
しおりを挟む
囀が転校してきてから、一週間が経った。その間も、月夜は彼女と関わっていた。月夜がそうしたいと思っていたのは確かだが、それ以前に、囀が彼女に積極的に関わってくるからだ。月夜としては、それで嬉しかった。学校で誰かに声をかけられるのは、少し不思議な感じがしたが、嫌な感じではなかった。
月夜が夜まで学校に残っていると、一週間の内、三日くらい囀に出会った。彼に尋ねると、月夜に会いに来た、とのことだったが、真意は分からない。以前みたいに、図書室に用があるわけではないみたいだった。本は、日中の内に借りておいて、それを家で読んでいるらしい。彼が借りる本はいつも特異で、なかなか優れた趣味をしているみたいだった。
その日の夜も、教室に残って月夜が読書をしていると、扉が開いて、囀が姿を現した。
「やあ」
部屋に入るなり、彼は月夜の傍にやって来る。
月夜は顔を上げて、小さく頷いた。
今日は一日中雨が降っていた。窓の外では、今も雨粒が硝子の表面を伝っている。校庭には所々に水溜りができ、毛細血管のように水の通り道を形成していた。サッカーゴールの前に大きな池のような溜まり目があり、きっと、今そこでサッカーをしたら、どちらかのチームは不利益を被る。
囀は教室の中をぶらぶらして、黒板の前で立ち止まった。彼はチョークを手に取り、落書きを始める。石灰が板上に打ちつけられる音が、無機質な教室に融合するように響いた。
月夜は、本から視線をずらして、正面の囀を見る。
その姿が、ほかの誰かと重なって見えた。
懐かしい感覚。
いつかの夜も、同じような光景を目にした。
「ねえ、月夜」落書きを続けながら、囀が言った。「僕と一緒に、外で遊ぼうよ」
月夜は窓の外を見る。
「今、雨が降っているよ」
「知っている」
「それでも、遊びたいの?」
「うん」
月夜は本を閉じ、立ち上がった。
「分かった」
囀はこちらを振り返り、困ったような顔で笑う。
「ごめん、冗談だよ。君が困る顔を見たくて、そんなこと言ったんだ」
月夜は首を傾げる。
「そう?」
「うん……。……ごめん」
「いいよ、全然」
彼女は再び座り、一度閉じた本をもう一度開く。
雨音が聞こえる。打ちつけられるような音だが、不快ではない。まるで、人間の生体音と共鳴するようだ。母親の胎内にいた頃は、こんな感じだったのかもしれない。
それは、自分が、唯一他者と物理的に繋がっていた時間だ。
しかも、強固な繋がりだった。
本当の意味で、生死をともにしていた。
母親の栄養分を受け取り、それを頼りに、生きていた。
しかし、一度外界に出てしまえば、もう、二度と、他者とそんな関係を作ることはできない。
せいぜい、手を繋いで、存在を確かめ合う程度。
あるいは、抱き合って、お互いに体温を交換するくらい。
それ以上の関係には、絶対になれない。
「おかしなことを考えているでしょう」落書きを終えた囀が、チョークを持ったまま振り返り、月夜に言った。「夜は、休息の時間だから、あまり、変なことは考えない方がいいよ」
「変なこと?」
「そんな顔をしているよ」
月夜は自分の頬に触れる。
「今日は、何を読んでいるの?」
囀に訊かれたから、月夜は本を持ち上げて、表紙を彼に見せた。
「なるほど。古典か」
「うん、古典」
「古典って、暗号解読みたいで、面白いよね」囀は話す。「英語もそうだけど、内容はともかく、読めたっていうだけで、達成感がある」
「囀が、いつも読んでいる本は、達成感があるもの?」
「どうかな……。図鑑とか、細部まで目を通すわけじゃないからね。ぱらぱら捲って、気になったページがあれば、ちょっと目を通すくらいだよ」
「ほかには?」
「ほかには、詩集とか」
「面白い?」
「図鑑よりは、面白いかもね。でも、それも、全部は読まない。なんとなく、勘で開いて、これだ、と思うものがあったら、読んでみるだけ」
「行間は、読まないの?」
「行間?」囀は笑った。「ああ、読むかもね。でも、なかなか難しいよ、それって」
「読まないと、テストでいい点がとれないし、学校でも上手くやっていけない」
「そうかもね」
机と机の間を通り、囀は月夜の前に来る。そのままじっと顔を見つめ、手を伸ばして、彼は彼女の頬に触れた。
「何?」月夜は尋ねる。
「いや、何も」
沈黙。
囀は、月夜の瞳を覗き込む。
それは、凍りつくように、冷徹だった。
けれど、彼は目を逸らさない。
その温度を、自分に取り込もうとする。
「チョーク、持ったままだよ」月夜は指摘した。
「ああ、そうだね」しかし、囀はそちらに意識を向けようとしない。
そのまま、三分が過ぎた。
何も起こらなかった。
誰も、何かが起こることを、期待していなかった。
期待しても、無駄だった。
囀は、月夜に言われた通り、チョークを黒板の所定の位置に戻した。板上に描かれた落書きを消し、掌を軽く払う。
「外に行こう」囀が言った。
「本当に?」月夜は、再び顔を上げる。
荷物を纏めて、二人で廊下に出た。雨の日の廊下は、空気中の水分が飽和して濡れている。気温は高くないのに、温度が身体に纏わり付いてくるようで不快だった。
昇降口に移動し、外履きに履き替える。建物の外に出ると、一気に雨の匂いがした。
校庭を歩く。靴の表面は濡れたが、中にまで水が入ってくることはなかった。
運動部が使うために形成された一画に、簡易な屋根と、その下にベンチが並べられたエリアがあった。風は強くないから、ベンチは濡れていない。月夜と囀は、そこに再び腰をかけた。
「雨の日って、いいよね」囀が言った。「特に、夜は」
月夜は黙って頷く。
傍にある棚の中に、バドミントンのラケットが仕舞われていた。囀はそれを取り出し、軽くスイングする。バドミントン部は体育館で活動するのに、なぜそれがここにあるのか、分からなかった。ただ、あるものは使える。理由が分からなくても、存在しさえすれば、利用することができる。
シャトルはないが、囀は一人でバドミントンを始めた。月夜が尋ねると、囀は自分にバドミントンの経験はないと言った。たしかに、動きはぎこちなくて、それっぽいステップを踏んでいるようにしか見えない。けれど、囀の動きはどこか俊敏で、型に合っていなくても、なぜか上手く見えた。そういう人間は、ときどきいる。何をやっても、格好良く見えるのだ。
囀にラケットを渡されて、月夜もそれを軽く振ってみたが、やり方が分からなかった。やり方といっても、手に持って、上から下に下ろすだけで良いが、そんな単純な動きでも、やはり迷いがある。囀のように思いついたままに動かせるのは、才能があるからかもしれない。
空は、当然、曇っている。
雨は、地面に溢れ、やがて消えていく。
遠目に見る夜の校舎は、どことなく不穏で、巨大だった。怪物のように見える。無言の圧力が、まるで学校に形作られた小規模な社会のように、自分を圧迫してくるみたいだった。
「もう、学校には、慣れた?」
何も話題がないから、月夜は他愛のないことを訊いた。
囀は、ラケットを振るのをやめて、月夜を振り返る。
「うん、まあね」
ラケットを持ったまま、囀は月夜の隣に座る。
「どうしたの、月夜」彼は言った。「浮かない顔してるよ」
月夜は顔を上げ、彼の横顔を見る。
「そう?」
「うん……。何かあった?」
「いや、何も」
「そう? なら、いいけど」
囀が持っているラケットは、グリップに巻かれたテープが剥がれかけている。表面は擦れ、白くなっている部分があった。もう、大分古いものだ。今までガットが切れなかったのは奇跡かもしれない。それとも、素振りされるばかりで、シャトルと触れる機会が少なかったのか……。
「僕の話をしようか?」
「囀の?」月夜は首を傾げ、それから頷いた。「うん、聞きたい」
囀は、まず、自分の好きなものについて話した。好きな食べ物はカレーライスで、好きな色は黄色。そして、好きなことは、本を読むこと。
嫌いなものは、あまりないらしい。唯一、争い事はない方が良い、と彼は言った。それは月夜も同感だった。
彼は、家族と一緒に暮らしている。でも、父親はいなくて、母親と二人で住んでいるらしい。母親は、いつも夜遅くまで働いているから、こんなふうに、夜に出歩いていても、何も言われないし、そもそも気づかれない。気づかれても、あの人は優しいから、きっと許してくれる、と囀は説明した。母親との仲は、どちらかというと良い方で、たまに一緒に外食したりする。けれど、そんなことができる日は限られていて、だから、平均よりは、コミュニケーションをとれる機会は少ない。寂しくはないが、ときどき話したくなることがある、とも彼は言った。一般的な感情で、何もおかしな点はないように月夜には思えた。
「で、月夜、君は?」一通り話し終えたタイミングで、囀は彼女に訊いた。
「私?」
「君の話も、聞かせてよ」
「君が、ずっと見てきたのが、私」
「本当に?」囀は愉快そうに笑う。「全部、真の姿?」
「真?」
「何も、偽っていない?」
「うん……。……でも、自分では、気づいていないだけかも」
「それは、まあ、そうだよ、誰だって」
「できる限り、素直には、している」
「じゃあ、信じるよ」
囀は、月夜の肩に触れる。
月夜は、彼の顔を見つめた。
しかし、やはり、何も起こらない。
距離がある。
そう感じた。
何が、そう感じさせるのか?
外見?
いや……。
そんなはずはない。
そんなことで、人を判断しては、いけない、と小学校で習ったはずだ。
でも……。
本当に、人は、見た目で他者を判断していないのだろうか?
しているのではないか?
したくなくても、しないように意識しても、結局は、そうするしかないのではないか?
青いから、男性?
赤いから、女性?
それが、人を決めるすべてか?
「今日は、ずっと、ここにいない?」囀が提案する。
「でも、明日も学校だよ」月夜は言った。「帰らなくて、いいの?」
「じゃあ、月夜の家に泊めてよ」
「囀の家の方が、先に着く」
「それなら、うちに泊まっていいよ」囀はウインクする。「嫌だ?」
月夜は考える。
「嫌ではない」
「なら、おいで」
「分かった、行く」
囀とともに、月夜は学校を立ち去る。正門は閉まっているから、今日も裏門から出た。それぞれが傘を差すせいで、距離がいつもより離れた。一つの傘に二人で入っても良かったが、不思議と、そうする気にはなれなかった。何が不思議なのか、そして、どうしてそうしようと思わなかったのか、すべて謎だ。
電車に乗る前に、近くのコンビニで、囀は軽食を買った。チョコレートクリームが挟まれたパンで、彼はそれを美味しそうに食べた。一口いるかと訊かれたが、食べたくなかったので、月夜は断った。
電車に乗り、ホームをいくつか通過して、囀の最寄り駅で下車する。
月夜が住んでいるのと、同じくらい静かな場所だった。地域的には、それほど離れていないから、雰囲気が変わらないのかもしれない。しかし、先日買い物をしたショッピングモールがある駅は、その間にある。
囀の家は、駅からすぐの場所にあるマンションだった。月夜は、一軒家に住んでいるので、マンションのシステムが珍しかった。自動ドアを通って建物に入り、エレベーターに乗り込む。回数表示が七を示したとき、囀は下りた。月夜もそれに続く。
廊下は、あまり広くないが、綺麗だった。外気に触れている。いくつも排水管が巡っており、工場みたいな感じがしないわけではない。
角を一度曲がり、囀はドアの前に立つ。七○九号室が彼の部屋だった。
お邪魔しますと言って、月夜は室内に入る。
玄関には、誰の靴も置かれていなかった。すぐ傍に棚があるから、その中に、すべて、仕舞われているのかもしれない。
廊下の先にリビング、その手前に左右に部屋があり、右が囀の部屋だった。浴室と洗面所は、玄関とリビングを繋ぐ廊下の中間にある。まず手を洗い、それから囀の自室に向かった。部屋に入ると、ダンボールがまだいくつも積まれたままになっていた。
「散らかっているけど、気にしないでね」鞄を下ろしながら、囀は言った。「整理しようと思っていたんだけど、結局、面倒臭くなって、先延ばしにしちゃった」
囀の部屋は、どちらかというと狭い。奥に窓が一つあるだけで、それ以外に、開放的な雰囲気を感じされるものはない。入り口から見て左手にクローゼットがあり、囀は、その中に、着ていた上着を仕舞った。そのとき、彼が所有している衣服が見えた。どれも多種多様で、多面的で、多角的なセンスだった。純粋に、凄いな、と月夜は思った。
正面にベッドがあり、その対面、つまり入り口側の壁面に机が置かれている。そうした家具は、全然華やかではなく、シンプルさを極めたように簡素だった。この部屋も、壁は白くて、無味な感じがする。意識的にそうしているのかもしれない。
囀にクッションを渡されて、月夜はその上に座った。暖房が効いてきたから、ブレザーを脱いで、ワイシャツ一枚になった。
「お風呂、入る?」自分は、机の前の椅子に座って、囀が尋ねた。
月夜は、じっと彼を見つめる。
「別に、何も変なことしないから、警戒しなくていいよ」彼は笑った。「僕は、そんな酷いやつじゃない」
「それは、疑っていない」
「じゃあ、何か、ほかに、気になることがあるの?」
「囀が、先に入ってきたら?」
「いいの?」
「うん……」
「あ、もしかして、そうしている間に、部屋を調べる算段とか?」
「違う」
「いいよ、調べても。何も、ないから」そう言って、囀は立ち上がる。「お母さんは、まだ、帰ってこないと思うけど……。万が一遭遇したら、事情、伝えておいてね」
月夜が頷くと、彼は部屋から出ていった。
月夜は、座ったまま、部屋を見渡す。
囀の机の上には、今は何も載っていなかったが、その向こう側にある簡易な本棚に、いくつか不思議な本が仕舞ってあった。背表紙には、ざっと見ただけでも、占い、ニュートン、哲学、妖怪、などの文字が見て取れる。本人が言っていた通り、様々なジャンルの本を読むようだ。ニュースやバラエティなど、多様な番組を一纏めにして、テレビと呼ぶみたいな感じがする。
後ろを向く。
ベッドの上には、暖かそうな毛布がかけられている。一人で寝るには充分な大きさだった。囀は、意外と活発だから、毎晩きちんと寝ないと疲れがとれないのではないか、と月夜は心配していたが、質の良い備品があるようで、安心した。
奥にある窓の手前に、壁が窪んだスペースがあって、そこに地球儀が置かれていた。あれは何に使うのだろう、と月夜は考える。単なるインテリアかもしれないが、囀の所有物となると、何か具体的な意味があるようにも思える。
部屋のドアが開き、囀が入ってくる。
「どうぞ」
月夜は、着替えを持ってきていなかったから、囀に貸してもらうことにした。月夜が身につけても問題のない服を、囀は充分持っていた。寝間着として、厚手のパジャマと、その上から羽織るパーカーを貸してもらった。
風呂は、月夜の家のものと大して変わらなかった。
お湯に浸かり、ゆっくりと息を吐く。自分の家のものと、設定温度が多少違ったが、問題なかった。少し熱いくらいだ。温泉に来たような感じはしなかったが、新しい生活が始まった錯覚を引き起こすことくらいはできそうだった。
身体と頭を洗い、シャワーを浴びる。風呂から出て、貸してもらった服に着替え、囀の自室に戻った。彼の部屋以外は、今は照明は消えている。廊下の途中で後ろを振り返ってみたが、リビングは暗くて、陰気だった。
囀は、机の前で本を読んでいた。
「おかえり」彼は言った。「もう、寝る?」
「どちらでも」月夜は答える。「何、読んでいるの?」
「本だよ」
「何の本?」
「今日は、世界の家に関する本」囀は説明した。「世界中に存在する、様々な家を、写真を通して見学できる」
彼の傍に近づいて、本の内容を確認する。写真は、どこか南の国の家を写したもので、木製の桟橋の傍に、塔のような形の洒落た家が建っていた。
「囀は、こういう家に住みたい?」
「住みたいといえば、住みたい」
彼はページを捲る。次は、日本と似ているが、少し異なる、都会に建てられた一軒家だった。メカニカルな印象で、硝子が一枚の壁をほとんど覆っている。室内は、近未来的な構造になっており、技術の進歩を感じさせるものだった。
「こういうのは、どう?」
「うーん、僕は、あまり、好きじゃないかな」
「さっきの方がいい?」
「個人的にはね」
そうやって、本を一緒に見て、時間が過ぎた。
明日も学校があるから、眠ることにした。
布団は一つしかないから、二人で寝るしかなかった。囀は、自分はリビングで寝るから良いと言ったが、月夜がそれを拒否した。
互いに背を向けて、目を閉じる。
暗い室内。
月夜は、彼が、どうして反対側を向いたのか、分からなかった。
「月夜、もう、寝た?」
十分くらい経過した頃、囀が声をかけてきた。
「ううん、まだ」月夜は、後ろを振り返る。
「今日は、付き合ってくれて、ありがとう」
「何に?」
「僕の我儘に」
「我儘?」
「無理矢理、僕の家に連れてきたような気がしてさ、なんだか、申し訳ない気持ちになった」
「そう……」
「迷惑かけたから、明日、お詫びに、何かプレゼントするよ」
月夜は首を振る。
「いらない」
「欲がないなあ、月夜は」
「私は、今日、得をした」
「そう?」
「うん」
「それなら、よかったよ」囀は笑った。「僕も、嬉しい」
そう言ったきり、囀は何も話さなくなった。暫くすると、彼の寝息が聞こえてきた。月夜は、いつもはまだ起きている時間だから、すぐには寝つけなかった。
自分が帰ってこなくて、フィルは心配しているだろうか、と今さらながら考える。でも、きっとそんなことはないだろうと思った。彼は、自分が帰ってこなくても、今日は、帰ってこなかったな、くらいにしか思わないに違いない。
考えようによっては、ロマンチックなシチュエーションだったが、全然そんな感じはしなかった。むしろ、すでにそういう局面は終わった気がする。囀は、自分の親友で、これからもずっと一緒にいる。そんな親密な関係だから、これ以上、友情を確かめ合う必要はない。だから、彼は何もしてこなかったし、自分もそれを求めなかった。
自分勝手な理由づけだ。
本当は、そんなこと、どうでも良かった。
意識的に呼吸を繰り返し、月夜は眠ろうとする。眠ろうとすれば、少しずつ眠くなる。そして、確実に眠れる。
そう考えたが、実際には、眠れなかった。
布団から抜け出し、窓の傍に寄る。まだ雨は降っていた。
囀の顔を覗き込む。
彼は穏やかに寝息を立てている。
しかし、彼は、突然瞼を持ち上げた。
目が合う。
「駄目だよ、月夜。ちゃんと寝ないと」彼は笑顔で言った。
「うん、ごめん」
「別に、謝らなくていいけど」囀は話す。「どうしたの? 家が恋しくなっちゃった?」
「ううん」
「じゃあ、早く寝なよ。朝になっちゃうよ」
「囀も、まだ、眠っていなかったの?」
「そうそう。ごめんね、寝たと思って、色々悪戯しようと思ったんでしょう?」
「思っていない」
「ほら、早く、戻りなよ」そう言って、囀はかけ布団を持ち上げる。「僕一人じゃ、寒いから」
月夜は、言われた通り、もう一度横になる。
今度は、囀は、彼女の方を向いた。
彼に見つめられる。
「何?」
月夜は尋ねる。
「子守唄でも、歌おうか?」
「歌えるの?」
「少しなら」
月夜は頷く。
「じゃあ、お願い」
囀は、何度か軽く咳払いをし、喉の調子を整える。
そうして、彼は歌い出す。
綺麗な声。
けれど、それは、子守唄ではなく、交響曲だった。
*
囀と一緒に学校に向かった。彼女の母親は、一度家に帰ってきたみたいだが、すでにいなかった。マンションから出て、昨日と逆の順序で駅に向かう。電車はすぐにやって来た。いつも通り、まだ早い時間だから、車内は空いていて、座ることができた。月夜にとっては、普段より数個駅を飛ばしただけだから、あまり新鮮な感じはしなかった。
今朝は晴れていた。冬を象徴するような、素晴らしい青空だ。しかし、空気は乾燥している。夏のような生々しさはなく、どこか哀愁感漂う雰囲気だった。
電車を降り、道を歩いて、学校に到着する。
教室に向かう前に、寄り道をして、二人は数学のノートを提出した。
「僕ね、確率の計算が苦手なんだよ」鞄からノートを取り出しながら、囀が言った。「なんでさ、あんなに、一つ一つ正確に数えなきゃいけないんだろうね。だいたいの数字が出せれば、いいと思うんだけど」
「たしかに」月夜は頷く。
「あ、やっぱり、そう思う?」
「でも、それだと、数学の意味がない」
ノートは、教師に直接提出するのではなく、数学の教師が詰める部屋の前に置かれた籠に入れることになっている。すでにいくつかのノートが入っていた。
廊下を歩いて、教室に向かう。まだ、クラスメートは来ていなかった。
この教室には、どこにも変わったところがない。どこも変わらないというのは、空間としておかしいが、教室と言われたら真っ先に思い浮かぶような、そんなテンプレートみたいな部屋だ。黒板は、前と後ろに二つあるが、基本的に前のものしか使われない。鞄を入れるためのロッカーは、ここにはない。すべて、昇降口の下駄箱を使うことになっている。掲示板は、黒板の隣に置かれており、いつも何かしらのプリントが貼られている。
月夜は勉強を始めた。今日は、囀の家で朝を迎えたから、まだ勉強をしていなかった。
囀はというと、相変わらず机に突っ伏して眠っていた。彼女は、暇があればその格好になって、寝息を立てる習性を持つ。日頃から眠いのか、それとも、いざというときのためにエネルギーを貯蓄しているのか分からないが、いつでも眠れるのは、それだけ周囲を信用している証拠だともいえる。電車の中でも、彼女はきっと一人で眠る。それは、この国に住むほとんどの人間に共通することだ。
時間が経過するにつれて、徐々に生徒が登校してくるようになった。教室には挨拶が飛び交い、くだらない話題でときどき盛り上がる。けれど、盛り上がったあとには、鉄槌が下されるごとく静寂が訪れることが多い。消費されるように、次から次へと人間関係の糸が繋ぎ変えられていく。
そして、八時十五分になった頃、事態は動いた。
クラスメートの一人が、登校してきた途端、大きな声で、図書室の本が盗まれた、と報告した。
月夜は顔を上げて、そちらを見る。その女子生徒は、たしか図書委員の一人だった。各委員の担当者は二人いるが、もう一人は覚えていない。その生徒は、ほかのクラスメートに聞こえるように、事件の概要について大きな声で説明した。
彼女の話によると、小説が一冊何者かに持ち出されたらしい。その本は、ある一年生が予約していたもので、本来なら今日貸し出しされるはずだった。昨日の放課後、別の生徒から返却されたその本が、今朝になって、突然姿を消したということだ。
こんな、よくある話題でも、生徒の半分くらいは、僅かながら胸を踊らせる。
それは、学校が退屈な証拠か?
少なくとも、月夜には、そんなふうに思えてならなかった。
顔を上げて、月夜は囀を確認する。
彼女は、寝ていた。
月夜が夜まで学校に残っていると、一週間の内、三日くらい囀に出会った。彼に尋ねると、月夜に会いに来た、とのことだったが、真意は分からない。以前みたいに、図書室に用があるわけではないみたいだった。本は、日中の内に借りておいて、それを家で読んでいるらしい。彼が借りる本はいつも特異で、なかなか優れた趣味をしているみたいだった。
その日の夜も、教室に残って月夜が読書をしていると、扉が開いて、囀が姿を現した。
「やあ」
部屋に入るなり、彼は月夜の傍にやって来る。
月夜は顔を上げて、小さく頷いた。
今日は一日中雨が降っていた。窓の外では、今も雨粒が硝子の表面を伝っている。校庭には所々に水溜りができ、毛細血管のように水の通り道を形成していた。サッカーゴールの前に大きな池のような溜まり目があり、きっと、今そこでサッカーをしたら、どちらかのチームは不利益を被る。
囀は教室の中をぶらぶらして、黒板の前で立ち止まった。彼はチョークを手に取り、落書きを始める。石灰が板上に打ちつけられる音が、無機質な教室に融合するように響いた。
月夜は、本から視線をずらして、正面の囀を見る。
その姿が、ほかの誰かと重なって見えた。
懐かしい感覚。
いつかの夜も、同じような光景を目にした。
「ねえ、月夜」落書きを続けながら、囀が言った。「僕と一緒に、外で遊ぼうよ」
月夜は窓の外を見る。
「今、雨が降っているよ」
「知っている」
「それでも、遊びたいの?」
「うん」
月夜は本を閉じ、立ち上がった。
「分かった」
囀はこちらを振り返り、困ったような顔で笑う。
「ごめん、冗談だよ。君が困る顔を見たくて、そんなこと言ったんだ」
月夜は首を傾げる。
「そう?」
「うん……。……ごめん」
「いいよ、全然」
彼女は再び座り、一度閉じた本をもう一度開く。
雨音が聞こえる。打ちつけられるような音だが、不快ではない。まるで、人間の生体音と共鳴するようだ。母親の胎内にいた頃は、こんな感じだったのかもしれない。
それは、自分が、唯一他者と物理的に繋がっていた時間だ。
しかも、強固な繋がりだった。
本当の意味で、生死をともにしていた。
母親の栄養分を受け取り、それを頼りに、生きていた。
しかし、一度外界に出てしまえば、もう、二度と、他者とそんな関係を作ることはできない。
せいぜい、手を繋いで、存在を確かめ合う程度。
あるいは、抱き合って、お互いに体温を交換するくらい。
それ以上の関係には、絶対になれない。
「おかしなことを考えているでしょう」落書きを終えた囀が、チョークを持ったまま振り返り、月夜に言った。「夜は、休息の時間だから、あまり、変なことは考えない方がいいよ」
「変なこと?」
「そんな顔をしているよ」
月夜は自分の頬に触れる。
「今日は、何を読んでいるの?」
囀に訊かれたから、月夜は本を持ち上げて、表紙を彼に見せた。
「なるほど。古典か」
「うん、古典」
「古典って、暗号解読みたいで、面白いよね」囀は話す。「英語もそうだけど、内容はともかく、読めたっていうだけで、達成感がある」
「囀が、いつも読んでいる本は、達成感があるもの?」
「どうかな……。図鑑とか、細部まで目を通すわけじゃないからね。ぱらぱら捲って、気になったページがあれば、ちょっと目を通すくらいだよ」
「ほかには?」
「ほかには、詩集とか」
「面白い?」
「図鑑よりは、面白いかもね。でも、それも、全部は読まない。なんとなく、勘で開いて、これだ、と思うものがあったら、読んでみるだけ」
「行間は、読まないの?」
「行間?」囀は笑った。「ああ、読むかもね。でも、なかなか難しいよ、それって」
「読まないと、テストでいい点がとれないし、学校でも上手くやっていけない」
「そうかもね」
机と机の間を通り、囀は月夜の前に来る。そのままじっと顔を見つめ、手を伸ばして、彼は彼女の頬に触れた。
「何?」月夜は尋ねる。
「いや、何も」
沈黙。
囀は、月夜の瞳を覗き込む。
それは、凍りつくように、冷徹だった。
けれど、彼は目を逸らさない。
その温度を、自分に取り込もうとする。
「チョーク、持ったままだよ」月夜は指摘した。
「ああ、そうだね」しかし、囀はそちらに意識を向けようとしない。
そのまま、三分が過ぎた。
何も起こらなかった。
誰も、何かが起こることを、期待していなかった。
期待しても、無駄だった。
囀は、月夜に言われた通り、チョークを黒板の所定の位置に戻した。板上に描かれた落書きを消し、掌を軽く払う。
「外に行こう」囀が言った。
「本当に?」月夜は、再び顔を上げる。
荷物を纏めて、二人で廊下に出た。雨の日の廊下は、空気中の水分が飽和して濡れている。気温は高くないのに、温度が身体に纏わり付いてくるようで不快だった。
昇降口に移動し、外履きに履き替える。建物の外に出ると、一気に雨の匂いがした。
校庭を歩く。靴の表面は濡れたが、中にまで水が入ってくることはなかった。
運動部が使うために形成された一画に、簡易な屋根と、その下にベンチが並べられたエリアがあった。風は強くないから、ベンチは濡れていない。月夜と囀は、そこに再び腰をかけた。
「雨の日って、いいよね」囀が言った。「特に、夜は」
月夜は黙って頷く。
傍にある棚の中に、バドミントンのラケットが仕舞われていた。囀はそれを取り出し、軽くスイングする。バドミントン部は体育館で活動するのに、なぜそれがここにあるのか、分からなかった。ただ、あるものは使える。理由が分からなくても、存在しさえすれば、利用することができる。
シャトルはないが、囀は一人でバドミントンを始めた。月夜が尋ねると、囀は自分にバドミントンの経験はないと言った。たしかに、動きはぎこちなくて、それっぽいステップを踏んでいるようにしか見えない。けれど、囀の動きはどこか俊敏で、型に合っていなくても、なぜか上手く見えた。そういう人間は、ときどきいる。何をやっても、格好良く見えるのだ。
囀にラケットを渡されて、月夜もそれを軽く振ってみたが、やり方が分からなかった。やり方といっても、手に持って、上から下に下ろすだけで良いが、そんな単純な動きでも、やはり迷いがある。囀のように思いついたままに動かせるのは、才能があるからかもしれない。
空は、当然、曇っている。
雨は、地面に溢れ、やがて消えていく。
遠目に見る夜の校舎は、どことなく不穏で、巨大だった。怪物のように見える。無言の圧力が、まるで学校に形作られた小規模な社会のように、自分を圧迫してくるみたいだった。
「もう、学校には、慣れた?」
何も話題がないから、月夜は他愛のないことを訊いた。
囀は、ラケットを振るのをやめて、月夜を振り返る。
「うん、まあね」
ラケットを持ったまま、囀は月夜の隣に座る。
「どうしたの、月夜」彼は言った。「浮かない顔してるよ」
月夜は顔を上げ、彼の横顔を見る。
「そう?」
「うん……。何かあった?」
「いや、何も」
「そう? なら、いいけど」
囀が持っているラケットは、グリップに巻かれたテープが剥がれかけている。表面は擦れ、白くなっている部分があった。もう、大分古いものだ。今までガットが切れなかったのは奇跡かもしれない。それとも、素振りされるばかりで、シャトルと触れる機会が少なかったのか……。
「僕の話をしようか?」
「囀の?」月夜は首を傾げ、それから頷いた。「うん、聞きたい」
囀は、まず、自分の好きなものについて話した。好きな食べ物はカレーライスで、好きな色は黄色。そして、好きなことは、本を読むこと。
嫌いなものは、あまりないらしい。唯一、争い事はない方が良い、と彼は言った。それは月夜も同感だった。
彼は、家族と一緒に暮らしている。でも、父親はいなくて、母親と二人で住んでいるらしい。母親は、いつも夜遅くまで働いているから、こんなふうに、夜に出歩いていても、何も言われないし、そもそも気づかれない。気づかれても、あの人は優しいから、きっと許してくれる、と囀は説明した。母親との仲は、どちらかというと良い方で、たまに一緒に外食したりする。けれど、そんなことができる日は限られていて、だから、平均よりは、コミュニケーションをとれる機会は少ない。寂しくはないが、ときどき話したくなることがある、とも彼は言った。一般的な感情で、何もおかしな点はないように月夜には思えた。
「で、月夜、君は?」一通り話し終えたタイミングで、囀は彼女に訊いた。
「私?」
「君の話も、聞かせてよ」
「君が、ずっと見てきたのが、私」
「本当に?」囀は愉快そうに笑う。「全部、真の姿?」
「真?」
「何も、偽っていない?」
「うん……。……でも、自分では、気づいていないだけかも」
「それは、まあ、そうだよ、誰だって」
「できる限り、素直には、している」
「じゃあ、信じるよ」
囀は、月夜の肩に触れる。
月夜は、彼の顔を見つめた。
しかし、やはり、何も起こらない。
距離がある。
そう感じた。
何が、そう感じさせるのか?
外見?
いや……。
そんなはずはない。
そんなことで、人を判断しては、いけない、と小学校で習ったはずだ。
でも……。
本当に、人は、見た目で他者を判断していないのだろうか?
しているのではないか?
したくなくても、しないように意識しても、結局は、そうするしかないのではないか?
青いから、男性?
赤いから、女性?
それが、人を決めるすべてか?
「今日は、ずっと、ここにいない?」囀が提案する。
「でも、明日も学校だよ」月夜は言った。「帰らなくて、いいの?」
「じゃあ、月夜の家に泊めてよ」
「囀の家の方が、先に着く」
「それなら、うちに泊まっていいよ」囀はウインクする。「嫌だ?」
月夜は考える。
「嫌ではない」
「なら、おいで」
「分かった、行く」
囀とともに、月夜は学校を立ち去る。正門は閉まっているから、今日も裏門から出た。それぞれが傘を差すせいで、距離がいつもより離れた。一つの傘に二人で入っても良かったが、不思議と、そうする気にはなれなかった。何が不思議なのか、そして、どうしてそうしようと思わなかったのか、すべて謎だ。
電車に乗る前に、近くのコンビニで、囀は軽食を買った。チョコレートクリームが挟まれたパンで、彼はそれを美味しそうに食べた。一口いるかと訊かれたが、食べたくなかったので、月夜は断った。
電車に乗り、ホームをいくつか通過して、囀の最寄り駅で下車する。
月夜が住んでいるのと、同じくらい静かな場所だった。地域的には、それほど離れていないから、雰囲気が変わらないのかもしれない。しかし、先日買い物をしたショッピングモールがある駅は、その間にある。
囀の家は、駅からすぐの場所にあるマンションだった。月夜は、一軒家に住んでいるので、マンションのシステムが珍しかった。自動ドアを通って建物に入り、エレベーターに乗り込む。回数表示が七を示したとき、囀は下りた。月夜もそれに続く。
廊下は、あまり広くないが、綺麗だった。外気に触れている。いくつも排水管が巡っており、工場みたいな感じがしないわけではない。
角を一度曲がり、囀はドアの前に立つ。七○九号室が彼の部屋だった。
お邪魔しますと言って、月夜は室内に入る。
玄関には、誰の靴も置かれていなかった。すぐ傍に棚があるから、その中に、すべて、仕舞われているのかもしれない。
廊下の先にリビング、その手前に左右に部屋があり、右が囀の部屋だった。浴室と洗面所は、玄関とリビングを繋ぐ廊下の中間にある。まず手を洗い、それから囀の自室に向かった。部屋に入ると、ダンボールがまだいくつも積まれたままになっていた。
「散らかっているけど、気にしないでね」鞄を下ろしながら、囀は言った。「整理しようと思っていたんだけど、結局、面倒臭くなって、先延ばしにしちゃった」
囀の部屋は、どちらかというと狭い。奥に窓が一つあるだけで、それ以外に、開放的な雰囲気を感じされるものはない。入り口から見て左手にクローゼットがあり、囀は、その中に、着ていた上着を仕舞った。そのとき、彼が所有している衣服が見えた。どれも多種多様で、多面的で、多角的なセンスだった。純粋に、凄いな、と月夜は思った。
正面にベッドがあり、その対面、つまり入り口側の壁面に机が置かれている。そうした家具は、全然華やかではなく、シンプルさを極めたように簡素だった。この部屋も、壁は白くて、無味な感じがする。意識的にそうしているのかもしれない。
囀にクッションを渡されて、月夜はその上に座った。暖房が効いてきたから、ブレザーを脱いで、ワイシャツ一枚になった。
「お風呂、入る?」自分は、机の前の椅子に座って、囀が尋ねた。
月夜は、じっと彼を見つめる。
「別に、何も変なことしないから、警戒しなくていいよ」彼は笑った。「僕は、そんな酷いやつじゃない」
「それは、疑っていない」
「じゃあ、何か、ほかに、気になることがあるの?」
「囀が、先に入ってきたら?」
「いいの?」
「うん……」
「あ、もしかして、そうしている間に、部屋を調べる算段とか?」
「違う」
「いいよ、調べても。何も、ないから」そう言って、囀は立ち上がる。「お母さんは、まだ、帰ってこないと思うけど……。万が一遭遇したら、事情、伝えておいてね」
月夜が頷くと、彼は部屋から出ていった。
月夜は、座ったまま、部屋を見渡す。
囀の机の上には、今は何も載っていなかったが、その向こう側にある簡易な本棚に、いくつか不思議な本が仕舞ってあった。背表紙には、ざっと見ただけでも、占い、ニュートン、哲学、妖怪、などの文字が見て取れる。本人が言っていた通り、様々なジャンルの本を読むようだ。ニュースやバラエティなど、多様な番組を一纏めにして、テレビと呼ぶみたいな感じがする。
後ろを向く。
ベッドの上には、暖かそうな毛布がかけられている。一人で寝るには充分な大きさだった。囀は、意外と活発だから、毎晩きちんと寝ないと疲れがとれないのではないか、と月夜は心配していたが、質の良い備品があるようで、安心した。
奥にある窓の手前に、壁が窪んだスペースがあって、そこに地球儀が置かれていた。あれは何に使うのだろう、と月夜は考える。単なるインテリアかもしれないが、囀の所有物となると、何か具体的な意味があるようにも思える。
部屋のドアが開き、囀が入ってくる。
「どうぞ」
月夜は、着替えを持ってきていなかったから、囀に貸してもらうことにした。月夜が身につけても問題のない服を、囀は充分持っていた。寝間着として、厚手のパジャマと、その上から羽織るパーカーを貸してもらった。
風呂は、月夜の家のものと大して変わらなかった。
お湯に浸かり、ゆっくりと息を吐く。自分の家のものと、設定温度が多少違ったが、問題なかった。少し熱いくらいだ。温泉に来たような感じはしなかったが、新しい生活が始まった錯覚を引き起こすことくらいはできそうだった。
身体と頭を洗い、シャワーを浴びる。風呂から出て、貸してもらった服に着替え、囀の自室に戻った。彼の部屋以外は、今は照明は消えている。廊下の途中で後ろを振り返ってみたが、リビングは暗くて、陰気だった。
囀は、机の前で本を読んでいた。
「おかえり」彼は言った。「もう、寝る?」
「どちらでも」月夜は答える。「何、読んでいるの?」
「本だよ」
「何の本?」
「今日は、世界の家に関する本」囀は説明した。「世界中に存在する、様々な家を、写真を通して見学できる」
彼の傍に近づいて、本の内容を確認する。写真は、どこか南の国の家を写したもので、木製の桟橋の傍に、塔のような形の洒落た家が建っていた。
「囀は、こういう家に住みたい?」
「住みたいといえば、住みたい」
彼はページを捲る。次は、日本と似ているが、少し異なる、都会に建てられた一軒家だった。メカニカルな印象で、硝子が一枚の壁をほとんど覆っている。室内は、近未来的な構造になっており、技術の進歩を感じさせるものだった。
「こういうのは、どう?」
「うーん、僕は、あまり、好きじゃないかな」
「さっきの方がいい?」
「個人的にはね」
そうやって、本を一緒に見て、時間が過ぎた。
明日も学校があるから、眠ることにした。
布団は一つしかないから、二人で寝るしかなかった。囀は、自分はリビングで寝るから良いと言ったが、月夜がそれを拒否した。
互いに背を向けて、目を閉じる。
暗い室内。
月夜は、彼が、どうして反対側を向いたのか、分からなかった。
「月夜、もう、寝た?」
十分くらい経過した頃、囀が声をかけてきた。
「ううん、まだ」月夜は、後ろを振り返る。
「今日は、付き合ってくれて、ありがとう」
「何に?」
「僕の我儘に」
「我儘?」
「無理矢理、僕の家に連れてきたような気がしてさ、なんだか、申し訳ない気持ちになった」
「そう……」
「迷惑かけたから、明日、お詫びに、何かプレゼントするよ」
月夜は首を振る。
「いらない」
「欲がないなあ、月夜は」
「私は、今日、得をした」
「そう?」
「うん」
「それなら、よかったよ」囀は笑った。「僕も、嬉しい」
そう言ったきり、囀は何も話さなくなった。暫くすると、彼の寝息が聞こえてきた。月夜は、いつもはまだ起きている時間だから、すぐには寝つけなかった。
自分が帰ってこなくて、フィルは心配しているだろうか、と今さらながら考える。でも、きっとそんなことはないだろうと思った。彼は、自分が帰ってこなくても、今日は、帰ってこなかったな、くらいにしか思わないに違いない。
考えようによっては、ロマンチックなシチュエーションだったが、全然そんな感じはしなかった。むしろ、すでにそういう局面は終わった気がする。囀は、自分の親友で、これからもずっと一緒にいる。そんな親密な関係だから、これ以上、友情を確かめ合う必要はない。だから、彼は何もしてこなかったし、自分もそれを求めなかった。
自分勝手な理由づけだ。
本当は、そんなこと、どうでも良かった。
意識的に呼吸を繰り返し、月夜は眠ろうとする。眠ろうとすれば、少しずつ眠くなる。そして、確実に眠れる。
そう考えたが、実際には、眠れなかった。
布団から抜け出し、窓の傍に寄る。まだ雨は降っていた。
囀の顔を覗き込む。
彼は穏やかに寝息を立てている。
しかし、彼は、突然瞼を持ち上げた。
目が合う。
「駄目だよ、月夜。ちゃんと寝ないと」彼は笑顔で言った。
「うん、ごめん」
「別に、謝らなくていいけど」囀は話す。「どうしたの? 家が恋しくなっちゃった?」
「ううん」
「じゃあ、早く寝なよ。朝になっちゃうよ」
「囀も、まだ、眠っていなかったの?」
「そうそう。ごめんね、寝たと思って、色々悪戯しようと思ったんでしょう?」
「思っていない」
「ほら、早く、戻りなよ」そう言って、囀はかけ布団を持ち上げる。「僕一人じゃ、寒いから」
月夜は、言われた通り、もう一度横になる。
今度は、囀は、彼女の方を向いた。
彼に見つめられる。
「何?」
月夜は尋ねる。
「子守唄でも、歌おうか?」
「歌えるの?」
「少しなら」
月夜は頷く。
「じゃあ、お願い」
囀は、何度か軽く咳払いをし、喉の調子を整える。
そうして、彼は歌い出す。
綺麗な声。
けれど、それは、子守唄ではなく、交響曲だった。
*
囀と一緒に学校に向かった。彼女の母親は、一度家に帰ってきたみたいだが、すでにいなかった。マンションから出て、昨日と逆の順序で駅に向かう。電車はすぐにやって来た。いつも通り、まだ早い時間だから、車内は空いていて、座ることができた。月夜にとっては、普段より数個駅を飛ばしただけだから、あまり新鮮な感じはしなかった。
今朝は晴れていた。冬を象徴するような、素晴らしい青空だ。しかし、空気は乾燥している。夏のような生々しさはなく、どこか哀愁感漂う雰囲気だった。
電車を降り、道を歩いて、学校に到着する。
教室に向かう前に、寄り道をして、二人は数学のノートを提出した。
「僕ね、確率の計算が苦手なんだよ」鞄からノートを取り出しながら、囀が言った。「なんでさ、あんなに、一つ一つ正確に数えなきゃいけないんだろうね。だいたいの数字が出せれば、いいと思うんだけど」
「たしかに」月夜は頷く。
「あ、やっぱり、そう思う?」
「でも、それだと、数学の意味がない」
ノートは、教師に直接提出するのではなく、数学の教師が詰める部屋の前に置かれた籠に入れることになっている。すでにいくつかのノートが入っていた。
廊下を歩いて、教室に向かう。まだ、クラスメートは来ていなかった。
この教室には、どこにも変わったところがない。どこも変わらないというのは、空間としておかしいが、教室と言われたら真っ先に思い浮かぶような、そんなテンプレートみたいな部屋だ。黒板は、前と後ろに二つあるが、基本的に前のものしか使われない。鞄を入れるためのロッカーは、ここにはない。すべて、昇降口の下駄箱を使うことになっている。掲示板は、黒板の隣に置かれており、いつも何かしらのプリントが貼られている。
月夜は勉強を始めた。今日は、囀の家で朝を迎えたから、まだ勉強をしていなかった。
囀はというと、相変わらず机に突っ伏して眠っていた。彼女は、暇があればその格好になって、寝息を立てる習性を持つ。日頃から眠いのか、それとも、いざというときのためにエネルギーを貯蓄しているのか分からないが、いつでも眠れるのは、それだけ周囲を信用している証拠だともいえる。電車の中でも、彼女はきっと一人で眠る。それは、この国に住むほとんどの人間に共通することだ。
時間が経過するにつれて、徐々に生徒が登校してくるようになった。教室には挨拶が飛び交い、くだらない話題でときどき盛り上がる。けれど、盛り上がったあとには、鉄槌が下されるごとく静寂が訪れることが多い。消費されるように、次から次へと人間関係の糸が繋ぎ変えられていく。
そして、八時十五分になった頃、事態は動いた。
クラスメートの一人が、登校してきた途端、大きな声で、図書室の本が盗まれた、と報告した。
月夜は顔を上げて、そちらを見る。その女子生徒は、たしか図書委員の一人だった。各委員の担当者は二人いるが、もう一人は覚えていない。その生徒は、ほかのクラスメートに聞こえるように、事件の概要について大きな声で説明した。
彼女の話によると、小説が一冊何者かに持ち出されたらしい。その本は、ある一年生が予約していたもので、本来なら今日貸し出しされるはずだった。昨日の放課後、別の生徒から返却されたその本が、今朝になって、突然姿を消したということだ。
こんな、よくある話題でも、生徒の半分くらいは、僅かながら胸を踊らせる。
それは、学校が退屈な証拠か?
少なくとも、月夜には、そんなふうに思えてならなかった。
顔を上げて、月夜は囀を確認する。
彼女は、寝ていた。
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
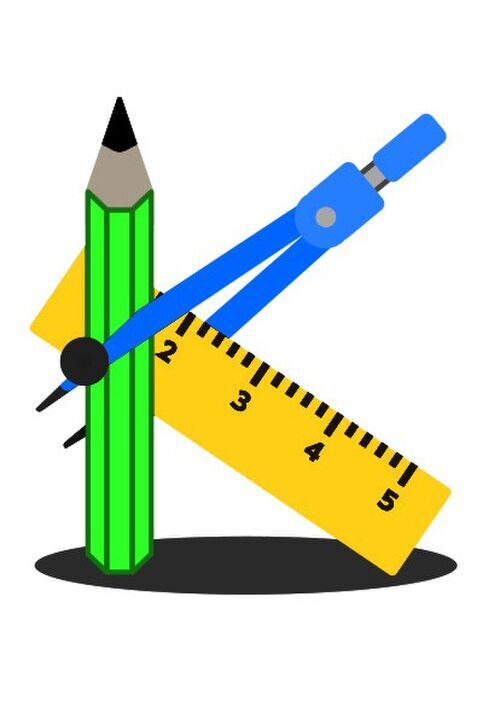
Next to Her Last Message
羽上帆樽
ライト文芸
森を抜けた先に、その邸宅はあった。草原が広がる雄大な空間に、ぽつんと建つ一軒の邸宅で、二人は女性から遺書の執筆作業を頼まれる。話によると、彼女は危篤の状態らしい。二人の子どもたちとともに一週間を過ごす中で、事態の食い違いに気がついた二人は、真の事実を知るべく観点を修正する。遺書とは何か? 誰のために書くのか? 答えはそれぞれ異なるもので良いが、そもそもの問題として、遺書を書く必要があるのかを考える必要がある。
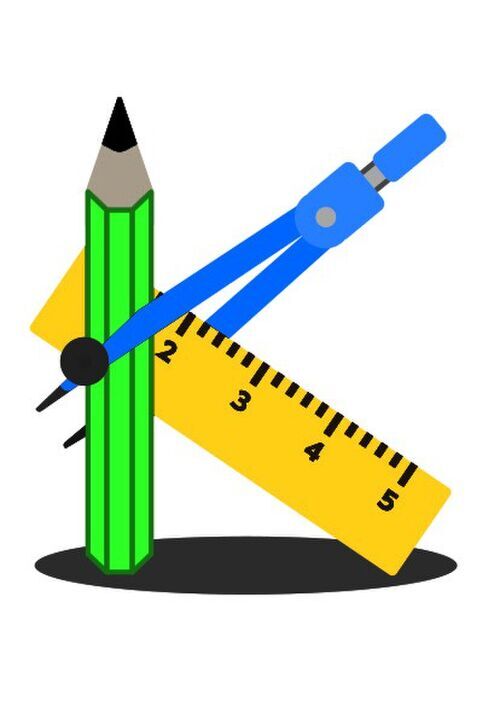
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
暗闇月夜は高校生になった。ここから彼女の物語は始まる。
行く先は不明。ただし、時間は常に人間の隣にあるが故に、進行を妨げることはできない。
毎日1000文字ずつ更新します。いつまで続くか分かりません。
終わりが不明瞭であるため、どこから入ってもらっても構いません。

【R15】メイド・イン・ヘブン
あおみなみ
ライト文芸
「私はここしか知らないけれど、多分ここは天国だと思う」
ミステリアスな美青年「ナル」と、恋人の「ベル」。
年の差カップルには、大きな秘密があった。

日給二万円の週末魔法少女 ~夏木聖那と三人の少女~
海獺屋ぼの
ライト文芸
ある日、女子校に通う夏木聖那は『魔法少女募集』という奇妙な求人広告を見つけた。
そして彼女はその求人の日当二万円という金額に目がくらんで週末限定の『魔法少女』をすることを決意する。
そんな普通の女子高生が魔法少女のアルバイトを通して大人へと成長していく物語。

薔薇の耽血(バラのたんけつ)
碧野葉菜
キャラ文芸
ある朝、萌木穏花は薔薇を吐いた——。
不治の奇病、“棘病(いばらびょう)”。
その病の進行を食い止める方法は、吸血族に血を吸い取ってもらうこと。
クラスメイトに淡い恋心を抱きながらも、冷徹な吸血族、黒川美汪の言いなりになる日々。
その病を、完治させる手段とは?
(どうして私、こんなことしなきゃ、生きられないの)
狂おしく求める美汪の真意と、棘病と吸血族にまつわる闇の歴史とは…?

パラダイス・ロスト
真波馨
ミステリー
架空都市K県でスーツケースに詰められた男の遺体が発見される。殺された男は、県警公安課のエスだった――K県警公安第三課に所属する公安警察官・新宮時也を主人公とした警察小説の第一作目。
※旧作『パラダイス・ロスト』を加筆修正した作品です。大幅な内容の変更はなく、一部設定が変更されています。旧作版は〈小説家になろう〉〈カクヨム〉にのみ掲載しています。

不眠症の上司と―― 千夜一夜の物語
菱沼あゆ
ライト文芸
「俺が寝るまで話し続けろ。
先に寝たら、どうなるのかわかってるんだろうな」
複雑な家庭環境で育った那智は、ある日、ひょんなことから、不眠症の上司、辰巳遥人を毎晩、膝枕して寝かしつけることになる。
職場では鬼のように恐ろしいうえに婚約者もいる遥人に膝枕なんて、恐怖でしかない、と怯える那智だったが。
やがて、遥人の不眠症の原因に気づき――。

〈社会人百合〉アキとハル
みなはらつかさ
恋愛
女の子拾いました――。
ある朝起きたら、隣にネイキッドな女の子が寝ていた!?
主人公・紅(くれない)アキは、どういったことかと問いただすと、酔っ払った勢いで、彼女・葵(あおい)ハルと一夜をともにしたらしい。
しかも、ハルは失踪中の大企業令嬢で……?
絵:Novel AI
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















