3 / 10
第3章 不平等
しおりを挟む
布団の中で目を覚ました。すぐ傍に、フィルの体温がある。月夜は起き上がり、軽く伸びをしてから立ち上がった。カーテンを開き、シャッターを上げる。まだ日は昇っていない。枕もとのデジタル時計は、午前五時を示している。空気は鉛のように冷えていた。
制服に着替えてから、フィルはそのままに、机に着いて勉強を始める。
朝のこの時間に勉強すると、なぜか集中できることが多かった。しようと思って集中することはないが、不思議と、今、集中できている、と実感する。集中しているときには、どんな雑念があっても、継続的に集中できる。本当に脳がはたらいているときは、自分を俯瞰的に見られるようになるみたいだ。
今日は数学の問題を解いた。月夜は、勉強を好きだと思ったことはないが、その中でも、数学は、まだ楽しい要素が多い、と感じる。覚えた方法を実際に使うのが、自分が成長しているみたいで面白いのかもしれない。実際に、それは成長できている証拠だし、勉強はそうやって進めていくものだ。けれど、古典とか、英語の勉強は、同じ性質を持っていながらも、いまいち面白さを感じにくい。この違いは、いったい何に起因するのだろうか。
途中で計算に行き詰まって、月夜はシャープペンシルを口に咥えた。
布団の方で気配がする。振り返ると、フィルが顔を上げてこちらを見ていた。
「やあ、今日も早いな、月夜」フィルが言った。
月夜は頷く。
「どうした? お腹が空いて、ついにペンを齧るようになったか?」
月夜は首を振った。
フィルは薄く笑い、大きな欠伸をする。
猫は、基本的に夜行性らしい。しかし、フィルは部分的には時間に束縛されていないから、どんな生活スタイルでも対応できる。もっとも、それは人間も同じだ。昼夜逆転生活を、逆転と認識していない人もいる。
何度考えても分からなかったから、月夜は教科書を見た。分からないところは、何が何でも自分の力で考え抜く、といったプライドは彼女にはない。教科書で調べるのも、自分の力を発揮している内だ。そして、そんな拘りは、ただ時間を無駄にするだけだ、とも思う。さらにいえば、時間を無駄にしない拘りというのも存在しない気がする。
解き方が分かって、なるほど、と彼女は思った。考えてみれば当たり前の話だった。しかし、それを当たり前と感じるのは、理論を逆に進んでいるからであり、正しい方向に進んだ場合は、こんなの分かるわけがない、と思うことが多い。
現実の社会も、きっとそうだろう。人間は、創造と破壊の歴史を繰り返してきたが、それを愚かだと感じるのは、現在から過去を振り返っているからだ。自分がその時代の当事者だったら、そんなふうには考えられない。
一時間が経過して、月夜は席を立った。
「もういいのか?」フィルが尋ねる。
「うん」リュックとブレザーを持って、月夜は部屋から出た。
蛇口から出る水は冷たかった。顔の感覚がなくなるような感じがする。手の感覚も一時的になくなった。一応、毎朝肌の手入れはしている。自分の美しさなんて、他人からしたらどうでも良いだろうが、なんとなく、そうしておいた方が良い気がする、というのがその理由だが、やめようと思えばいつでもやめられそうだった(あえてやめる必要もないが)。髪も、寝ていたから、当然、乱れている。手櫛で解し、プラスチック製の櫛でさらに梳かして、なるべくストレートになるように工夫する。もっとも、月夜はそれほど髪は長くないから、平均よりは時間はかからなかった。
リビングに入り、すべてのシャッターを上げる。
すぐに踵を返し、靴を履いて、月夜は玄関の外に出た。
途中までフィルも一緒だったが、散歩に出かけると言って、彼はどこかに行ってしまった。
人気のない冬の道を、月夜は一人で歩く。マンホールを踏んでみたが、特に滑らなかった。
寂れた駅舎に入り、改札を通って、ホームに立つ。
背後に自動販売機。そのモーター音が、この静かな街に似合っているように思えた。
空は、まだ滲むように明るくなり始めたばかりで、夜と朝の境界といえる。
雲が浮かんでいた。
間もなく、電車がやって来る。車内は空いており、月夜はいつもの席に腰かけた。たまに別の席を選ぶこともあるが、今日は意識的に昨日と同じ席を選んだ。そうすれば、囀に会える可能性が高い、と考えたからだ。
そして、予想した通りに、いくつか先の駅で囀が乗車してきた。
「やあ、おはよう」にこにこしながら、囀が言った。
月夜は軽く頷く。囀は月夜の右隣に腰かけ、鞄を膝の上に載せた。彼女はスカートを履いている。
「本は、面白かった?」月夜は尋ねた。
「ああ、うん、面白かったよ」囀は話す。「なかなかファンタジックで、うーん、最近読んだ中では、けっこう上位かな」
「最近は、ほかに、どんな本を読んだの?」
「色々とね」囀は身体を倒し、月夜の顔を下から覗き込む。「国語辞書とか、恋愛小説とか、子ども用の絵本とか、色々」
「本、好き?」
「好きだって、昨日言わなかったっけ?」
「うん、言った」
「好きという言葉を、聞きたいの?」
「うん、聞きたい」
「好きだよ、月夜」
「何が?」
「本が」
いつもの駅で電車を降りる。人気はない。道路は、一部が凍っていた。昨日雨が降ったのか、それとも露が下りたのか、分からなかった。
「そういえば、囀は、どうして、今日も、こんなに早く学校に行くの?」
道路を歩きながら月夜は尋ねた。
「月夜に、会えると思ったからだよ」囀は答える。「予想、当たってよかった」
予想ではなく、予測ではないか、と月夜は思ったが、黙っていた。
「そういう月夜は、どうして? どうして、毎朝早く行くの?」
「遅れるよりは、いいから」
「遅刻は嫌い? 優等生なんだね、月夜って」
「遅刻は、好きではない。優等生というのは、違うと思う」
「夜遅くまで、学校に残っているからね」
「うん……」
囀は楽しそうだ。
月夜は、目だけで彼女の表情を確認した。
「今日さ、学校が終わったあと、出かけようよ」歩いていると、突然囀が提案した。「月夜さ、買い物とか、あまりしない方じゃない? 僕が案内するから、一緒に行こう」
「買いたいものは、ない」
「じゃあ、僕のショッピングに付き合って」
月夜は頷く。
「分かった」
「やったね」
学校の門が見える。隣の小さな扉から敷地内に入る。今日は、二人とも昇降口に向かった。ロッカータイプの下駄箱から上履きを取り出し、置いたままになっている教科書もリュックに入れる。反対に、今日使わない参考書は、下駄箱の中に仕舞っておいた。囀は、まだ教科書が届いていないようだ。
階段を上り、教室に到着する。
「誰もいない教室って、最高だよね」自分の席に座りながら、囀が言った。
「いつも、自分がいる」
「それ、どういう意味?」
「自分をカウントするか、しないか、という問題」
「ああ、そういうこと」囀は頷く。「うんうん、たしかに、気づかなかったなあ……」
基本的に、月夜の机の中には、何も入っていない。教科書の類は、すべてさっきの下駄箱に仕舞うようにしている。
「ねえ、月夜さ、ちょっと、学校を案内してよ」
「案内?」月夜は顔を上げる。
「そうそう」囀は言った。「まだ、慣れていないから、どこに何があるのか、教えて」
「いいよ」
廊下に出ると、教室より寒かった。窓が所々開いているからだ。中庭の噴水は今日も凍っている。眼下に見える食堂の屋根には、薄く霜が貼り付いていた。
廊下を進み、移動教室、音楽室、各科目の教員の部屋など、色々な場所を巡った。といっても、月夜もすべての部屋を知っているわけではない。自分とは関係のない科目の教室は知らないし、管理人室など、存在は知っていても、どこにあるのか分からない部屋もある。そういう意味では、学校探検は月夜も面白かった。途中で何人か教員とすれ違ったが、誰も二人を気に留めなかった。
美術室の前にやって来たとき、囀がその中に入りたいと言い出した。
「鍵がかかっているから、開かないよ」月夜は言った。
「でも、入りたい」囀は催促する。「どんな感じか、見てみたい」
「どうして?」
「単純な興味だよ。月夜は、入ったことあるの?」
「一年生の頃に、何度か」
「気になる」囀は月夜の袖を掴む。「先生、呼んできてよ」
「まだ、来ていないよ」月夜は言った。「隣が、準備室だから、そこにいるはずだけど、まだ、電気が点いていない」
「じゃあ、ここで待っていよう」
「寒いけど、平気?」
「うん、全然大丈夫」
そういうことで、二人で美術室の前に立ち尽くすことになった。
月夜は正面を向いたまま固まり、囀は後ろを向いて窓の外を見ている。
こんなふうに、二人で学校の中を歩き回るのは、久し振りだな、と月夜は思った。
楽しくないわけではない。むしろ、心は躍っている。
けれど……。
心の底からは、楽しめなかった。
心というものが自分にはあるのか、月夜は分からない。そして、何をやっても楽しめないのは、彼女の特徴だった。楽しい気はする。ただ、それが本当の意味で楽しいのか、分からない。楽しさの上澄みにだけ触れて、楽しんでいるふりをしているだけかもしれない。
それは、楽しみだけでなく、悲しみも、寂しさも、すべてそうだった。美味しさだって、きっとその内の一つだろう。
自分は、囀が死んでも、きっと悲しめないし、寂しさも感じられない、と月夜は思う。
それは、いけないことか?
世間的には、そうだろう。
でも、人が死ぬのは、当たり前のことだ。
それを、いちいち悲しんだり、寂しいと思うのは、なぜか?
今日も酸素が存在しているのを確認して、喜ぶ人間がいるだろうか?
両者は、当たり前という意味で、共通している。
それなのに、どうして、違う問題として扱いたがるのか?
不思議だった。
二十分くらいしたところで、美術の教師がやって来た。まだ若い女性で、痩せている。月夜が事情を話すと、快く承諾してくれた。教師は準備室を通って教室に移動し、中から鍵を開ける。彼女は、これから職員会議があるといって、すぐにその場から立ち去った。見学が終わったら、そのままにして、戻って良いとのことだった。
美術室には、木製の大きな机が六つ並んでいる。一つ一つの机には、周囲にそれぞれ六脚ずつ椅子が配置されている。六、という数字に、何か拘りがあるのかもしれない、と月夜は考えたが、教室の広さと、机の大きさを考えれば、その数が一番纏まりが良いのかもしれない。
窓枠のちょっとしたスペースに、ほかの学年の生徒が作った工作が置かれていた。紙で作られているが、何か分からない。絵の具が塗られていて、奇妙な色彩だった。
部屋は、どちらかというと、埃っぽい。しかし、汚いという印象は受けない。適度に汚れている。生活感がある、とでもいえば良いか。
窓があるのとは反対側の壁には、硝子で覆われた棚があって、廊下から見ると、ショーウインドウのようになっているのが分かる。そこには、油絵が飾られていた。人の手を描いたものだ。
「なんか、いいなあ」教室の中をゆっくり歩き回りながら、囀が言った。
「囀は、美術が好きなの?」
「美術って、何だと思う?」
月夜は考える。
「絵画や、彫刻」
「それだけ?」
「私には、分からない」
「実は、僕もだよ」囀は笑った。「でもね、美術、という言葉の響きが、好きなの」
「言葉?」
「うーん、それも、少し違うかな……。言葉、というか、美術、という概念が好き、の方が近いかな」
「なんとなく、分かるような、気が、しない、でもない」
教室の後ろには、人物画のモデルにでもするのか、白い石材で作られた、上半身だけの人形が置かれている。西洋的な雰囲気だ。大半は布がかけられているが、いくつかは、それが剥がれて、生気のない目がこちらを見ていた。
「囀は、美術部に入るの?」
月夜が尋ねると、囀は彼女の方を見た。
「入らないよ。月夜は?」
「部活?」
「そう」
「入っていない」
「ま、そうだよね」
「どうして?」
「なんとなく」囀は話す。「そんな感じがする」
美術室の見学は、十五分ほどで終わった。廊下に出ると、もう生徒の声が溢れていた。階段を下り、教室に向かう。部屋に入り、それぞれ自分の席に着いた。
月夜は、昨日日直だったから、今日の担当者に日誌を渡した。日誌は、何のためにあると思うか、とその生徒に訊いても良かったが、変な印象を抱かれると思って、やめておいた。
担任が教室に入ってくる。しかし、まだホームルームが始まる時間ではない。
教室は、魂が解放されたように騒がしい。大勢の笑い声が木霊して、ハウリングみたいになっている。何も、具体的な内容は聞き取れない。つまり、雑音でしかない。けれど、聞いていて不快ではなかった。そこには、すぐ傍に人がいる、友達でも、全然親しくもない、ただの知り合いにも関わらず、人の暖かさ、人が傍にいるという安心さが、確かに感じられる。
結局、人は一人では生きていけない、という指摘は、間違えていないのだ、と月夜は思う。
結局、と断る意味は何か?
一人で生きていけないことはないと、抗おうとした爪痕か?
では、どうして、一人で生きていこうとしたのか?
どうして、そんなことを思ったのか?
なぜか?
抵抗こそが、生きるための活力だからか?
チャイムが鳴り、ホームルームの時間になる。全員で起立し、礼をする。そして、また着席。
教師が今日の連絡事項を伝え、それに少数の生徒が反応する。伝達がすべて終われば、受信する側は回線を断ち切る。
一時限目の授業は、古典だった。教室を移動する必要はない。
五分間だけ空き時間があるが、その間に、囀が月夜の傍にやって来た。
「何?」
彼女が何も言わないから、月夜は囀に尋ねた。
「今日さ、お昼、一緒に食べようよ」
「お昼?」月夜は話す。「私は、ご飯は食べない」
「月夜の分まで作ってきたから、食べてよ」囀は言った。「僕が、そうしてほしいの。迷惑かもしれないけど、どうしても、食べてもらいたい」
月夜は頷いた。
「分かった。じゃあ、食べる」
囀は微笑んだ。
古典の授業は、いつも通り退屈だった。退屈、というのは少し間違えている。内容が退屈なのではなく、やっていることがいつもと同じで、好い加減飽きてきた、というのが詳細な説明になる。
文章を読んで、内容を理解する。
しかし、それまでだ。
それ以上続かない。
そこから発展させて、何かを考えることは皆無に等しい。
なぜ、こんなことをやらせるのか、という問いの答えは、大学受験で必要だから、というものになるのだろう。
あまり、良くはない、と月夜は思う。
良くない、というのは、いまいち分からない感情だが……。
シャープペンシルを指で回して、空気を撹拌した。
そんな調子で授業を受けて、あっという間に昼になった。囀に教室から連れ出され、彼女のあとをついていくと、屋上へと続く階段の踊り場に案内された。
「ここで、食べよう」囀は言った。「なんか、いい感じの雰囲気だし」
月夜には、彼女の言う、良い感じの雰囲気、というのが分からなかった。
囀は、本当に二人分の弁当を作ってきていた。そう言っていたのだから、当たり前だが、出任せの可能性も月夜は想定していた。しかし、それならそれでも良い、と彼女は考える。出任せを言ってまで、自分と一緒に昼食をとりたかったのだ、と思えば、嬉しくなるからだ。
囀が作ってきたのは、サンドウィッチだった。玉子やレタス、ハムなどが挟まれた標準的なもので、少しスパイシーだった。調味料は、胡椒とマヨネーズらしい。不思議な組み合わせだったが、初めての味で、美味しかった。
「月夜はさ、どうして、いつも、お弁当食べないの?」
口にパンを詰めながら、囀が質問した。
月夜はお茶を飲み、彼女の質問に答える。
「食べたい、と思わないから」
「お腹、空かないの?」
「空くけど、それほど、空かない」
囀は笑った。
「変なの。どっち? 食べられないわけじゃないんでしょう?」
「うん」
「食べたくないのは、ほかに理由があるの?」
「食べたくないわけじゃないよ。食べたい、と思わないだけ」月夜は説明する。「ほかには、死んだ生き物を、自分の身体に入れたくないから、というのもある」
囀は、月夜をじっと見つめる。
「それ、冗談?」
「冗談?」
「いや、何でもないや」囀は言った。「そっか……。それは、うん、まあ……、分からなくはないよ。動物を殺すのって、可哀相だもんね」
「うん」
「でもさ、自分で取り込もうと思わなくても、たとえば、細菌とか、微生物は、身体の中に入ってくるよ」
「そう……。だから、矛盾している」
そう言って、月夜は下を向く。パンを千切って口に入れ、ゆっくりと咀嚼した。
「そんなことを、考えているの?」
月夜は顔を上げる。
「え?」
「なんか、月夜って、思っていた以上に深刻だね」
「そうかな」
「そうだよ、絶対」囀は笑顔で言った。「もう少し、自分に優しくしてもいいんじゃない?」
自分に優しくするとは、どういう意味だろう、と月夜は考える。
「どうしたら、自分に優しくできるの?」
「え? うーん、それは……」囀は腕を組む。「自分が、本当にやりたいと思うことに、素直になる、とかかな」
月夜は頷く。
「なるほど」
「月夜は、本当に、何も食べたくないと思うの?」
「たぶん」
「そっか……。……うーん、じゃあ、しょうがないなあ……」
階段の踊り場は、薄暗くて、少し埃っぽかった。美術室よりは汚い。すぐ傍にドアがあり、その先には屋上が続いている。普通は、その先は生徒だけでは入れない。天文学部など、一部の部活動は利用しているらしいが、飛び降り自殺を防ぐためか、普段は鍵がかかっている。天文学部の人間は、飛び降りても良い、ということだろうか。ルールとしては、多少おかしいと思われるが……。
「月夜、今日の午後、付き合ってね」
囀が二つ目のサンドウィッチを手に持って、月夜に話しかけた。
「買い物?」月夜は首を傾げる。
「うん、そう。きっと楽しいよ。色々、知らないものが見られて、感動するかも」
「最近、感動する経験をしていない」
「じゃあ、ちょうどいいじゃん。やっぱり、定期的に感動しないと、人に優しくできないもんね」
「そうなの?」
「僕の見解では」囀は頷く。
「囀は、人に優しくしたいの?」
「え? ああ、うん、どうかな……。……優しくして、損はないかな、という程度かな」
「今でも、平均的には、優しいと思うよ」
「それ、褒めているの?」囀は苦笑いする。
「特に、褒めてはいない。それが事実だと思った」
「そう言われると、なんだか嬉しいかも」
「あと、人にだけじゃなくて、自分にも、優しい、と思う」
「うーん、それはどうかなあ……」
「さっき、そう説明していなかった?」
「ああ、そういうこと? あ、そうか。じゃあ、さっきの説明は、なかったことにして」
「どうして?」
「いやあ、だってさあ……」囀は言った。「なんか、恥ずかしいから」
「分かった。なかったことにする」
「え、いや、それは、ちょっと、困る」
「何が?」
「説明するのが難しい」
「簡単な説明って、ある?」
「あるよ」
「たとえば?」
「たとえば……。……ジョン万次郎の本名が、意外と知られていない理由、とか」
昼食をとり終え、二人は教室に戻った。午後の授業が始まるまで、あと二十分ほどある。囀は、自分の机に突っ伏して眠ってしまった。月夜は、次の英語の授業でテストがあるから、軽くその復習をした。
長閑な昼休みだ。
一生、このままでも良かった。
午後の授業が始まり、テスト用紙が配られた。これは、いわゆる小テストと呼ばれるもので、定期的に行われ、僅かに成績に加算される。成績に加算されるというだけで、どういうわけか、生徒はやる気を出す。まるで、成績をとるために学校に来ているみたいだ。
でも、自分のその内の一人だ、と月夜は思った。
もちろん、それだけではないが、それを大切にしているのは確かだ。
難なくテストが終わり、通常の授業に入る。ネイティブが話す音声を聞いて、教科書に書かれた内容を確認する。分からない単語があれば、その都度調べ、記憶しようと努力する。プリントが配られ、近所の生徒と、互いに発音し合ったり、問題を出し合ったりするパートもあった。どれも、事務的で、あまり面白くなかった。
英文を一人で読んでいるときが、きっと一番面白い。
今日は、冬休み明けだから、午後の授業はそれだけだった。
他人の教師が教室に戻ってきて、ホームルームを行う。今日は、掃除がある日だが、月夜は担当ではなかった。机の上に椅子を載せて、前に移動させ、昇降口へ向かう。囀も掃除はなかったから、彼女と一緒に廊下を歩いた。
「学校って、楽しいね」囀が言った。
「どういうところが?」
「なんか、ほのぼのとしているところとか」
月夜は、彼女が言った意味を考える。
「月夜は、どう? 学校は好き?」
「うん、少しは」
「あ、じゃあ、嫌いなところもあるの?」
「それは、どんなものでも、そう」
「まあ、そうだね」
靴を履き替えて外に出る。月夜は、この時間帯に帰るのは久し振りだった。多くの生徒が、流れを作りながら、駅へと向かって歩いている。最寄り駅はその一つしかなく、そして、皆同じ路線だから、この集団が、車内まで続くことになる。上りと下りで二手に分かれるから、人数は半分になるが、空間が狭くなるせいで、密度はむしろ上がる。
いつも通りの電車に乗って、月夜と囀は帰路についた。車内は混んでいたから、座ることはできなかった。
囀は、いつも降りる駅を通り過ぎて、月夜の家がある方向にさらに進み、途中の駅で下車した。月夜も彼女に続く。
都会とも、田舎ともいえない、そんな街だった。
交通量は、多いともいえないし、少ないともいえない。
景観も、良いともいえないし、悪いともいえそうにない。
曖昧さを売りにしているような気さえする。
囀のあとについて歩き、駅構内に築かれたデパートに入った。
「月夜は、何か、見たいものはある?」歩きながら、囀が尋ねた。
「ない」月夜は答える。
混雑しているが、歩くのが困難なほどではない。
某有名なブランドの洋服売り場に来て、二人はそこで衣服を見た。
「これ、似合いそうじゃない?」
そう言って囀が持ってきたのは、黒いカーディガンだった。
月夜は、それを受け取り、上半身に当てる。鏡の前に立ち、自分の姿を見た。
「自分では、分からない」
「似合っていると思うよ。僕が、プレゼントしようか?」
「いや、いいよ」
「いやいや、付き合ってもらっているんだし、遠慮することないって」
「カーディガンは、持っているから、いらない」
「じゃあ、何が欲しい?」
「うーん、何も……」
そう言いかけたとき、ベージュ色のロングスカートが月夜の視界に入った。
「……そういえば、スカートは、あまり持っていなかった」
囀は、月夜が見ているスカートを取り、彼女に当てる。
「うん、なかなかいいじゃん。じゃあ、それね」
「囀の方が、似合うんじゃない?」
「うーん、どうかなあ」
「何を着ても、似合うと思うよ」
囀は、目を細めて、口もとを上げる。
「どうもありがとう」彼女は言った。「でも、それ、知っているよ」
制服に着替えてから、フィルはそのままに、机に着いて勉強を始める。
朝のこの時間に勉強すると、なぜか集中できることが多かった。しようと思って集中することはないが、不思議と、今、集中できている、と実感する。集中しているときには、どんな雑念があっても、継続的に集中できる。本当に脳がはたらいているときは、自分を俯瞰的に見られるようになるみたいだ。
今日は数学の問題を解いた。月夜は、勉強を好きだと思ったことはないが、その中でも、数学は、まだ楽しい要素が多い、と感じる。覚えた方法を実際に使うのが、自分が成長しているみたいで面白いのかもしれない。実際に、それは成長できている証拠だし、勉強はそうやって進めていくものだ。けれど、古典とか、英語の勉強は、同じ性質を持っていながらも、いまいち面白さを感じにくい。この違いは、いったい何に起因するのだろうか。
途中で計算に行き詰まって、月夜はシャープペンシルを口に咥えた。
布団の方で気配がする。振り返ると、フィルが顔を上げてこちらを見ていた。
「やあ、今日も早いな、月夜」フィルが言った。
月夜は頷く。
「どうした? お腹が空いて、ついにペンを齧るようになったか?」
月夜は首を振った。
フィルは薄く笑い、大きな欠伸をする。
猫は、基本的に夜行性らしい。しかし、フィルは部分的には時間に束縛されていないから、どんな生活スタイルでも対応できる。もっとも、それは人間も同じだ。昼夜逆転生活を、逆転と認識していない人もいる。
何度考えても分からなかったから、月夜は教科書を見た。分からないところは、何が何でも自分の力で考え抜く、といったプライドは彼女にはない。教科書で調べるのも、自分の力を発揮している内だ。そして、そんな拘りは、ただ時間を無駄にするだけだ、とも思う。さらにいえば、時間を無駄にしない拘りというのも存在しない気がする。
解き方が分かって、なるほど、と彼女は思った。考えてみれば当たり前の話だった。しかし、それを当たり前と感じるのは、理論を逆に進んでいるからであり、正しい方向に進んだ場合は、こんなの分かるわけがない、と思うことが多い。
現実の社会も、きっとそうだろう。人間は、創造と破壊の歴史を繰り返してきたが、それを愚かだと感じるのは、現在から過去を振り返っているからだ。自分がその時代の当事者だったら、そんなふうには考えられない。
一時間が経過して、月夜は席を立った。
「もういいのか?」フィルが尋ねる。
「うん」リュックとブレザーを持って、月夜は部屋から出た。
蛇口から出る水は冷たかった。顔の感覚がなくなるような感じがする。手の感覚も一時的になくなった。一応、毎朝肌の手入れはしている。自分の美しさなんて、他人からしたらどうでも良いだろうが、なんとなく、そうしておいた方が良い気がする、というのがその理由だが、やめようと思えばいつでもやめられそうだった(あえてやめる必要もないが)。髪も、寝ていたから、当然、乱れている。手櫛で解し、プラスチック製の櫛でさらに梳かして、なるべくストレートになるように工夫する。もっとも、月夜はそれほど髪は長くないから、平均よりは時間はかからなかった。
リビングに入り、すべてのシャッターを上げる。
すぐに踵を返し、靴を履いて、月夜は玄関の外に出た。
途中までフィルも一緒だったが、散歩に出かけると言って、彼はどこかに行ってしまった。
人気のない冬の道を、月夜は一人で歩く。マンホールを踏んでみたが、特に滑らなかった。
寂れた駅舎に入り、改札を通って、ホームに立つ。
背後に自動販売機。そのモーター音が、この静かな街に似合っているように思えた。
空は、まだ滲むように明るくなり始めたばかりで、夜と朝の境界といえる。
雲が浮かんでいた。
間もなく、電車がやって来る。車内は空いており、月夜はいつもの席に腰かけた。たまに別の席を選ぶこともあるが、今日は意識的に昨日と同じ席を選んだ。そうすれば、囀に会える可能性が高い、と考えたからだ。
そして、予想した通りに、いくつか先の駅で囀が乗車してきた。
「やあ、おはよう」にこにこしながら、囀が言った。
月夜は軽く頷く。囀は月夜の右隣に腰かけ、鞄を膝の上に載せた。彼女はスカートを履いている。
「本は、面白かった?」月夜は尋ねた。
「ああ、うん、面白かったよ」囀は話す。「なかなかファンタジックで、うーん、最近読んだ中では、けっこう上位かな」
「最近は、ほかに、どんな本を読んだの?」
「色々とね」囀は身体を倒し、月夜の顔を下から覗き込む。「国語辞書とか、恋愛小説とか、子ども用の絵本とか、色々」
「本、好き?」
「好きだって、昨日言わなかったっけ?」
「うん、言った」
「好きという言葉を、聞きたいの?」
「うん、聞きたい」
「好きだよ、月夜」
「何が?」
「本が」
いつもの駅で電車を降りる。人気はない。道路は、一部が凍っていた。昨日雨が降ったのか、それとも露が下りたのか、分からなかった。
「そういえば、囀は、どうして、今日も、こんなに早く学校に行くの?」
道路を歩きながら月夜は尋ねた。
「月夜に、会えると思ったからだよ」囀は答える。「予想、当たってよかった」
予想ではなく、予測ではないか、と月夜は思ったが、黙っていた。
「そういう月夜は、どうして? どうして、毎朝早く行くの?」
「遅れるよりは、いいから」
「遅刻は嫌い? 優等生なんだね、月夜って」
「遅刻は、好きではない。優等生というのは、違うと思う」
「夜遅くまで、学校に残っているからね」
「うん……」
囀は楽しそうだ。
月夜は、目だけで彼女の表情を確認した。
「今日さ、学校が終わったあと、出かけようよ」歩いていると、突然囀が提案した。「月夜さ、買い物とか、あまりしない方じゃない? 僕が案内するから、一緒に行こう」
「買いたいものは、ない」
「じゃあ、僕のショッピングに付き合って」
月夜は頷く。
「分かった」
「やったね」
学校の門が見える。隣の小さな扉から敷地内に入る。今日は、二人とも昇降口に向かった。ロッカータイプの下駄箱から上履きを取り出し、置いたままになっている教科書もリュックに入れる。反対に、今日使わない参考書は、下駄箱の中に仕舞っておいた。囀は、まだ教科書が届いていないようだ。
階段を上り、教室に到着する。
「誰もいない教室って、最高だよね」自分の席に座りながら、囀が言った。
「いつも、自分がいる」
「それ、どういう意味?」
「自分をカウントするか、しないか、という問題」
「ああ、そういうこと」囀は頷く。「うんうん、たしかに、気づかなかったなあ……」
基本的に、月夜の机の中には、何も入っていない。教科書の類は、すべてさっきの下駄箱に仕舞うようにしている。
「ねえ、月夜さ、ちょっと、学校を案内してよ」
「案内?」月夜は顔を上げる。
「そうそう」囀は言った。「まだ、慣れていないから、どこに何があるのか、教えて」
「いいよ」
廊下に出ると、教室より寒かった。窓が所々開いているからだ。中庭の噴水は今日も凍っている。眼下に見える食堂の屋根には、薄く霜が貼り付いていた。
廊下を進み、移動教室、音楽室、各科目の教員の部屋など、色々な場所を巡った。といっても、月夜もすべての部屋を知っているわけではない。自分とは関係のない科目の教室は知らないし、管理人室など、存在は知っていても、どこにあるのか分からない部屋もある。そういう意味では、学校探検は月夜も面白かった。途中で何人か教員とすれ違ったが、誰も二人を気に留めなかった。
美術室の前にやって来たとき、囀がその中に入りたいと言い出した。
「鍵がかかっているから、開かないよ」月夜は言った。
「でも、入りたい」囀は催促する。「どんな感じか、見てみたい」
「どうして?」
「単純な興味だよ。月夜は、入ったことあるの?」
「一年生の頃に、何度か」
「気になる」囀は月夜の袖を掴む。「先生、呼んできてよ」
「まだ、来ていないよ」月夜は言った。「隣が、準備室だから、そこにいるはずだけど、まだ、電気が点いていない」
「じゃあ、ここで待っていよう」
「寒いけど、平気?」
「うん、全然大丈夫」
そういうことで、二人で美術室の前に立ち尽くすことになった。
月夜は正面を向いたまま固まり、囀は後ろを向いて窓の外を見ている。
こんなふうに、二人で学校の中を歩き回るのは、久し振りだな、と月夜は思った。
楽しくないわけではない。むしろ、心は躍っている。
けれど……。
心の底からは、楽しめなかった。
心というものが自分にはあるのか、月夜は分からない。そして、何をやっても楽しめないのは、彼女の特徴だった。楽しい気はする。ただ、それが本当の意味で楽しいのか、分からない。楽しさの上澄みにだけ触れて、楽しんでいるふりをしているだけかもしれない。
それは、楽しみだけでなく、悲しみも、寂しさも、すべてそうだった。美味しさだって、きっとその内の一つだろう。
自分は、囀が死んでも、きっと悲しめないし、寂しさも感じられない、と月夜は思う。
それは、いけないことか?
世間的には、そうだろう。
でも、人が死ぬのは、当たり前のことだ。
それを、いちいち悲しんだり、寂しいと思うのは、なぜか?
今日も酸素が存在しているのを確認して、喜ぶ人間がいるだろうか?
両者は、当たり前という意味で、共通している。
それなのに、どうして、違う問題として扱いたがるのか?
不思議だった。
二十分くらいしたところで、美術の教師がやって来た。まだ若い女性で、痩せている。月夜が事情を話すと、快く承諾してくれた。教師は準備室を通って教室に移動し、中から鍵を開ける。彼女は、これから職員会議があるといって、すぐにその場から立ち去った。見学が終わったら、そのままにして、戻って良いとのことだった。
美術室には、木製の大きな机が六つ並んでいる。一つ一つの机には、周囲にそれぞれ六脚ずつ椅子が配置されている。六、という数字に、何か拘りがあるのかもしれない、と月夜は考えたが、教室の広さと、机の大きさを考えれば、その数が一番纏まりが良いのかもしれない。
窓枠のちょっとしたスペースに、ほかの学年の生徒が作った工作が置かれていた。紙で作られているが、何か分からない。絵の具が塗られていて、奇妙な色彩だった。
部屋は、どちらかというと、埃っぽい。しかし、汚いという印象は受けない。適度に汚れている。生活感がある、とでもいえば良いか。
窓があるのとは反対側の壁には、硝子で覆われた棚があって、廊下から見ると、ショーウインドウのようになっているのが分かる。そこには、油絵が飾られていた。人の手を描いたものだ。
「なんか、いいなあ」教室の中をゆっくり歩き回りながら、囀が言った。
「囀は、美術が好きなの?」
「美術って、何だと思う?」
月夜は考える。
「絵画や、彫刻」
「それだけ?」
「私には、分からない」
「実は、僕もだよ」囀は笑った。「でもね、美術、という言葉の響きが、好きなの」
「言葉?」
「うーん、それも、少し違うかな……。言葉、というか、美術、という概念が好き、の方が近いかな」
「なんとなく、分かるような、気が、しない、でもない」
教室の後ろには、人物画のモデルにでもするのか、白い石材で作られた、上半身だけの人形が置かれている。西洋的な雰囲気だ。大半は布がかけられているが、いくつかは、それが剥がれて、生気のない目がこちらを見ていた。
「囀は、美術部に入るの?」
月夜が尋ねると、囀は彼女の方を見た。
「入らないよ。月夜は?」
「部活?」
「そう」
「入っていない」
「ま、そうだよね」
「どうして?」
「なんとなく」囀は話す。「そんな感じがする」
美術室の見学は、十五分ほどで終わった。廊下に出ると、もう生徒の声が溢れていた。階段を下り、教室に向かう。部屋に入り、それぞれ自分の席に着いた。
月夜は、昨日日直だったから、今日の担当者に日誌を渡した。日誌は、何のためにあると思うか、とその生徒に訊いても良かったが、変な印象を抱かれると思って、やめておいた。
担任が教室に入ってくる。しかし、まだホームルームが始まる時間ではない。
教室は、魂が解放されたように騒がしい。大勢の笑い声が木霊して、ハウリングみたいになっている。何も、具体的な内容は聞き取れない。つまり、雑音でしかない。けれど、聞いていて不快ではなかった。そこには、すぐ傍に人がいる、友達でも、全然親しくもない、ただの知り合いにも関わらず、人の暖かさ、人が傍にいるという安心さが、確かに感じられる。
結局、人は一人では生きていけない、という指摘は、間違えていないのだ、と月夜は思う。
結局、と断る意味は何か?
一人で生きていけないことはないと、抗おうとした爪痕か?
では、どうして、一人で生きていこうとしたのか?
どうして、そんなことを思ったのか?
なぜか?
抵抗こそが、生きるための活力だからか?
チャイムが鳴り、ホームルームの時間になる。全員で起立し、礼をする。そして、また着席。
教師が今日の連絡事項を伝え、それに少数の生徒が反応する。伝達がすべて終われば、受信する側は回線を断ち切る。
一時限目の授業は、古典だった。教室を移動する必要はない。
五分間だけ空き時間があるが、その間に、囀が月夜の傍にやって来た。
「何?」
彼女が何も言わないから、月夜は囀に尋ねた。
「今日さ、お昼、一緒に食べようよ」
「お昼?」月夜は話す。「私は、ご飯は食べない」
「月夜の分まで作ってきたから、食べてよ」囀は言った。「僕が、そうしてほしいの。迷惑かもしれないけど、どうしても、食べてもらいたい」
月夜は頷いた。
「分かった。じゃあ、食べる」
囀は微笑んだ。
古典の授業は、いつも通り退屈だった。退屈、というのは少し間違えている。内容が退屈なのではなく、やっていることがいつもと同じで、好い加減飽きてきた、というのが詳細な説明になる。
文章を読んで、内容を理解する。
しかし、それまでだ。
それ以上続かない。
そこから発展させて、何かを考えることは皆無に等しい。
なぜ、こんなことをやらせるのか、という問いの答えは、大学受験で必要だから、というものになるのだろう。
あまり、良くはない、と月夜は思う。
良くない、というのは、いまいち分からない感情だが……。
シャープペンシルを指で回して、空気を撹拌した。
そんな調子で授業を受けて、あっという間に昼になった。囀に教室から連れ出され、彼女のあとをついていくと、屋上へと続く階段の踊り場に案内された。
「ここで、食べよう」囀は言った。「なんか、いい感じの雰囲気だし」
月夜には、彼女の言う、良い感じの雰囲気、というのが分からなかった。
囀は、本当に二人分の弁当を作ってきていた。そう言っていたのだから、当たり前だが、出任せの可能性も月夜は想定していた。しかし、それならそれでも良い、と彼女は考える。出任せを言ってまで、自分と一緒に昼食をとりたかったのだ、と思えば、嬉しくなるからだ。
囀が作ってきたのは、サンドウィッチだった。玉子やレタス、ハムなどが挟まれた標準的なもので、少しスパイシーだった。調味料は、胡椒とマヨネーズらしい。不思議な組み合わせだったが、初めての味で、美味しかった。
「月夜はさ、どうして、いつも、お弁当食べないの?」
口にパンを詰めながら、囀が質問した。
月夜はお茶を飲み、彼女の質問に答える。
「食べたい、と思わないから」
「お腹、空かないの?」
「空くけど、それほど、空かない」
囀は笑った。
「変なの。どっち? 食べられないわけじゃないんでしょう?」
「うん」
「食べたくないのは、ほかに理由があるの?」
「食べたくないわけじゃないよ。食べたい、と思わないだけ」月夜は説明する。「ほかには、死んだ生き物を、自分の身体に入れたくないから、というのもある」
囀は、月夜をじっと見つめる。
「それ、冗談?」
「冗談?」
「いや、何でもないや」囀は言った。「そっか……。それは、うん、まあ……、分からなくはないよ。動物を殺すのって、可哀相だもんね」
「うん」
「でもさ、自分で取り込もうと思わなくても、たとえば、細菌とか、微生物は、身体の中に入ってくるよ」
「そう……。だから、矛盾している」
そう言って、月夜は下を向く。パンを千切って口に入れ、ゆっくりと咀嚼した。
「そんなことを、考えているの?」
月夜は顔を上げる。
「え?」
「なんか、月夜って、思っていた以上に深刻だね」
「そうかな」
「そうだよ、絶対」囀は笑顔で言った。「もう少し、自分に優しくしてもいいんじゃない?」
自分に優しくするとは、どういう意味だろう、と月夜は考える。
「どうしたら、自分に優しくできるの?」
「え? うーん、それは……」囀は腕を組む。「自分が、本当にやりたいと思うことに、素直になる、とかかな」
月夜は頷く。
「なるほど」
「月夜は、本当に、何も食べたくないと思うの?」
「たぶん」
「そっか……。……うーん、じゃあ、しょうがないなあ……」
階段の踊り場は、薄暗くて、少し埃っぽかった。美術室よりは汚い。すぐ傍にドアがあり、その先には屋上が続いている。普通は、その先は生徒だけでは入れない。天文学部など、一部の部活動は利用しているらしいが、飛び降り自殺を防ぐためか、普段は鍵がかかっている。天文学部の人間は、飛び降りても良い、ということだろうか。ルールとしては、多少おかしいと思われるが……。
「月夜、今日の午後、付き合ってね」
囀が二つ目のサンドウィッチを手に持って、月夜に話しかけた。
「買い物?」月夜は首を傾げる。
「うん、そう。きっと楽しいよ。色々、知らないものが見られて、感動するかも」
「最近、感動する経験をしていない」
「じゃあ、ちょうどいいじゃん。やっぱり、定期的に感動しないと、人に優しくできないもんね」
「そうなの?」
「僕の見解では」囀は頷く。
「囀は、人に優しくしたいの?」
「え? ああ、うん、どうかな……。……優しくして、損はないかな、という程度かな」
「今でも、平均的には、優しいと思うよ」
「それ、褒めているの?」囀は苦笑いする。
「特に、褒めてはいない。それが事実だと思った」
「そう言われると、なんだか嬉しいかも」
「あと、人にだけじゃなくて、自分にも、優しい、と思う」
「うーん、それはどうかなあ……」
「さっき、そう説明していなかった?」
「ああ、そういうこと? あ、そうか。じゃあ、さっきの説明は、なかったことにして」
「どうして?」
「いやあ、だってさあ……」囀は言った。「なんか、恥ずかしいから」
「分かった。なかったことにする」
「え、いや、それは、ちょっと、困る」
「何が?」
「説明するのが難しい」
「簡単な説明って、ある?」
「あるよ」
「たとえば?」
「たとえば……。……ジョン万次郎の本名が、意外と知られていない理由、とか」
昼食をとり終え、二人は教室に戻った。午後の授業が始まるまで、あと二十分ほどある。囀は、自分の机に突っ伏して眠ってしまった。月夜は、次の英語の授業でテストがあるから、軽くその復習をした。
長閑な昼休みだ。
一生、このままでも良かった。
午後の授業が始まり、テスト用紙が配られた。これは、いわゆる小テストと呼ばれるもので、定期的に行われ、僅かに成績に加算される。成績に加算されるというだけで、どういうわけか、生徒はやる気を出す。まるで、成績をとるために学校に来ているみたいだ。
でも、自分のその内の一人だ、と月夜は思った。
もちろん、それだけではないが、それを大切にしているのは確かだ。
難なくテストが終わり、通常の授業に入る。ネイティブが話す音声を聞いて、教科書に書かれた内容を確認する。分からない単語があれば、その都度調べ、記憶しようと努力する。プリントが配られ、近所の生徒と、互いに発音し合ったり、問題を出し合ったりするパートもあった。どれも、事務的で、あまり面白くなかった。
英文を一人で読んでいるときが、きっと一番面白い。
今日は、冬休み明けだから、午後の授業はそれだけだった。
他人の教師が教室に戻ってきて、ホームルームを行う。今日は、掃除がある日だが、月夜は担当ではなかった。机の上に椅子を載せて、前に移動させ、昇降口へ向かう。囀も掃除はなかったから、彼女と一緒に廊下を歩いた。
「学校って、楽しいね」囀が言った。
「どういうところが?」
「なんか、ほのぼのとしているところとか」
月夜は、彼女が言った意味を考える。
「月夜は、どう? 学校は好き?」
「うん、少しは」
「あ、じゃあ、嫌いなところもあるの?」
「それは、どんなものでも、そう」
「まあ、そうだね」
靴を履き替えて外に出る。月夜は、この時間帯に帰るのは久し振りだった。多くの生徒が、流れを作りながら、駅へと向かって歩いている。最寄り駅はその一つしかなく、そして、皆同じ路線だから、この集団が、車内まで続くことになる。上りと下りで二手に分かれるから、人数は半分になるが、空間が狭くなるせいで、密度はむしろ上がる。
いつも通りの電車に乗って、月夜と囀は帰路についた。車内は混んでいたから、座ることはできなかった。
囀は、いつも降りる駅を通り過ぎて、月夜の家がある方向にさらに進み、途中の駅で下車した。月夜も彼女に続く。
都会とも、田舎ともいえない、そんな街だった。
交通量は、多いともいえないし、少ないともいえない。
景観も、良いともいえないし、悪いともいえそうにない。
曖昧さを売りにしているような気さえする。
囀のあとについて歩き、駅構内に築かれたデパートに入った。
「月夜は、何か、見たいものはある?」歩きながら、囀が尋ねた。
「ない」月夜は答える。
混雑しているが、歩くのが困難なほどではない。
某有名なブランドの洋服売り場に来て、二人はそこで衣服を見た。
「これ、似合いそうじゃない?」
そう言って囀が持ってきたのは、黒いカーディガンだった。
月夜は、それを受け取り、上半身に当てる。鏡の前に立ち、自分の姿を見た。
「自分では、分からない」
「似合っていると思うよ。僕が、プレゼントしようか?」
「いや、いいよ」
「いやいや、付き合ってもらっているんだし、遠慮することないって」
「カーディガンは、持っているから、いらない」
「じゃあ、何が欲しい?」
「うーん、何も……」
そう言いかけたとき、ベージュ色のロングスカートが月夜の視界に入った。
「……そういえば、スカートは、あまり持っていなかった」
囀は、月夜が見ているスカートを取り、彼女に当てる。
「うん、なかなかいいじゃん。じゃあ、それね」
「囀の方が、似合うんじゃない?」
「うーん、どうかなあ」
「何を着ても、似合うと思うよ」
囀は、目を細めて、口もとを上げる。
「どうもありがとう」彼女は言った。「でも、それ、知っているよ」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
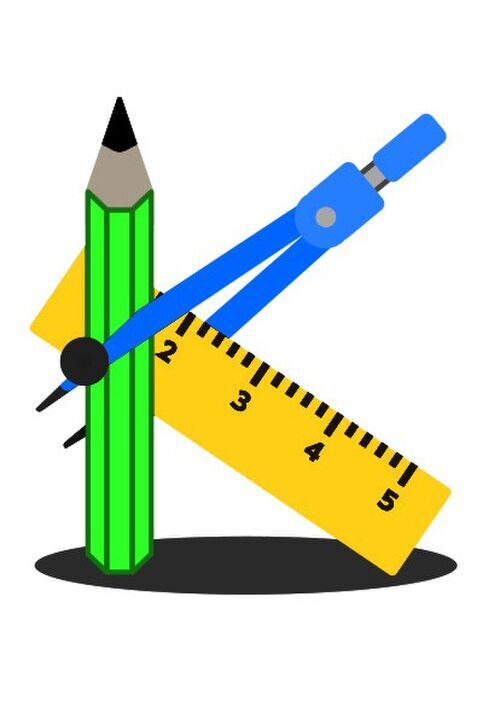
Next to Her Last Message
羽上帆樽
ライト文芸
森を抜けた先に、その邸宅はあった。草原が広がる雄大な空間に、ぽつんと建つ一軒の邸宅で、二人は女性から遺書の執筆作業を頼まれる。話によると、彼女は危篤の状態らしい。二人の子どもたちとともに一週間を過ごす中で、事態の食い違いに気がついた二人は、真の事実を知るべく観点を修正する。遺書とは何か? 誰のために書くのか? 答えはそれぞれ異なるもので良いが、そもそもの問題として、遺書を書く必要があるのかを考える必要がある。
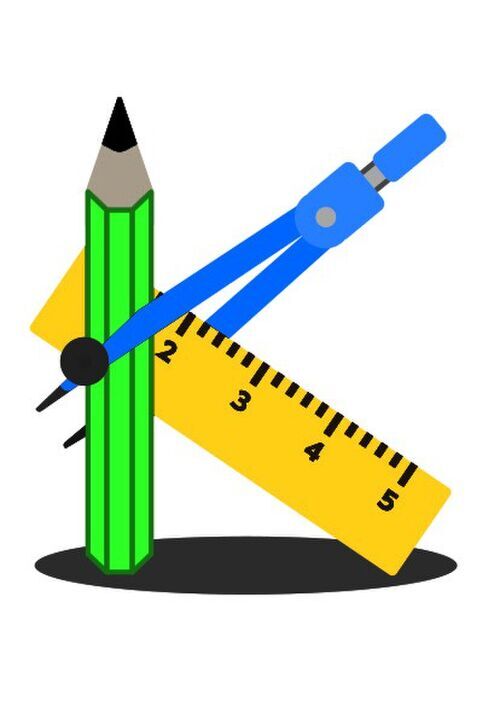
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
暗闇月夜は高校生になった。ここから彼女の物語は始まる。
行く先は不明。ただし、時間は常に人間の隣にあるが故に、進行を妨げることはできない。
毎日1000文字ずつ更新します。いつまで続くか分かりません。
終わりが不明瞭であるため、どこから入ってもらっても構いません。

【R15】メイド・イン・ヘブン
あおみなみ
ライト文芸
「私はここしか知らないけれど、多分ここは天国だと思う」
ミステリアスな美青年「ナル」と、恋人の「ベル」。
年の差カップルには、大きな秘密があった。

日給二万円の週末魔法少女 ~夏木聖那と三人の少女~
海獺屋ぼの
ライト文芸
ある日、女子校に通う夏木聖那は『魔法少女募集』という奇妙な求人広告を見つけた。
そして彼女はその求人の日当二万円という金額に目がくらんで週末限定の『魔法少女』をすることを決意する。
そんな普通の女子高生が魔法少女のアルバイトを通して大人へと成長していく物語。

〈社会人百合〉アキとハル
みなはらつかさ
恋愛
女の子拾いました――。
ある朝起きたら、隣にネイキッドな女の子が寝ていた!?
主人公・紅(くれない)アキは、どういったことかと問いただすと、酔っ払った勢いで、彼女・葵(あおい)ハルと一夜をともにしたらしい。
しかも、ハルは失踪中の大企業令嬢で……?
絵:Novel AI

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

薔薇の耽血(バラのたんけつ)
碧野葉菜
キャラ文芸
ある朝、萌木穏花は薔薇を吐いた——。
不治の奇病、“棘病(いばらびょう)”。
その病の進行を食い止める方法は、吸血族に血を吸い取ってもらうこと。
クラスメイトに淡い恋心を抱きながらも、冷徹な吸血族、黒川美汪の言いなりになる日々。
その病を、完治させる手段とは?
(どうして私、こんなことしなきゃ、生きられないの)
狂おしく求める美汪の真意と、棘病と吸血族にまつわる闇の歴史とは…?

差し伸べられなかった手で空を覆った
楠富 つかさ
ライト文芸
地方都市、空の宮市の公立高校で主人公・猪俣愛弥は、美人だが少々ナルシストで物言いが哲学的なクラスメイト・卯花彩瑛と出逢う。コミュ障で馴染めない愛弥と、周囲を寄せ付けない彩瑛は次第に惹かれていくが……。
生きることを見つめ直す少女たちが過ごす青春の十二ヵ月。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















