2 / 10
第2章 不自然
しおりを挟む
夜になった。
当たり前だが、すでに生徒の姿はない。しかし、月夜は教室に残って、勉強をしていた。今日は本を持ってきていないから、必然的に勉強をするしかない。勉強といっても、試験のための勉強で、自分の能力を上げるのが目的ではなかった。そんなことには、彼女は魅力を感じない。そもそも、自分という人間に、魅力があるのかも疑わしい。そんなものは、むしろない方が安全だ。他人から相手にされない方が、ストレスも溜まりにくい。もっとも、そんなことでストレスが溜まるとも思えないが……。
窓の外は寒そうだった。もう雪は降っていないが、校庭に少し残っている。
前方を見る。真っ黒な黒板があった。真っ黒な、と断るということは、黒くない黒板もあるということか。
月夜はシャープペンシルを机に置いて、軽く伸びをした。彼女は、今日、一度も食事をとっていない。別に、お腹は空かなかった。水筒にお茶を入れて持ってきたから、それは少し飲んだが、それも、喉が渇いたと感じたからではなかった。タイミングを見計らって、そろそろ水分補給をしておいた方が良いかな、と考えて実行したにすぎない。
椅子から立ち上がり、身体を左右に倒す。
掌が天井を向く。
そのとき、窓の向こう側で、何かが光った気がした。
彼女はそちらに近づき、眼下の校庭を見下ろす。
誰かがいた。
懐中電灯を持っているようだ。
光は一瞬この教室を照らし、すぐに別の方を向いた。その人物は、月夜の存在には気づいていないようだ。
懐中電灯の明かりは、校舎の中へと消えていった。
こんなことは初めてだった。月夜は、ほとんど毎日夜まで学校に残るが、見知らぬ誰かと遭遇したことは一度もない。教師も全員帰るし、宿直という文化はこの学校にはない。しかし、どういうわけか、裏門は必ず開いていた。だから、学校から帰るときは、彼女はそこから外に出る。誰かが意図的に鍵を外しているのか、また、誰がその門を管理しているのか、彼女は知らなかった。
教室から出て、先ほどの人物に会ってみよう、と月夜は思った。会ってみるというよりは、そっと観察してみる、といった方がニュアンスとしては近い。見知らぬ人間には、こんな夜中でなくても、会わない方が無難だ。突然殺されるかもしれない。
しかし、月夜は、殺されても構わない、とも感じていた。
薄暗い廊下を歩く。リノリウムの床と上履きが接触する。プラスチック製の鉛筆キャップが落ちていて、彼女はそれを蹴ってしまった。キャップは、ちゃちな音を立てながら、暗い廊下を転がっていく。壁に何度か当たり、弾かれて、床の上をバウンドした。動きが完全に静止したところで、彼女はそれを拾い、ブレザーのポケットに仕舞う。誰のものか分からないから、明日の朝、教室の教壇に置いておこう、と思った。
校舎に入るには、昇降口を通るしかない。職員玄関は、この時間は閉まっている。廊下の角を曲がって、階段を下りれば、昇降口はすぐだ。
しかし、昇降口に辿り着いても、誰もいなかった。
すでにここを通過してしまったのかもしれない。となると、もうどこにいるか分からない。校舎はそれほど広くないが、隠れようと思えば、どこにでも隠れられる。けれど、相手は自分以外には誰もいないと思っているだろうから、特に隠れる意味はない。
昇降口に立ち尽くし、どうしようか、と月夜は考える。
すぐ傍に自習室があるが、今は鍵がかかっていて開かない。この時間帯でも、鍵が開いている部屋、つまり、もともと鍵が存在しない部屋は限られる。あの人物が何をしにここへ来たのか分からないが、学校には部屋と廊下しかないから、部屋にいるか、廊下を歩いているかの二つの可能性しか考えられない。前者なら、その部屋に用がある、後者なら、ただ探索しに来た、と考えるのが妥当だろう。
情報が不足していて、これ以上は考えられそうにない。
月夜は、とりあえず、階段を下りて、一階に移動した。
目の前に、再び自習室。
その右手に食堂。食堂にも鍵がかかっている。
廊下を進む。
食堂の向かいには、図書室がある。
月夜は、その前で立ち止まった。
鍵が開いている。
普通なら、図書室の鍵は、司書が帰宅するタイミングでかけられる。
つまり、司書がかけ忘れたか、そうでなければ、今開けられたかの二つの場合しか考えられない。
そして……。
月夜は、きっと、今開けられたのだろう、と思った。
根拠はない。純粋に、そんな予感がした。
長い把手がついた両開きの扉をこちらに引き、彼女は図書室に足を踏み入れる。そこに下駄箱があり、スリッパがいくつも並んでいた。月夜は上履きを脱ぎ、スリッパに履き替える。その先に、もう一枚の扉。しかし、そこにも鍵はかかっておらず、これで、司書がかけ忘れた可能性は一気に低くなった。
二つ目の扉を開けて、月夜は中に入る。
真っ暗だった。
けれど……。
天井に、懐中電灯の明かりが踊っているのが、瞬時に分かった。
あの人物はここにいる。
図書室の中央には、大きなテーブルがいくつか並べられており、そこは、集団で学習できるスペースになっている。その右手には個室のブースが存在する。それらのスペースを挟んで、書棚は左右に設置されているが、懐中電灯の明かりは、左側の天井に反射していた。足音は聞こえない。月夜は、スリッパに履き替えたから、静かに歩くのは難しい。なるべく音を立てないように扉を閉めたが、すでに相手に気づかれている可能性もある。
誰もいないカウンターを通り過ぎて、左手に進む。書棚はそんなに高くないから、相手がどこにいるのか、すぐに分かった。
人影が見える。
その人物は、しゃがみ込んで、低い位置にある本を手に取って読んでいる。懐中電灯は膝の上に置かれているみたいで、だから、不安定で、光が揺れているようだった。
月夜は、真っ直ぐ進んで、その人物の前に立つ。
近くで見て、それが少年であることが分かった。
彼はゆっくりと顔を上げ、彼女を見る。
少年は笑った。
「君が、夜の万人?」
月夜は首を傾げる。
「夜の、万人、とは?」
「噂で聞いたんだ」彼は立ち上がった。「こんなに遅くまで、学校に残っていたら駄目だよ、月夜」
月夜は、自分の名前を呼ばれたから、驚いた。
「君は、誰?」
「僕?」少年は両手を広げる。「見て、分からない?」
月夜は彼の姿を観察する。髪は程良い長さで、長すぎず、また短すぎもしなかった。黒いデニム生地のズボンに、黒いパーカーを身につけている。
「……囀?」
月夜がそう言うと、少年は薄く微笑んだ。
「正解」
彼は、その場で一回転し、正面に向き直って、深くお辞儀をする。
「どうぞ、よろしく」
「うん……」
「あれ、なんか、想像していたほど驚かないね」囀は月夜に顔を近づける。「君、ちゃんと、目、付いているよね?」
「どうして、こんな時間に、学校に来たの?」
「それ、僕も訊かなかったっけ?」
「訊いたかも」
「じゃあ、まず、月夜から教えてよ」そう言って、囀は再びその場にしゃがみ込む。「僕は、君の話が聞きたい」
「私は、なんとなく、夜の学校が好きだから」
「へえ、そうなの?」
「囀は、どうして?」
「うん、ちょっと、忘れ物をしたから」
「何を忘れたの?」月夜も、囀の傍にしゃがんだ。スカートが少し広がったが、気にしなかった。
「うん、あのね、本を借りようと思っていたんだけど、それを忘れたんだ」囀は月夜の足もとに目を向ける。それから、スカートを指でさして、直すように示した。「僕、夜は読書に時間を当てているんだけど、そのために、毎日、学校で本を借りるんだ。でもね、転校初日で色々と考え事をしていたのか、そんな肝心なことを忘れて、家に帰っちゃったんだ。だから、もう一回ここまで来て、読みたい本を探していた」
「そっか」
「そうだよ。どう? 納得した?」
「した」
「端的な回答だね、月夜」
「端的の意味が分からない」
囀は笑った。
囀には、どうやら、二つの人格があるようだ、と月夜は思った。いや、人格というのはおかしいかもしれない。意識、といった方が近いか。そして、人間は、普通、二つ以上の意識を備えているものだから、囀の場合だけそこにフォーカスするのも、やはりおかしいと感じた。
ただ……。
囀は、その二つの意識を、顕著な形で区別しているようだ。具体的には、服装の違いでそれを示す。日中、月夜は、囀の一方の姿を認識していた。そして、夜になったから、囀は趣向を百八十度転換した。そんな二面性を兼ね備える特異な存在と、初日から親しくなれたのは、もしかすると、運命かもしれない、という気がしないわけではない。けれど、運命などというものはない。少なくとも、月夜は信じていない。
囀には、表と裏がある。いや、それら二つが、明確に区別されている。
月夜は、そんな囀が、より一層好きになった。
この感情は、確かだった。
夜の学校より、囀の方が好きだ、と感じた。
それは、束の間だとしても、素敵な感情に思えた。
また、綺麗な感情にも思えた。
いや、そう思いたかったのか……。
「月夜、そんな所にしゃがんで、何をしているのかな?」囀が顔を上げて、彼女を見た。
「囀が、本を探し終えるのを、待っている」
「どうして?」
「一緒に帰ろうかな、と思ったから」
「君さ、僕が好きでしょう?」
「うん。でも、どうして?」
「分かるんだ、そういうの」彼はウインクする。「勘なんだけど、これが、なかなか当たる」
「もう、帰る?」
「でも、君には、ほかに愛している人がいるね。それは誰?」
「それは、秘密」
「なるほど。だから、少し困っているわけだ」
「困る? どうして?」
「あれ、困っていない?」
「特には」
「へえ……。なかなか、フレキシブルだね」囀は頷く。「でも、一般的には、一人を好きにならないと、いけないらしいよ」
「なぜ?」
「さあ、知らない。そういう文化というか、風習なんだ、この国では」
「不思議だね」
「うん、まったく」
本を一冊持って、囀は立ち上がった。小説ではない。図鑑のようだ。
「それを、読むの?」月夜は尋ねる。
「そう」彼は言った。「説明文を読んでいるだけで、面白い」
「何の図鑑?」
「小人」
「小人?」
囀は月夜に本の表紙を見せる。『世界の小人名鑑』と書かれていた。
「たしかに、面白そう」
「君も読む?」
「囀が、返したあとで、借りに来る」
「三日くらいで読めるかな」
二人で図書室を出た。
「そういえば、どうやって、この部屋に入ったの?」階段を上りながら、月夜は彼に質問した。
「鍵を借りたんだよ」
「どうやって?」
「借りたというよりは、持ち出した、の方が正しいかな」
「勝手に?」
「そう」
「なるほど」
「僕を咎めないの、月夜」
「どうして、咎めるの?」
「いけないことをしたんだよ。友人なら、注意するのが普通じゃない?」
「いけないことをしても、許容するのが、友人だと思う」
昇降口に来て、上履きから外履きに履き替える。石造りの階段を下りて、裏門から学校の敷地の外に出た。すぐ傍に線路がある。
朝来たのとは逆に道を進み、駅がある方へ向かっていった。月夜が、自分の腕時計で時刻を確認すると、もう日付けが変わっていた。まだ電車はあるが、高校生は、この時間には出歩いてはいけない。補導の対象になる。
「月夜は、いつもこんな感じなの?」
「そう」月夜は頷いた。「囀は、本を読むのが、好きなの?」
「まあ、好きといえば、好きかな。でも、特別好きじゃないよ。月夜は?」
「特別ではないけど、好き」
「じゃあ、僕と同じだ」
駅の光が見える。近未来的な階段を上り、定期券をタッチして改札を抜ける。人の数は疎らだった。それでも、誰もいないわけではない。夜は人間の活動時間ではない、と定められているわけではないのに、多くの人間が、昼に活動し、夜は休養に当てる。そんな行動心理が月夜は不思議だった。夜の方が、素晴らしいではないか、というのが彼女の率直な体感で、こんな素晴らしい時間を、瞼を閉じて過ごす人々が、月夜には理解できない。
エスカレーターで下に移動し、ホームで電車が来るのを待った。彼らがここにいることを、不思議に思う人はいない。いるかもしれないが、皆見て見ぬふりをする。あるいは、興味のない対象は、視界から自動的に除外するようにしている。
「月夜、驚いた?」
立っていると、突然囀が訊いてきた。
月夜は彼に顔を向ける。
「何が?」
「僕の、この格好」
「少し」
「どうしてって訊かないんだね」
「訊いた方がよかった?」
「うーん、それもありかな。そういうのって、訊かれると、嬉しいものだし」囀は目を細める。「あまりね、気にされすぎるのもよくないけど、うん、君みたいに、適度な距離感で触れられるのは、全然構わない、と思う」
「じゃあ、どうして、そんな格好をしているの?」
「これが、僕のデフォルトだからだよ」囀は話す。「似合っているでしょう?」
「うん、凄く」
「いつもと、どっちの方がいい?」
「いつも、が、まだ、私には分からない」
「そっか。じゃあ、もう少ししたら、同じ質問をしよう」
「ねえ、囀」
「何?」
「手、繋いでもいい?」
囀は月夜を見る。
彼は、そのとき、初めて月夜の瞳を真っ直ぐ見つめた。
月夜は、そのとき、初めて彼に瞳を真っ直ぐ見つめられた。
「何か、寂しいことがあるの?」
目を逸らさず、囀は尋ねる。
「寂しいとは、感じないけど、なんとなく」
「分かった。いいよ」
腕を伸ばして、月夜は囀の手を握る。
適度に温かかった。
しかし、冷たいような気もする。
不思議だ。
まるで、風邪を引いているような感じがする。
熱が出ていて、とても熱いのに、同時に寒気もする。
そんな感じだった。
「手、冷たいね、月夜」囀は話す。「血液が足りていないんじゃない?」
「そうかも」
「分けてあげようか、僕のを」
「今はいらない」
「じゃあ、明日あげよう」
「明日も、いらない」
「吸血鬼だったら、素敵だよね、月夜が」
「月夜、だから?」
「そうそう」囀は笑う。「うーん、なんか、いい感じだ」
アナウンスが響き、電車がホームに入ってきた。ここには、ホームドアは設置されていない。
降りる人はいなかった。席も空いていた。
月夜と、囀は、並んで座った。
電車が走り出す。
暫くの間、二人は無言。
アナウンスだけが、自然音のように振る舞う。
月夜は、手を持ち上げて、自分の掌と、囀の掌が、上手く結合している様を観察した。
「手を繋ぐのが、そんなに珍しい?」
月夜は顔を上げる。
「うん、少し」
「繋いだこと、ない?」
「ある、少し」
「どう?」
「どうって?」
「その人と、僕の手は、違う?」
「違う、少し」
「もう、離したくないでしょう?」囀は月夜に顔を近づける。「いいよ、離さなくても。ずっと、このまま一緒にいよう」
「魅力的だけど、断る」
「うん、ストレートで、しかも、正しい回答」
「ごめんね」
「いいよ、謝らなくて」
いくつか駅を通過して、囀は月夜より先に電車を降りた。別れ際に、彼はなぜかピースサインを月夜に向けてきたが、彼女にはその意味が分からなかったので、応じなかった。
電車に乗り続け、間もなく月夜も下車する。改札を抜けて、駅舎を出ると、静かな街並みが目前に広がっていた。自動車の走行音が時折聞こえるだけで、人の気配、また動物の存在は、どこにも感じられない。
空で星が輝いていた。オリオン座が見える。月は今日は見えなかった。
駅舎から見て左右に別れる道を、月夜は左に向かって歩き出す。この一帯には、どういうわけか街灯が立っていない。だから、道は真っ暗だ。どこかに黒猫が隠れていても、きっと見つからない。
だが、月夜は、彼がいるのに気づいた。
彼女の知り合いの、黒猫のフィルが、道路の隅に行儀よく座ったまま、じっとこちらを見つめていた。
傍に近づいて、月夜は彼を抱き上げる。
「ただいま」月夜は言った。「ずっと、待っていたの?」
黄色い瞳をくりくりと動かして、フィルは答える。
「ずっとではないな。暫く、といえばいいか」
「なるほど」
「今日は、いつもより早かったな。何かあったのか?」
「何かは、あった」
「詳しく聞きたいところだが、寒いから、さっさと帰ろう」
「うん」
月夜の肩に乗ったまま、フィルは自分の脚を舐める。彼は、歳の割には、身体は小さい。尻尾は適度に長く、今は先は丸まっていた。揺れていないところを見ると、それほど機嫌が良いわけではないらしい。
「今日は、誰かに会っていたみたいだな」フィルが言った。
「どうして、分かるの?」
「いつもと、違う匂いがする」
「どんな匂い?」
「分からない」フィルは答える。「ただ、お前の匂いでないことは、分かる」
「匂いで、人を判断しているの?」
「見た目で判断するよりは、悪くないだろう?」
「そうかも」
「学校で、そいつと一緒にいたのか?」
「うん、そう」
「何をしていた?」
「どうして、そんなに気になるの?」
「なんとなくな。別に、興味があるわけじゃないさ」
「フィルが、今、一番興味があるのは、どんなこと?」
「月夜に見つからないように、新しいガールフレンドを作ることか」
「それは、君の自由だから、私には関係ない」
自宅に到着し、鍵を解錠してドアを開ける。閉めきっていたから、室内の空気は淀んでいる。洗面所で手を洗い、嗽をして、リビングに移動。リュックをソファに下ろし、カーテンを開け、シャッターを持ち上げて、外の空気を室内に取り込んだ。寒いが、暖房の人工的な空気に晒されるよりは良い。月夜がソファに座ると、彼女の膝にフィルが飛び乗ってきた。
「風呂に、入ろう」
月夜は、フィルを見る。
「私と、一緒に、入りたいの?」
「一人じゃ入れないんだ。察してくれ」
「了解。察する」彼女は頷く。「でも、その前に、日記を書く」
「どうぞ、お好きに」
リュックからノートを取り出して、月夜はそれを開く。シャープペンシルを持ち、今日経験したことをそこに記した。
リビングの照明は灯っていない。
真っ暗だが、何も見えないわけではなかった。
フィルの瞳は、暗闇を照らすほど強い光を放っていない。
「月夜、外に出るときは、コートを着よう」
月夜がノートを自分の膝に置いたから、フィルは今は床にいる。
彼の方を見ないで、月夜は尋ねた。
「どうして?」
フィルは、前脚を伸ばして、月夜の膝に触れ、体勢を維持し、彼女の手もとを覗き込む。
「寒いと、風邪を引くからに決まっているじゃないか」
「残念ながら、コートを持っていない」
「じゃあ、買いに行こう」
「どこに?」
「どこでも」彼は話す。「今の季節なら、どんな店でも売っているさ」
「何色が、似合うかな?」
「さあ、白とかじゃないか」
「白、とか、というのは、ほかに、どんな候補があることを示しているの?」
「ベージュや、黒」
「どちらも、似合わないと思う」
「何を着ても、似合うと思うがな、月夜は」
「うん……」
「集中しているな」
「何に?」
「日記の執筆に」
「集中は、していない」
「では、今は、何に集中しているんだ?」
「何にも、集中は、していない」
「嘘だな」
「どうして?」
「新参者に、集中しようとしているだろう?」
月夜は顔を上げる。
「新参者?」
「今日、新しく会ったやつがいるんじゃないのか?」
「さっき言っていた、違う匂いがする人?」
「そうだ」
月夜は、数秒間黙ってフィルを見つめた。
それから、顔を下に戻しつつ、頷いた。
「そうかも、しれない」
「やっぱり」
「やっぱり、とは?」
「ある程度、予想していたんだ」
「何を?」
「そろそろ、目移りするんじゃないか、と」
「うん、ちょっと、言い方が、どうか、と思う」
「しかし、言っている内容は同じだろう?」
「さあ、どうだろう……」
日記を書き終え、キッチンに入って、機器を操作して湯を沸かす。冷蔵庫を開け、買っておいたお茶を取り出し、コップに注いで飲んだ。相変わらず喉は渇いていないし、お腹も空いていない。
リビングに戻ると、フィルがいなかった。
「フィル?」
月夜は声をかける。
見ると、硝子戸が開いていた。その向こうに、猫のシルエットが見える。
戸を開けた先は、ウッドデッキになっており、その柵の上に、フィルはちょこんと座っていた。
「どうしたの?」月夜は彼に尋ねる。彼の横に並び、頭を撫でた。「もう少ししたら、お風呂に入るよ」
「静かだ」
月夜は右手にある山を見る。
「うん、それは、いつもそうだよ」
「星が、綺麗だ」
「うん、それも、いつもそう」
フィルは月夜を見る。
「いつもではないだろう」
「うん、そうかな」
風が吹いた。
「これから、何が起きるんだろうな」フィルが言った。「地球は、どうなってしまうのか」
「……どういう意味?」
「何百億年か先の未来を、心配しているんだ」
「まだ、そんなに生きるつもりなの?」
「俺はもう死んでいるよ。そうではなく、ほかの種の心配をしている」
「フィルが、そんなことをする必要は、ない」
「それは、俺が決めることだ」
「そっか」
周辺にある家々の窓に、もう明かりは灯っていない。皆、眠っている。それぞれの人間には、それぞれの生活があり、そして、それぞれの人生がある。普段あまり意識しないことだが、窓の明かりの数だけ、家族が存在する。明かりだけ灯ることはない。
自分は、誰かと家族を作るだろうか、と月夜は考える。
そんな価値はないと思った。
価値がないというのは、自分に、家族を作るだけの存在意義がない、という意味ではない。そんな単純な話なら良いが、そうではなく、そもそも、家族というふうに、人の集まりを括る意味があるのかといった、根底を疑う思考といえる。
フィルは、自分の家族ではない、と月夜は思う。彼は、あくまで知り合いだ。それは、きっと囀も同じだろう。月夜には、友人と呼べる者がいない。いや、いるといえばいるが、いないといえばいない。そんな、曖昧な関係ばかりだ。
あと一年もすれば、高校を卒業して、新たな進路を歩むことになる。おそらく進学するだろうが、ほかの道もないわけではない。今まで基本路線に沿って生きてきたから、今後も、その方針に則るのが一番手っ取り早いだろう、と考えただけだ。その選択に拘っているわけではない。生きてさえいれば、あとは何でも良い、と月夜は思う。
本当は、明日死んでしまっても良かった。
一人で死ぬのは少し寂しいが、死んだら、そんな寂しさもどこかへと消える。
「お風呂に、入ろう」
月夜は、フィルを抱えて言った。
「ああ、そうだな」フィルは応える。
室内に戻り、硝子戸を閉めて、二人で浴室に向かった。服を脱ぎ、シャワーを浴びる。その間、フィルは一人で湯に浸かっていた。
「湯気が凄いな、月夜」水に浮かびながら、フィルが天井を見て言った。「まるで、揚げ物をしているみたいだ」
「揚げ物のときは、湯気ではなく、煙」
月夜は応えたが、シャワーの音で声は掻き消される。
「え、なんだって?」
「揚げ物は、美味しい」
しかし、なぜか、その言葉は伝わった。
「お前が、そんなことを言うはずがないね」
月夜は、シャワーを止め、フィルを持ち上げる。
「都合の良いことばかり、言わないで」
フィルは笑った。
「それは、こちらの台詞だ」
当たり前だが、すでに生徒の姿はない。しかし、月夜は教室に残って、勉強をしていた。今日は本を持ってきていないから、必然的に勉強をするしかない。勉強といっても、試験のための勉強で、自分の能力を上げるのが目的ではなかった。そんなことには、彼女は魅力を感じない。そもそも、自分という人間に、魅力があるのかも疑わしい。そんなものは、むしろない方が安全だ。他人から相手にされない方が、ストレスも溜まりにくい。もっとも、そんなことでストレスが溜まるとも思えないが……。
窓の外は寒そうだった。もう雪は降っていないが、校庭に少し残っている。
前方を見る。真っ黒な黒板があった。真っ黒な、と断るということは、黒くない黒板もあるということか。
月夜はシャープペンシルを机に置いて、軽く伸びをした。彼女は、今日、一度も食事をとっていない。別に、お腹は空かなかった。水筒にお茶を入れて持ってきたから、それは少し飲んだが、それも、喉が渇いたと感じたからではなかった。タイミングを見計らって、そろそろ水分補給をしておいた方が良いかな、と考えて実行したにすぎない。
椅子から立ち上がり、身体を左右に倒す。
掌が天井を向く。
そのとき、窓の向こう側で、何かが光った気がした。
彼女はそちらに近づき、眼下の校庭を見下ろす。
誰かがいた。
懐中電灯を持っているようだ。
光は一瞬この教室を照らし、すぐに別の方を向いた。その人物は、月夜の存在には気づいていないようだ。
懐中電灯の明かりは、校舎の中へと消えていった。
こんなことは初めてだった。月夜は、ほとんど毎日夜まで学校に残るが、見知らぬ誰かと遭遇したことは一度もない。教師も全員帰るし、宿直という文化はこの学校にはない。しかし、どういうわけか、裏門は必ず開いていた。だから、学校から帰るときは、彼女はそこから外に出る。誰かが意図的に鍵を外しているのか、また、誰がその門を管理しているのか、彼女は知らなかった。
教室から出て、先ほどの人物に会ってみよう、と月夜は思った。会ってみるというよりは、そっと観察してみる、といった方がニュアンスとしては近い。見知らぬ人間には、こんな夜中でなくても、会わない方が無難だ。突然殺されるかもしれない。
しかし、月夜は、殺されても構わない、とも感じていた。
薄暗い廊下を歩く。リノリウムの床と上履きが接触する。プラスチック製の鉛筆キャップが落ちていて、彼女はそれを蹴ってしまった。キャップは、ちゃちな音を立てながら、暗い廊下を転がっていく。壁に何度か当たり、弾かれて、床の上をバウンドした。動きが完全に静止したところで、彼女はそれを拾い、ブレザーのポケットに仕舞う。誰のものか分からないから、明日の朝、教室の教壇に置いておこう、と思った。
校舎に入るには、昇降口を通るしかない。職員玄関は、この時間は閉まっている。廊下の角を曲がって、階段を下りれば、昇降口はすぐだ。
しかし、昇降口に辿り着いても、誰もいなかった。
すでにここを通過してしまったのかもしれない。となると、もうどこにいるか分からない。校舎はそれほど広くないが、隠れようと思えば、どこにでも隠れられる。けれど、相手は自分以外には誰もいないと思っているだろうから、特に隠れる意味はない。
昇降口に立ち尽くし、どうしようか、と月夜は考える。
すぐ傍に自習室があるが、今は鍵がかかっていて開かない。この時間帯でも、鍵が開いている部屋、つまり、もともと鍵が存在しない部屋は限られる。あの人物が何をしにここへ来たのか分からないが、学校には部屋と廊下しかないから、部屋にいるか、廊下を歩いているかの二つの可能性しか考えられない。前者なら、その部屋に用がある、後者なら、ただ探索しに来た、と考えるのが妥当だろう。
情報が不足していて、これ以上は考えられそうにない。
月夜は、とりあえず、階段を下りて、一階に移動した。
目の前に、再び自習室。
その右手に食堂。食堂にも鍵がかかっている。
廊下を進む。
食堂の向かいには、図書室がある。
月夜は、その前で立ち止まった。
鍵が開いている。
普通なら、図書室の鍵は、司書が帰宅するタイミングでかけられる。
つまり、司書がかけ忘れたか、そうでなければ、今開けられたかの二つの場合しか考えられない。
そして……。
月夜は、きっと、今開けられたのだろう、と思った。
根拠はない。純粋に、そんな予感がした。
長い把手がついた両開きの扉をこちらに引き、彼女は図書室に足を踏み入れる。そこに下駄箱があり、スリッパがいくつも並んでいた。月夜は上履きを脱ぎ、スリッパに履き替える。その先に、もう一枚の扉。しかし、そこにも鍵はかかっておらず、これで、司書がかけ忘れた可能性は一気に低くなった。
二つ目の扉を開けて、月夜は中に入る。
真っ暗だった。
けれど……。
天井に、懐中電灯の明かりが踊っているのが、瞬時に分かった。
あの人物はここにいる。
図書室の中央には、大きなテーブルがいくつか並べられており、そこは、集団で学習できるスペースになっている。その右手には個室のブースが存在する。それらのスペースを挟んで、書棚は左右に設置されているが、懐中電灯の明かりは、左側の天井に反射していた。足音は聞こえない。月夜は、スリッパに履き替えたから、静かに歩くのは難しい。なるべく音を立てないように扉を閉めたが、すでに相手に気づかれている可能性もある。
誰もいないカウンターを通り過ぎて、左手に進む。書棚はそんなに高くないから、相手がどこにいるのか、すぐに分かった。
人影が見える。
その人物は、しゃがみ込んで、低い位置にある本を手に取って読んでいる。懐中電灯は膝の上に置かれているみたいで、だから、不安定で、光が揺れているようだった。
月夜は、真っ直ぐ進んで、その人物の前に立つ。
近くで見て、それが少年であることが分かった。
彼はゆっくりと顔を上げ、彼女を見る。
少年は笑った。
「君が、夜の万人?」
月夜は首を傾げる。
「夜の、万人、とは?」
「噂で聞いたんだ」彼は立ち上がった。「こんなに遅くまで、学校に残っていたら駄目だよ、月夜」
月夜は、自分の名前を呼ばれたから、驚いた。
「君は、誰?」
「僕?」少年は両手を広げる。「見て、分からない?」
月夜は彼の姿を観察する。髪は程良い長さで、長すぎず、また短すぎもしなかった。黒いデニム生地のズボンに、黒いパーカーを身につけている。
「……囀?」
月夜がそう言うと、少年は薄く微笑んだ。
「正解」
彼は、その場で一回転し、正面に向き直って、深くお辞儀をする。
「どうぞ、よろしく」
「うん……」
「あれ、なんか、想像していたほど驚かないね」囀は月夜に顔を近づける。「君、ちゃんと、目、付いているよね?」
「どうして、こんな時間に、学校に来たの?」
「それ、僕も訊かなかったっけ?」
「訊いたかも」
「じゃあ、まず、月夜から教えてよ」そう言って、囀は再びその場にしゃがみ込む。「僕は、君の話が聞きたい」
「私は、なんとなく、夜の学校が好きだから」
「へえ、そうなの?」
「囀は、どうして?」
「うん、ちょっと、忘れ物をしたから」
「何を忘れたの?」月夜も、囀の傍にしゃがんだ。スカートが少し広がったが、気にしなかった。
「うん、あのね、本を借りようと思っていたんだけど、それを忘れたんだ」囀は月夜の足もとに目を向ける。それから、スカートを指でさして、直すように示した。「僕、夜は読書に時間を当てているんだけど、そのために、毎日、学校で本を借りるんだ。でもね、転校初日で色々と考え事をしていたのか、そんな肝心なことを忘れて、家に帰っちゃったんだ。だから、もう一回ここまで来て、読みたい本を探していた」
「そっか」
「そうだよ。どう? 納得した?」
「した」
「端的な回答だね、月夜」
「端的の意味が分からない」
囀は笑った。
囀には、どうやら、二つの人格があるようだ、と月夜は思った。いや、人格というのはおかしいかもしれない。意識、といった方が近いか。そして、人間は、普通、二つ以上の意識を備えているものだから、囀の場合だけそこにフォーカスするのも、やはりおかしいと感じた。
ただ……。
囀は、その二つの意識を、顕著な形で区別しているようだ。具体的には、服装の違いでそれを示す。日中、月夜は、囀の一方の姿を認識していた。そして、夜になったから、囀は趣向を百八十度転換した。そんな二面性を兼ね備える特異な存在と、初日から親しくなれたのは、もしかすると、運命かもしれない、という気がしないわけではない。けれど、運命などというものはない。少なくとも、月夜は信じていない。
囀には、表と裏がある。いや、それら二つが、明確に区別されている。
月夜は、そんな囀が、より一層好きになった。
この感情は、確かだった。
夜の学校より、囀の方が好きだ、と感じた。
それは、束の間だとしても、素敵な感情に思えた。
また、綺麗な感情にも思えた。
いや、そう思いたかったのか……。
「月夜、そんな所にしゃがんで、何をしているのかな?」囀が顔を上げて、彼女を見た。
「囀が、本を探し終えるのを、待っている」
「どうして?」
「一緒に帰ろうかな、と思ったから」
「君さ、僕が好きでしょう?」
「うん。でも、どうして?」
「分かるんだ、そういうの」彼はウインクする。「勘なんだけど、これが、なかなか当たる」
「もう、帰る?」
「でも、君には、ほかに愛している人がいるね。それは誰?」
「それは、秘密」
「なるほど。だから、少し困っているわけだ」
「困る? どうして?」
「あれ、困っていない?」
「特には」
「へえ……。なかなか、フレキシブルだね」囀は頷く。「でも、一般的には、一人を好きにならないと、いけないらしいよ」
「なぜ?」
「さあ、知らない。そういう文化というか、風習なんだ、この国では」
「不思議だね」
「うん、まったく」
本を一冊持って、囀は立ち上がった。小説ではない。図鑑のようだ。
「それを、読むの?」月夜は尋ねる。
「そう」彼は言った。「説明文を読んでいるだけで、面白い」
「何の図鑑?」
「小人」
「小人?」
囀は月夜に本の表紙を見せる。『世界の小人名鑑』と書かれていた。
「たしかに、面白そう」
「君も読む?」
「囀が、返したあとで、借りに来る」
「三日くらいで読めるかな」
二人で図書室を出た。
「そういえば、どうやって、この部屋に入ったの?」階段を上りながら、月夜は彼に質問した。
「鍵を借りたんだよ」
「どうやって?」
「借りたというよりは、持ち出した、の方が正しいかな」
「勝手に?」
「そう」
「なるほど」
「僕を咎めないの、月夜」
「どうして、咎めるの?」
「いけないことをしたんだよ。友人なら、注意するのが普通じゃない?」
「いけないことをしても、許容するのが、友人だと思う」
昇降口に来て、上履きから外履きに履き替える。石造りの階段を下りて、裏門から学校の敷地の外に出た。すぐ傍に線路がある。
朝来たのとは逆に道を進み、駅がある方へ向かっていった。月夜が、自分の腕時計で時刻を確認すると、もう日付けが変わっていた。まだ電車はあるが、高校生は、この時間には出歩いてはいけない。補導の対象になる。
「月夜は、いつもこんな感じなの?」
「そう」月夜は頷いた。「囀は、本を読むのが、好きなの?」
「まあ、好きといえば、好きかな。でも、特別好きじゃないよ。月夜は?」
「特別ではないけど、好き」
「じゃあ、僕と同じだ」
駅の光が見える。近未来的な階段を上り、定期券をタッチして改札を抜ける。人の数は疎らだった。それでも、誰もいないわけではない。夜は人間の活動時間ではない、と定められているわけではないのに、多くの人間が、昼に活動し、夜は休養に当てる。そんな行動心理が月夜は不思議だった。夜の方が、素晴らしいではないか、というのが彼女の率直な体感で、こんな素晴らしい時間を、瞼を閉じて過ごす人々が、月夜には理解できない。
エスカレーターで下に移動し、ホームで電車が来るのを待った。彼らがここにいることを、不思議に思う人はいない。いるかもしれないが、皆見て見ぬふりをする。あるいは、興味のない対象は、視界から自動的に除外するようにしている。
「月夜、驚いた?」
立っていると、突然囀が訊いてきた。
月夜は彼に顔を向ける。
「何が?」
「僕の、この格好」
「少し」
「どうしてって訊かないんだね」
「訊いた方がよかった?」
「うーん、それもありかな。そういうのって、訊かれると、嬉しいものだし」囀は目を細める。「あまりね、気にされすぎるのもよくないけど、うん、君みたいに、適度な距離感で触れられるのは、全然構わない、と思う」
「じゃあ、どうして、そんな格好をしているの?」
「これが、僕のデフォルトだからだよ」囀は話す。「似合っているでしょう?」
「うん、凄く」
「いつもと、どっちの方がいい?」
「いつも、が、まだ、私には分からない」
「そっか。じゃあ、もう少ししたら、同じ質問をしよう」
「ねえ、囀」
「何?」
「手、繋いでもいい?」
囀は月夜を見る。
彼は、そのとき、初めて月夜の瞳を真っ直ぐ見つめた。
月夜は、そのとき、初めて彼に瞳を真っ直ぐ見つめられた。
「何か、寂しいことがあるの?」
目を逸らさず、囀は尋ねる。
「寂しいとは、感じないけど、なんとなく」
「分かった。いいよ」
腕を伸ばして、月夜は囀の手を握る。
適度に温かかった。
しかし、冷たいような気もする。
不思議だ。
まるで、風邪を引いているような感じがする。
熱が出ていて、とても熱いのに、同時に寒気もする。
そんな感じだった。
「手、冷たいね、月夜」囀は話す。「血液が足りていないんじゃない?」
「そうかも」
「分けてあげようか、僕のを」
「今はいらない」
「じゃあ、明日あげよう」
「明日も、いらない」
「吸血鬼だったら、素敵だよね、月夜が」
「月夜、だから?」
「そうそう」囀は笑う。「うーん、なんか、いい感じだ」
アナウンスが響き、電車がホームに入ってきた。ここには、ホームドアは設置されていない。
降りる人はいなかった。席も空いていた。
月夜と、囀は、並んで座った。
電車が走り出す。
暫くの間、二人は無言。
アナウンスだけが、自然音のように振る舞う。
月夜は、手を持ち上げて、自分の掌と、囀の掌が、上手く結合している様を観察した。
「手を繋ぐのが、そんなに珍しい?」
月夜は顔を上げる。
「うん、少し」
「繋いだこと、ない?」
「ある、少し」
「どう?」
「どうって?」
「その人と、僕の手は、違う?」
「違う、少し」
「もう、離したくないでしょう?」囀は月夜に顔を近づける。「いいよ、離さなくても。ずっと、このまま一緒にいよう」
「魅力的だけど、断る」
「うん、ストレートで、しかも、正しい回答」
「ごめんね」
「いいよ、謝らなくて」
いくつか駅を通過して、囀は月夜より先に電車を降りた。別れ際に、彼はなぜかピースサインを月夜に向けてきたが、彼女にはその意味が分からなかったので、応じなかった。
電車に乗り続け、間もなく月夜も下車する。改札を抜けて、駅舎を出ると、静かな街並みが目前に広がっていた。自動車の走行音が時折聞こえるだけで、人の気配、また動物の存在は、どこにも感じられない。
空で星が輝いていた。オリオン座が見える。月は今日は見えなかった。
駅舎から見て左右に別れる道を、月夜は左に向かって歩き出す。この一帯には、どういうわけか街灯が立っていない。だから、道は真っ暗だ。どこかに黒猫が隠れていても、きっと見つからない。
だが、月夜は、彼がいるのに気づいた。
彼女の知り合いの、黒猫のフィルが、道路の隅に行儀よく座ったまま、じっとこちらを見つめていた。
傍に近づいて、月夜は彼を抱き上げる。
「ただいま」月夜は言った。「ずっと、待っていたの?」
黄色い瞳をくりくりと動かして、フィルは答える。
「ずっとではないな。暫く、といえばいいか」
「なるほど」
「今日は、いつもより早かったな。何かあったのか?」
「何かは、あった」
「詳しく聞きたいところだが、寒いから、さっさと帰ろう」
「うん」
月夜の肩に乗ったまま、フィルは自分の脚を舐める。彼は、歳の割には、身体は小さい。尻尾は適度に長く、今は先は丸まっていた。揺れていないところを見ると、それほど機嫌が良いわけではないらしい。
「今日は、誰かに会っていたみたいだな」フィルが言った。
「どうして、分かるの?」
「いつもと、違う匂いがする」
「どんな匂い?」
「分からない」フィルは答える。「ただ、お前の匂いでないことは、分かる」
「匂いで、人を判断しているの?」
「見た目で判断するよりは、悪くないだろう?」
「そうかも」
「学校で、そいつと一緒にいたのか?」
「うん、そう」
「何をしていた?」
「どうして、そんなに気になるの?」
「なんとなくな。別に、興味があるわけじゃないさ」
「フィルが、今、一番興味があるのは、どんなこと?」
「月夜に見つからないように、新しいガールフレンドを作ることか」
「それは、君の自由だから、私には関係ない」
自宅に到着し、鍵を解錠してドアを開ける。閉めきっていたから、室内の空気は淀んでいる。洗面所で手を洗い、嗽をして、リビングに移動。リュックをソファに下ろし、カーテンを開け、シャッターを持ち上げて、外の空気を室内に取り込んだ。寒いが、暖房の人工的な空気に晒されるよりは良い。月夜がソファに座ると、彼女の膝にフィルが飛び乗ってきた。
「風呂に、入ろう」
月夜は、フィルを見る。
「私と、一緒に、入りたいの?」
「一人じゃ入れないんだ。察してくれ」
「了解。察する」彼女は頷く。「でも、その前に、日記を書く」
「どうぞ、お好きに」
リュックからノートを取り出して、月夜はそれを開く。シャープペンシルを持ち、今日経験したことをそこに記した。
リビングの照明は灯っていない。
真っ暗だが、何も見えないわけではなかった。
フィルの瞳は、暗闇を照らすほど強い光を放っていない。
「月夜、外に出るときは、コートを着よう」
月夜がノートを自分の膝に置いたから、フィルは今は床にいる。
彼の方を見ないで、月夜は尋ねた。
「どうして?」
フィルは、前脚を伸ばして、月夜の膝に触れ、体勢を維持し、彼女の手もとを覗き込む。
「寒いと、風邪を引くからに決まっているじゃないか」
「残念ながら、コートを持っていない」
「じゃあ、買いに行こう」
「どこに?」
「どこでも」彼は話す。「今の季節なら、どんな店でも売っているさ」
「何色が、似合うかな?」
「さあ、白とかじゃないか」
「白、とか、というのは、ほかに、どんな候補があることを示しているの?」
「ベージュや、黒」
「どちらも、似合わないと思う」
「何を着ても、似合うと思うがな、月夜は」
「うん……」
「集中しているな」
「何に?」
「日記の執筆に」
「集中は、していない」
「では、今は、何に集中しているんだ?」
「何にも、集中は、していない」
「嘘だな」
「どうして?」
「新参者に、集中しようとしているだろう?」
月夜は顔を上げる。
「新参者?」
「今日、新しく会ったやつがいるんじゃないのか?」
「さっき言っていた、違う匂いがする人?」
「そうだ」
月夜は、数秒間黙ってフィルを見つめた。
それから、顔を下に戻しつつ、頷いた。
「そうかも、しれない」
「やっぱり」
「やっぱり、とは?」
「ある程度、予想していたんだ」
「何を?」
「そろそろ、目移りするんじゃないか、と」
「うん、ちょっと、言い方が、どうか、と思う」
「しかし、言っている内容は同じだろう?」
「さあ、どうだろう……」
日記を書き終え、キッチンに入って、機器を操作して湯を沸かす。冷蔵庫を開け、買っておいたお茶を取り出し、コップに注いで飲んだ。相変わらず喉は渇いていないし、お腹も空いていない。
リビングに戻ると、フィルがいなかった。
「フィル?」
月夜は声をかける。
見ると、硝子戸が開いていた。その向こうに、猫のシルエットが見える。
戸を開けた先は、ウッドデッキになっており、その柵の上に、フィルはちょこんと座っていた。
「どうしたの?」月夜は彼に尋ねる。彼の横に並び、頭を撫でた。「もう少ししたら、お風呂に入るよ」
「静かだ」
月夜は右手にある山を見る。
「うん、それは、いつもそうだよ」
「星が、綺麗だ」
「うん、それも、いつもそう」
フィルは月夜を見る。
「いつもではないだろう」
「うん、そうかな」
風が吹いた。
「これから、何が起きるんだろうな」フィルが言った。「地球は、どうなってしまうのか」
「……どういう意味?」
「何百億年か先の未来を、心配しているんだ」
「まだ、そんなに生きるつもりなの?」
「俺はもう死んでいるよ。そうではなく、ほかの種の心配をしている」
「フィルが、そんなことをする必要は、ない」
「それは、俺が決めることだ」
「そっか」
周辺にある家々の窓に、もう明かりは灯っていない。皆、眠っている。それぞれの人間には、それぞれの生活があり、そして、それぞれの人生がある。普段あまり意識しないことだが、窓の明かりの数だけ、家族が存在する。明かりだけ灯ることはない。
自分は、誰かと家族を作るだろうか、と月夜は考える。
そんな価値はないと思った。
価値がないというのは、自分に、家族を作るだけの存在意義がない、という意味ではない。そんな単純な話なら良いが、そうではなく、そもそも、家族というふうに、人の集まりを括る意味があるのかといった、根底を疑う思考といえる。
フィルは、自分の家族ではない、と月夜は思う。彼は、あくまで知り合いだ。それは、きっと囀も同じだろう。月夜には、友人と呼べる者がいない。いや、いるといえばいるが、いないといえばいない。そんな、曖昧な関係ばかりだ。
あと一年もすれば、高校を卒業して、新たな進路を歩むことになる。おそらく進学するだろうが、ほかの道もないわけではない。今まで基本路線に沿って生きてきたから、今後も、その方針に則るのが一番手っ取り早いだろう、と考えただけだ。その選択に拘っているわけではない。生きてさえいれば、あとは何でも良い、と月夜は思う。
本当は、明日死んでしまっても良かった。
一人で死ぬのは少し寂しいが、死んだら、そんな寂しさもどこかへと消える。
「お風呂に、入ろう」
月夜は、フィルを抱えて言った。
「ああ、そうだな」フィルは応える。
室内に戻り、硝子戸を閉めて、二人で浴室に向かった。服を脱ぎ、シャワーを浴びる。その間、フィルは一人で湯に浸かっていた。
「湯気が凄いな、月夜」水に浮かびながら、フィルが天井を見て言った。「まるで、揚げ物をしているみたいだ」
「揚げ物のときは、湯気ではなく、煙」
月夜は応えたが、シャワーの音で声は掻き消される。
「え、なんだって?」
「揚げ物は、美味しい」
しかし、なぜか、その言葉は伝わった。
「お前が、そんなことを言うはずがないね」
月夜は、シャワーを止め、フィルを持ち上げる。
「都合の良いことばかり、言わないで」
フィルは笑った。
「それは、こちらの台詞だ」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
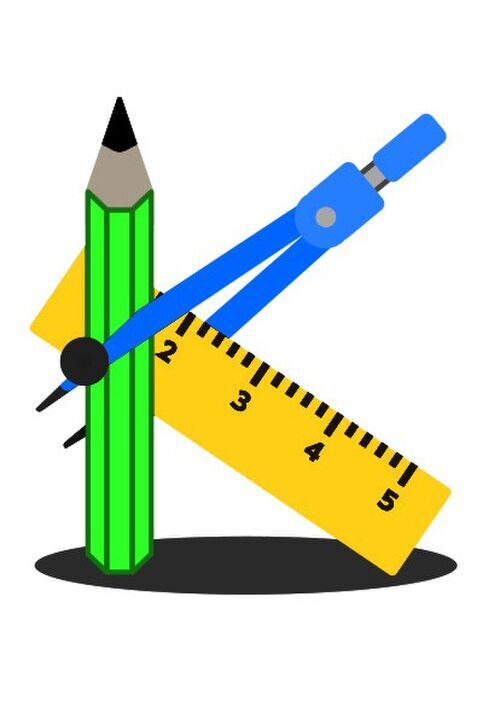
Next to Her Last Message
羽上帆樽
ライト文芸
森を抜けた先に、その邸宅はあった。草原が広がる雄大な空間に、ぽつんと建つ一軒の邸宅で、二人は女性から遺書の執筆作業を頼まれる。話によると、彼女は危篤の状態らしい。二人の子どもたちとともに一週間を過ごす中で、事態の食い違いに気がついた二人は、真の事実を知るべく観点を修正する。遺書とは何か? 誰のために書くのか? 答えはそれぞれ異なるもので良いが、そもそもの問題として、遺書を書く必要があるのかを考える必要がある。
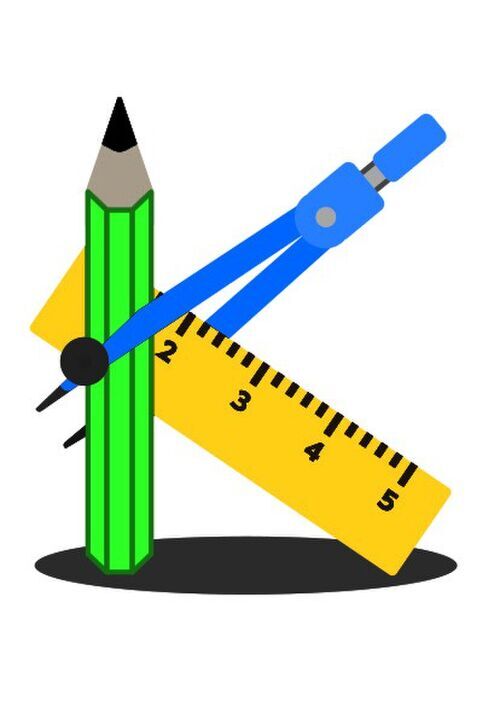
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
暗闇月夜は高校生になった。ここから彼女の物語は始まる。
行く先は不明。ただし、時間は常に人間の隣にあるが故に、進行を妨げることはできない。
毎日1000文字ずつ更新します。いつまで続くか分かりません。
終わりが不明瞭であるため、どこから入ってもらっても構いません。

【R15】メイド・イン・ヘブン
あおみなみ
ライト文芸
「私はここしか知らないけれど、多分ここは天国だと思う」
ミステリアスな美青年「ナル」と、恋人の「ベル」。
年の差カップルには、大きな秘密があった。

日給二万円の週末魔法少女 ~夏木聖那と三人の少女~
海獺屋ぼの
ライト文芸
ある日、女子校に通う夏木聖那は『魔法少女募集』という奇妙な求人広告を見つけた。
そして彼女はその求人の日当二万円という金額に目がくらんで週末限定の『魔法少女』をすることを決意する。
そんな普通の女子高生が魔法少女のアルバイトを通して大人へと成長していく物語。

命(アニマ)の声が聴こえる
和本明子
ライト文芸
ある地方の市役所(観光課)に勤める幸一は、新任したばかりの市長の辞令で町興しの企画を考えていた。良い案が浮かばず、気分転換にと偶然視聴したアニメから、実妹(美幸)によく似た声を耳にした。美幸は声優を志していたが、事故で他界していた。その妹の声に似た声優は「伊吹まどか」だと知るが。。。

〈社会人百合〉アキとハル
みなはらつかさ
恋愛
女の子拾いました――。
ある朝起きたら、隣にネイキッドな女の子が寝ていた!?
主人公・紅(くれない)アキは、どういったことかと問いただすと、酔っ払った勢いで、彼女・葵(あおい)ハルと一夜をともにしたらしい。
しかも、ハルは失踪中の大企業令嬢で……?
絵:Novel AI

差し伸べられなかった手で空を覆った
楠富 つかさ
ライト文芸
地方都市、空の宮市の公立高校で主人公・猪俣愛弥は、美人だが少々ナルシストで物言いが哲学的なクラスメイト・卯花彩瑛と出逢う。コミュ障で馴染めない愛弥と、周囲を寄せ付けない彩瑛は次第に惹かれていくが……。
生きることを見つめ直す少女たちが過ごす青春の十二ヵ月。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















