5 / 10
第5章 不条理
しおりを挟む
昼休みになった。
月夜は、今日も囀に呼び出されて、彼女と一緒に昼食をとることになった。といっても、月夜は今日は食べ物を貰うのは遠慮しておいた。お腹が空いていなかったし、特に食べたいとも思わなかったからだ。
囀は月夜の分まで弁当を作ってきていたが、その分は、ほかの生徒に譲ったみたいだった。彼女はそれなりに融通が利く。
前回は階段の踊り場で食べたから、今日は食堂に行った。食堂の中は混んでいるが、空いている席がないわけではない。苦しい空気の中で、口を開くのを厭わないのであれば、そこで食事をするのは自由だ。
食堂では、学食を買うことができるが、持ち込みも許可されている。ラーメンを家から持ってくるのは困難なので、どうしてもラーメンを食べたい人は、食堂で注文しなくてはならない。それでも、いつも家で食べているラーメンが恋しくて、あれがないとどうしようもない、生きていけるかさえ分からない、という人は、無理をしてでも家からラーメンを持ってくる必要がある(そんな人は滅多にいないが)。
長いテーブルが縦にいくつも並んでおり、最後のテーブルの向こう側は、中庭に繋がっている。食堂の正面に図書室があり、すぐ傍に購買もあった。
月夜と囀は、空いている席を探して、適当に腰をかけた。ここからだと、ステージがよく見える。もっとも、今日は何の催しもないらしい。ときどき、軽音楽部や有志のバンドが、楽器を演奏していることがある。
囀は一人で昼食をとり始めた。今日は標準的なお弁当だった。ふりかけがかかった白米に、いくつかの惣菜の詰め合わせ。野菜はブロッコリーとニンジンで、緑と橙色だった(これでは、説明になっていないが、気にしてはいけない)。
「食堂にいながら、何も食べないって、面白いね」ご飯を口に入れながら、片手で口もとを押さえて、囀が言った。「本当に大丈夫?」
「全然、平気」
囀は周囲を見渡す。
「ここの食堂って、こんなに混雑しているんだね」
月夜は首を傾げた。
「囀が、前通っていた学校では、こんな感じじゃなかったの?」
「うん……。なんか、こう……、もう少し寂れた感じだった」
「何を、食べた?」
「そこで?」
「うん」
「僕はね、あまり使ったことはないよ」囀は言った。「あ、でも、春巻きは美味しかったかな」
冬なのに、アイスを食べている者がいる。もちろん、どの季節に何を食べようと、個人の自由だ。真夏にチーズフォンデュを食べても、誰にも文句は言われない。
「このあとさ、ちょっと、図書室に行ってもいい?」卵焼きを箸で掴んで、囀は尋ねた。
「いいよ。いってらっしゃい」
「月夜も一緒に来るんだよ」
「どうして?」
「一緒の方がいいでしょう?」
「そうなの?」
「もう、変なこと言わないでよ」
変なことを言ったつもりはなかった、と月夜は思う。
「もう、昨日の本は、読み終わったの?」
「うん、まあ……。あれは、読むというより、見る感じだったから」囀は話した。「そういう、読み方が決まっていないものが、一番、読むのが難しい」
「現代文のテストも、難しいよ」
「え、そう?」
「うん」
「たとえば、どんなところが?」
「筆者が、本当はどう思っているのか、分からないのに、質問してくるところ、とか」
「ああ、なるほど……」箸を上下に振り、囀は奇怪なジェスチャーをする。「先生、言っていたよね。筆者が言いたいことを、上手く汲み取れないと、問題には答えられないって……」
「うん」
「そんなこと、無理だよね」
「そう、だと、思う」
沈黙。
月夜は後ろを振り返る。硝子越しに、中庭の様子が見えた。今は、ほとんど人はいない。やはり、寒いからだろう。もう少し暖かい季節だと、幾人かの男子生徒が、噴水の縁を走り回っていたりする。
食堂の傍に自動販売機があった。月夜は、そこで飲み物を買ったことは一度もない。自動販売機は、どのような仕組みになっているのだろう、と彼女はぼんやりと考える。特に、落ちてくる経路が気になった。ある程度の高さがあるのに、缶やペットボトルは意外なほど無傷だ。おそらく、直線的に自由落下してくるのではないだろう。何かしら、ルートのようなものがあるのだ。
正面を向くと、囀がにこにこ笑っていた。
「何か、いいことがあった?」不思議に思って、月夜は尋ねる。
「あったあった」囀は頷いた。
「何?」
「月夜の、髪が、こう、ふわって、宙に舞うところが見られた」
「それが、いいこと?」
「そうだよ。素敵じゃない? そういう場面に遭遇するのって……」
そうなのか、と月夜は考える。たしかに、言われてみれば、そんな気がしないでもない。
囀はすぐに弁当を食べ終わり、二人は食堂の出口に向かった。彼女は、普段はよく眠っているが、食後は活発に動けるようだ。
「月夜、アイス食べる?」
そう言いながら、囀はすでにショーケース型の冷凍庫に手を伸ばしている。
「いらない」
小銭を担当者に渡し、囀はバー形のチョコレートアイスを食べ始めた。
当然、アイスを食べながら図書室には入れない。食堂の傍の壁によって、月夜は囀がアイスを食べ終えるのを待った。
「美味しい?」
月夜の質問を受けて、囀は笑顔で頷く。
「正直、ご飯よりも、こっちの方が美味しい」
「じゃあ、毎日、アイスを食べれば、いいんじゃない?」
「うーん、本当はそうしたいところなんだけど、それだと、やっぱり、体調を悪くするかな」
「体調を悪くすると、問題なの?」
「一般的にはね」囀は言った。「それに、学生である以上、体調を崩すことはできないよ」
アイスの塵を捨てて、囀は、おまたせ、と月夜に言った。
二人で図書室に入る。上履きからスリッパに履き替える際、どれを選ぶか迷ったが、月夜は、左右の足先に均等なバランスで「図書室」と書かれたものを選んだ。そのマークは、すべてのスリッパに書かれているが、書いた人が違うのか、大きさや字体がバラバラだ。
図書室に入ると、カウンターの向こうに司書がいた。
司書は、一人の女子生徒と話していた。
特に聞き耳を立てたわけではないが、月夜には二人の会話が聞こえた。
「まだ、見つからないんですか?」女子生徒が尋ねる。
「ええ、そうなの」司書が答えた。「ごめんね。見つかったら、すぐに届けるからね」
「いえ、急がなくても、大丈夫です」
「予約しておいたのに、本当に……」
囀は気にしていないみたいだったが、月夜には、それが、今朝、彼女のクラスの図書委員が言っていた、小説の失踪事件についての会話だと分かった。事件、という言い方は多少大袈裟かもしれないが、盗まれたのだから、事件に変わりはない。
囀のあとについて、月夜も書棚の間を歩いた。昼休みだから、テーブルで本を読んでいる生徒もいる。個別のブースでは、受験生らしい者が、何人も勉強していた。もうすぐ、本番を迎えるらしい。本番前だからといって、意気込んで勉強しても、大きく変わらないのではないか、と月夜は考える。むしろ、本番前だからこそ、違うことをして頭を切り替えた方が良い。
小説のコーナーには行かないで、囀は絵本が展示された場所で立ち止まった。
「囀は、小説は読まないの?」
しゃがみ込んで本を手に取った彼女に、月夜は質問した。
「小説?」囀は答える。「読まないことはないけど、最近は、ストーリーとかじゃなくて、写真とか、絵とか、そういうものを見ることが多いかな」
囀の隣に一緒に座って、月夜も絵本を一冊取り出す。熊が主人公のもので、巨大なグリーンピースが描かれていた。熊と、巨大なグリーンピースとの間に、どんな関係があるのだろう、と思って、月夜は本を開く。読み進めると、孤島に眠っていると噂されるグリーンピースを、村一番の熊が探しにいく、というストーリーだと分かった。それでは、グリーンピースと、孤島では、何か関係があるのか、と思ったが、最後までストーリーを追っても、その点については何も説明されていなかった。
月夜は、本を閉じ、それを膝の上に置く。
目を横に向ける。
すぐ傍に、本を持っていない方の、囀の垂れ下がった手があった。
それを握ろうか、と月夜は考える。
勝手に触れて、怒られないだろうか。
きっと、囀なら怒らないだろうが、月夜は、少し、彼女の手に触れるのを躊躇した。
それは……。
それは、どうしてだろう?
勇気?
勇気が足りないから?
「ねえ、月夜」囀が、本のページを開いたまま、それを月夜に近づけた。「これ、見てよ」
月夜は本を覗き込む。
完熟したトマトが、階段を転がっていた。
「それが、どうかしたの?」
「おかしいよね、こんなの」囀は笑いながら話す。「小さい子に、こんなの見せて、いいのかな」
「何が、駄目なの?」
「だってさあ……」しかし、囀はそれ以上続けようとしない。
月夜は、思いきって、囀の手を握った。
接触。
体温。
温かった。
顔を上げて、囀の様子を観察する。
しかし、彼女は何の反応も示さない。
月夜は、手を握る力を強める。
「しかもさあ……」囀は、再び本のページを月夜に見せた。「これなんか、もう、大変だよね」
今度は、ピーマンが海を泳いでいた。
「それが、何?」
「変だと思わない?」
それよりも変なことが、今起こっているではないか、と月夜は思う。
「思わない」
「普通、ピーマンは泳がないじゃん」
月夜には囀のセンスは分からなかった。
借りる本を一冊持って、囀は静かに立ち上がる。月夜は彼女の手を離し、何事もなかったかのように顔を澄ませた。
そのまま、じっと囀を見つめる。
「何?」彼女は首を傾げた。
「何も」月夜は答える。
カウンターに本を持っていき、バーコードを認識してもらうことで、貸し出しは完了する。絵本を抱えた囀と一緒に、月夜は図書室を出た。
食堂の硝子戸から、壁にかけられた時計を見る。
昼休みは、あと十分だった。
階段を上って、教室がある階まで移動する。生徒の多くは、まだ廊下の外に出て話していた。次の授業は移動する必要がないから、チャイムが鳴る直前まで、時間を有効活用している生徒が多い。
机の中から教科書とノート、筆箱を取り出し、授業の体勢を整える。月夜は視線を右斜め前方に向けて、囀の姿を確認した。彼女は、さすがにもう眠っていない。身体を後ろに向けて、そこに座るクラスメートと話していた。
囀は、誰といるときでも常に笑顔だ。
本当に常ではなくても、そうした印象を抱く。
教室前の扉が開いて、現代文の教師が現れた。チャイムが鳴り、授業が始まる。
手に持っているシャープペンシルは、教師の板書に反応するように正しく動き、ノートに炭素を擦り付ける。間違えたら消しゴムで消し、再び書き直す。その繰り返し。ノートをとるのが授業の目的ではないが、現実として、そうなっているのは確かだ。手を動かすことで、ある程度集中力は高まるらしいが、集中しようと思っていないのであれば、効果は認められない。
教室の午後の空気は、停滞気味で、充満気味で、そして、沈殿気味だった。天井に顔を向けても、そこに開放的な空はない。唯一、開いていなくても外界と繋がる窓は、月夜の席からは離れている。暖房が効いていて、気分が悪くなりそうだったが、気分が悪くなっても、彼女が困ることはなかった。
今、自分が突然死んでしまったら、クラスメートはどうするだろう?
久し振りに、面白いことを思いついた気がした。
彼らの反応を想像するのが面白いのではない。
様々なシチュエーションで、自分が死ぬのを想像するのが、面白いのだ。
本来なら、死と場所はほとんど関係がない。どこで死のうと、死んだ者はもう死んだのだ。それ以上その人とコミュニケーションをとることはできないし、思い出という補助機能を除けば、回線は完全に遮断されるに等しい。
けれども、人間は、自分であろうと、他人であろうと、死亡する時や場所を大事にしたがる。そこに価値を見出そうとする。どうせ死ぬなら、愛する人に看取られながら死にたいとか、あまりにも若い内に死にたくないとか、そうした不思議なことを口にする。
それは、どうしてだろう?
どのようなシチュエーションで死んでも、自分は一人しかいないのだから、その人にとっては、それはほかの誰にも経験できない、唯一絶対のもので、価値が認められるはずだ。
でも……。
……自分は、どうだろう?
やはり、死ぬときは誰かと一緒が良い、と感じるだろうか?
自分の知り合いを一人ずつ挙げて、彼らとともに死亡する、あるいは彼らに看取られて死亡する情景を、月夜は一つ一つシミュレーションしていった。
どれも、素敵だと思えた。
もちろん、自分一人で死ぬ情景も思い描いた。
けれど、それも、それはそれで良いと思った。
自分が死んでも、彼らは、その後も生き続けていく。彼らがまだ生きているという事実さえ成立していれば、自分がどうなろうと、どうでも良い。自分の目を通して、それを確かめることができなくても、全然問題ではない。
それが、愛というものではないか?
……愛。
なんて、チープな言葉だろう。
しかし、それと同時に、いや、それだからこそ、価値を持った言葉だといえる。
それでは……。
そもそも、事実とは何だろうか?
考え事をしていても、シャープペンシルは勝手に動く。ときどき、教科書の該当する部分に傍線を引いたり、重要な段落に印をつけたりもする。どれも単純な作業で、面白くはない。教科書に書かれている文章は、この授業の中で唯一面白い。教師が話す内容は、抽象化してしまえば教科書に書かれていることと同じで、はっきりいって、重要ではない。
ノートを千切って、紙飛行機を折って飛ばしたら、少しは楽しくなるだろうか、と月夜は考える。
実際にやってみようとは思わなかった。
恥ずかしいからではない。
自分に対するイメージを壊したくないから、というのは、少しある。
けれど、それ以上に、やらなくても、どうなるか予想がついた。
だから、やらなかった。
予想は、一つには絞れない。それはどんな場合でもそうだ。
それなら、いくつも予想すれば良い。それだけで、何が起きても、充分な準備を持って接することができる。
授業はあっという間に終わった。あっという間だと感じるのは、集中していたからかもしれないが、集中とは、しようと思ってできるものではないので、月夜は何の努力もいらなかったし、努力をしたつもりなどなかった。
次の授業は移動する必要があったから、荷物を纏めて、月夜は立ち上がった。もう、次の授業で最後だから、リュックも一緒に持っていく。こういう日は、最後のホームルームは省略されることになっている。
教室から出ようとしたところで、自然と囀と合流した。
「月夜は、次は何?」
歩きながら、月夜は答える。
「地学」
「なんか、現代文ってさ、面白いよね」囀は話した。「文章の意味を、紐解いていくのが」
「文章の意味を、紐解く?」
「そうそう」囀は説明する。「つまり、したがって、しかし、みたいにさ、その下に、それらの言葉が示す要素がくっついているわけでしょう? で、そういうふうに示されたものは、きちんと、その全体の中で役割を果たしているわけで……」
月夜は頷く。
「そういうのが、面白い」
「ごめん、よく、分からない」
囀は月夜を見た。
「分かってよ」囀は微笑む。「説明が下手なのは承知しているけど、なんとか、理解して」
囀が今した説明を思い返し、月夜はもう一度理解しようとする。ニュアンスは伝わったが、それで合っているという確信はなかった。
「少し、分かったような、気がする」
「本当?」
「うん」
「ああ、よかった」
囀と別れて、地学教室に入る。この部屋は、常に暗くて、如何にも実験室という感じがする。しかし、地学はあまり実験を伴わない授業だから、そのイメージは本質とはずれている。地学では、観察もあまりしない。配られたプリントに目を通して、教師の説明を聞くだけだ。プリントには、中身のない括弧が並んでいて、そこに、教師が言ったことを一つずつ記していく。だから、ノートをとるよりは労力は少なくて済む。ただし、理科系の科目は、覚えなくてはならない用語が多く、かつそれらの用語はあとで触れる別の単元に繋がっていることが多いから、一つずつ丁寧に覚えないと、後々お釈迦になる(お釈迦というのは、ここでは、存在の名称ではない)。
それでも、現代文よりは負荷はかからないから、月夜は手を動かしつつも、頭では別のことを考えていた。
今日の朝聞いた話と、図書館で耳にした話が、少し気になった。
あの女子生徒は、無事に小説を手に入れられただろうか?
いや、きっと、まだだ。
本はどうして消えてしまったのか、と月夜は多少不思議に思う。
疑問に感じるのは、興味を抱く前兆だ。
だから、彼女は、この出来事に関して、後々興味を抱くかもしれない。
小説は昨日の午後に返却されたが、今日の朝にはなくなっていた。つまり、誰かが盗めるとしたら、その間の時間、つまり、夜の間でしかない。
盗んだのではないとしたら、本はどうやって消えたのだろう?
考えられるのは、司書が嘘を吐いている、という可能性だ。したがって、本は実際には消えていない。消えたように錯覚させられた。図書委員のあの女子生徒が嘘を吐いているということは、おそらくないだろう。その女子生徒と、司書が、口裏を合わせているという可能性もなくはないが、一般的に考えられない。そもそもの問題として、司書が生徒に嫌がらせをしたら、処分される危機になりかねないから、司書が嘘を吐いているというのも、現実的にはありえない。
となると……。
やはり、誰かが盗んだのだ。
いったい、誰が、何のために、そんなことをしたのだろう?
地震が起こる仕組みについて、教師は落ち着いた声で説明している。日本の周囲を取り囲むプレートの名前を括弧に入れ、記憶する。しかし、今記憶したことは、明日には忘れているから、明日もう一度記憶し直す必要がある。
断層の種類を三つ覚え、それぞれを示す図に矢印を描き込んだ。これは、断層の動きを示している。
ホットスポット、という単語が出てきた。これは、日常的にも使われる用語だが、地学の分野でも専門用語して使うらしい。
そうこうしている内に、再びチャイムが鳴り、授業は終わった。
教室には戻らず、図書室に向かう。小説消失事件の行方が気になったからではない。そこで勉強しようと思ったからだ。図書室は、年中暖房が効いているため、月夜はあまり好きではなかったが、教室ではほかに残る生徒がいるので、彼らが帰るまでここにいることにした。
図書室は空いていた。
受験生の姿もちらほらと見られる。
司書が挨拶をしてきたから、月夜は軽く会釈した。
なんとなく、天井に目を向ける。
白い照明が灯っていた。
個人用のブースが空いていたから、テーブル席ではなく、月夜はそちらを選んで腰かけた。リュックを脇に置き、そこから勉強道具を取り出す。
忘れない内に、今の地学の授業で習ったことを、軽く復習しておこうと思った。
プレート、断層、ホットスポット……。
自分は、地球の住人なんだ、と月夜は思う。
しかし、それだけだった。
もし、火星の住人だったら、自分は火星の住人なんだ、と思っただろう。
電子辞書を起動し、分からない単語を調べる。教科書には書かれていない用語も出てきたから、それらの意味も調べた。
シャープペンシルを回す。
ノックして、芯を出す。
単語を何度か繰り返し書き、なるべく記憶に残るようにする。
突然、背後から抱きつかれる。
振り返ると、囀の顔がすぐ近くにあった。
「何?」
月夜は尋ねる。
「ん?」
声を発するだけで、囀は答えない。
その体勢のまま、二人は数秒間硬直する。
「どこが、具合が悪いの?」
月夜は質問した。
「具合は、悪いといえば、悪いかな」囀は話す。「だけど、体調が悪いわけじゃないから、大丈夫だよ」
「ここは、図書室だから、あまり、そういうことは、しない方がいいと思う」
「そうだね」そう言って、囀は月夜から離れた。「勉強?」
「うん」
「今日も、いつも通り?」
「そうだよ」
「じゃあ、僕もここで勉強しよう」
月夜の隣を通り、囀は彼女の向かい側の席に着いた。三面を囲む衝立があるから、月夜も、囀も、互いの姿を見ることはできない。
図書室は、本領を発揮するように静かだ。シャープペンシルをノックする音、ノートのページを捲る音、消しゴムの滓を払う音、ときには、嚔まで……。それらは明らかに物理的な振動だが、不思議と不快な感じはしない。そうした音を聞くことで、逆に静かだと感じるくらいだ。静かさを感じさせる音というのが、この世界には存在する。
囀が勉強している様子を、月夜は初めてしっかり見た。正確には、そんな様子は見えないが、なんとなく、気配が伝わってくるような感じがした。
顔を手もとに戻して、月夜は自分の勉強を進める。地学の復習は終わったから、今度は現代社会の教科書を開いた。ここに書かれていることは、今を生きる人間にとっては、幾分重要になる。少なくとも、数学や英語よりは実践的だ。だからといって、現代社会という科目の価値が、総体的に上がるわけではない。単純な価値だけで考えれば、数学の方が上のように月夜には思える。
窓にはカーテンが引かれているから、今は外の光は室内に差し込んでいない。それでも、もう太陽が大分傾きかけているのが分かった。外で部活動をする生徒は、こんな夕暮れ時の風景を、どのように捉えているのだろう、と月夜はなんとなく考える。それは、つまり、夕空が果たす象徴ということだ。部活動に所属していない人間の場合、夕空と帰宅がイコールの関係で繋がれているが、これから部活動をする人間はそうではない。人によっては、楽しさだったり、あるいは辛さの象徴なのかもしれない。
一時間が経過した頃、月夜は荷物を纏めて席を立った。
彼女の向こう側で、囀がそれに反応する。
「もう、教室に行く?」囀が尋ねた。
月夜は黙って頷く。
日が沈んだあとの校舎は、どことなくノスタルジックな雰囲気を纏っている。実際に、懐かしさを感じる要因などないのに、橙色の光を見るだけで、懐かしい気分になる。これは、如何なる道程を経て引き起こされる感情か。
教室の扉を開けた。
室内には、誰もいなかった。
囀は窓の傍に近づき、もうほとんど闇と化しつつある校庭を見下ろす。
「こんな時間まで、一生懸命汗を流して運動している人って、素敵だね」
月夜は自分の席に着き、彼女の独り言に応える。
「囀も、汗を流しながら、勉強をしたら?」
「嫌だよ、そんなの」囀は笑った。「汗でノートが見えなくなっちゃうよ」
「運動部に入ってみたいの?」
「一日くらいは、体験してみたいかな」
「一日なら、やらせてほしいと言えば、どの部活でも、やらせてくれると思うよ」
「月夜なら、どこの部活動がいい?」
「私は、テニス部」
「へえ……。それには、何か理由があるの?」
「それしか、思い浮かばなかった」
「適当だなあ」
その指摘は正しかったから、月夜は頷いた。
「囀は?」
月夜の質問を受けて、囀は得意そうな顔をする。
「僕はね、もう、生まれる前から、どこの部活に入るか決まっているんだよ」
「どこ?」
「ナイーブ」囀は言った。「ね、ぴったりでしょう?」
月夜は、今日も囀に呼び出されて、彼女と一緒に昼食をとることになった。といっても、月夜は今日は食べ物を貰うのは遠慮しておいた。お腹が空いていなかったし、特に食べたいとも思わなかったからだ。
囀は月夜の分まで弁当を作ってきていたが、その分は、ほかの生徒に譲ったみたいだった。彼女はそれなりに融通が利く。
前回は階段の踊り場で食べたから、今日は食堂に行った。食堂の中は混んでいるが、空いている席がないわけではない。苦しい空気の中で、口を開くのを厭わないのであれば、そこで食事をするのは自由だ。
食堂では、学食を買うことができるが、持ち込みも許可されている。ラーメンを家から持ってくるのは困難なので、どうしてもラーメンを食べたい人は、食堂で注文しなくてはならない。それでも、いつも家で食べているラーメンが恋しくて、あれがないとどうしようもない、生きていけるかさえ分からない、という人は、無理をしてでも家からラーメンを持ってくる必要がある(そんな人は滅多にいないが)。
長いテーブルが縦にいくつも並んでおり、最後のテーブルの向こう側は、中庭に繋がっている。食堂の正面に図書室があり、すぐ傍に購買もあった。
月夜と囀は、空いている席を探して、適当に腰をかけた。ここからだと、ステージがよく見える。もっとも、今日は何の催しもないらしい。ときどき、軽音楽部や有志のバンドが、楽器を演奏していることがある。
囀は一人で昼食をとり始めた。今日は標準的なお弁当だった。ふりかけがかかった白米に、いくつかの惣菜の詰め合わせ。野菜はブロッコリーとニンジンで、緑と橙色だった(これでは、説明になっていないが、気にしてはいけない)。
「食堂にいながら、何も食べないって、面白いね」ご飯を口に入れながら、片手で口もとを押さえて、囀が言った。「本当に大丈夫?」
「全然、平気」
囀は周囲を見渡す。
「ここの食堂って、こんなに混雑しているんだね」
月夜は首を傾げた。
「囀が、前通っていた学校では、こんな感じじゃなかったの?」
「うん……。なんか、こう……、もう少し寂れた感じだった」
「何を、食べた?」
「そこで?」
「うん」
「僕はね、あまり使ったことはないよ」囀は言った。「あ、でも、春巻きは美味しかったかな」
冬なのに、アイスを食べている者がいる。もちろん、どの季節に何を食べようと、個人の自由だ。真夏にチーズフォンデュを食べても、誰にも文句は言われない。
「このあとさ、ちょっと、図書室に行ってもいい?」卵焼きを箸で掴んで、囀は尋ねた。
「いいよ。いってらっしゃい」
「月夜も一緒に来るんだよ」
「どうして?」
「一緒の方がいいでしょう?」
「そうなの?」
「もう、変なこと言わないでよ」
変なことを言ったつもりはなかった、と月夜は思う。
「もう、昨日の本は、読み終わったの?」
「うん、まあ……。あれは、読むというより、見る感じだったから」囀は話した。「そういう、読み方が決まっていないものが、一番、読むのが難しい」
「現代文のテストも、難しいよ」
「え、そう?」
「うん」
「たとえば、どんなところが?」
「筆者が、本当はどう思っているのか、分からないのに、質問してくるところ、とか」
「ああ、なるほど……」箸を上下に振り、囀は奇怪なジェスチャーをする。「先生、言っていたよね。筆者が言いたいことを、上手く汲み取れないと、問題には答えられないって……」
「うん」
「そんなこと、無理だよね」
「そう、だと、思う」
沈黙。
月夜は後ろを振り返る。硝子越しに、中庭の様子が見えた。今は、ほとんど人はいない。やはり、寒いからだろう。もう少し暖かい季節だと、幾人かの男子生徒が、噴水の縁を走り回っていたりする。
食堂の傍に自動販売機があった。月夜は、そこで飲み物を買ったことは一度もない。自動販売機は、どのような仕組みになっているのだろう、と彼女はぼんやりと考える。特に、落ちてくる経路が気になった。ある程度の高さがあるのに、缶やペットボトルは意外なほど無傷だ。おそらく、直線的に自由落下してくるのではないだろう。何かしら、ルートのようなものがあるのだ。
正面を向くと、囀がにこにこ笑っていた。
「何か、いいことがあった?」不思議に思って、月夜は尋ねる。
「あったあった」囀は頷いた。
「何?」
「月夜の、髪が、こう、ふわって、宙に舞うところが見られた」
「それが、いいこと?」
「そうだよ。素敵じゃない? そういう場面に遭遇するのって……」
そうなのか、と月夜は考える。たしかに、言われてみれば、そんな気がしないでもない。
囀はすぐに弁当を食べ終わり、二人は食堂の出口に向かった。彼女は、普段はよく眠っているが、食後は活発に動けるようだ。
「月夜、アイス食べる?」
そう言いながら、囀はすでにショーケース型の冷凍庫に手を伸ばしている。
「いらない」
小銭を担当者に渡し、囀はバー形のチョコレートアイスを食べ始めた。
当然、アイスを食べながら図書室には入れない。食堂の傍の壁によって、月夜は囀がアイスを食べ終えるのを待った。
「美味しい?」
月夜の質問を受けて、囀は笑顔で頷く。
「正直、ご飯よりも、こっちの方が美味しい」
「じゃあ、毎日、アイスを食べれば、いいんじゃない?」
「うーん、本当はそうしたいところなんだけど、それだと、やっぱり、体調を悪くするかな」
「体調を悪くすると、問題なの?」
「一般的にはね」囀は言った。「それに、学生である以上、体調を崩すことはできないよ」
アイスの塵を捨てて、囀は、おまたせ、と月夜に言った。
二人で図書室に入る。上履きからスリッパに履き替える際、どれを選ぶか迷ったが、月夜は、左右の足先に均等なバランスで「図書室」と書かれたものを選んだ。そのマークは、すべてのスリッパに書かれているが、書いた人が違うのか、大きさや字体がバラバラだ。
図書室に入ると、カウンターの向こうに司書がいた。
司書は、一人の女子生徒と話していた。
特に聞き耳を立てたわけではないが、月夜には二人の会話が聞こえた。
「まだ、見つからないんですか?」女子生徒が尋ねる。
「ええ、そうなの」司書が答えた。「ごめんね。見つかったら、すぐに届けるからね」
「いえ、急がなくても、大丈夫です」
「予約しておいたのに、本当に……」
囀は気にしていないみたいだったが、月夜には、それが、今朝、彼女のクラスの図書委員が言っていた、小説の失踪事件についての会話だと分かった。事件、という言い方は多少大袈裟かもしれないが、盗まれたのだから、事件に変わりはない。
囀のあとについて、月夜も書棚の間を歩いた。昼休みだから、テーブルで本を読んでいる生徒もいる。個別のブースでは、受験生らしい者が、何人も勉強していた。もうすぐ、本番を迎えるらしい。本番前だからといって、意気込んで勉強しても、大きく変わらないのではないか、と月夜は考える。むしろ、本番前だからこそ、違うことをして頭を切り替えた方が良い。
小説のコーナーには行かないで、囀は絵本が展示された場所で立ち止まった。
「囀は、小説は読まないの?」
しゃがみ込んで本を手に取った彼女に、月夜は質問した。
「小説?」囀は答える。「読まないことはないけど、最近は、ストーリーとかじゃなくて、写真とか、絵とか、そういうものを見ることが多いかな」
囀の隣に一緒に座って、月夜も絵本を一冊取り出す。熊が主人公のもので、巨大なグリーンピースが描かれていた。熊と、巨大なグリーンピースとの間に、どんな関係があるのだろう、と思って、月夜は本を開く。読み進めると、孤島に眠っていると噂されるグリーンピースを、村一番の熊が探しにいく、というストーリーだと分かった。それでは、グリーンピースと、孤島では、何か関係があるのか、と思ったが、最後までストーリーを追っても、その点については何も説明されていなかった。
月夜は、本を閉じ、それを膝の上に置く。
目を横に向ける。
すぐ傍に、本を持っていない方の、囀の垂れ下がった手があった。
それを握ろうか、と月夜は考える。
勝手に触れて、怒られないだろうか。
きっと、囀なら怒らないだろうが、月夜は、少し、彼女の手に触れるのを躊躇した。
それは……。
それは、どうしてだろう?
勇気?
勇気が足りないから?
「ねえ、月夜」囀が、本のページを開いたまま、それを月夜に近づけた。「これ、見てよ」
月夜は本を覗き込む。
完熟したトマトが、階段を転がっていた。
「それが、どうかしたの?」
「おかしいよね、こんなの」囀は笑いながら話す。「小さい子に、こんなの見せて、いいのかな」
「何が、駄目なの?」
「だってさあ……」しかし、囀はそれ以上続けようとしない。
月夜は、思いきって、囀の手を握った。
接触。
体温。
温かった。
顔を上げて、囀の様子を観察する。
しかし、彼女は何の反応も示さない。
月夜は、手を握る力を強める。
「しかもさあ……」囀は、再び本のページを月夜に見せた。「これなんか、もう、大変だよね」
今度は、ピーマンが海を泳いでいた。
「それが、何?」
「変だと思わない?」
それよりも変なことが、今起こっているではないか、と月夜は思う。
「思わない」
「普通、ピーマンは泳がないじゃん」
月夜には囀のセンスは分からなかった。
借りる本を一冊持って、囀は静かに立ち上がる。月夜は彼女の手を離し、何事もなかったかのように顔を澄ませた。
そのまま、じっと囀を見つめる。
「何?」彼女は首を傾げた。
「何も」月夜は答える。
カウンターに本を持っていき、バーコードを認識してもらうことで、貸し出しは完了する。絵本を抱えた囀と一緒に、月夜は図書室を出た。
食堂の硝子戸から、壁にかけられた時計を見る。
昼休みは、あと十分だった。
階段を上って、教室がある階まで移動する。生徒の多くは、まだ廊下の外に出て話していた。次の授業は移動する必要がないから、チャイムが鳴る直前まで、時間を有効活用している生徒が多い。
机の中から教科書とノート、筆箱を取り出し、授業の体勢を整える。月夜は視線を右斜め前方に向けて、囀の姿を確認した。彼女は、さすがにもう眠っていない。身体を後ろに向けて、そこに座るクラスメートと話していた。
囀は、誰といるときでも常に笑顔だ。
本当に常ではなくても、そうした印象を抱く。
教室前の扉が開いて、現代文の教師が現れた。チャイムが鳴り、授業が始まる。
手に持っているシャープペンシルは、教師の板書に反応するように正しく動き、ノートに炭素を擦り付ける。間違えたら消しゴムで消し、再び書き直す。その繰り返し。ノートをとるのが授業の目的ではないが、現実として、そうなっているのは確かだ。手を動かすことで、ある程度集中力は高まるらしいが、集中しようと思っていないのであれば、効果は認められない。
教室の午後の空気は、停滞気味で、充満気味で、そして、沈殿気味だった。天井に顔を向けても、そこに開放的な空はない。唯一、開いていなくても外界と繋がる窓は、月夜の席からは離れている。暖房が効いていて、気分が悪くなりそうだったが、気分が悪くなっても、彼女が困ることはなかった。
今、自分が突然死んでしまったら、クラスメートはどうするだろう?
久し振りに、面白いことを思いついた気がした。
彼らの反応を想像するのが面白いのではない。
様々なシチュエーションで、自分が死ぬのを想像するのが、面白いのだ。
本来なら、死と場所はほとんど関係がない。どこで死のうと、死んだ者はもう死んだのだ。それ以上その人とコミュニケーションをとることはできないし、思い出という補助機能を除けば、回線は完全に遮断されるに等しい。
けれども、人間は、自分であろうと、他人であろうと、死亡する時や場所を大事にしたがる。そこに価値を見出そうとする。どうせ死ぬなら、愛する人に看取られながら死にたいとか、あまりにも若い内に死にたくないとか、そうした不思議なことを口にする。
それは、どうしてだろう?
どのようなシチュエーションで死んでも、自分は一人しかいないのだから、その人にとっては、それはほかの誰にも経験できない、唯一絶対のもので、価値が認められるはずだ。
でも……。
……自分は、どうだろう?
やはり、死ぬときは誰かと一緒が良い、と感じるだろうか?
自分の知り合いを一人ずつ挙げて、彼らとともに死亡する、あるいは彼らに看取られて死亡する情景を、月夜は一つ一つシミュレーションしていった。
どれも、素敵だと思えた。
もちろん、自分一人で死ぬ情景も思い描いた。
けれど、それも、それはそれで良いと思った。
自分が死んでも、彼らは、その後も生き続けていく。彼らがまだ生きているという事実さえ成立していれば、自分がどうなろうと、どうでも良い。自分の目を通して、それを確かめることができなくても、全然問題ではない。
それが、愛というものではないか?
……愛。
なんて、チープな言葉だろう。
しかし、それと同時に、いや、それだからこそ、価値を持った言葉だといえる。
それでは……。
そもそも、事実とは何だろうか?
考え事をしていても、シャープペンシルは勝手に動く。ときどき、教科書の該当する部分に傍線を引いたり、重要な段落に印をつけたりもする。どれも単純な作業で、面白くはない。教科書に書かれている文章は、この授業の中で唯一面白い。教師が話す内容は、抽象化してしまえば教科書に書かれていることと同じで、はっきりいって、重要ではない。
ノートを千切って、紙飛行機を折って飛ばしたら、少しは楽しくなるだろうか、と月夜は考える。
実際にやってみようとは思わなかった。
恥ずかしいからではない。
自分に対するイメージを壊したくないから、というのは、少しある。
けれど、それ以上に、やらなくても、どうなるか予想がついた。
だから、やらなかった。
予想は、一つには絞れない。それはどんな場合でもそうだ。
それなら、いくつも予想すれば良い。それだけで、何が起きても、充分な準備を持って接することができる。
授業はあっという間に終わった。あっという間だと感じるのは、集中していたからかもしれないが、集中とは、しようと思ってできるものではないので、月夜は何の努力もいらなかったし、努力をしたつもりなどなかった。
次の授業は移動する必要があったから、荷物を纏めて、月夜は立ち上がった。もう、次の授業で最後だから、リュックも一緒に持っていく。こういう日は、最後のホームルームは省略されることになっている。
教室から出ようとしたところで、自然と囀と合流した。
「月夜は、次は何?」
歩きながら、月夜は答える。
「地学」
「なんか、現代文ってさ、面白いよね」囀は話した。「文章の意味を、紐解いていくのが」
「文章の意味を、紐解く?」
「そうそう」囀は説明する。「つまり、したがって、しかし、みたいにさ、その下に、それらの言葉が示す要素がくっついているわけでしょう? で、そういうふうに示されたものは、きちんと、その全体の中で役割を果たしているわけで……」
月夜は頷く。
「そういうのが、面白い」
「ごめん、よく、分からない」
囀は月夜を見た。
「分かってよ」囀は微笑む。「説明が下手なのは承知しているけど、なんとか、理解して」
囀が今した説明を思い返し、月夜はもう一度理解しようとする。ニュアンスは伝わったが、それで合っているという確信はなかった。
「少し、分かったような、気がする」
「本当?」
「うん」
「ああ、よかった」
囀と別れて、地学教室に入る。この部屋は、常に暗くて、如何にも実験室という感じがする。しかし、地学はあまり実験を伴わない授業だから、そのイメージは本質とはずれている。地学では、観察もあまりしない。配られたプリントに目を通して、教師の説明を聞くだけだ。プリントには、中身のない括弧が並んでいて、そこに、教師が言ったことを一つずつ記していく。だから、ノートをとるよりは労力は少なくて済む。ただし、理科系の科目は、覚えなくてはならない用語が多く、かつそれらの用語はあとで触れる別の単元に繋がっていることが多いから、一つずつ丁寧に覚えないと、後々お釈迦になる(お釈迦というのは、ここでは、存在の名称ではない)。
それでも、現代文よりは負荷はかからないから、月夜は手を動かしつつも、頭では別のことを考えていた。
今日の朝聞いた話と、図書館で耳にした話が、少し気になった。
あの女子生徒は、無事に小説を手に入れられただろうか?
いや、きっと、まだだ。
本はどうして消えてしまったのか、と月夜は多少不思議に思う。
疑問に感じるのは、興味を抱く前兆だ。
だから、彼女は、この出来事に関して、後々興味を抱くかもしれない。
小説は昨日の午後に返却されたが、今日の朝にはなくなっていた。つまり、誰かが盗めるとしたら、その間の時間、つまり、夜の間でしかない。
盗んだのではないとしたら、本はどうやって消えたのだろう?
考えられるのは、司書が嘘を吐いている、という可能性だ。したがって、本は実際には消えていない。消えたように錯覚させられた。図書委員のあの女子生徒が嘘を吐いているということは、おそらくないだろう。その女子生徒と、司書が、口裏を合わせているという可能性もなくはないが、一般的に考えられない。そもそもの問題として、司書が生徒に嫌がらせをしたら、処分される危機になりかねないから、司書が嘘を吐いているというのも、現実的にはありえない。
となると……。
やはり、誰かが盗んだのだ。
いったい、誰が、何のために、そんなことをしたのだろう?
地震が起こる仕組みについて、教師は落ち着いた声で説明している。日本の周囲を取り囲むプレートの名前を括弧に入れ、記憶する。しかし、今記憶したことは、明日には忘れているから、明日もう一度記憶し直す必要がある。
断層の種類を三つ覚え、それぞれを示す図に矢印を描き込んだ。これは、断層の動きを示している。
ホットスポット、という単語が出てきた。これは、日常的にも使われる用語だが、地学の分野でも専門用語して使うらしい。
そうこうしている内に、再びチャイムが鳴り、授業は終わった。
教室には戻らず、図書室に向かう。小説消失事件の行方が気になったからではない。そこで勉強しようと思ったからだ。図書室は、年中暖房が効いているため、月夜はあまり好きではなかったが、教室ではほかに残る生徒がいるので、彼らが帰るまでここにいることにした。
図書室は空いていた。
受験生の姿もちらほらと見られる。
司書が挨拶をしてきたから、月夜は軽く会釈した。
なんとなく、天井に目を向ける。
白い照明が灯っていた。
個人用のブースが空いていたから、テーブル席ではなく、月夜はそちらを選んで腰かけた。リュックを脇に置き、そこから勉強道具を取り出す。
忘れない内に、今の地学の授業で習ったことを、軽く復習しておこうと思った。
プレート、断層、ホットスポット……。
自分は、地球の住人なんだ、と月夜は思う。
しかし、それだけだった。
もし、火星の住人だったら、自分は火星の住人なんだ、と思っただろう。
電子辞書を起動し、分からない単語を調べる。教科書には書かれていない用語も出てきたから、それらの意味も調べた。
シャープペンシルを回す。
ノックして、芯を出す。
単語を何度か繰り返し書き、なるべく記憶に残るようにする。
突然、背後から抱きつかれる。
振り返ると、囀の顔がすぐ近くにあった。
「何?」
月夜は尋ねる。
「ん?」
声を発するだけで、囀は答えない。
その体勢のまま、二人は数秒間硬直する。
「どこが、具合が悪いの?」
月夜は質問した。
「具合は、悪いといえば、悪いかな」囀は話す。「だけど、体調が悪いわけじゃないから、大丈夫だよ」
「ここは、図書室だから、あまり、そういうことは、しない方がいいと思う」
「そうだね」そう言って、囀は月夜から離れた。「勉強?」
「うん」
「今日も、いつも通り?」
「そうだよ」
「じゃあ、僕もここで勉強しよう」
月夜の隣を通り、囀は彼女の向かい側の席に着いた。三面を囲む衝立があるから、月夜も、囀も、互いの姿を見ることはできない。
図書室は、本領を発揮するように静かだ。シャープペンシルをノックする音、ノートのページを捲る音、消しゴムの滓を払う音、ときには、嚔まで……。それらは明らかに物理的な振動だが、不思議と不快な感じはしない。そうした音を聞くことで、逆に静かだと感じるくらいだ。静かさを感じさせる音というのが、この世界には存在する。
囀が勉強している様子を、月夜は初めてしっかり見た。正確には、そんな様子は見えないが、なんとなく、気配が伝わってくるような感じがした。
顔を手もとに戻して、月夜は自分の勉強を進める。地学の復習は終わったから、今度は現代社会の教科書を開いた。ここに書かれていることは、今を生きる人間にとっては、幾分重要になる。少なくとも、数学や英語よりは実践的だ。だからといって、現代社会という科目の価値が、総体的に上がるわけではない。単純な価値だけで考えれば、数学の方が上のように月夜には思える。
窓にはカーテンが引かれているから、今は外の光は室内に差し込んでいない。それでも、もう太陽が大分傾きかけているのが分かった。外で部活動をする生徒は、こんな夕暮れ時の風景を、どのように捉えているのだろう、と月夜はなんとなく考える。それは、つまり、夕空が果たす象徴ということだ。部活動に所属していない人間の場合、夕空と帰宅がイコールの関係で繋がれているが、これから部活動をする人間はそうではない。人によっては、楽しさだったり、あるいは辛さの象徴なのかもしれない。
一時間が経過した頃、月夜は荷物を纏めて席を立った。
彼女の向こう側で、囀がそれに反応する。
「もう、教室に行く?」囀が尋ねた。
月夜は黙って頷く。
日が沈んだあとの校舎は、どことなくノスタルジックな雰囲気を纏っている。実際に、懐かしさを感じる要因などないのに、橙色の光を見るだけで、懐かしい気分になる。これは、如何なる道程を経て引き起こされる感情か。
教室の扉を開けた。
室内には、誰もいなかった。
囀は窓の傍に近づき、もうほとんど闇と化しつつある校庭を見下ろす。
「こんな時間まで、一生懸命汗を流して運動している人って、素敵だね」
月夜は自分の席に着き、彼女の独り言に応える。
「囀も、汗を流しながら、勉強をしたら?」
「嫌だよ、そんなの」囀は笑った。「汗でノートが見えなくなっちゃうよ」
「運動部に入ってみたいの?」
「一日くらいは、体験してみたいかな」
「一日なら、やらせてほしいと言えば、どの部活でも、やらせてくれると思うよ」
「月夜なら、どこの部活動がいい?」
「私は、テニス部」
「へえ……。それには、何か理由があるの?」
「それしか、思い浮かばなかった」
「適当だなあ」
その指摘は正しかったから、月夜は頷いた。
「囀は?」
月夜の質問を受けて、囀は得意そうな顔をする。
「僕はね、もう、生まれる前から、どこの部活に入るか決まっているんだよ」
「どこ?」
「ナイーブ」囀は言った。「ね、ぴったりでしょう?」
0
お気に入りに追加
1
あなたにおすすめの小説
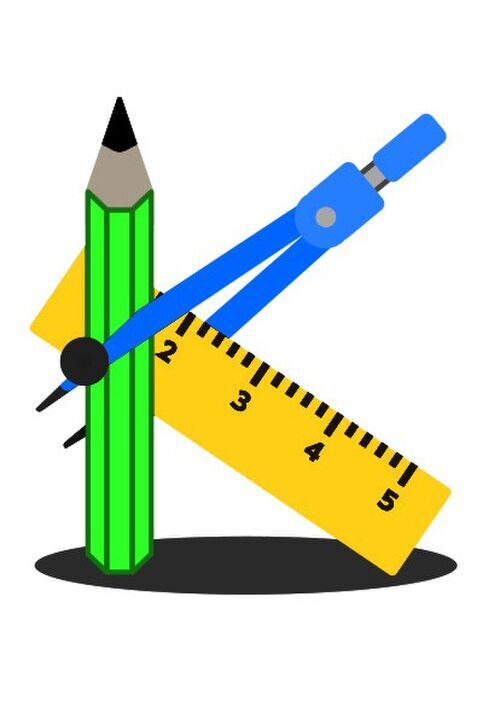
Next to Her Last Message
羽上帆樽
ライト文芸
森を抜けた先に、その邸宅はあった。草原が広がる雄大な空間に、ぽつんと建つ一軒の邸宅で、二人は女性から遺書の執筆作業を頼まれる。話によると、彼女は危篤の状態らしい。二人の子どもたちとともに一週間を過ごす中で、事態の食い違いに気がついた二人は、真の事実を知るべく観点を修正する。遺書とは何か? 誰のために書くのか? 答えはそれぞれ異なるもので良いが、そもそもの問題として、遺書を書く必要があるのかを考える必要がある。
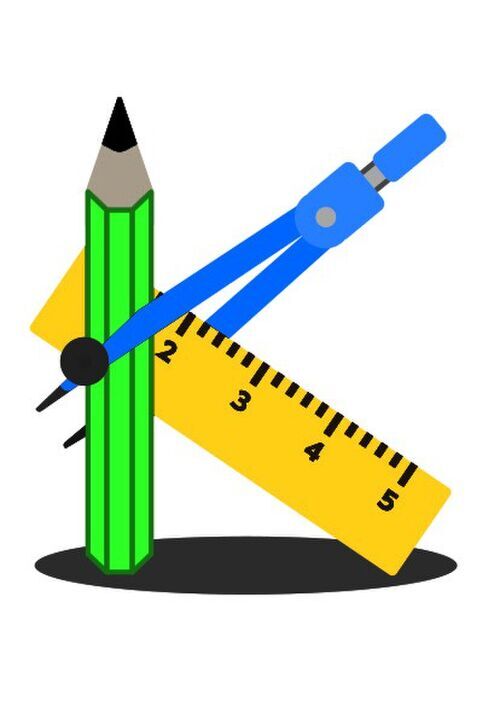
舞台装置は闇の中
羽上帆樽
ライト文芸
暗闇月夜は高校生になった。ここから彼女の物語は始まる。
行く先は不明。ただし、時間は常に人間の隣にあるが故に、進行を妨げることはできない。
毎日1000文字ずつ更新します。いつまで続くか分かりません。
終わりが不明瞭であるため、どこから入ってもらっても構いません。

【R15】メイド・イン・ヘブン
あおみなみ
ライト文芸
「私はここしか知らないけれど、多分ここは天国だと思う」
ミステリアスな美青年「ナル」と、恋人の「ベル」。
年の差カップルには、大きな秘密があった。

日給二万円の週末魔法少女 ~夏木聖那と三人の少女~
海獺屋ぼの
ライト文芸
ある日、女子校に通う夏木聖那は『魔法少女募集』という奇妙な求人広告を見つけた。
そして彼女はその求人の日当二万円という金額に目がくらんで週末限定の『魔法少女』をすることを決意する。
そんな普通の女子高生が魔法少女のアルバイトを通して大人へと成長していく物語。

魔界最強に転生した社畜は、イケメン王子に奪い合われることになりました
タタミ
BL
ブラック企業に務める社畜・佐藤流嘉。
クリスマスも残業確定の非リア人生は、トラックの激突により突然終了する。
死後目覚めると、目の前で見目麗しい天使が微笑んでいた。
「ここは天国ではなく魔界です」
天使に会えたと喜んだのもつかの間、そこは天国などではなく魔法が当たり前にある世界・魔界だと知らされる。そして流嘉は、魔界に君臨する最強の支配者『至上様』に転生していたのだった。
「至上様、私に接吻を」
「あっ。ああ、接吻か……って、接吻!?なんだそれ、まさかキスですか!?」
何が起こっているのかわからないうちに、流嘉の前に現れたのは美しい4人の王子。この4王子にキスをして、結婚相手を選ばなければならないと言われて──!?

〈社会人百合〉アキとハル
みなはらつかさ
恋愛
女の子拾いました――。
ある朝起きたら、隣にネイキッドな女の子が寝ていた!?
主人公・紅(くれない)アキは、どういったことかと問いただすと、酔っ払った勢いで、彼女・葵(あおい)ハルと一夜をともにしたらしい。
しかも、ハルは失踪中の大企業令嬢で……?
絵:Novel AI

差し伸べられなかった手で空を覆った
楠富 つかさ
ライト文芸
地方都市、空の宮市の公立高校で主人公・猪俣愛弥は、美人だが少々ナルシストで物言いが哲学的なクラスメイト・卯花彩瑛と出逢う。コミュ障で馴染めない愛弥と、周囲を寄せ付けない彩瑛は次第に惹かれていくが……。
生きることを見つめ直す少女たちが過ごす青春の十二ヵ月。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由
フルーツパフェ
大衆娯楽
クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。
トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。
いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。
考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。
赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。
言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。
たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















