13 / 24
12 「ふるさとの夕陽」【御前音楽会】
しおりを挟む
ライヒェンバッハ伯爵夫人はビッテンフェルト男爵夫人よりも少し年上かなってカンジの美人の人だ。
お子さんはみんな嫁いでしまったりドクリツして領地の管理や商売のために家を出てしまっていたり士官として軍隊に行っていたりするので、まだ小学生のタオが可愛くて仕方がないらしい。
「あのおカタい皇帝陛下をその気にさせたなんて! タオ、あなたスゴいわ。
いいこと? 堂々と胸を張って、落ち着いて弾くのよ!」
皇宮に向かう馬車の中で、帝国の正式な女性用礼装である丈長の白のテュニカにショールを羽織った伯爵夫人はコウフンしながらそう言った。
「ああ、ヤヨイちゃんもいればよかったのにね。あの子ったら、いつもカンジンな時にお仕事が忙しくなっちゃうのですもの!」
でも、演奏する本人のタオは緊張しているのかムッツリと押し黙ってずっと窓の外を眺め続けていた。手は大事だから握らない。その代わり、彼の膝頭に手を置いてやった。
皇宮は元老院の北隣にある。
この地上でもっとも強大な帝国皇帝のお屋敷だから、きっとゴーカケンラン? な建物を想像していたら、ぜんぜんそんなことなかった。元老院の議場を取り囲むようにいくつかある政府の建物と同じ黒い石の、クィリナリスの貴族の家よりも小さいんじゃないかなと思わせるようなジミなカンジのお屋敷だった。南側の広い元老院前広場とは反対の北に向いた皇宮前の広場はずっと規模が小さく、しかもほかの政府の庁舎の車寄せも兼ねていた。そのあまりのジミさにちょっと戸惑ってしまうほどだった。
ただ、警備の憲兵隊は何人かいて、ここが帝国皇帝の住まいだということをあらためて感じさせていた。すでに何台かの馬車が止まっていて、荷台の上に覆いがされたカーキ色じゃない青いトラックまでいた。
ぼくたちは馬車を降り、ビッテンフェルト家よりも小さなエントランスからなかに入った。
皇宮は中もジミだった。貴族の家には必ずと言っていいほどあるアトリウムもなかった。その代わり、エントランスホールは広く、白いテュニカの人たちがそこここに集っていたり忙しそうに行きかったりしていた。
黒御影石の壁にはズラリと絵がかけてあった。
「ミハイル、御覧なさい。代々の帝国皇帝の肖像画よ」
伯爵夫人が教えてくれた。
白いトーガ姿のもあったが、多くは軍服に赤いマントを翻した颯爽とした立ち姿。その肖像画たちを眺めているとやっと帝国皇帝の皇宮に来たジッカン? が湧いて来た。
「素晴らしいわ。わたしも皇宮におじゃまするのは初めてなの。タオのおかげね」
壁の肖像画たちに見惚れていると、
「やあ、タオ! 来たな!」
快活そうな太い声がした。
クセのある金髪を短く刈り込んだ真っ白なテュニカの大柄な男の人がやってきた。
「まあ、ウィルヘルム! いつもタオがお世話になって・・・」
「これはメーテル! ようこそ『皇宮音楽会』へ」
この人が近衛軍団でのビッテンフェルト准将の同僚将軍ブランケンハイム侯爵か・・・。
階級は准将のいっこ上の少将だと男爵から聞いていた。軍服姿でないせいか、いつもキアイ入りまくりの准将よりもだいぶ穏やかに見える。今回の音楽会の発起人で世話役の人だとタオからも聞いていた。
帝国に来た頃はこのテュニカという服がとても違和感だったのを思い出す。軽くて薄すぎる、と。でも今はぼくもその軽さと薄さに慣れてしまった。
そのぼくの目にも真っ白なテュニカは別格に映る。子どもはもとより、かなり年配の人が着てもまったくヘンな感じがしないどころか、とても若々しく生気? にあふれていてとても清潔感? を感じる。強い陽射しのせいで年中日焼けしているからかもしれない。
真っ白なテュニカのブランケンハイム侯爵は、とても若々しく、溌溂としていた。ビッテンフェルト男爵と同じ軍人だからなおさらそう見えるのかもしれない。
でも、侯爵と男爵って、どう違うんだ?
「メーテル! やっとこの日が参りましたな。タオの成長ぶりには目を見張るものがありますな。彼の奏でる音には貴女もきっと驚きますぞお・・・」
そう言って侯爵は鷹揚に両手を広げ微笑んだ。
「さ、タオ。さっそく準備にかかるとしよう。メーテルは控室へどうぞ」
「じゃあね、タオ。しっかり、がんばるのよ」
伯爵夫人はまた知り合いの人を見つけたのか「まあ、フランツ・・・」とエントランス脇の部屋の中に入っていった。知り合いの多い人なんだな、と思った。
「あの、侯爵・・・」
すると、それまで押し黙っていたタオが顔を上げた。
「なんだね、タオ」
「彼はミハイルです。ぼくのともだちなんです。出番まで彼と一緒にいたいんです。いいですか?」
「おお、もちろんだとも!」
と、侯爵は言った。そして、ぼくを見下ろしてニヤ、と笑った。
「そうか。キミがあの猪武者のところの北の留学生だな。彼がよくキミのことを話していた」
「イノシシムシャ?」
すると、ブランケンハイム侯爵はイタズラそうにウィンクして指を口に当て声を潜めた。
「なに。あのビッテンフェルトのアダ名さ。彼には言わないでくれよ」
同じ近衛軍団の旅団長だから、准将とはライバル? なのだろう。ぼくは吹き出しそうになるのを堪えつつ、貴族なのにちっとも奢らないし威張らない、子供のぼくにさえフレンドリーな侯爵に好感を持った。
エントランスの奥の広間のようなところが会場のようだった。
黒御影石のエントランスとは違い、四方を白い壁に囲われたその広間の真正面に暖炉がある。その上に帝国の鷲の紋章がかけられていた。高い天井にはいくつかの天窓、天井近くの壁には明かり取りの窓がありエントランスよりも明るい感じがした。
その右手の壁の真ん中に、エントランスにかけられていたのよりひと際大きな肖像画があった。
それが誰の肖像画なのかはすぐにわかった。社会の教科書の挿絵に載っていたのは色の無い線で描かれたものだったが、そのポーズと姿がまったく一緒だったからだ。
教科書にはこう書かれていた。
神君(デイブス)カエサル。
軍服姿でアタマに月桂冠を着け、深紅のマントを颯爽と風になびかせて彼方のほうを指さしている厳めしい顔。
これがきっとオリジナル? の画なのだろう。
ボーっと画を見上げていたら反対側の壁のドアが開いて大きな黒いテーブルのようなものが運び込まれてきた。それは正面の暖炉の真ん前よりやや左に置かれ、上のふたがぱか、と開けられた。
何だろう。
そう思っていると、その黒いテーブルの端に椅子を寄せて来たタオが座り、テーブルの端のもう一つの蓋を開けた。そして、ポン、とそこを叩いた。
ああ、ピアノだ。
タオの指が鍵盤を舞った。左の低い音から右の高い音まで。まるで川を流れる水のように音が流れ出た。その広間が一瞬で音楽会の会場に変わったのがわかった。かっかの家のは茶色い箱だったが、これはテーブル型のピアノなのだ。箱のピアノに比べると、音の広がりがスゴい。
4人の白いテュニカの人たちがはいってきた。男の人と女の人が2人ずつ。みんなヘンな形の黒いケースを持っていた。その人たちに、タオは「こんちわ」とあいさつを交わしていた。
「楽団の人たちだよ」
と、タオが教えてくれた。
彼らは黒いケースを開けて大きいのや小さいのの茶色い楽器を取り出した。それぞれに4本の弦が張ってあるヤツ。それと、長い矢みたいなの。そしてピアノの周りに集まった。タオが鍵盤の一つをポン、と打つと、みんな矢で楽器の弦を擦り始めた。弦の音が鳴った。
ああ、なるほど。音を合わせているんだな・・・。
それぐらいのことはまだ音楽のことをよく知らないぼくにもわかる。
侯爵がピアノの傍に来てタオに何かを話しかけた。タオがそれに何かを言った。すると、侯爵が誰かを呼んで、その誰かが開いた大きなふたの中に何かの棒を突っ込んだ。タオが一つの音をポンポンと連続して叩く。そしてまた、流れる水の音。
ああ、これは音を調節してるんだ。
すでにそこはタオの世界だった。他の人が窺い知ることのできない彼だけの世界。彼は自分の世界の中にしっかりとしたイメージを持っていて、それを形にしようとしているのだ。ぼくより3つも下の小さな体の中に無限の世界が詰まっている。そんな気がした。こんなヤツはぼくの里にも居ないし、まだ全てを見たわけじゃないけれど、この広い帝国中を探しても、そうはいない。
やっぱりタオは、スゴいやつだ。
しばらくして納得したのか、タオはその誰かに何かを言い、ぼくを振り向いた。
「ミーシャ、そこに居ててね。もうちょっとだから」
「大丈夫だよ、タオ。ここにいるよ」
と、ぼくは応えた。
こんなスゴいヤツに頼られている。とても誇らしい気持ちがした。
タオが指慣らしをしている間に暖炉の前と広間の床に椅子が並べられた。
暖炉の前には4つ。そして、一段低くなった床にはざっと50ほどの椅子が暖炉と向かい合わせに置かれていった。それが客席なのだろう。小学校のぼくのクラスよりも少し多い程度。へえ、案外と少ないものだな。
ふいにぽん、と肩を叩かれた。ブランケンハイム侯爵だった。
「タオは上手だろう」
「ええ、とても・・・」
「ミハイル、と言ったね。キミも音楽が好きみたいだな」
「はい。タオのピアノを聞きながら宿題をするととてもはかどるんです」
と、ぼくは答えた。
「うむ。それも音楽の効能のひとつだな」
侯爵は笑った。
ビッテンフェルト男爵とおなじ近衛軍団の将官なのに、男爵とはだいぶ違うなと思った。なんというか、知性的? というか、穏やか、というか・・・。
タオのピアノと茶色い楽器の人たちの合奏が始まった。でもそれはすぐに途中で終わった。出だしの練習というか確認? をしているのだろう。
「そうだ! キミの里にも音楽はあるだろう。どんなものだい?」
「音楽というか、歌と踊りです」
「ほう、どんな歌だい?」
「あの、祭りの時とかに、村のみんなが広場に集まって歌う歌です。今年も小麦がたんと実った。さあ刈り入れだ。そんな意味の歌です。
はじめはゆっくりと歌います。こんな風に拍手で拍子をとりながら。で、だんだん拍子が早くなってきます。そうすると、みんなの中から踊り自慢が前に出てみんなの輪の真ん中で踊り出すんです。で、次第に踊り手が増えて来ます。で、歌も速くなってきます。で、踊ってる人のうち速さについて来れない人が出て来てみんなの輪の中に引き戻されるんですが、途中でへたっちゃったバツとしてしこたまお酒を飲まされるんです。で、ツブれます」
「うわっはっは! それで?」
「で、さいごに3人か2人が、いずれも踊り自慢の人が残って踊り続けるんですが、そのころになると歌は猛烈な速さになってて、歌う方も口が回らないくらいになってきます。で、最後まで踊り続けた人がその年の優勝ってわけです。やっぱりしこたまお酒を飲まされて、やっぱりツブれます。優勝賞品で贈られた羊を枕にして寝ちゃいます」
「うわっはっは! 結局みんな飲まされてツブされるわけか! そりゃあ愉快だな」
「こんなスゴい音楽に比べるのも、恥ずかしいんですが・・・」
「そんなことはないぞ、ミハイル。それはその民族の日々の暮らしから生まれた自然な文化というものだ」
と、侯爵は言った。
「キミたちの北の種族は村同士たびたび小競り合いをしていると聞いた。当然にいつも緊張を強いられる毎日を送っていることだろう。察するにそうした緊張から一時でも逃れたいという願望が生み出した祭りであり歌であり音楽なのだろうな。我々帝国人もキミたちも同じ人間だ。歌や踊りや音楽で感情を発散させたいというのは人間として自然なことだと思う」
侯爵の言葉は「野蛮人」と言われている北の里から来たぼくを安心させた。そこでふと前から思っていたことを尋ねたくなった。
「あの、こうしゃく。訊いてもいいですか」
「いいとも。なんでも言ってみたまえ」
「皇帝陛下はハデな催しがお嫌いな方だと聞きましたが、音楽はお好きなんですね。だってこういう音楽会にはおいでになるわけですから」
すると、侯爵はゆっくりと首を振った。
「いいや、ミハイル。陛下は帝国の風である『質実剛健』のカタマリのような御方なのだ。舞踏会や晩餐会だけでなく、音楽もお嫌いなのだ。お嫌いだった。陛下は音楽に対してなにか誤解をお持ちなのだと思う」
「え、そうなんですか?」
「そうだとも。だから、こうしてこの音楽会を催せるまでにするために、わたしやヤン閣下は大変な苦労を重ねて来たのだ」
「それは、何故ですか」
「よき文化、よき音楽を帝国にあまねく隅々まで及ぼし根付かせることが、すなわち帝国人の幸福につながると思っているのでね。そのためには陛下のご理解が是非とも必要だからなのだよ、ミハイル。陛下もタオのピアノを聴けばきっとお心を開いてくださる。そう信じているのだ」
「侯爵閣下、そろそろ、お時間です」
侯爵の家の人か皇宮の人か、会場になる広間の準備をしていた人がやってきて侯爵に告げた。
「おお、そうか。では客を入れるとしよう」
係の人にそう言って、侯爵はパンパンと手を叩いた。
「そろそろいいかね? 」
楽団の人とタオが練習を止めた。
「ヨハン、仕上がりは良さそうだな」
侯爵が一番小さい楽器の年嵩の男の人に声を掛けた。侯爵と同じ歳ほどのひとだ。
「ええ、侯爵。上々です。タオもね」
ヨハンと呼ばれた人がピアノを振り返った。タオはニコッと笑ってアタマを下げた。
侯爵が音を奏でるピアノの側に寄った。
「タオ、落ち着いてな。いつもの練習だと思って気楽にやりたまえ」
すると、別の係の人がやってきて侯爵に言った。
「閣下、内親王殿下がお着きになられました」
「おいでになったか、ではお迎えせねばな」
侯爵は教えてくれた。
「わがブランケンハイム家には今、東のノール王国の王女様、アンジェリーカ内親王がご寄宿なされているのだ。今夜はせっかくの皇帝陛下御臨席の機会だからとお招きしたのだよ」
そういうと、侯爵はぼくの肩にぽんと手を置いた。
「ミハイル。タオにはキミが必要らしい。傍についていてやってくれ」
楽団の人たちとタオとぼくは広間の続きの小部屋に移った。
小さなテーブルの上にはコーヒーのポットやいろんなお菓子のお皿が載っていた。
皇宮の人たちだろうか、いくつかのカンテラを下げた人たちが来て壁のフックやテーブルの上に明かりを掛けていき、窓を閉めて部屋を出ていった。
楽団の人たちはすぐにテーブルに集まってコーヒーを注いだりお菓子を食べたりして落ち着いていた。
だけど、タオだけは落ち着かなげに部屋の中を歩き回っていた。
「タオ、マカロン食べなよ。チョコレートも。美味しいよ。ねえ、キミもどう?」
ぼくは楽団の人に勧められた甘いお菓子を食べた。ビッテンフェルト家で食べたのとはまたちがった美味しさのものだった。でも、タオが気になった。
小皿のひとつを取って壁際を落ち着かなげに行ったり来たりしている「小さな巨人」に勧めた。とりあえず、椅子に座らせた。
「ありがと、ミーシャ・・・」
ひとくちは食べたけど、かけらを皿に戻したタオはまた立ち上がって歩き始めた。
ヨハンという楽団のリーダーの人がぼくに向かってゆっくりと首を振った。彼をそっとしておいて。そんな風に。
広間に通じるドアの向こうがざわめきだした。お客さんたちが入って来たらしかった。
ドアに近づいてそっと隙間を開けた。色とりどりのテュニカやトーガ。平民とさして変わらない服装だけれど、一見してみんな貴族の人たちであることはぼくにもわかった。どこが違うのかと聞かれると困るけれど、なんか、違うのだ。立ち振る舞いとか、みんなこういう催しに慣れている。強いて言えば、そんなカンジ。こうした違いがわかるのは男爵家であるビッテンフェルト家にいるお陰だと思う。みんな、手に白い紙を持っている。演目を書いたプログラム? というヤツだろう。
すると、ひと際キレイで可愛らしい女の子が目を惹いた。ぼくよりひとつかふたつほど年上らしい。薄いピンクの少し丈の短いテュニカにお揃いのショールを巻いている。つん、とすましたブルネット。気品? そんな空気を漂わせた女の子だ。彼女はライヒェンバッハ伯爵夫人と話しながら広間に入って来た、
ああ、あれがノールとかいうところのお姫様だな・・・。
その女の子の後からはいってきたブランケンハイム侯爵が彼女の手を取って一番前の白い布がかけられた椅子のひとつに誘った。ゆっくり会釈した彼女はキレイに膝をそろえて座った。こういうところはぼくのクラスの女の子にはない品? を感じさせた。なるほど。と、ぼくは思った。
ほどなく、一番前の白い布のいくつかの席を除いてすべての椅子が埋まった。
いつの間にかテュニカの上に同じく純白のトーガを身に着けた侯爵が、客席の前に立った。
「皆さま、お待たせいたしました。
陛下はご政務のため今少し遅れられるとのことでございますが、定刻となりましたのでこれより音楽会を始めたいと思います。
では、プログラムナンバー一番。モーツァルト作曲、『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』。演奏はブランケンハイム室内楽団です。お聴きください」
ぼくの後ろで楽団の人が席を立った。
「じゃあね、行ってくるよ。タオを頼むね」
ヨハンがウィンクし、楽器を持ってドアを開けた。あとの3人が続いて広間に出ていった。客席から拍手が起こった。
4人がピアノの横のステージに立ち、一礼して席に着いた。客席の灯りが落とされ、ステージだけが明るく照らされた。
演奏が、始まった。
音を立てないようにドアを閉めた。
ドアの横には演目を書いた紙が貼られていて壁のカンテラに照らされていた。紙に書かれた一番上を読んだ。アイネ・クライネ・ナハトムジーク。「小さな夜の曲」といった名前の、可愛らしい華やかな曲だ。
タオはまだ、歩き回っていた。
仕方がないからテーブルの上のいろんな形のチョコレートをつまみ、ちろちろ燃えるコンロの上のポットからショコラをカップに注いで飲んだ。甘くて美味しい。チョコレートもショコラも同じ意味なのに食べるのと飲むのでは名前が違う。帝国語は不思議だなと思っていると、タオが傍に来てチョコをつまんでぼくのカップからショコラを飲んだ。
「キミが食べてるから食べたくなっちゃったよ」
と、タオは言った。
弦楽四重奏の曲が何曲か演奏され、その途中で客席の方がざわめきだした。
「演目の途中ですが、皆さま! 皇帝陛下がお見えになられました」
皇宮付きの人がそう呼ばわるのが聞こえた。
まるで、タオの出番が来るのを待っていたかのように、その人は現れた。
「ああ、みなさん! どうかそのまま。遅れてしまい、大変申し訳ない」
そっとドアの隙間から広間をうかがった。
黒髪を短く刈り込んだめっちゃ背の高い颯爽とした人。初めて帝国皇帝を見たぼくの第一印象はそれだった。
この人が、この世界でもっとも大きくて強い帝国の、陸海空30万の帝国軍の総司令官でもある、帝国人3000万人の一番上に立つ、皇帝陛下、か・・・。
そんなエライ人なのにとてもていねいで腰が低くて奥ゆかしい。腰を上げてお辞儀しようとする人たちを抑えて軽い会釈をしながら、侯爵に案内されて最前列の白い布の席に着いた。ステージに近づくにつれてその顔は、でも、険しく見えた。
ビッテンフェルト男爵の10倍は厳めしく浅黒い顔には深い皺が刻まれていた。すぐ後ろにいたほっそりして優し気な女の人や、さらにその後ろにヤン閣下がいたから余計にそう見えるのかもしれない。女の人は皇帝陛下の奥さんだろう。皇帝の奥さんだから「皇后陛下」と呼ぶのだろう。
陛下は先に最前列にいたアンジェリーカ内親王の手を取って恭しく手の甲にキスした。陛下が椅子に座った。皇后陛下もヤン閣下もノールのお姫様に挨拶して席に着いた。それでやっと客席が静かになった。
楽団の演奏が再開された。
だけど、皇帝陛下は不機嫌そうだった。陛下のトーガの下のサンダルから踵が浮いて、カクカクと貧乏ゆすりしているのが見えた。陛下は気が短い方なのかもしれない。あるいは、侯爵が言ったようにやっぱり音楽がお嫌いなのだろう。そう思った。なぜか厳めしい顔の皇帝陛下にシンキンカン? が沸いた。
弦楽四重奏が終わった。いよいよタオの出番だ。
4人がぼくのいる「楽屋」に引き上げて来た。
「よし! タオ。行くぞ」
「タオ、頑張って!」
ヨハンやいちばん大きな楽器を抱えた女の人がタオに声をかけてくれた。
「うん」
タオは応えた。そしてぼくにこう言った。
「ミーシャ、居てくれてありがとね。客席に行って。キミにもちゃんとぼくのピアノを聴いて欲しいんだ」
「うん、わかった。タオ。頑張れ!」
「うん」
そうしてタオは広間へのドアを出ていった。
客席から拍手が起こったのを聞き、ぼくは小部屋を出て一度エントランスに出て広間の入り口に向かった。ドアのところにいた皇宮付きの人からプログラムを貰ってそっと中に入った。
そこだけ灯りに照らされたピアノ。その側にタオが立った。皇帝陛下と客席とに挨拶してピアノの前に座った。楽譜はなかった。弾く曲はもう全部暗記しているのだろう。
曲が始まった。
ぼくは一番後ろの空いた席に座り、わずかな灯りでプログラムを読んだ。
「皇宮演奏会第二部 タオ・ヴァインライヒによるピアノ独奏」
プログラムにはそう書かれてあった。
モーツァルト ピアノソナタ 第16番 ハ長調 K.54より第1楽章
Piano Sonata No.16 in C major K.545 1. Allegro
ショパン 19曲のワルツ より第6番 「小犬のワルツ」 Op.64-1 変ニ長調
Chopin, Frederic:19 waltzes Valse No.6"Petit chien" Des-Dur Op.64-1
チャイコフスキー 「四季」12の性格的描写より6月「舟歌」 Op.37bis ト短調
Tchaikovsky, Pytr Il'ich:Les saisons - 12 Morceaux caracteristiques No.6 "Barcarolle" g-moll
リスト コンソレーション(慰め) S.172
Liszt, Franz:Consolations S.172 R.12
ラフマニノフ :10の前奏曲集(プレリュード)より 第4番 Op.23-4 ニ長調
Rakhmaninov, Sergei Vasil'evich:10 Preludes Andante cantabile D-Dur Op.23-4
演目の最後に、タオの簡単な略歴が書いてあった。
「プレーヤー タオ・ヴァインライヒ。
ハインケル17年。チナ王国(当時。現マルセイユ郡東部チナ領)ナイグン生まれ。
ルディー7年。チナ戦役時に両親と弟を喪い、アイゼネス・クロイツ受章の帝国陸軍軍人ヴァインライヒ少尉の許に引き取られ養子となる。そこでピアノと出会い急速に上達を見る。
天性の音感と類まれなる優れた技巧による古典ピアノ曲のレパートリーは多岐に上る。今音楽会によりデビュー。第24ウルリッヒ・シュナイザー クィリナリス小学校4年在学中」
大人たちに囲まれ大人たちに注目されて演奏しているタオをあらためて見ると、ぼくとはまるきりかけ離れた、どこか遠くから来た知らない天才少年のように感じてしまう。だけど、ピアノを弾いているのは紛れもなくぼくと同じクラスの、あの溶けたチョコレートをくれた、タオなのだ。
そのことに、不思議な気持ちがした。
曲は軽やかなものから始まって楽しいけれどとても素早い指の動きがある曲に変わり、やがてゆるやかだけど悲し気なもの、そして聴く人の心を慰めるような、優しい曲へと移って行った。
周りの人たちはみんな身じろぎもせずにタオの奏でる音楽に魅入っていた。泣いている女の人もいた。感動してるんだ。そう思った。タオのピアノには人の心を動かす何かがあるのだ。
ぼくの席からは皇帝陛下の顔までは見えなかったが、ノールのお姫様の横顔は見えた。お姫様も、泣いていた。
自然に皇帝陛下の足元に目がいった。貧乏ゆすりは、なくなっていた。
華美な催しや音楽がキライな皇帝陛下さえその気にさせる。
ぼくのともだち。
タオは本当に、スゴいヤツだ。
タオは黙々とピアノに向かった。
演目は残すところあと1曲だけになった。
ピアノの前のタオが、立ち上がった。
「皇帝陛下、皇后陛下。そして、みなさん。
本日はブランケンハイム楽団とぼくの演奏会においでいただき、ありがとうございました。また、今夜の演奏会を準備して下さったブランケンハイム侯爵とヤン閣下、そしてスタッフの方々にもお礼を申し上げます。ありがとうございました。
お楽しみいただいた演奏会も次の曲で最後になります。
この曲はぼくにとって特に思い入れの深い曲です。
作曲した人は1000年以上前のろしあという国の人です。彼はピアノが上手な人だったのですが、かくめいと戦争でふるさとを追われ、一度も祖国に帰ることなく異国の地で亡くなりました。そしてふるさとを思いながら多くの曲を残した人だとバカロレアのせんせいから教わりました。
誰にもふるさとはあるでしょう。誰にも子どものころ遊び疲れてともだちと一緒に見た、西のかなたに落ちる夕陽を眺めた記憶はあるでしょう。
この曲に出会ったとき、ぼくもふるさとを思いました。ナイグンの街の丘の向こうに落ちる夕陽を思い出し、父や母や弟やともだちや近所の人たちの顔を思い出しました。
この曲は、そんな記憶を呼び覚ましてくれる曲だと、ぼくは思います。名前が番号だけの曲なので、ぼくが勝手に名前を付けました。
『ふるさとの夕陽』という曲です。
では、聴いてください」
そして、タオはピアノに向かい、奏で始めた。
それは、それまでに何度も聴いた曲だった。
だけど、あのかっかの家で聴いたのとはどこかが違った。音色を聴いてこみ上げてくるイメージがより鮮やかになる。
ふるさとの朝。どの家からも上がる朝ごはんを作る煙の匂いが、朝食を囲む家族の顔が、朝日を浴びて萌える山々の緑が、鮮やかに蘇る。
ヨーゼフやゲオルギーと共に弓矢を持って駆け回った森の木々が、沢に流れる美しい小川のせせらぎが、獲物を見つけ弓を引き絞る時の緊張感が、蘇る。
そして獲った獲物を担いで尾根を越える時、みんなで一緒に見た山々の向こうに落ちる夕陽の美しい赤さを想い出す。
ああ、故郷が恋しい・・・。
なんて、素晴らしいんだ。
いつの間にかぼくの頬は、濡れていた。
ふと、両隣を見ると、女の人だけでなく、男の人もみんな目を潤ませているのが微かな灯りに見えた。
音楽というのは、スゴいな・・・。
こんなにも人の心を揺り動かすなんて。
タオは、スゴいな・・・。
曲が終わった。
会場はしんと静まり返っていた。
その静けさを破ったのは、最前列の背の高い影だった。
皇帝陛下は席を立ってパンパンパンと手を鳴らした。
すると誰言うともなくみんなが席を立ち拍手を送り始めた。ぼくの隣の貴族の女の人は唇を噛み締め、流れる涙を拭きながら懸命に拍手を送っていた。
誰の顔にもこの言葉が浮かんでいるように見えた。
素晴らしい・・・。
ステージの上に拍手に応えて頭を下げているタオの姿があった。
お客さんたちがみんな会場から去った後、陛下のつぶやきがぼくにも聞こえた。
「しばし、ピアノの演奏者と話がしたい」
お子さんはみんな嫁いでしまったりドクリツして領地の管理や商売のために家を出てしまっていたり士官として軍隊に行っていたりするので、まだ小学生のタオが可愛くて仕方がないらしい。
「あのおカタい皇帝陛下をその気にさせたなんて! タオ、あなたスゴいわ。
いいこと? 堂々と胸を張って、落ち着いて弾くのよ!」
皇宮に向かう馬車の中で、帝国の正式な女性用礼装である丈長の白のテュニカにショールを羽織った伯爵夫人はコウフンしながらそう言った。
「ああ、ヤヨイちゃんもいればよかったのにね。あの子ったら、いつもカンジンな時にお仕事が忙しくなっちゃうのですもの!」
でも、演奏する本人のタオは緊張しているのかムッツリと押し黙ってずっと窓の外を眺め続けていた。手は大事だから握らない。その代わり、彼の膝頭に手を置いてやった。
皇宮は元老院の北隣にある。
この地上でもっとも強大な帝国皇帝のお屋敷だから、きっとゴーカケンラン? な建物を想像していたら、ぜんぜんそんなことなかった。元老院の議場を取り囲むようにいくつかある政府の建物と同じ黒い石の、クィリナリスの貴族の家よりも小さいんじゃないかなと思わせるようなジミなカンジのお屋敷だった。南側の広い元老院前広場とは反対の北に向いた皇宮前の広場はずっと規模が小さく、しかもほかの政府の庁舎の車寄せも兼ねていた。そのあまりのジミさにちょっと戸惑ってしまうほどだった。
ただ、警備の憲兵隊は何人かいて、ここが帝国皇帝の住まいだということをあらためて感じさせていた。すでに何台かの馬車が止まっていて、荷台の上に覆いがされたカーキ色じゃない青いトラックまでいた。
ぼくたちは馬車を降り、ビッテンフェルト家よりも小さなエントランスからなかに入った。
皇宮は中もジミだった。貴族の家には必ずと言っていいほどあるアトリウムもなかった。その代わり、エントランスホールは広く、白いテュニカの人たちがそこここに集っていたり忙しそうに行きかったりしていた。
黒御影石の壁にはズラリと絵がかけてあった。
「ミハイル、御覧なさい。代々の帝国皇帝の肖像画よ」
伯爵夫人が教えてくれた。
白いトーガ姿のもあったが、多くは軍服に赤いマントを翻した颯爽とした立ち姿。その肖像画たちを眺めているとやっと帝国皇帝の皇宮に来たジッカン? が湧いて来た。
「素晴らしいわ。わたしも皇宮におじゃまするのは初めてなの。タオのおかげね」
壁の肖像画たちに見惚れていると、
「やあ、タオ! 来たな!」
快活そうな太い声がした。
クセのある金髪を短く刈り込んだ真っ白なテュニカの大柄な男の人がやってきた。
「まあ、ウィルヘルム! いつもタオがお世話になって・・・」
「これはメーテル! ようこそ『皇宮音楽会』へ」
この人が近衛軍団でのビッテンフェルト准将の同僚将軍ブランケンハイム侯爵か・・・。
階級は准将のいっこ上の少将だと男爵から聞いていた。軍服姿でないせいか、いつもキアイ入りまくりの准将よりもだいぶ穏やかに見える。今回の音楽会の発起人で世話役の人だとタオからも聞いていた。
帝国に来た頃はこのテュニカという服がとても違和感だったのを思い出す。軽くて薄すぎる、と。でも今はぼくもその軽さと薄さに慣れてしまった。
そのぼくの目にも真っ白なテュニカは別格に映る。子どもはもとより、かなり年配の人が着てもまったくヘンな感じがしないどころか、とても若々しく生気? にあふれていてとても清潔感? を感じる。強い陽射しのせいで年中日焼けしているからかもしれない。
真っ白なテュニカのブランケンハイム侯爵は、とても若々しく、溌溂としていた。ビッテンフェルト男爵と同じ軍人だからなおさらそう見えるのかもしれない。
でも、侯爵と男爵って、どう違うんだ?
「メーテル! やっとこの日が参りましたな。タオの成長ぶりには目を見張るものがありますな。彼の奏でる音には貴女もきっと驚きますぞお・・・」
そう言って侯爵は鷹揚に両手を広げ微笑んだ。
「さ、タオ。さっそく準備にかかるとしよう。メーテルは控室へどうぞ」
「じゃあね、タオ。しっかり、がんばるのよ」
伯爵夫人はまた知り合いの人を見つけたのか「まあ、フランツ・・・」とエントランス脇の部屋の中に入っていった。知り合いの多い人なんだな、と思った。
「あの、侯爵・・・」
すると、それまで押し黙っていたタオが顔を上げた。
「なんだね、タオ」
「彼はミハイルです。ぼくのともだちなんです。出番まで彼と一緒にいたいんです。いいですか?」
「おお、もちろんだとも!」
と、侯爵は言った。そして、ぼくを見下ろしてニヤ、と笑った。
「そうか。キミがあの猪武者のところの北の留学生だな。彼がよくキミのことを話していた」
「イノシシムシャ?」
すると、ブランケンハイム侯爵はイタズラそうにウィンクして指を口に当て声を潜めた。
「なに。あのビッテンフェルトのアダ名さ。彼には言わないでくれよ」
同じ近衛軍団の旅団長だから、准将とはライバル? なのだろう。ぼくは吹き出しそうになるのを堪えつつ、貴族なのにちっとも奢らないし威張らない、子供のぼくにさえフレンドリーな侯爵に好感を持った。
エントランスの奥の広間のようなところが会場のようだった。
黒御影石のエントランスとは違い、四方を白い壁に囲われたその広間の真正面に暖炉がある。その上に帝国の鷲の紋章がかけられていた。高い天井にはいくつかの天窓、天井近くの壁には明かり取りの窓がありエントランスよりも明るい感じがした。
その右手の壁の真ん中に、エントランスにかけられていたのよりひと際大きな肖像画があった。
それが誰の肖像画なのかはすぐにわかった。社会の教科書の挿絵に載っていたのは色の無い線で描かれたものだったが、そのポーズと姿がまったく一緒だったからだ。
教科書にはこう書かれていた。
神君(デイブス)カエサル。
軍服姿でアタマに月桂冠を着け、深紅のマントを颯爽と風になびかせて彼方のほうを指さしている厳めしい顔。
これがきっとオリジナル? の画なのだろう。
ボーっと画を見上げていたら反対側の壁のドアが開いて大きな黒いテーブルのようなものが運び込まれてきた。それは正面の暖炉の真ん前よりやや左に置かれ、上のふたがぱか、と開けられた。
何だろう。
そう思っていると、その黒いテーブルの端に椅子を寄せて来たタオが座り、テーブルの端のもう一つの蓋を開けた。そして、ポン、とそこを叩いた。
ああ、ピアノだ。
タオの指が鍵盤を舞った。左の低い音から右の高い音まで。まるで川を流れる水のように音が流れ出た。その広間が一瞬で音楽会の会場に変わったのがわかった。かっかの家のは茶色い箱だったが、これはテーブル型のピアノなのだ。箱のピアノに比べると、音の広がりがスゴい。
4人の白いテュニカの人たちがはいってきた。男の人と女の人が2人ずつ。みんなヘンな形の黒いケースを持っていた。その人たちに、タオは「こんちわ」とあいさつを交わしていた。
「楽団の人たちだよ」
と、タオが教えてくれた。
彼らは黒いケースを開けて大きいのや小さいのの茶色い楽器を取り出した。それぞれに4本の弦が張ってあるヤツ。それと、長い矢みたいなの。そしてピアノの周りに集まった。タオが鍵盤の一つをポン、と打つと、みんな矢で楽器の弦を擦り始めた。弦の音が鳴った。
ああ、なるほど。音を合わせているんだな・・・。
それぐらいのことはまだ音楽のことをよく知らないぼくにもわかる。
侯爵がピアノの傍に来てタオに何かを話しかけた。タオがそれに何かを言った。すると、侯爵が誰かを呼んで、その誰かが開いた大きなふたの中に何かの棒を突っ込んだ。タオが一つの音をポンポンと連続して叩く。そしてまた、流れる水の音。
ああ、これは音を調節してるんだ。
すでにそこはタオの世界だった。他の人が窺い知ることのできない彼だけの世界。彼は自分の世界の中にしっかりとしたイメージを持っていて、それを形にしようとしているのだ。ぼくより3つも下の小さな体の中に無限の世界が詰まっている。そんな気がした。こんなヤツはぼくの里にも居ないし、まだ全てを見たわけじゃないけれど、この広い帝国中を探しても、そうはいない。
やっぱりタオは、スゴいやつだ。
しばらくして納得したのか、タオはその誰かに何かを言い、ぼくを振り向いた。
「ミーシャ、そこに居ててね。もうちょっとだから」
「大丈夫だよ、タオ。ここにいるよ」
と、ぼくは応えた。
こんなスゴいヤツに頼られている。とても誇らしい気持ちがした。
タオが指慣らしをしている間に暖炉の前と広間の床に椅子が並べられた。
暖炉の前には4つ。そして、一段低くなった床にはざっと50ほどの椅子が暖炉と向かい合わせに置かれていった。それが客席なのだろう。小学校のぼくのクラスよりも少し多い程度。へえ、案外と少ないものだな。
ふいにぽん、と肩を叩かれた。ブランケンハイム侯爵だった。
「タオは上手だろう」
「ええ、とても・・・」
「ミハイル、と言ったね。キミも音楽が好きみたいだな」
「はい。タオのピアノを聞きながら宿題をするととてもはかどるんです」
と、ぼくは答えた。
「うむ。それも音楽の効能のひとつだな」
侯爵は笑った。
ビッテンフェルト男爵とおなじ近衛軍団の将官なのに、男爵とはだいぶ違うなと思った。なんというか、知性的? というか、穏やか、というか・・・。
タオのピアノと茶色い楽器の人たちの合奏が始まった。でもそれはすぐに途中で終わった。出だしの練習というか確認? をしているのだろう。
「そうだ! キミの里にも音楽はあるだろう。どんなものだい?」
「音楽というか、歌と踊りです」
「ほう、どんな歌だい?」
「あの、祭りの時とかに、村のみんなが広場に集まって歌う歌です。今年も小麦がたんと実った。さあ刈り入れだ。そんな意味の歌です。
はじめはゆっくりと歌います。こんな風に拍手で拍子をとりながら。で、だんだん拍子が早くなってきます。そうすると、みんなの中から踊り自慢が前に出てみんなの輪の真ん中で踊り出すんです。で、次第に踊り手が増えて来ます。で、歌も速くなってきます。で、踊ってる人のうち速さについて来れない人が出て来てみんなの輪の中に引き戻されるんですが、途中でへたっちゃったバツとしてしこたまお酒を飲まされるんです。で、ツブれます」
「うわっはっは! それで?」
「で、さいごに3人か2人が、いずれも踊り自慢の人が残って踊り続けるんですが、そのころになると歌は猛烈な速さになってて、歌う方も口が回らないくらいになってきます。で、最後まで踊り続けた人がその年の優勝ってわけです。やっぱりしこたまお酒を飲まされて、やっぱりツブれます。優勝賞品で贈られた羊を枕にして寝ちゃいます」
「うわっはっは! 結局みんな飲まされてツブされるわけか! そりゃあ愉快だな」
「こんなスゴい音楽に比べるのも、恥ずかしいんですが・・・」
「そんなことはないぞ、ミハイル。それはその民族の日々の暮らしから生まれた自然な文化というものだ」
と、侯爵は言った。
「キミたちの北の種族は村同士たびたび小競り合いをしていると聞いた。当然にいつも緊張を強いられる毎日を送っていることだろう。察するにそうした緊張から一時でも逃れたいという願望が生み出した祭りであり歌であり音楽なのだろうな。我々帝国人もキミたちも同じ人間だ。歌や踊りや音楽で感情を発散させたいというのは人間として自然なことだと思う」
侯爵の言葉は「野蛮人」と言われている北の里から来たぼくを安心させた。そこでふと前から思っていたことを尋ねたくなった。
「あの、こうしゃく。訊いてもいいですか」
「いいとも。なんでも言ってみたまえ」
「皇帝陛下はハデな催しがお嫌いな方だと聞きましたが、音楽はお好きなんですね。だってこういう音楽会にはおいでになるわけですから」
すると、侯爵はゆっくりと首を振った。
「いいや、ミハイル。陛下は帝国の風である『質実剛健』のカタマリのような御方なのだ。舞踏会や晩餐会だけでなく、音楽もお嫌いなのだ。お嫌いだった。陛下は音楽に対してなにか誤解をお持ちなのだと思う」
「え、そうなんですか?」
「そうだとも。だから、こうしてこの音楽会を催せるまでにするために、わたしやヤン閣下は大変な苦労を重ねて来たのだ」
「それは、何故ですか」
「よき文化、よき音楽を帝国にあまねく隅々まで及ぼし根付かせることが、すなわち帝国人の幸福につながると思っているのでね。そのためには陛下のご理解が是非とも必要だからなのだよ、ミハイル。陛下もタオのピアノを聴けばきっとお心を開いてくださる。そう信じているのだ」
「侯爵閣下、そろそろ、お時間です」
侯爵の家の人か皇宮の人か、会場になる広間の準備をしていた人がやってきて侯爵に告げた。
「おお、そうか。では客を入れるとしよう」
係の人にそう言って、侯爵はパンパンと手を叩いた。
「そろそろいいかね? 」
楽団の人とタオが練習を止めた。
「ヨハン、仕上がりは良さそうだな」
侯爵が一番小さい楽器の年嵩の男の人に声を掛けた。侯爵と同じ歳ほどのひとだ。
「ええ、侯爵。上々です。タオもね」
ヨハンと呼ばれた人がピアノを振り返った。タオはニコッと笑ってアタマを下げた。
侯爵が音を奏でるピアノの側に寄った。
「タオ、落ち着いてな。いつもの練習だと思って気楽にやりたまえ」
すると、別の係の人がやってきて侯爵に言った。
「閣下、内親王殿下がお着きになられました」
「おいでになったか、ではお迎えせねばな」
侯爵は教えてくれた。
「わがブランケンハイム家には今、東のノール王国の王女様、アンジェリーカ内親王がご寄宿なされているのだ。今夜はせっかくの皇帝陛下御臨席の機会だからとお招きしたのだよ」
そういうと、侯爵はぼくの肩にぽんと手を置いた。
「ミハイル。タオにはキミが必要らしい。傍についていてやってくれ」
楽団の人たちとタオとぼくは広間の続きの小部屋に移った。
小さなテーブルの上にはコーヒーのポットやいろんなお菓子のお皿が載っていた。
皇宮の人たちだろうか、いくつかのカンテラを下げた人たちが来て壁のフックやテーブルの上に明かりを掛けていき、窓を閉めて部屋を出ていった。
楽団の人たちはすぐにテーブルに集まってコーヒーを注いだりお菓子を食べたりして落ち着いていた。
だけど、タオだけは落ち着かなげに部屋の中を歩き回っていた。
「タオ、マカロン食べなよ。チョコレートも。美味しいよ。ねえ、キミもどう?」
ぼくは楽団の人に勧められた甘いお菓子を食べた。ビッテンフェルト家で食べたのとはまたちがった美味しさのものだった。でも、タオが気になった。
小皿のひとつを取って壁際を落ち着かなげに行ったり来たりしている「小さな巨人」に勧めた。とりあえず、椅子に座らせた。
「ありがと、ミーシャ・・・」
ひとくちは食べたけど、かけらを皿に戻したタオはまた立ち上がって歩き始めた。
ヨハンという楽団のリーダーの人がぼくに向かってゆっくりと首を振った。彼をそっとしておいて。そんな風に。
広間に通じるドアの向こうがざわめきだした。お客さんたちが入って来たらしかった。
ドアに近づいてそっと隙間を開けた。色とりどりのテュニカやトーガ。平民とさして変わらない服装だけれど、一見してみんな貴族の人たちであることはぼくにもわかった。どこが違うのかと聞かれると困るけれど、なんか、違うのだ。立ち振る舞いとか、みんなこういう催しに慣れている。強いて言えば、そんなカンジ。こうした違いがわかるのは男爵家であるビッテンフェルト家にいるお陰だと思う。みんな、手に白い紙を持っている。演目を書いたプログラム? というヤツだろう。
すると、ひと際キレイで可愛らしい女の子が目を惹いた。ぼくよりひとつかふたつほど年上らしい。薄いピンクの少し丈の短いテュニカにお揃いのショールを巻いている。つん、とすましたブルネット。気品? そんな空気を漂わせた女の子だ。彼女はライヒェンバッハ伯爵夫人と話しながら広間に入って来た、
ああ、あれがノールとかいうところのお姫様だな・・・。
その女の子の後からはいってきたブランケンハイム侯爵が彼女の手を取って一番前の白い布がかけられた椅子のひとつに誘った。ゆっくり会釈した彼女はキレイに膝をそろえて座った。こういうところはぼくのクラスの女の子にはない品? を感じさせた。なるほど。と、ぼくは思った。
ほどなく、一番前の白い布のいくつかの席を除いてすべての椅子が埋まった。
いつの間にかテュニカの上に同じく純白のトーガを身に着けた侯爵が、客席の前に立った。
「皆さま、お待たせいたしました。
陛下はご政務のため今少し遅れられるとのことでございますが、定刻となりましたのでこれより音楽会を始めたいと思います。
では、プログラムナンバー一番。モーツァルト作曲、『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』。演奏はブランケンハイム室内楽団です。お聴きください」
ぼくの後ろで楽団の人が席を立った。
「じゃあね、行ってくるよ。タオを頼むね」
ヨハンがウィンクし、楽器を持ってドアを開けた。あとの3人が続いて広間に出ていった。客席から拍手が起こった。
4人がピアノの横のステージに立ち、一礼して席に着いた。客席の灯りが落とされ、ステージだけが明るく照らされた。
演奏が、始まった。
音を立てないようにドアを閉めた。
ドアの横には演目を書いた紙が貼られていて壁のカンテラに照らされていた。紙に書かれた一番上を読んだ。アイネ・クライネ・ナハトムジーク。「小さな夜の曲」といった名前の、可愛らしい華やかな曲だ。
タオはまだ、歩き回っていた。
仕方がないからテーブルの上のいろんな形のチョコレートをつまみ、ちろちろ燃えるコンロの上のポットからショコラをカップに注いで飲んだ。甘くて美味しい。チョコレートもショコラも同じ意味なのに食べるのと飲むのでは名前が違う。帝国語は不思議だなと思っていると、タオが傍に来てチョコをつまんでぼくのカップからショコラを飲んだ。
「キミが食べてるから食べたくなっちゃったよ」
と、タオは言った。
弦楽四重奏の曲が何曲か演奏され、その途中で客席の方がざわめきだした。
「演目の途中ですが、皆さま! 皇帝陛下がお見えになられました」
皇宮付きの人がそう呼ばわるのが聞こえた。
まるで、タオの出番が来るのを待っていたかのように、その人は現れた。
「ああ、みなさん! どうかそのまま。遅れてしまい、大変申し訳ない」
そっとドアの隙間から広間をうかがった。
黒髪を短く刈り込んだめっちゃ背の高い颯爽とした人。初めて帝国皇帝を見たぼくの第一印象はそれだった。
この人が、この世界でもっとも大きくて強い帝国の、陸海空30万の帝国軍の総司令官でもある、帝国人3000万人の一番上に立つ、皇帝陛下、か・・・。
そんなエライ人なのにとてもていねいで腰が低くて奥ゆかしい。腰を上げてお辞儀しようとする人たちを抑えて軽い会釈をしながら、侯爵に案内されて最前列の白い布の席に着いた。ステージに近づくにつれてその顔は、でも、険しく見えた。
ビッテンフェルト男爵の10倍は厳めしく浅黒い顔には深い皺が刻まれていた。すぐ後ろにいたほっそりして優し気な女の人や、さらにその後ろにヤン閣下がいたから余計にそう見えるのかもしれない。女の人は皇帝陛下の奥さんだろう。皇帝の奥さんだから「皇后陛下」と呼ぶのだろう。
陛下は先に最前列にいたアンジェリーカ内親王の手を取って恭しく手の甲にキスした。陛下が椅子に座った。皇后陛下もヤン閣下もノールのお姫様に挨拶して席に着いた。それでやっと客席が静かになった。
楽団の演奏が再開された。
だけど、皇帝陛下は不機嫌そうだった。陛下のトーガの下のサンダルから踵が浮いて、カクカクと貧乏ゆすりしているのが見えた。陛下は気が短い方なのかもしれない。あるいは、侯爵が言ったようにやっぱり音楽がお嫌いなのだろう。そう思った。なぜか厳めしい顔の皇帝陛下にシンキンカン? が沸いた。
弦楽四重奏が終わった。いよいよタオの出番だ。
4人がぼくのいる「楽屋」に引き上げて来た。
「よし! タオ。行くぞ」
「タオ、頑張って!」
ヨハンやいちばん大きな楽器を抱えた女の人がタオに声をかけてくれた。
「うん」
タオは応えた。そしてぼくにこう言った。
「ミーシャ、居てくれてありがとね。客席に行って。キミにもちゃんとぼくのピアノを聴いて欲しいんだ」
「うん、わかった。タオ。頑張れ!」
「うん」
そうしてタオは広間へのドアを出ていった。
客席から拍手が起こったのを聞き、ぼくは小部屋を出て一度エントランスに出て広間の入り口に向かった。ドアのところにいた皇宮付きの人からプログラムを貰ってそっと中に入った。
そこだけ灯りに照らされたピアノ。その側にタオが立った。皇帝陛下と客席とに挨拶してピアノの前に座った。楽譜はなかった。弾く曲はもう全部暗記しているのだろう。
曲が始まった。
ぼくは一番後ろの空いた席に座り、わずかな灯りでプログラムを読んだ。
「皇宮演奏会第二部 タオ・ヴァインライヒによるピアノ独奏」
プログラムにはそう書かれてあった。
モーツァルト ピアノソナタ 第16番 ハ長調 K.54より第1楽章
Piano Sonata No.16 in C major K.545 1. Allegro
ショパン 19曲のワルツ より第6番 「小犬のワルツ」 Op.64-1 変ニ長調
Chopin, Frederic:19 waltzes Valse No.6"Petit chien" Des-Dur Op.64-1
チャイコフスキー 「四季」12の性格的描写より6月「舟歌」 Op.37bis ト短調
Tchaikovsky, Pytr Il'ich:Les saisons - 12 Morceaux caracteristiques No.6 "Barcarolle" g-moll
リスト コンソレーション(慰め) S.172
Liszt, Franz:Consolations S.172 R.12
ラフマニノフ :10の前奏曲集(プレリュード)より 第4番 Op.23-4 ニ長調
Rakhmaninov, Sergei Vasil'evich:10 Preludes Andante cantabile D-Dur Op.23-4
演目の最後に、タオの簡単な略歴が書いてあった。
「プレーヤー タオ・ヴァインライヒ。
ハインケル17年。チナ王国(当時。現マルセイユ郡東部チナ領)ナイグン生まれ。
ルディー7年。チナ戦役時に両親と弟を喪い、アイゼネス・クロイツ受章の帝国陸軍軍人ヴァインライヒ少尉の許に引き取られ養子となる。そこでピアノと出会い急速に上達を見る。
天性の音感と類まれなる優れた技巧による古典ピアノ曲のレパートリーは多岐に上る。今音楽会によりデビュー。第24ウルリッヒ・シュナイザー クィリナリス小学校4年在学中」
大人たちに囲まれ大人たちに注目されて演奏しているタオをあらためて見ると、ぼくとはまるきりかけ離れた、どこか遠くから来た知らない天才少年のように感じてしまう。だけど、ピアノを弾いているのは紛れもなくぼくと同じクラスの、あの溶けたチョコレートをくれた、タオなのだ。
そのことに、不思議な気持ちがした。
曲は軽やかなものから始まって楽しいけれどとても素早い指の動きがある曲に変わり、やがてゆるやかだけど悲し気なもの、そして聴く人の心を慰めるような、優しい曲へと移って行った。
周りの人たちはみんな身じろぎもせずにタオの奏でる音楽に魅入っていた。泣いている女の人もいた。感動してるんだ。そう思った。タオのピアノには人の心を動かす何かがあるのだ。
ぼくの席からは皇帝陛下の顔までは見えなかったが、ノールのお姫様の横顔は見えた。お姫様も、泣いていた。
自然に皇帝陛下の足元に目がいった。貧乏ゆすりは、なくなっていた。
華美な催しや音楽がキライな皇帝陛下さえその気にさせる。
ぼくのともだち。
タオは本当に、スゴいヤツだ。
タオは黙々とピアノに向かった。
演目は残すところあと1曲だけになった。
ピアノの前のタオが、立ち上がった。
「皇帝陛下、皇后陛下。そして、みなさん。
本日はブランケンハイム楽団とぼくの演奏会においでいただき、ありがとうございました。また、今夜の演奏会を準備して下さったブランケンハイム侯爵とヤン閣下、そしてスタッフの方々にもお礼を申し上げます。ありがとうございました。
お楽しみいただいた演奏会も次の曲で最後になります。
この曲はぼくにとって特に思い入れの深い曲です。
作曲した人は1000年以上前のろしあという国の人です。彼はピアノが上手な人だったのですが、かくめいと戦争でふるさとを追われ、一度も祖国に帰ることなく異国の地で亡くなりました。そしてふるさとを思いながら多くの曲を残した人だとバカロレアのせんせいから教わりました。
誰にもふるさとはあるでしょう。誰にも子どものころ遊び疲れてともだちと一緒に見た、西のかなたに落ちる夕陽を眺めた記憶はあるでしょう。
この曲に出会ったとき、ぼくもふるさとを思いました。ナイグンの街の丘の向こうに落ちる夕陽を思い出し、父や母や弟やともだちや近所の人たちの顔を思い出しました。
この曲は、そんな記憶を呼び覚ましてくれる曲だと、ぼくは思います。名前が番号だけの曲なので、ぼくが勝手に名前を付けました。
『ふるさとの夕陽』という曲です。
では、聴いてください」
そして、タオはピアノに向かい、奏で始めた。
それは、それまでに何度も聴いた曲だった。
だけど、あのかっかの家で聴いたのとはどこかが違った。音色を聴いてこみ上げてくるイメージがより鮮やかになる。
ふるさとの朝。どの家からも上がる朝ごはんを作る煙の匂いが、朝食を囲む家族の顔が、朝日を浴びて萌える山々の緑が、鮮やかに蘇る。
ヨーゼフやゲオルギーと共に弓矢を持って駆け回った森の木々が、沢に流れる美しい小川のせせらぎが、獲物を見つけ弓を引き絞る時の緊張感が、蘇る。
そして獲った獲物を担いで尾根を越える時、みんなで一緒に見た山々の向こうに落ちる夕陽の美しい赤さを想い出す。
ああ、故郷が恋しい・・・。
なんて、素晴らしいんだ。
いつの間にかぼくの頬は、濡れていた。
ふと、両隣を見ると、女の人だけでなく、男の人もみんな目を潤ませているのが微かな灯りに見えた。
音楽というのは、スゴいな・・・。
こんなにも人の心を揺り動かすなんて。
タオは、スゴいな・・・。
曲が終わった。
会場はしんと静まり返っていた。
その静けさを破ったのは、最前列の背の高い影だった。
皇帝陛下は席を立ってパンパンパンと手を鳴らした。
すると誰言うともなくみんなが席を立ち拍手を送り始めた。ぼくの隣の貴族の女の人は唇を噛み締め、流れる涙を拭きながら懸命に拍手を送っていた。
誰の顔にもこの言葉が浮かんでいるように見えた。
素晴らしい・・・。
ステージの上に拍手に応えて頭を下げているタオの姿があった。
お客さんたちがみんな会場から去った後、陛下のつぶやきがぼくにも聞こえた。
「しばし、ピアノの演奏者と話がしたい」
0
あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム
ピコサイクス
青春
顔は普通、性格も地味。
けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。
学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?
大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。
真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。


キャバ嬢(ハイスペック)との同棲が、僕の高校生活を色々と変えていく。
たかなしポン太
青春
僕のアパートの前で、巨乳美人のお姉さんが倒れていた。
助けたそのお姉さんは一流大卒だが内定取り消しとなり、就職浪人中のキャバ嬢だった。
でもまさかそのお姉さんと、同棲することになるとは…。
「今日のパンツってどんなんだっけ? ああ、これか。」
「ちょっと、確認しなくていいですから!」
「これ、可愛いでしょ? 色違いでピンクもあるんだけどね。綿なんだけど生地がサラサラで、この上の部分のリボンが」
「もういいです! いいですから、パンツの説明は!」
天然高学歴キャバ嬢と、心優しいDT高校生。
異色の2人が繰り広げる、水色パンツから始まる日常系ラブコメディー!
※小説家になろうとカクヨムにも同時掲載中です。
※本作品はフィクションであり、実在の人物や団体、製品とは一切関係ありません。

失恋中なのに隣の幼馴染が僕をかまってきてウザいんですけど?
さいとう みさき
青春
雄太(ゆうた)は勇気を振り絞ってその思いを彼女に告げる。
しかしあっさりと玉砕。
クールビューティーで知られる彼女は皆が憧れる存在だった。
しかしそんな雄太が落ち込んでいる所を、幼馴染たちが寄ってたかってからかってくる。
そんな幼馴染の三大女神と呼ばれる彼女たちに今日も翻弄される雄太だったのだが……
病み上がりなんで、こんなのです。
プロット無し、山なし、谷なし、落ちもなしです。
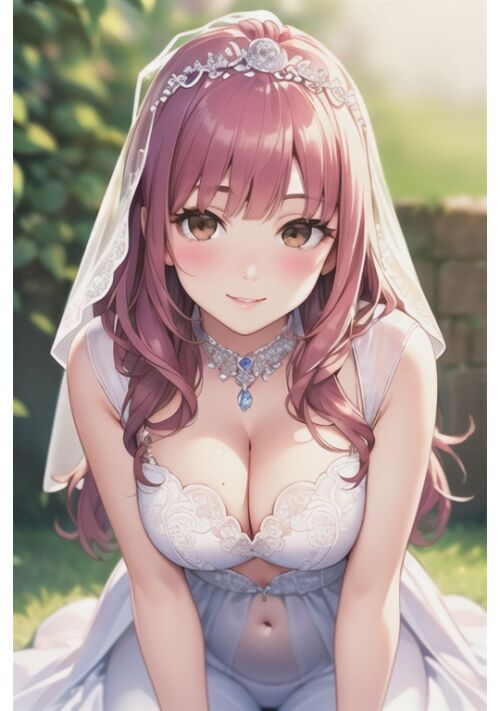
兄貴のお嫁さんは異世界のセクシー・エルフ! 巨乳の兄嫁にひと目惚れ!!
オズ研究所《横須賀ストーリー紅白へ》
ファンタジー
夏休み前、友朗は祖父の屋敷の留守を預かっていた。
その屋敷に兄貴と共に兄嫁が現れた。シェリーと言う名の巨乳の美少女エルフだった。
友朗はシェリーにひと目惚れしたが、もちろん兄嫁だ。好きだと告白する事は出来ない。
兄貴とシェリーが仲良くしているのを見ると友朗は嫉妬心が芽生えた。
そして兄貴が事故に遭い、両足を骨折し入院してしまった。
当分の間、友朗はセクシー・エルフのシェリーとふたりっきりで暮らすことになった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















