9 / 62
浮気され婚約破棄された公爵令嬢は、王女殿下となる
2
しおりを挟む
セレスティーヌのカラダを買ったクリスティーヌは、お妃教育が終了していることから、王女殿下としての記憶を失ったことになっても困ることはない。
女官や側近の中では、セレスティーヌ様は以前の記憶を失う前の王女殿下よりも王女殿下らしくなったと評されている。
そして、いよいよ学園に入る。国立学園に本来なら、入学するところなのだが、この前、リチャードが男爵令嬢に誑かされて、公爵令嬢が自害するという事件が起きたばかりなので、今年度の入学辞退者は相当数に上る。
学園内でのセキュリティに問題があるから、こういう事件が起きると問題視されたからである。
セレスティーヌも少し考えて、他国の学園に留学することにしたのである。セレスティーヌ狙いの逆玉の輿狙いがないとも言い切れないから。
他国で身分を隠し、楽しい学園生活を送りたいと希望している。
でもセレスティーヌが今のところ王位継承権第1位になったものだから、おいそれと他国に行きにくいことも事実である。
それでも前世クリスティーヌだったセレスティーヌは、王女殿下でありながら、公爵令嬢気分なのだから仕方がない。
いくつかの国の入学試験を受けたら、みんな合格したのだ。そらそうだ。前世、卒業した記憶があるのだから、入学試験ぐらいちょろいものである。
いろいろ悩んだ挙句、やっぱり近場の隣国モントオールに行くことにする。
ちょっと日帰りで買い物にも行ける近さということもあり、小さい時にいい思い出があった国だから、といってももちろん、クリスティーヌ時代のことなのだ。
クリスティーヌは、6歳から8歳までこのモントオール国に住んでいたことがあったから、地の利だけでなく土地勘もある。
モントオール国では、とりあえず寮に入ることになったのだが、この寮長が鬼だったのだ。
門限は厳しく、一分でも遅れたら、連帯責任を取らされ皆でグランドを走らせられる。朝もそう、一分でも寝坊をする者がいると、朝食抜きになってしまう。
最初は、それでも同じ年頃の人たちといることだけで楽しかったのだが、2年生になる頃には、さすがに厳しくされることに辟易を感じ、寮を出て、一軒家を借りることになったのである。
護衛の騎士もその方がいいみたいで、けっこう朝寝坊ができるようになったのだ。朝寝坊をして、好きなものを食べ、パーティなどで遅くなっても怒られない自由な生活を満喫する。
これでこそ学生生活よね、留学した甲斐があるというもの。サンドラのお城に入れば、こうはいかない。寮生活程厳しくはないが、似たようなもので、周りの目があり自由に過ごせない。
そんなある日、1年生の時に同じ寮のルームメイトだったモントオール国の公爵令嬢スーザン・プリメリア嬢が、ダンスパーティに誘ってきたのである。
もちろん行きますとも!二つ返事で承諾し、ドレス選びをする。なんで、公爵令嬢なのに、寮生活していたかと言うと、お友達が作りたかったかららしい。
ちょっと高位貴族の令嬢になれば、なかなか政略ばかりで本当の意味での仲良し友達ができない。
セレスティーヌも、ついこの間まで18年間も公爵令嬢をやっていたので、スーザンの気持ちはよくわかる。
ダンスパーティなど名目で、本来の意味は、ニッポンの盆踊りと同じでナンパが目的なのであるが、それを言ってしまったら、身も蓋もない。未婚者だけでなく、既婚者でさえも一夜の愛を求める。主催者側が余程しっかりしていないと、売春や乱交の温床になりかねない。
スーザンはそのあたりのことを理解しているのか?きっとただのダンスパーティぐらいにしかわかっていないだろう。
セレスティーヌも表向きのダンスパーティに参加する意向だが、クリスティーヌさえもそのことに気づいていない。
ただ、スーザンは、寮のルームメイトであったセレスティーヌに少々関心を持っていて、もっとお喋りがしたいだけなのである。学園の授業の合間に喋ると言っても、限度があるから。
だから親に普通の夜会をするのと同じノリで、ダンスパーティをしたいと申し出て、ビックリされたのである。
「スーザン、夜会ではなく本当に、ダンスパーティでいいのかい?」
「学園の寮で、仲良しになったお友達を呼んで、朝まで語り明かしたいのよ。学園の寮でそんなことすれば、いっぺんに朝食抜きになってしまうから、それは避けたいのよ。」
「それは女の子の友達と?」
「ええ。セレンというサンドラ国の女性よ。学年トップの成績保持者なのよ。」
プリメリアの両親は、目を輝かせながら話すスーザンを微笑ましく思う反面心配する。
そして、スーザンには、内緒で夜会の準備をする。ダンスパーティではなく普通のパーティとしての招待客を吟味する。雰囲気に興じて、踊りたい人は踊ればいいという感じに、楽団にもオーダーを入れる。
普通のパーティとダンスパーティとは、設えが異なる。普通のパーティは、中央に飲み物、食べ物を置き、ダンスパーティは、中央に踊るためのスペースを開けるので、飲食物は壁際へ置かれ、テーブルなどもそのあたりに適当に置いてある。
今回は、折衷型で真ん中付近にダンスを踊ろうと思えば踊れるスペースを配し、飲食物のテーブルもセンター近くにある。
最初に主催者側の公爵夫妻が一曲踊り、ダンスパーティの趣で始まるが、あくまでも普通の夜会である。スーザンとセレスティーヌは、隅っこのテーブルで、お料理をつつきながらおしゃべりに興じている。
そこへスーザンの兄がやってきて、セレスティーヌに手を差し伸べながら
「スーザンの次兄でスティーヴ・プリメリアと申します。よろしければ一曲踊っていただけないでしょうか?」
聞けば、前世クリスティーヌと同い年の19歳、彼女も婚約者もいなくスーザンの友達を狙っていたとか?
「スティーヴお兄様!邪魔しないでいただけますか?わたくしまだ、セレンと喋り足りないのでございますわよ。」
「いいじゃないか、ダンスパーティなのに、一曲も踊らないというのはおかしいだろ?」
「ぅぐぐ……。これは、ダンスパーティ風の夜会とかわりませんわ。ですから……。」
スーザンが抗議している間に、さっさとセレスティーヌの手を取り、センターへ向かうスティーヴ。セレスティーヌも久しぶりのダンスに心ときめく。
クリスティーヌ時代は、よく踊ったのだが、セレスティーヌになってからは、一度も踊っていない。王女殿下にダンスを誘うことはプロポーズするのと同じ意味があるからで、まだ学園にも行っていない少女にプロポーズはできないからと自粛されていたのである。
センターに着き、挨拶をしてから踊り出す。セレスティーヌのダンスは優雅で目を見張るものがある。周りにいた貴族たちは、皆、歓談を中断して、セレスティーヌの踊りに注目している。
「気高い品がある。美しい。」
「あれでこそ舞姫だ。どこの令嬢か?」
「なんでもサンドラ国の令嬢らしい。」
「ほぅ……。」プリメリア公爵夫妻も、あのスーザンが言っていた令嬢がスティーヴの嫁さんとして申し分がないことがわかると、なんとか嫁に来てもらえないか交渉したいと思っている。
あのダンスの様子からして、さぞかし高位貴族の令嬢に違いないだろう。
スーザンは、掘り出し物の令嬢と友達になってくれたものだと感心する。
しかし、スティーヴは次兄であるから、長兄はすでに結婚している。プリメリアの家督を継がすのは、今のところ、長兄であるが、もし、あのサンドラの令嬢が嫁に来てくれたら、次兄に継がすということも一つの選択肢になる。
嫁さんになる女性の器次第で、男の出世は決まると言っても過言ではない。
ダンスが終わってからというもの、公爵夫妻を交えて、懸命にセレスティーヌを口説き始めたスティーヴに、スーザンはカンカンに怒っているのである。
「スティーヴお兄様!セレンはわたくしのお友達なんでございますわよ。それをお父様やお母様までご一緒になられて、わたくしからセレンを取り上げないでいただけるかしら?」
「では、スーザンも一曲踊ってきたら、良かろう。誰か、スーザンと踊ってくれるような殊勝な?貴族令息は……?あ!幼馴染のロバートが壁にもたれている!ロバートを誘って、踊ってくるといい。」
「はぁ?なんで、わたくしがあんな野暮ったいうすのろバカ男と踊らなければいけないのかしら?」
「そう言うな。スーザンがダンスパーティをしたいと言い出したのだから、一曲ぐらい踊っても罰は当たらないだろう。」
「はぁ……。」
スーザンは、こんなことなら、夜会と言えばよかったと後悔するも後の祭り、ダンスパーティと言ったことで墓穴を掘ってしまったのだ。
もう公爵夫妻は、我が娘のスーザンのことなど眼中になく、いかにセレンと婚約するかで頭を巡らせている。スティーヴも懸命に口説くが、セレスティーヌは王女であるから、そう簡単に結婚してもよろしくてよ。とは、口が裂けても言えない。
もう婚約はコリゴリなのである。前世は5歳でリチャードに見初められ、厳しいお妃教育の上、男爵令嬢と浮気され婚約破棄されたのだから、こんな屈辱的なことはない。公爵令嬢でありながら、男爵令嬢に負けてしまった自分への腹立たしさと悔しさは今でも覚えている。
だからこそ、自害の道を選んだのだ。あのまま生き恥をさらして生き続けるなど、誇り高きクリスティーヌには我慢できないことであったからだ。
まぁ、リチャードに比べたら、100倍はマシなスティーヴではある。
王女殿下という立場でなく、クリスティーヌで、しかもリチャードの婚約者でなければ、OKを即答していただろうが、今は、王女殿下なのである。
「結婚してもよろしいですけど、わたくし一人娘でありますから、家を継いでいただける方としか結婚できないのでございますわ。」
「そんなもの、子供を二人産めば、すぐに解決できる問題であろうが。……わかった。スティーヴ、養子に行け。こんないい令嬢を逃したら、もうないぞ。」
「は?まぁ、養子でもいいけど……。」
「それに結婚は2年後、学園を卒業してからのお話しとなります。それにわたくしの両親とも会っていただかなければなりませんし、いろいろ手続きが煩雑になりますので、婚約ではなく、親友のお兄様とのお約束程度なら、可能でございます。」
ついに、セレスティーヌは折れてしまったのだ。
「ただし、わたくしの両親が反対してしまったら、このお話は流れるものと覚悟してくださいませ。」
「わかった。2年後まで精進して、セレンのご両親に認めてもらえるような男になる。」
女官や側近の中では、セレスティーヌ様は以前の記憶を失う前の王女殿下よりも王女殿下らしくなったと評されている。
そして、いよいよ学園に入る。国立学園に本来なら、入学するところなのだが、この前、リチャードが男爵令嬢に誑かされて、公爵令嬢が自害するという事件が起きたばかりなので、今年度の入学辞退者は相当数に上る。
学園内でのセキュリティに問題があるから、こういう事件が起きると問題視されたからである。
セレスティーヌも少し考えて、他国の学園に留学することにしたのである。セレスティーヌ狙いの逆玉の輿狙いがないとも言い切れないから。
他国で身分を隠し、楽しい学園生活を送りたいと希望している。
でもセレスティーヌが今のところ王位継承権第1位になったものだから、おいそれと他国に行きにくいことも事実である。
それでも前世クリスティーヌだったセレスティーヌは、王女殿下でありながら、公爵令嬢気分なのだから仕方がない。
いくつかの国の入学試験を受けたら、みんな合格したのだ。そらそうだ。前世、卒業した記憶があるのだから、入学試験ぐらいちょろいものである。
いろいろ悩んだ挙句、やっぱり近場の隣国モントオールに行くことにする。
ちょっと日帰りで買い物にも行ける近さということもあり、小さい時にいい思い出があった国だから、といってももちろん、クリスティーヌ時代のことなのだ。
クリスティーヌは、6歳から8歳までこのモントオール国に住んでいたことがあったから、地の利だけでなく土地勘もある。
モントオール国では、とりあえず寮に入ることになったのだが、この寮長が鬼だったのだ。
門限は厳しく、一分でも遅れたら、連帯責任を取らされ皆でグランドを走らせられる。朝もそう、一分でも寝坊をする者がいると、朝食抜きになってしまう。
最初は、それでも同じ年頃の人たちといることだけで楽しかったのだが、2年生になる頃には、さすがに厳しくされることに辟易を感じ、寮を出て、一軒家を借りることになったのである。
護衛の騎士もその方がいいみたいで、けっこう朝寝坊ができるようになったのだ。朝寝坊をして、好きなものを食べ、パーティなどで遅くなっても怒られない自由な生活を満喫する。
これでこそ学生生活よね、留学した甲斐があるというもの。サンドラのお城に入れば、こうはいかない。寮生活程厳しくはないが、似たようなもので、周りの目があり自由に過ごせない。
そんなある日、1年生の時に同じ寮のルームメイトだったモントオール国の公爵令嬢スーザン・プリメリア嬢が、ダンスパーティに誘ってきたのである。
もちろん行きますとも!二つ返事で承諾し、ドレス選びをする。なんで、公爵令嬢なのに、寮生活していたかと言うと、お友達が作りたかったかららしい。
ちょっと高位貴族の令嬢になれば、なかなか政略ばかりで本当の意味での仲良し友達ができない。
セレスティーヌも、ついこの間まで18年間も公爵令嬢をやっていたので、スーザンの気持ちはよくわかる。
ダンスパーティなど名目で、本来の意味は、ニッポンの盆踊りと同じでナンパが目的なのであるが、それを言ってしまったら、身も蓋もない。未婚者だけでなく、既婚者でさえも一夜の愛を求める。主催者側が余程しっかりしていないと、売春や乱交の温床になりかねない。
スーザンはそのあたりのことを理解しているのか?きっとただのダンスパーティぐらいにしかわかっていないだろう。
セレスティーヌも表向きのダンスパーティに参加する意向だが、クリスティーヌさえもそのことに気づいていない。
ただ、スーザンは、寮のルームメイトであったセレスティーヌに少々関心を持っていて、もっとお喋りがしたいだけなのである。学園の授業の合間に喋ると言っても、限度があるから。
だから親に普通の夜会をするのと同じノリで、ダンスパーティをしたいと申し出て、ビックリされたのである。
「スーザン、夜会ではなく本当に、ダンスパーティでいいのかい?」
「学園の寮で、仲良しになったお友達を呼んで、朝まで語り明かしたいのよ。学園の寮でそんなことすれば、いっぺんに朝食抜きになってしまうから、それは避けたいのよ。」
「それは女の子の友達と?」
「ええ。セレンというサンドラ国の女性よ。学年トップの成績保持者なのよ。」
プリメリアの両親は、目を輝かせながら話すスーザンを微笑ましく思う反面心配する。
そして、スーザンには、内緒で夜会の準備をする。ダンスパーティではなく普通のパーティとしての招待客を吟味する。雰囲気に興じて、踊りたい人は踊ればいいという感じに、楽団にもオーダーを入れる。
普通のパーティとダンスパーティとは、設えが異なる。普通のパーティは、中央に飲み物、食べ物を置き、ダンスパーティは、中央に踊るためのスペースを開けるので、飲食物は壁際へ置かれ、テーブルなどもそのあたりに適当に置いてある。
今回は、折衷型で真ん中付近にダンスを踊ろうと思えば踊れるスペースを配し、飲食物のテーブルもセンター近くにある。
最初に主催者側の公爵夫妻が一曲踊り、ダンスパーティの趣で始まるが、あくまでも普通の夜会である。スーザンとセレスティーヌは、隅っこのテーブルで、お料理をつつきながらおしゃべりに興じている。
そこへスーザンの兄がやってきて、セレスティーヌに手を差し伸べながら
「スーザンの次兄でスティーヴ・プリメリアと申します。よろしければ一曲踊っていただけないでしょうか?」
聞けば、前世クリスティーヌと同い年の19歳、彼女も婚約者もいなくスーザンの友達を狙っていたとか?
「スティーヴお兄様!邪魔しないでいただけますか?わたくしまだ、セレンと喋り足りないのでございますわよ。」
「いいじゃないか、ダンスパーティなのに、一曲も踊らないというのはおかしいだろ?」
「ぅぐぐ……。これは、ダンスパーティ風の夜会とかわりませんわ。ですから……。」
スーザンが抗議している間に、さっさとセレスティーヌの手を取り、センターへ向かうスティーヴ。セレスティーヌも久しぶりのダンスに心ときめく。
クリスティーヌ時代は、よく踊ったのだが、セレスティーヌになってからは、一度も踊っていない。王女殿下にダンスを誘うことはプロポーズするのと同じ意味があるからで、まだ学園にも行っていない少女にプロポーズはできないからと自粛されていたのである。
センターに着き、挨拶をしてから踊り出す。セレスティーヌのダンスは優雅で目を見張るものがある。周りにいた貴族たちは、皆、歓談を中断して、セレスティーヌの踊りに注目している。
「気高い品がある。美しい。」
「あれでこそ舞姫だ。どこの令嬢か?」
「なんでもサンドラ国の令嬢らしい。」
「ほぅ……。」プリメリア公爵夫妻も、あのスーザンが言っていた令嬢がスティーヴの嫁さんとして申し分がないことがわかると、なんとか嫁に来てもらえないか交渉したいと思っている。
あのダンスの様子からして、さぞかし高位貴族の令嬢に違いないだろう。
スーザンは、掘り出し物の令嬢と友達になってくれたものだと感心する。
しかし、スティーヴは次兄であるから、長兄はすでに結婚している。プリメリアの家督を継がすのは、今のところ、長兄であるが、もし、あのサンドラの令嬢が嫁に来てくれたら、次兄に継がすということも一つの選択肢になる。
嫁さんになる女性の器次第で、男の出世は決まると言っても過言ではない。
ダンスが終わってからというもの、公爵夫妻を交えて、懸命にセレスティーヌを口説き始めたスティーヴに、スーザンはカンカンに怒っているのである。
「スティーヴお兄様!セレンはわたくしのお友達なんでございますわよ。それをお父様やお母様までご一緒になられて、わたくしからセレンを取り上げないでいただけるかしら?」
「では、スーザンも一曲踊ってきたら、良かろう。誰か、スーザンと踊ってくれるような殊勝な?貴族令息は……?あ!幼馴染のロバートが壁にもたれている!ロバートを誘って、踊ってくるといい。」
「はぁ?なんで、わたくしがあんな野暮ったいうすのろバカ男と踊らなければいけないのかしら?」
「そう言うな。スーザンがダンスパーティをしたいと言い出したのだから、一曲ぐらい踊っても罰は当たらないだろう。」
「はぁ……。」
スーザンは、こんなことなら、夜会と言えばよかったと後悔するも後の祭り、ダンスパーティと言ったことで墓穴を掘ってしまったのだ。
もう公爵夫妻は、我が娘のスーザンのことなど眼中になく、いかにセレンと婚約するかで頭を巡らせている。スティーヴも懸命に口説くが、セレスティーヌは王女であるから、そう簡単に結婚してもよろしくてよ。とは、口が裂けても言えない。
もう婚約はコリゴリなのである。前世は5歳でリチャードに見初められ、厳しいお妃教育の上、男爵令嬢と浮気され婚約破棄されたのだから、こんな屈辱的なことはない。公爵令嬢でありながら、男爵令嬢に負けてしまった自分への腹立たしさと悔しさは今でも覚えている。
だからこそ、自害の道を選んだのだ。あのまま生き恥をさらして生き続けるなど、誇り高きクリスティーヌには我慢できないことであったからだ。
まぁ、リチャードに比べたら、100倍はマシなスティーヴではある。
王女殿下という立場でなく、クリスティーヌで、しかもリチャードの婚約者でなければ、OKを即答していただろうが、今は、王女殿下なのである。
「結婚してもよろしいですけど、わたくし一人娘でありますから、家を継いでいただける方としか結婚できないのでございますわ。」
「そんなもの、子供を二人産めば、すぐに解決できる問題であろうが。……わかった。スティーヴ、養子に行け。こんないい令嬢を逃したら、もうないぞ。」
「は?まぁ、養子でもいいけど……。」
「それに結婚は2年後、学園を卒業してからのお話しとなります。それにわたくしの両親とも会っていただかなければなりませんし、いろいろ手続きが煩雑になりますので、婚約ではなく、親友のお兄様とのお約束程度なら、可能でございます。」
ついに、セレスティーヌは折れてしまったのだ。
「ただし、わたくしの両親が反対してしまったら、このお話は流れるものと覚悟してくださいませ。」
「わかった。2年後まで精進して、セレンのご両親に認めてもらえるような男になる。」
0
お気に入りに追加
39
あなたにおすすめの小説

スライムの恩返しで、劣等生が最強になりました
福澤賢二郎
ファンタジー
「スライムの恩返しで劣等生は最強になりました」は、劣等生の魔術師エリオットがスライムとの出会いをきっかけに最強の力を手に入れ、王女アリアを守るため数々の試練に立ち向かう壮大な冒険ファンタジー。友情や禁断の恋、そして大陸の未来を賭けた戦いが描かれ、成長と希望の物語が展開します。
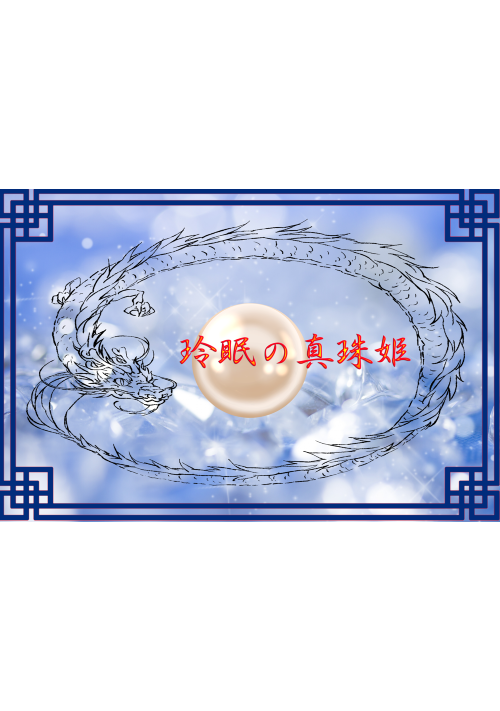
玲眠の真珠姫
紺坂紫乃
ファンタジー
空に神龍族、地上に龍人族、海に龍神族が暮らす『龍』の世界――三龍大戦から約五百年、大戦で最前線に立った海底竜宮の龍王姫・セツカは魂を真珠に封じて眠りについていた。彼女を目覚めさせる為、義弟にして恋人であった若き隻眼の将軍ロン・ツーエンは、セツカの伯父であり、義父でもある龍王の命によって空と地上へと旅立つ――この純愛の先に待ち受けるものとは? ロンの悲願は成就なるか。中華風幻獣冒険大河ファンタジー、開幕!!


[完結]回復魔法しか使えない私が勇者パーティを追放されたが他の魔法を覚えたら最強魔法使いになりました
mikadozero
ファンタジー
3月19日 HOTランキング4位ありがとうございます。三月二十日HOTランキング2位ありがとうございます。
ーーーーーーーーーーーーー
エマは突然勇者パーティから「お前はパーティを抜けろ」と言われて追放されたエマは生きる希望を失う。
そんなところにある老人が助け舟を出す。
そのチャンスをエマは自分のものに変えようと努力をする。
努力をすると、結果がついてくるそう思い毎日を過ごしていた。
エマは一人前の冒険者になろうとしていたのだった。

最強の英雄は幼馴染を守りたい
なつめ猫
ファンタジー
異世界に魔王を倒す勇者として間違えて召喚されてしまった桂木(かつらぎ)優斗(ゆうと)は、女神から力を渡される事もなく一般人として異世界アストリアに降り立つが、勇者召喚に失敗したリメイラール王国は、世界中からの糾弾に恐れ優斗を勇者として扱う事する。
そして勇者として戦うことを強要された優斗は、戦いの最中、自分と同じように巻き込まれて召喚されてきた幼馴染であり思い人の神楽坂(かぐらざか)都(みやこ)を目の前で、魔王軍四天王に殺されてしまい仇を取る為に、復讐を誓い長い年月をかけて戦う術を手に入れ魔王と黒幕である女神を倒す事に成功するが、その直後、次元の狭間へと呑み込まれてしまい意識を取り戻した先は、自身が異世界に召喚される前の現代日本であった。

病弱少女、転生して健康な肉体(最強)を手に入れる~友達が欲しくて魔境を旅立ちましたが、どうやら私の魔法は少しおかしいようです~
アトハ
ファンタジー
【短いあらすじ】
普通を勘違いした魔界育ちの少女が、王都に旅立ちうっかり無双してしまう話(前世は病院少女なので、本人は「超健康な身体すごい!!」と無邪気に喜んでます)
【まじめなあらすじ】
主人公のフィアナは、前世では一生を病院で過ごした病弱少女であったが……、
「健康な身体って凄い! 神さま、ありがとう!(ドラゴンをワンパンしながら)」
転生して、超健康な身体(最強!)を手に入れてしまう。
魔界で育ったフィアナには、この世界の普通が分からない。
友達を作るため、王都の学園へと旅立つことになるのだが……、
「なるほど! 王都では、ドラゴンを狩るには許可が必要なんですね!」
「「「違う、そうじゃない!!」」」
これは魔界で育った超健康な少女が、うっかり無双してしまうお話である。
※他サイトにも投稿中
※旧タイトル
病弱少女、転生して健康な肉体(最強)を手に入れる~友達が欲しくて魔境を旅立ちましたが、どうやら私の魔法は少しおかしいようです~

【完結】帝国から追放された最強のチーム、リミッター外して無双する
エース皇命
ファンタジー
【HOTランキング2位獲得作品】
スペイゴール大陸最強の帝国、ユハ帝国。
帝国に仕え、最強の戦力を誇っていたチーム、『デイブレイク』は、突然議会から追放を言い渡される。
しかし帝国は気づいていなかった。彼らの力が帝国を拡大し、恐るべき戦力を誇示していたことに。
自由になった『デイブレイク』のメンバー、エルフのクリス、バランス型のアキラ、強大な魔力を宿すジャック、杖さばきの達人ランラン、絶世の美女シエナは、今まで抑えていた実力を完全開放し、ゼロからユハ帝国を超える国を建国していく。
※この世界では、杖と魔法を使って戦闘を行います。しかし、あの稲妻型の傷を持つメガネの少年のように戦うわけではありません。どうやって戦うのかは、本文を読んでのお楽しみです。杖で戦う戦士のことを、本文では杖士(ブレイカー)と描写しています。
※舞台の雰囲気は中世ヨーロッパ〜近世ヨーロッパに近いです。
〜『デイブレイク』のメンバー紹介〜
・クリス(男・エルフ・570歳)
チームのリーダー。もともとはエルフの貴族の家系だったため、上品で高潔。白く透明感のある肌に、整った顔立ちである。エルフ特有のとがった耳も特徴的。メンバーからも信頼されているが……
・アキラ(男・人間・29歳)
杖術、身体能力、頭脳、魔力など、あらゆる面のバランスが取れたチームの主力。独特なユーモアのセンスがあり、ムードメーカーでもある。唯一の弱点が……
・ジャック(男・人間・34歳)
怪物級の魔力を持つ杖士。その魔力が強大すぎるがゆえに、普段はその魔力を抑え込んでいるため、感情をあまり出さない。チームで唯一の黒人で、ドレッドヘアが特徴的。戦闘で右腕を失って以来義手を装着しているが……
・ランラン(女・人間・25歳)
優れた杖の腕前を持ち、チームを支える杖士。陽気でチャレンジャーな一面もあり、可愛さも武器である。性格の共通点から、アキラと親しく、親友である。しかし実は……
・シエナ(女・人間・28歳)
絶世の美女。とはいっても杖士としての実力も高く、アキラと同じくバランス型である。誰もが羨む美貌をもっているが、本人はあまり自信がないらしく、相手の反応を確認しながら静かに話す。あるメンバーのことが……

いっとう愚かで、惨めで、哀れな末路を辿るはずだった令嬢の矜持
空月
ファンタジー
古くからの名家、貴き血を継ぐローゼンベルグ家――その末子、一人娘として生まれたカトレア・ローゼンベルグは、幼い頃からの婚約者に婚約破棄され、遠方の別荘へと療養の名目で送られた。
その道中に惨めに死ぬはずだった未来を、突然現れた『バグ』によって回避して、ただの『カトレア』として生きていく話。
※悪役令嬢で婚約破棄物ですが、ざまぁもスッキリもありません。
※以前投稿していた「いっとう愚かで惨めで哀れだった令嬢の果て」改稿版です。文章量が1.5倍くらいに増えています。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















