あなたにおすすめの小説

二本のヤツデの求める物
あんど もあ
ファンタジー
夫の父の病が重篤と聞き、領地から王都の伯爵邸にやって来たナタリーと夫と娘のクリスティナ。クリスティナは屋敷の玄関の両脇に植えられた二本の大きなヤツデが気に入ったようだ。
新たな生活を始めようとするナタリーたちだが、次々と不幸が襲いかかり……。

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い
青の雀
恋愛
夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。
神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。
もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。
生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。
過去世と同じ轍を踏みたくない……

婚約破棄された公爵令嬢は虐げられた国から出ていくことにしました~国から追い出されたのでよその国で竜騎士を目指します~
ヒンメル
ファンタジー
マグナス王国の公爵令嬢マチルダ・スチュアートは他国出身の母の容姿そっくりなためかこの国でうとまれ一人浮いた存在だった。
そんなマチルダが王家主催の夜会にて婚約者である王太子から婚約破棄を告げられ、国外退去を命じられる。
自分と同じ容姿を持つ者のいるであろう国に行けば、目立つこともなく、穏やかに暮らせるのではないかと思うのだった。
マチルダの母の祖国ドラガニアを目指す旅が今始まる――
※文章を書く練習をしています。誤字脱字や表現のおかしい所などがあったら優しく教えてやってください。
※第二章まで完結してます。現在、最終章について考え中です(第二章が考えていた話から離れてしまいました(^_^;))
書くスピードが亀より遅いので、お待たせしてすみませんm(__)m
※小説家になろう様にも投稿しています。

私の風呂敷は青いあいつのよりもちょっとだけいい
しろこねこ
ファンタジー
前世を思い出した15歳のリリィが風呂敷を発見する。その風呂敷は前世の記憶にある青いロボットのもつホニャララ風呂敷のようで、それよりもちょっとだけ高性能なやつだった。風呂敷を手にしたリリィが自由を手にする。
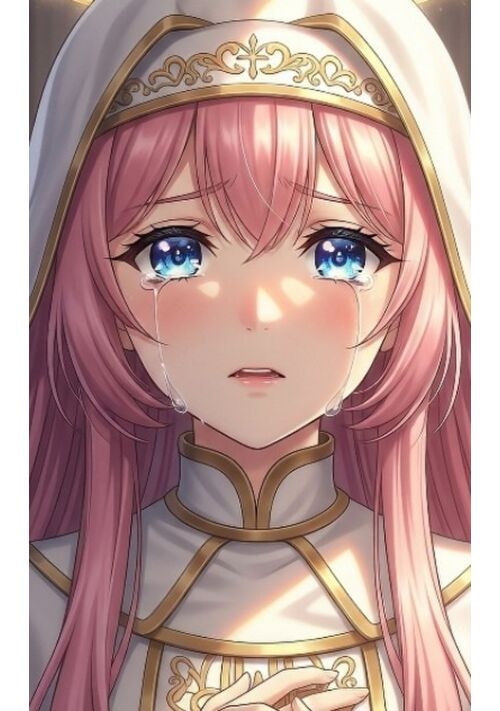
聖女は聞いてしまった
夕景あき
ファンタジー
「道具に心は不要だ」
父である国王に、そう言われて育った聖女。
彼女の周囲には、彼女を心を持つ人間として扱う人は、ほとんどいなくなっていた。
聖女自身も、自分の心の動きを無視して、聖女という治癒道具になりきり何も考えず、言われた事をただやり、ただ生きているだけの日々を過ごしていた。
そんな日々が10年過ぎた後、勇者と賢者と魔法使いと共に聖女は魔王討伐の旅に出ることになる。
旅の中で心をとり戻し、勇者に恋をする聖女。
しかし、勇者の本音を聞いてしまった聖女は絶望するのだった·····。
ネガティブ思考系聖女の恋愛ストーリー!
※ハッピーエンドなので、安心してお読みください!

それは思い出せない思い出
あんど もあ
ファンタジー
俺には、食べた事の無いケーキの記憶がある。
丸くて白くて赤いのが載ってて、切ると三角になる、甘いケーキ。自分であのケーキを作れるようになろうとケーキ屋で働くことにした俺は、無意識に周りの人を幸せにしていく。


雨の少女
朝山みどり
ファンタジー
アンナ・レイナードは、雨を操るレイナード家の一人娘。母キャサリンは代々その力を継ぐ「特命伯爵」であり、豊穣を司る王家と並び国を支える家柄だ。外交官の父ブライトは家を留守にしがちだが、手紙や贈り物を欠かさず、アンナは両親と穏やかな日々を送っていた。ある日、母は「明日から雨を降らせる」と言い、アンナと一緒に街へ買い物に出かける。温かな手を引かれて歩くひととき、本と飴を選ぶ楽しさ、それはアンナにとってかけがえのない記憶だった。
やがて雨が降り始め、国は潤ったが、異常気象の兆しが見え始める。キャサリンは雨を止めようと努力するが、うまくいかず、王家やサニダ家に助けを求めても返事はない。やがて体を壊し、キャサリンはアンナに虹色のペンダントを託して息を引き取った。アンナは悲しみを胸に、自らの力で雨を止め、空に虹をかけた。
葬儀の後、父はすぐ王宮へ戻り、アンナの生活は一変する。ある日、継母ミラベルとその娘マリアンが屋敷に現れ、「この家を任された」と告げる。手紙には父の字でそう記されていた。以来、アンナの大切な物や部屋までも奪われ、小屋で一人暮らすことになる。父からの手紙はミラベルとマリアンにのみ届き、アンナ宛てには一通も来ない。ペンダントを握って耐える日々が続いた。
「なろう」にも投稿しております。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















