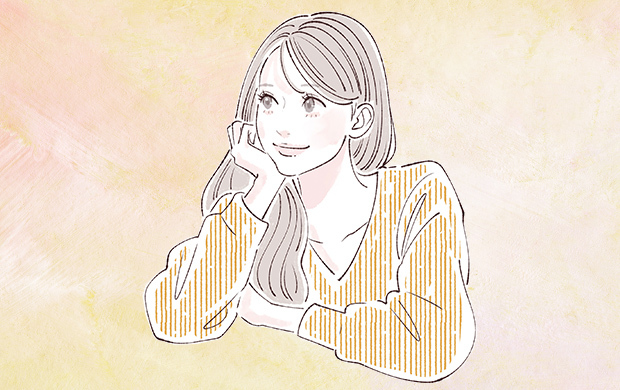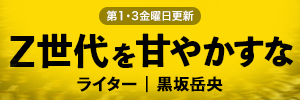政治に翻弄される公立大学の悲しき宿命…地方で相次ぐ首長の介入と私大の公立化
2021.08.01
ビジネスジャーナル
この公立化は、定員割れに悩む地方私大の最終的な救済策と言われている。前述の高知工科大と山陽小野田市立山口東京理科大のほかにも、2010年に静岡文化芸術大学と名桜大学、2012年に鳥取環境大学、2014年に長岡造形大学、2016年に福知山公立大学、2017年に長野大学、2018年に公立諏訪東京理科大学、2019年に公立千歳科学技術大学、という具合である。
では、なぜ最初から公立にしなかったのか。私大の方が経営のプロに任せられるし、公立大より高い学費を取れるからだろう。ところが、地方では都会の大学経営の手法が通用せず、既存の私学は敬遠し始めた。そのため、施設などは地元自治体がつくり、経営は民営(実質は公務員)という公設民営方式になった、というわけだ。
しかし、伝統もなく、就職先は不透明、学費は高いということで志願者は集まらず、定員割れが続き、公立化を迫られた。その結果、地方交付税の公立大学分の財政負担サポートもあり、学費は他の公立大並みに安くなった。また、公立大ということで地元高校の進学指導サポートも強まり、定員割れも解消した。
ちなみに、定員割れでないのに公立化した静岡文化芸術大学は、公立法人化の制度ができたことがきっかけになったという。当時の2代目学長は、先般の知事選で再選された川勝平太静岡県知事である。
地方公立大の隠れた効用とは?
公立大というと、大阪府立大学と大阪市立大学の統合によるマンモス校の誕生や、横浜市立大学に続いて名古屋市立大学にデータサイエンス学部の設置が発表されるなど、ビビッドなビッグニュースが多い。しかし、地方公立大学の隠れた効用に、もっと目を向けるべきだ。
公立大学協会のデータによると、たとえば公立大の域内(県立なら県内、市立なら市内)の志願者数は3割程度、入学者は4割弱なのに、所在地の都道府県への卒業生の就職率は45%程度をキープしている。人材の地元就職率は、相対的に好ましいレベルだ。
一方で、ジェンダーの視点から大学教員数の女性比率を見ると、学長は公立20.9%、国立4.7%、私立11.6%で、副学長は公立14.5%、国立9.4%、私立13.4%となっている。学長・副学長を除く教授は公立21.9%、国立10.4%、私立20.2%だ。私立には女子大学が多く、公立も女子系の短期大学が母体の大学が少なくないことを考慮に入れるべきであるが、この伝統を活かしてさらなるジェンダー格差解消を大いに期待したい。
また、設置主体が地方自治体だけに地域貢献は主な使命であるが、滋賀県立大学、広島市立大学、岡山県立大学、北九州市立大学などは、文部科学省の地方の知的拠点(COC+)大学として、国立大と伍してリーダーシップを発揮してきた。
これからは、地方再生に果たす公立大の役割が大きくなることは間違いない。
(文=木村誠/教育ジャーナリスト)
●木村誠(きむら・まこと)
早稲田大学政経学部新聞学科卒業、学研勤務を経てフリー。近著に『「地方国立大学」の時代-2020年に何が起こるのか』(中公ラクレ)。他に『大学大崩壊』『大学大倒産時代』(ともに朝日新書)など。