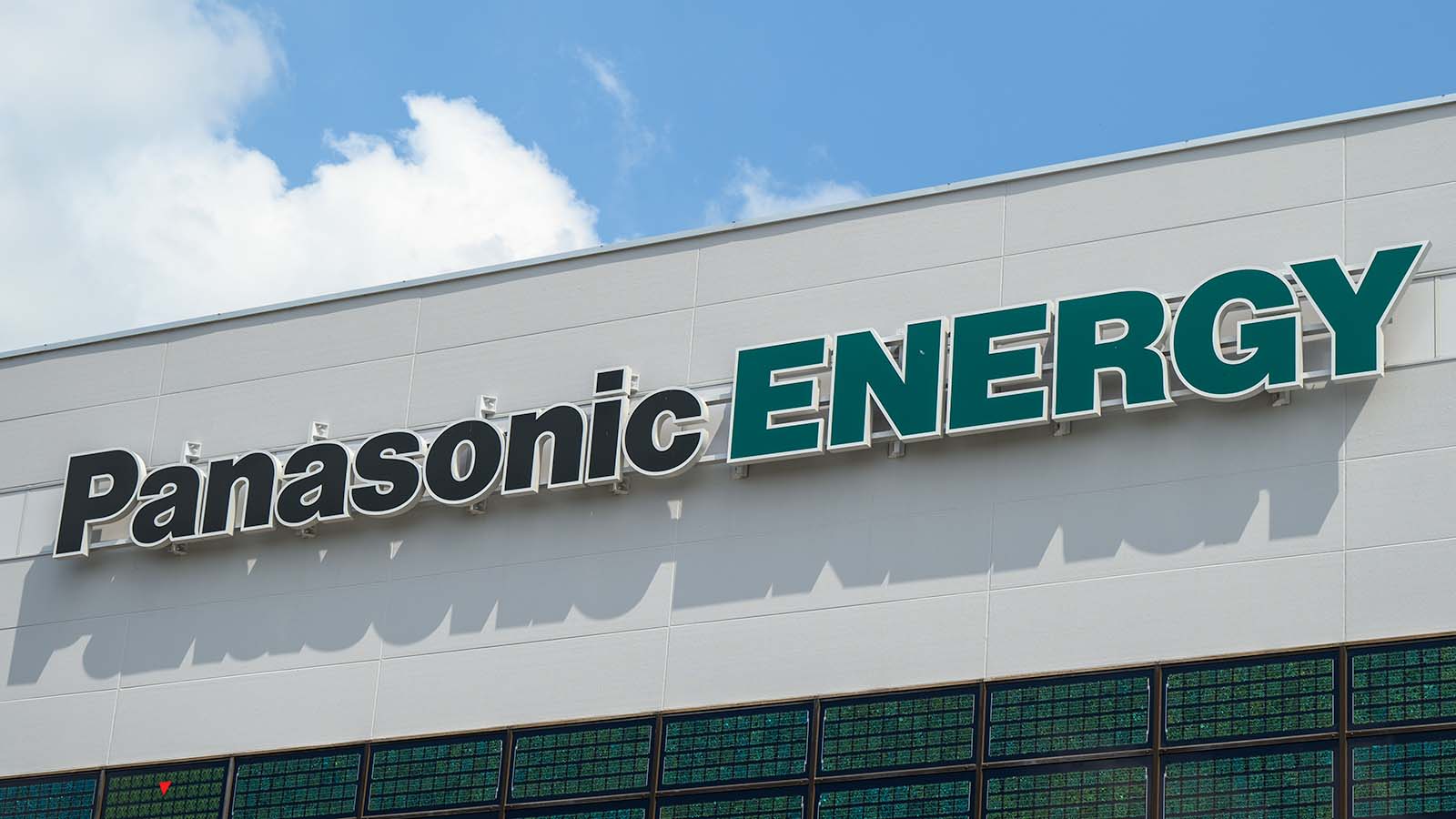追い込まれたドコモ、「値下げ競争再燃」へ火蓋切る
2024.11.21
東洋経済オンライン
KDDIは11月12日から、UQモバイルの20GB・月額3278円のプランについて、価格据え置きで30GBに変更し、さらに特典として3GBを追加。必要に応じてデータ量を購入するオンライン専用プラン「povo(ポヴォ)」についても、月間30GBの利用を意識し、1年間で360GBを使えるオプションを用意した。
?橋誠社長は11月1日の決算会見で、「中容量帯の競争が少しホットになってきている。もともとスタートしたのはドコモからだが、いち早くわれわれとしては対応しようと思った」と狙いを語った。
ソフトバンクも11月から、オンライン専用ブランド「LINEMO(ラインモ)」の月額2970円で20GB使えるプランについて、30GBまで同価格で利用できるように変更。ワイモバイルでも月間30GBの利用を意識し、データ増量オプションの改定を実施した。宮川潤一社長は11月8日の決算会見で、「行き過ぎた値下げは中長期目線で見ると、本当にいいのか疑問を感じるが、1社でも動きがあると対抗せざるをえない。売られたケンカは買う」とたんかを切った。
3G停波がさらなる打撃に?
他社の追随によって、即座にアハモの価格面での競争優位性を失ったドコモだが、さらなるシェアの拡大に向けた手は打つのか。
決算説明会で今後の方針を問われたNTTの島田社長は、「これ以上やっても(他社が)ドコモから取れないと思うところまではやり続けようと思っている」と述べた。その時期について、「それは相手次第だ。1年になるかもしれないし、半年なのかもしれないが、35%のシェアは必須だ」と強気の姿勢を崩さなかった。
ドコモにとって、将来の契約減につながる大イベントが目前に控えていることからも、今は正念場といえる。2026年3月に予定する通信規格「3G」の停波だ。
シニアユーザーが多いとされるドコモは、いわゆる「ガラケー」を主に使う3Gユーザーの契約が足元で600万程度存在し、強制解約などでサービス終了が通信収入の下押し要因になると見込まれる。前田社長は「(今後も)人口減や3Gサービス終了の影響で、一定程度、モバイル通信収入は下がっていく見込みだ。コンシューマ通信事業としては2026年度には下げ止めたい」と話す。
とくにこれから重要になってくるのが、シニアユーザーに代わって今後ドコモの収益に貢献する、若年層ユーザーの獲得だ。「人口減を見据え、将来の収益の礎となる顧客基盤の獲得、シェア拡大にしっかり注力すべき時だ」(前田社長)。

6月に就任したばかりのNTTドコモの前田義晃社長。ポイントや決済事業など非通信分野に長く携わってきたが、まずは本業の立て直しを迫られている(記者撮影)
もっとも、スマホが広く普及している業界はすでに成熟期を迎え、「ゼロサムゲーム」の様相を呈しつつある。2020年にキャリア事業に本格参入した楽天モバイルも、競争力のある低廉な料金プランと営業力で契約者数を急拡大し、存在感を増す。
MM総研の横田英明副所長は「昔“大横綱”だったドコモは今、競合と肩を並べている状態だ。失われたブランド力を回復するのは大変チャレンジングで、今のドコモの動向を見ていると、再び携帯料金が下がっていく可能性は高いと思う。これから、キャリアにとってはなかなか大変な戦争になるだろう」と予想する。
本業の立て直しに本格着手し、追加対抗策も示唆するドコモ。追い込まれた王者の反転攻勢を受け、物価が上昇するインフレ局面から切り離されていた国内通信業界は、これからさらに逆方向へと大きく舵を切ろうとしている。