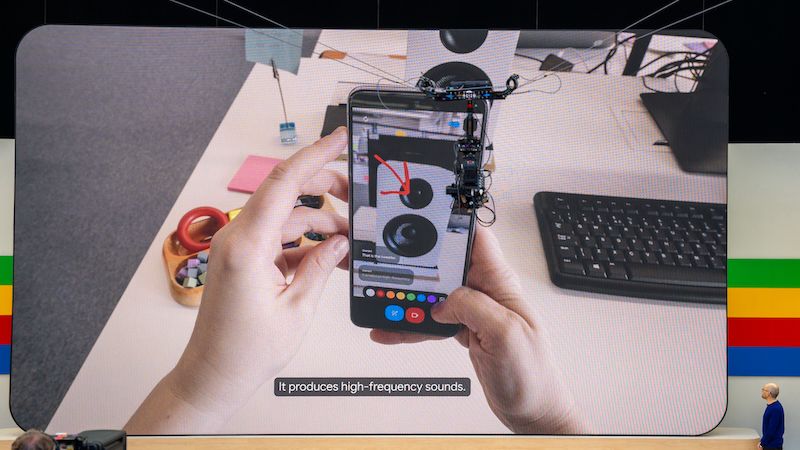コンピュータが「人間のように行動できない」理由
2023.06.30
東洋経済オンライン
旧式のヒーターでも最新型のスマートヒーターでも、このようなルールがヒーターの頭脳の土台をなしている。
このような条件付きの命令を組み合わせることで原始的な生成規則システムが作られ、ルールが多いほど複雑な課題を扱うことができる。
たとえば小学生に引き算の筆算を教えるには、「下の数字が上の数字よりも大きければ、上の数字の左の数字から1を借りる」といった10個ほどのルールが必要だ。
複雑な課題の中にはこのようなルールを何千も必要とするものもある。医療診断や住宅ローンの審査など、特定の課題における人間の判断を真似たプログラム、いわゆる「エキスパートシステム」を構築することもできる。
そのような課題に関してはこの方法論はある程度成功を収めている。しかし、生成規則だけでは人間の思考のモデルとして十分でないことも明らかになっている。
ニューエルとサイモンが失敗した根本原因は、人間の生活が多様であることによる。大腸菌などの単純な生物は一連の反射的ルールだけで生きられるが、もっと複雑な生活を送る生物ではそうはいかないのだ。
腐った食べ物を前にしたときの反応
例として、腐った食べ物や毒入りの食べ物を避けるという一見単純な課題について考えてみよう。そのような食べ物の中には匂いで判別できるものもあるが、そうした「嫌な」匂いには膨大な種類がある。
腐った食べ物の中には見た目や味や触感などで見分けられるものもあるが、それにもたくさんのタイプがある。すっぱい牛乳とカビの生えたパンとでは、見た目も匂いもまったく違う。そのような指標の強弱も重要である。
見た目はちょっと怪しいが匂いは問題ないのであれば、代わりの食べ物を見つけられる見通しや難しさによっては食べたいかもしれない。
見た目がすごく変であれば、匂いが問題なくても避けたいかもしれない。しかし飢え死にしそうだったら、見た目を気にせずに口にするかもしれない。
考えられる状況と反応のあらゆる組み合わせに対して、具体的で厳格で許容範囲の狭いルールを当てはめていたら、脳がパンクしてしまうだろう。そこで別の方法論が必要となる。
その方法論を提供してくれるのが情動だ。
反射作用では、ある特定の誘因(たとえば牛乳がすこしすっぱい匂いがするが、ここ何日も食べ物を口にしていないし、近くにほかの食べ物や飲み物はないかもしれない)が、それに合わせた自動的な反応(たとえばその牛乳を飲む)を引き起こす。
しかし情動の働き方はそれと異なる。誘因はもっと漠然としているし(飲み物の見た目や匂いがおかしい)、それから直接引き起こされるのは行動でなく、強弱さまざまな情動(ちょっと嫌だ)である。
すると脳はその情動と、ほかにいくつかの要素(ここ何日も食べ物を口にしていない、近くにほかの食べ物や飲み物はないかもしれない)を考慮して、反応のしかたを「計算」する。
こうすれば、一定の誘因/反応のルールを膨大な数取り揃えておく必要がなくなる。しかも柔軟性が大幅に高まるため、さまざまな反応のしかた(何もしないことも含む)を検討して、熟慮の上で決断を下すことができる。
脳は情動に対する反応を決める際に、複数の要素を考慮に入れる。いまの例では、どれだけ腹が空いているか、ほかの食べ物を探しに行くのがどのくらい嫌であるかなど、いくつかの状況を考慮する。
そこに関わってくるのが理性的な心だ。情動が引き起こされると、事実や目的や道理、および情動的要素に基づく精神的計算によって行動が導き出される。状況が複雑な場合には、このように情動と理性を組み合わせることで、実行可能な正解をより効率的なルートで達成できるのだ。