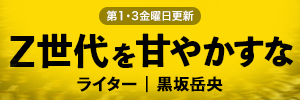作家たるもの、本が出ることだけに満足してはいけない

本は売れるにこしたことはない
本は売れてこそ作家にも恩恵をもたらす。出版とは、言うまでもなく本を商品としてつくり、本を売るビジネスである。出版社にとっても、作家にとっても、本は売れたほうがよい。これも当然のことだ。確かに多くの本の中には、世に出ることに大きな意味があるというものも存在する。とはいえ、どんな本であれ売れたほうがよいのである。なぜなら、売れているということは、よほどの例外を除けば、売れた本の数だけ読者がいることになるからだ。読者がいてこそ本は本となる。読者のいない本は単なる記録だ。
本が売れているというのは、現象的には重版が続き、発行部数が伸び、どこの書店の店頭にも、その本が置かれているという状態である。ひとつの本が書店で「目立つ」という状態になるのは、10万部を超えたあたりからだろう。2万部超の本は、十分売れているといえるのだが、まだ目立つという存在には至らない。しかし、書店ではさほど目立っていなくても、2万部以上の本は、出版関係者の間では注目されている。データ上は、はっきりと結果が出ているからだ。データを重視する最近の出版関係者は、売れている本、勢いのある本は、こまめにチェックしている。ゆえに、売れている本の作家は注目される。
注目されるというのは間接的ではあるが、出版が本業の販促に直結するビジネス書の作家にとっては、大きなメリットとなる。では、出版そのものの直接的な経済的メリットは、どのくらい本が売れたら顕在化するのだろうか。出版の経済的メリットとは印税である。本を出せば印税が入ってくる。自費出版でなければ、本を出してリターンがないということはない。必ず何らかの収入は発生する。その一方で、作家にもコストは必ず発生する。したがって、作家にも出版による損益はあるのだ。損益をしっかり把握せず、本が出たことだけを喜ぶのでは、作家としては些(いささ)かナイーブと言わざるを得ない。
作家にとっての損益分岐点
現在、ビジネス書は定価1,500円前後がボリュームゾーンで、初版の発行部数は5,000~1万部前後であることが多い。重版がかからない、初版発行だけで終わってしまうと、作家の直接収入である印税は一律ではないので、はっきりとはいえないが、刷り部数印税では、おおよそ50万円~90万円、実売部数印税では、本の売れ行きしだいといで金額が決まってくる。出版した本が初版で終わってしまえば収入はこれで確定だ。
この収入に対するコストは、作家の「労働」である原稿作成と校正、打合せ等の「作業」である。原稿作成には、相当に原稿の速い人であっても、1日4時間ペースで30日くらいかかる。時間にして120時間だ。これに校正作業が加わる。校正は、やはり速い人でも、初校・再校に15時間程度を費やす。それに編集者との打ち合わせに5時間程度は取るため、合計で140時間。これが一冊の本を出版するための作家の「労働時間」である。
印税を時間当たりで換算すると、だいたい2,857円~6,429円となる。この「時間給」は、一般的なパート・アルバイトの時給に比べるとかなり高額だが、ビジネス書作家の本業の収入に比べると相当に見劣りするはずだ。講演・研修、顧問料を時給換算すれば、最低でもこの数倍の水準となるはずである。つまり、理論上は140時間のうちの半分でも本業に使っていれば、印税収入の何倍かを稼げたということになる。したがって、せっかく出した本でも初版で終わっては、その労力から考えると出版は「骨折り損」だったと言える。本が「初版倒れ」で終われば、出版社は赤字で、作家も損ということに終わる。
では、出版が作家にとって黒字となるのは何部くらいからだろうか。単純に前述のパターンで重版を続けていけば、1万部を超えたところで刷り部数印税収入は100万円~120万円程度と推測される(実売部数印税の場合は、やはり売れ行きしだいで金額が決まる)。作家の「労働時間」は初版発行時と変わらないので、刷り部数印税をベースにすると、「時間給」は4,000円~1万円前後だ。2万部を超えるようになると刷り部数印税は240万円~300万円となり、また実売部数印税も、刷り部数印税の水準に近くなる。重版が続いているということは、実売部数が伸びていることに他ならないからだ。
時給にして1万7,000円~2万円程度となり、まだ本業には及ばないものの、ようやく本業の水準に近づいてくる。つまり、2万部を超えたあたりからが作家にとって、出版の損益分岐点なのである。このあたりを超えて、なお重版が続いていけば、出版も経済的に悪い商売ではない。
オススメ記事
まだ記事はありません。「ビジネス書業界の裏話」 記事一覧
- 第50回 出版界の再編と作家の未来
- 第51回 ビジネス書作家の在り方とは
- 第45回 作家たるもの、本が出ることだけに満足してはいけない
- 第44回 作家に必要な「頭の中を一行にまとめる」技術
- 第43回 作家の「顔」が見える本が売れる理由