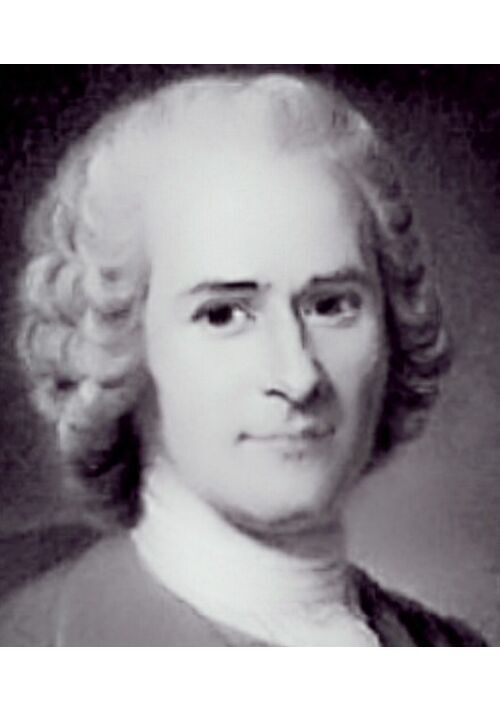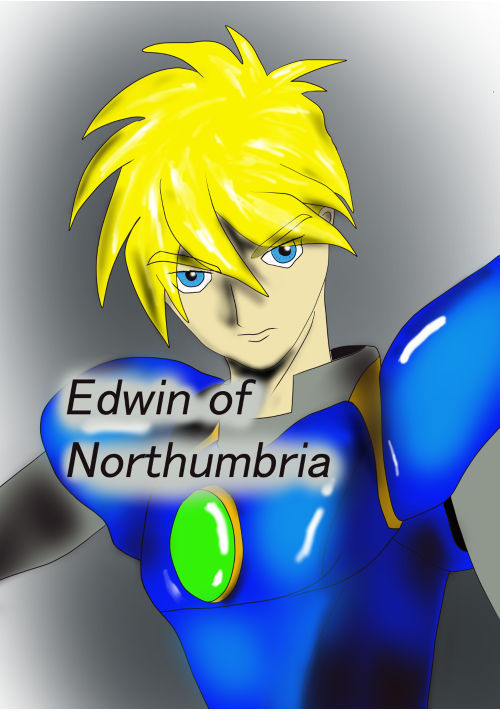49 / 49
第四章 愛よ義よ
前夜①
しおりを挟む
「どうしたのです勝太郎、もう終わりですか。戦場の敵は待ってはくれません。膝をおとしたら首をとりに群がってきますよ。すぐに立ちあがりなさい!」
地に片膝をおとしていた勝太郎は、肩を大きく上下さげて息をあらげ、のどにこみ上げてきたすっぱいものをぐっと飲みこんで押しもどす。
ふらつきながら立ちあがり、ふたたび木剣を正眼に置いた。
いましがた打たれた腹がじんと痛み、剣先がゆれる。今日はかれこれ七回も斬りたおされたのだから無理もない。
「なんの、私はまだまだやれますよ……母上」
三間むこう、木剣をひっさげて仁王立ちで待っていたあさ子は、無言のままうなずくと腰を深く半身にしずめ、脇にかまえて応じた。
「兄上、がんばれ。母さまにまけるな!」
縁側から稽古を見守っていた国子が、かわいらしい声援をおくってくれる。祖母の菊子と弟の勝治も見ている。
もうこれ以上、ぶざまな負け姿をみせるわけにはゆかない。
いくら母がなみなみならぬ腕前とはいえ、しょせんは女子だ。男として兄として、何としても一本はとってやりたいところだ。
父の善左衛門が京都守護職で出張中のあいだ、勝太郎は剣術をならいはじめた。本来ならば憧れの佐々木只三郎とおなじ精武流にするはずだったが、いかんせん武寮のおもだった使い手たちは京出張で忙しい。
城下には高齢となったが涼斎もいるし、稽古相手に困らないという理由により母や祖父とおなじ安光流をえらんだのだった。
勝太郎はまだ元服まえの十五歳。前髪つきの横顔はあどけない。
悔しげに歯をくいしばり、正眼から上段にうつした木剣の手のうちを絞りなおした。
「えいッ」
その年にしては鋭い太刀筋だった。母の動きにも似た、滑るように深い踏みこみに導かれ、カツンッ――と木剣が割れんばかりに当たる。
が、あさ子はやすやすと受け、からめて切り落とし、いいようにあしらわれた勝太郎が前後に揺れてたたらを踏んだ。
さらに足絡み、鳩尾への肘うち。後ろへひっくりかえりそうになった勝太郎が、思わず諸手をあげてしまった。
「甘い!」
がら空きになった腹に、水平に旋風のような一刀がどっと入った。
「うっ……」
臓物が上下に割れたような心地がして、苦悶の表情にかわった勝太郎は、息をつまらせて背を丸めた。
それでもあさ子は追撃の手をゆるめない。ひらりと身を旋回させて脚を打ち、背を打ち、勝太郎が顔を歪めて両膝をおとした。
「膝を落とすなと言いました」
そして首元へヒタリと木剣を乗せ、脈を断つようにすぅ――とゆっくり引いた。
またしても万事休す、首をとられた。
武芸者のきびしい眼光をたもったまま、あさ子がつきはなすように言った。
「もしもここが戦場ならばあなたは何もできないまま、むざむざと死んだことになります。これは無駄死にというものです」
「はい……」
「どうして止めを刺されるまえに組み付かなかったのですか。脚が動かなければ、倒れながら噛みつくこともできたはずです」
「それは、あまりに無作法ではないかと……」
「いいえ。演武は演武、戦場は戦場です。日新館で教授される稽古場にかぎったお行儀のよい剣法では、実戦のときは役にたちませぬ。日ごろの稽古はだいじな時にそのままあらわれるもの。行住坐臥、いつも戦場にあると心得なさい、緊張を保ちなさい。それが武家というものです」
「はい……しかと肝に銘じます」
この一月に鳥羽伏見の戦で外祖父の原源右衛門が戦没した。以来、あさ子の稽古はより一層激しさを増した。
源右衛門は齢五十をすぎてもなお仁王のような体格をした人であったが、孫たちにはとても優しいおじいさんだったから、勝太郎にとっても衝撃的だった。
風雲急をつげるいま、母がきびしくしてくれるのはもちろん己のことを思ってくれているのだと勝太郎も承知をしているが、袋竹刀と防具を用いずに木剣で仕合をするのだからたまったものではない。日新館でも木剣の仕合などは危険がともなうので滅多にやらないものだ。
しかも禁じ手はなし。柔の技をくみあわて何でもありだ。つばぜり合いをしていると肘を入れてくるし、先日は指をとられて折られかけた。
今日こそは一本を取ってやろうと覚悟をさだめ、工夫を凝らしたつもりだったがまったく及ばない。逆に八本も取られて何もさせてもらえなかった。
すでに全身が痣だらけになり、腕が痛くてあがらない。まるで猫の手の内にもてあそばれる鼠のようだったのは前回とおなじで、すっかり自信を喪失させられてしまった。
ゆっくりと歩みよってきたあさ子が、両方の口角を釣りあげ、にっこりと微笑んだ。童のときのように勝太郎を立たせ、稽古袴についた土をはらいながら言った。
「――前回より太刀筋が一段と鋭くなりましたね」
「ほ、本当ですか」
「ええ。腕と腰の力もつよくなりました。私から一本をとるのも、もうすぐのことだと思いますよ。はげみなさい。河原家の男子として、旦那様のように京や江戸まで名を轟かすのです」
「はい、精進いたします!」
するともう一人、生意気にも襷掛けに白鉢巻をした小僧が、木剣を手に名乗りでた。
「母上、私にもご教授をお願いします!」
次男の勝治だ。十歳になる。
「まぁ、勇ましいですこと」
まだ満足にふれない木剣をもちだして来たのは、兄に母をとられてしまった心地がして、張り合ったつもりでいるのだろう。
武家の男子として、たくましく成長しようとしている子供たち。あさ子にとってこれほど喜ばしいことはない。
二人とも抱きしめてやりたくなったが、うなずいて武芸者の顔にもどった。
「よく言いました。では母が稽古をつけてさしあげましょう。ですが剣を手にしたからには、これより母のことを敵と思うのです。命を賭して戦う敵です。勝治にはそれができますか」
「はい、できます!」
「よろしい。では打ちこんできてごらんなさい」
そうした熱気にみちみちた稽古がつづくさなか、開け放っていた門から唐突に不穏な気配がはいってきたとあさ子は気づいた。
「また、来たのね――」
背で察知して手をとめ、振りかえりざまに睨みつけた。
河原屋敷の門口にあらわれたのは、二人の侍だった。いずれも二十半ばで大柄、見知らぬ顔であるが、装いからして士中の者であると見てまちがいない。一人は右腕に包帯を巻いて吊り、もう一人は顔半分を包帯でくくりびっこを引いている。
あれは戦傷者だ。日新館の病院からやってきたのだろう。
ほどなく応接にでた伊右衛門と押し問答をはじめたのが見えた。肩をつきとばされた伊右衛門はよろめいて地に尻もちをついた。
そこへあさ子と勝太郎が急ぎ足で詰めよる。
「無礼でありましょう。何の用ですか」
憎悪をむきだしにした二人が、あさ子を一瞥してぞんざいに用向きをつげた。
「我らは別撰隊の者。奥方に用はござらん。国産奉行の河原殿に面会を願っただけであったが、この老いぼれが駄目だ、帰れという。無礼なのはこ奴のほうでありましょう。中間ふぜいが、斬り捨てられぬだけありがたいと思っていただきたい」
「…………」
勝太郎は抗議しようと一歩まえにでかけたが、あさ子がそれを制して木剣を手渡した。
「さがっていなさい、相手は成人した武家です。あなたと揉めたら斬りあいになってしまうでしょう。ここは私が」
「しかし――」
「いいから見ていなさい。手をだしは一切無用ですよ。わかりましたか」
「は、はい……」
しぶしぶ引きさがった勝太郎をのこし、あさ子が無遠慮にすたすたと歩みよった。
「河原は不在です。命により今朝がた発ちました。かわりに家をあずかる私がご用を承りましょう」
「奥方は我らを侮られるか。嘘を申されては困る」
「さてはて、私の聞き間違いでしょうか。いま、私が嘘をついていると謗られましたな」
「女子と言い争うつもりはない。にしても、奥方を対応にださせ屋敷のなかに隠れているとは、いかにも戦を恐れて会津の武名をおとしめんとする御奉行殿らしい。これ以上の問答は無用、中をあらためさせてもらう」
踵をかえした二人のまえに、あさ子がさっとまわりこんで立ちふさがった。
それがあまりにも素早かったので、男たちはそろって意表をつかれた顔になりはしたが、顔に包帯を巻いた侍が虻でも追いはらうような仕草で押し退けようとした。
が、肩に触れるやいなや、
「無礼者!」
女の気合にみちた声とともに視界がぐるりとまわり、背中を石畳にたたきつけられた。受身をとりそこなったので体がしびれて動けなくなる。
「何をするか」
もう一人が左手であさ子の肩を後ろからつかんだのだが、いや、つかもうとしたはずがすでに懐のなかにもぐりこまれていたので驚かされた。
はっと息を飲んだ瞬間、女のものとは思えない激しい衝撃を身に浴び、やはり石畳のうえに背から落ちていた。
渾身の体当たりをされ、身が浮いたところで足を掬われたのだ。
いくら負傷をした者たちとはいえ、戦経験のある兵二人がまたたく間に地に伏せられたのだ。はたから見ていた勝太郎は、母のあざやかな手際におどろくばかりである。また、自分はそこまで弱くないのかも知れない、などとも思えた。
とうのあさ子はとどめをさすわけでもなく片膝をおとし、頭をさげて静かな声音で諭すように言った。
「日光口の戦に出兵なされた方々とお見受けいたします。国家のため、宰相様のおんため、また会津の安寧のため、身を賭して城下をお守りいただきましたこと、城下の娘子たち一同は心より敬仰し、どんなに感謝を申し上げても足りぬほどです」
やっと起きあがった侍たちは、驚いてたがいの顔を見あう。
「――なれど、その心は河原も同じであります。河原は臆病者でも、卑怯者でも、ましてや戦を恐れているのでもありませぬ。御家老の梶原様とともに皆さまがお使いになられる武備をぬかりなく整えつつ、かたわらで奥羽諸藩との交渉に奔走する最中なのです。これは宰相様の上意に沿うものであって、古来より諜略と兵站は兵法において欠かせぬもの。戦ははじまった時にはすでに勝敗が決しているともいいます。つまり備えこそ要、備えあっての談判、談判が決裂したときこそ戦場におりて雌雄を決するのが武家というものではありますまいか。したがいまして河原は、断じて皆さまがご心配をなされているような二心をいだいているというわけではござりませぬ」
なぜだか知れないが、この女から見事に投げ飛ばされてしまったし、兵法の正論まで聞かされた。抗議にきたつもりが、つぎにどのような態度をとったらよいのかわからなくなった侍たちは、もののけを見るような心地すらおぼえていた。
するとそこによく聞きなれた野太い声が、門口からにぎやかに響いてきた。
「だから言わんことではない。こうなるからやめておけと儂は止めたのに、なぜ素直に聞き入れなかった。どうだ、すこしは目が覚めたであろう」
嬉々とした態でやってきたのは、戦支度の高津仲三郎だった。
「お前たち二人は若いから知らぬであろうが、この河原屋敷の奥方を誰と心得るか。なんと、あの鬼瓦殿の愛娘様であらせられるぞ」
「えっ……」
それがどれほど存外であったものか、二人は目をまるくさせ顔面蒼白となって居直った。
ついさっきまでの態度とあまりの豹変ぶりに、勝太郎は噴きだしそうになって笑いをこらえた。
呆れたように仲三郎が諭す。
「ゆえに梶原様や河原殿が、宰相様の御首をみすみす薩長土に差しだすつもりのはずがなかろう。そんなものは家中と世をよくわきまえぬ者らが勝手にめぐらせた下衆の勘ぐりにすぎない。惑わされるな、おちついて智恵をめぐらせよ。河原殿は公用方として公事奉行として京で七年も勤め、幕府や諸国、公卿の重役とわたりあい、鳥羽伏見でお義父上と旧友を亡くされた。その憤懣やるかたないお気持ちなど、お前らにはわかるまい。わからないことがわかったのなら、さっさと河原殿の奥方に非礼を侘びて病院で大人しくしているがいい。さきに前線へでて待っているから、癒えたときには出てきて存分にはたらけ。それこそ我ら武官の奉じるべき役目であって、同胞に疑いの矛先を向けることではない」
侍たちは目がさめたように丁重な詫びを述べて帰っていったが、あさ子は門前まで見送り、お大事にと言ったものである。
仲三郎が大きな体を小さく丸めて謝った。
「すまぬ、おあさ。あの二人はとくに激烈な部類で儂にも止めきれなかった。目を離したすきに病院をぬけだしていて、ここへ押しかけてしまった」
あさ子がクスリと笑って首を横にふる。
「いいえ、お気になさらず。もう慣れっこですから」
「なにっ、こうしたことはよくあるのか」
「ええ、これで河原に会わせろと訪ねてきたのは四組目、もうかれこれ九人目になります。話してもお引とりをいただけない場合は、今日のようにわざと挑発をして投げ飛ばしてきました。さすがに女相手に抜刀なさる方はなく、負けたとなれば恥じて他人には言えますまい」
「なるほど、そうか。ハハ、これは驚いた。そうだな、たしかに情けなくて人には言えなくなる。さすがは源さんゆずりの腕前だ、ガハハ」
源右衛門が亡くなってから、河原家のことを気にかけた宝蔵院流の猛者たちがたびたび訪ねてくるようになった。
日新館と家中に名をとどろかせた男たちが、あさ子のまえに来ると心をゆるして親しげに笑っている。
それが勝太郎にとっては不思議であり、母のことが誇らしくも思えるのだった。
地に片膝をおとしていた勝太郎は、肩を大きく上下さげて息をあらげ、のどにこみ上げてきたすっぱいものをぐっと飲みこんで押しもどす。
ふらつきながら立ちあがり、ふたたび木剣を正眼に置いた。
いましがた打たれた腹がじんと痛み、剣先がゆれる。今日はかれこれ七回も斬りたおされたのだから無理もない。
「なんの、私はまだまだやれますよ……母上」
三間むこう、木剣をひっさげて仁王立ちで待っていたあさ子は、無言のままうなずくと腰を深く半身にしずめ、脇にかまえて応じた。
「兄上、がんばれ。母さまにまけるな!」
縁側から稽古を見守っていた国子が、かわいらしい声援をおくってくれる。祖母の菊子と弟の勝治も見ている。
もうこれ以上、ぶざまな負け姿をみせるわけにはゆかない。
いくら母がなみなみならぬ腕前とはいえ、しょせんは女子だ。男として兄として、何としても一本はとってやりたいところだ。
父の善左衛門が京都守護職で出張中のあいだ、勝太郎は剣術をならいはじめた。本来ならば憧れの佐々木只三郎とおなじ精武流にするはずだったが、いかんせん武寮のおもだった使い手たちは京出張で忙しい。
城下には高齢となったが涼斎もいるし、稽古相手に困らないという理由により母や祖父とおなじ安光流をえらんだのだった。
勝太郎はまだ元服まえの十五歳。前髪つきの横顔はあどけない。
悔しげに歯をくいしばり、正眼から上段にうつした木剣の手のうちを絞りなおした。
「えいッ」
その年にしては鋭い太刀筋だった。母の動きにも似た、滑るように深い踏みこみに導かれ、カツンッ――と木剣が割れんばかりに当たる。
が、あさ子はやすやすと受け、からめて切り落とし、いいようにあしらわれた勝太郎が前後に揺れてたたらを踏んだ。
さらに足絡み、鳩尾への肘うち。後ろへひっくりかえりそうになった勝太郎が、思わず諸手をあげてしまった。
「甘い!」
がら空きになった腹に、水平に旋風のような一刀がどっと入った。
「うっ……」
臓物が上下に割れたような心地がして、苦悶の表情にかわった勝太郎は、息をつまらせて背を丸めた。
それでもあさ子は追撃の手をゆるめない。ひらりと身を旋回させて脚を打ち、背を打ち、勝太郎が顔を歪めて両膝をおとした。
「膝を落とすなと言いました」
そして首元へヒタリと木剣を乗せ、脈を断つようにすぅ――とゆっくり引いた。
またしても万事休す、首をとられた。
武芸者のきびしい眼光をたもったまま、あさ子がつきはなすように言った。
「もしもここが戦場ならばあなたは何もできないまま、むざむざと死んだことになります。これは無駄死にというものです」
「はい……」
「どうして止めを刺されるまえに組み付かなかったのですか。脚が動かなければ、倒れながら噛みつくこともできたはずです」
「それは、あまりに無作法ではないかと……」
「いいえ。演武は演武、戦場は戦場です。日新館で教授される稽古場にかぎったお行儀のよい剣法では、実戦のときは役にたちませぬ。日ごろの稽古はだいじな時にそのままあらわれるもの。行住坐臥、いつも戦場にあると心得なさい、緊張を保ちなさい。それが武家というものです」
「はい……しかと肝に銘じます」
この一月に鳥羽伏見の戦で外祖父の原源右衛門が戦没した。以来、あさ子の稽古はより一層激しさを増した。
源右衛門は齢五十をすぎてもなお仁王のような体格をした人であったが、孫たちにはとても優しいおじいさんだったから、勝太郎にとっても衝撃的だった。
風雲急をつげるいま、母がきびしくしてくれるのはもちろん己のことを思ってくれているのだと勝太郎も承知をしているが、袋竹刀と防具を用いずに木剣で仕合をするのだからたまったものではない。日新館でも木剣の仕合などは危険がともなうので滅多にやらないものだ。
しかも禁じ手はなし。柔の技をくみあわて何でもありだ。つばぜり合いをしていると肘を入れてくるし、先日は指をとられて折られかけた。
今日こそは一本を取ってやろうと覚悟をさだめ、工夫を凝らしたつもりだったがまったく及ばない。逆に八本も取られて何もさせてもらえなかった。
すでに全身が痣だらけになり、腕が痛くてあがらない。まるで猫の手の内にもてあそばれる鼠のようだったのは前回とおなじで、すっかり自信を喪失させられてしまった。
ゆっくりと歩みよってきたあさ子が、両方の口角を釣りあげ、にっこりと微笑んだ。童のときのように勝太郎を立たせ、稽古袴についた土をはらいながら言った。
「――前回より太刀筋が一段と鋭くなりましたね」
「ほ、本当ですか」
「ええ。腕と腰の力もつよくなりました。私から一本をとるのも、もうすぐのことだと思いますよ。はげみなさい。河原家の男子として、旦那様のように京や江戸まで名を轟かすのです」
「はい、精進いたします!」
するともう一人、生意気にも襷掛けに白鉢巻をした小僧が、木剣を手に名乗りでた。
「母上、私にもご教授をお願いします!」
次男の勝治だ。十歳になる。
「まぁ、勇ましいですこと」
まだ満足にふれない木剣をもちだして来たのは、兄に母をとられてしまった心地がして、張り合ったつもりでいるのだろう。
武家の男子として、たくましく成長しようとしている子供たち。あさ子にとってこれほど喜ばしいことはない。
二人とも抱きしめてやりたくなったが、うなずいて武芸者の顔にもどった。
「よく言いました。では母が稽古をつけてさしあげましょう。ですが剣を手にしたからには、これより母のことを敵と思うのです。命を賭して戦う敵です。勝治にはそれができますか」
「はい、できます!」
「よろしい。では打ちこんできてごらんなさい」
そうした熱気にみちみちた稽古がつづくさなか、開け放っていた門から唐突に不穏な気配がはいってきたとあさ子は気づいた。
「また、来たのね――」
背で察知して手をとめ、振りかえりざまに睨みつけた。
河原屋敷の門口にあらわれたのは、二人の侍だった。いずれも二十半ばで大柄、見知らぬ顔であるが、装いからして士中の者であると見てまちがいない。一人は右腕に包帯を巻いて吊り、もう一人は顔半分を包帯でくくりびっこを引いている。
あれは戦傷者だ。日新館の病院からやってきたのだろう。
ほどなく応接にでた伊右衛門と押し問答をはじめたのが見えた。肩をつきとばされた伊右衛門はよろめいて地に尻もちをついた。
そこへあさ子と勝太郎が急ぎ足で詰めよる。
「無礼でありましょう。何の用ですか」
憎悪をむきだしにした二人が、あさ子を一瞥してぞんざいに用向きをつげた。
「我らは別撰隊の者。奥方に用はござらん。国産奉行の河原殿に面会を願っただけであったが、この老いぼれが駄目だ、帰れという。無礼なのはこ奴のほうでありましょう。中間ふぜいが、斬り捨てられぬだけありがたいと思っていただきたい」
「…………」
勝太郎は抗議しようと一歩まえにでかけたが、あさ子がそれを制して木剣を手渡した。
「さがっていなさい、相手は成人した武家です。あなたと揉めたら斬りあいになってしまうでしょう。ここは私が」
「しかし――」
「いいから見ていなさい。手をだしは一切無用ですよ。わかりましたか」
「は、はい……」
しぶしぶ引きさがった勝太郎をのこし、あさ子が無遠慮にすたすたと歩みよった。
「河原は不在です。命により今朝がた発ちました。かわりに家をあずかる私がご用を承りましょう」
「奥方は我らを侮られるか。嘘を申されては困る」
「さてはて、私の聞き間違いでしょうか。いま、私が嘘をついていると謗られましたな」
「女子と言い争うつもりはない。にしても、奥方を対応にださせ屋敷のなかに隠れているとは、いかにも戦を恐れて会津の武名をおとしめんとする御奉行殿らしい。これ以上の問答は無用、中をあらためさせてもらう」
踵をかえした二人のまえに、あさ子がさっとまわりこんで立ちふさがった。
それがあまりにも素早かったので、男たちはそろって意表をつかれた顔になりはしたが、顔に包帯を巻いた侍が虻でも追いはらうような仕草で押し退けようとした。
が、肩に触れるやいなや、
「無礼者!」
女の気合にみちた声とともに視界がぐるりとまわり、背中を石畳にたたきつけられた。受身をとりそこなったので体がしびれて動けなくなる。
「何をするか」
もう一人が左手であさ子の肩を後ろからつかんだのだが、いや、つかもうとしたはずがすでに懐のなかにもぐりこまれていたので驚かされた。
はっと息を飲んだ瞬間、女のものとは思えない激しい衝撃を身に浴び、やはり石畳のうえに背から落ちていた。
渾身の体当たりをされ、身が浮いたところで足を掬われたのだ。
いくら負傷をした者たちとはいえ、戦経験のある兵二人がまたたく間に地に伏せられたのだ。はたから見ていた勝太郎は、母のあざやかな手際におどろくばかりである。また、自分はそこまで弱くないのかも知れない、などとも思えた。
とうのあさ子はとどめをさすわけでもなく片膝をおとし、頭をさげて静かな声音で諭すように言った。
「日光口の戦に出兵なされた方々とお見受けいたします。国家のため、宰相様のおんため、また会津の安寧のため、身を賭して城下をお守りいただきましたこと、城下の娘子たち一同は心より敬仰し、どんなに感謝を申し上げても足りぬほどです」
やっと起きあがった侍たちは、驚いてたがいの顔を見あう。
「――なれど、その心は河原も同じであります。河原は臆病者でも、卑怯者でも、ましてや戦を恐れているのでもありませぬ。御家老の梶原様とともに皆さまがお使いになられる武備をぬかりなく整えつつ、かたわらで奥羽諸藩との交渉に奔走する最中なのです。これは宰相様の上意に沿うものであって、古来より諜略と兵站は兵法において欠かせぬもの。戦ははじまった時にはすでに勝敗が決しているともいいます。つまり備えこそ要、備えあっての談判、談判が決裂したときこそ戦場におりて雌雄を決するのが武家というものではありますまいか。したがいまして河原は、断じて皆さまがご心配をなされているような二心をいだいているというわけではござりませぬ」
なぜだか知れないが、この女から見事に投げ飛ばされてしまったし、兵法の正論まで聞かされた。抗議にきたつもりが、つぎにどのような態度をとったらよいのかわからなくなった侍たちは、もののけを見るような心地すらおぼえていた。
するとそこによく聞きなれた野太い声が、門口からにぎやかに響いてきた。
「だから言わんことではない。こうなるからやめておけと儂は止めたのに、なぜ素直に聞き入れなかった。どうだ、すこしは目が覚めたであろう」
嬉々とした態でやってきたのは、戦支度の高津仲三郎だった。
「お前たち二人は若いから知らぬであろうが、この河原屋敷の奥方を誰と心得るか。なんと、あの鬼瓦殿の愛娘様であらせられるぞ」
「えっ……」
それがどれほど存外であったものか、二人は目をまるくさせ顔面蒼白となって居直った。
ついさっきまでの態度とあまりの豹変ぶりに、勝太郎は噴きだしそうになって笑いをこらえた。
呆れたように仲三郎が諭す。
「ゆえに梶原様や河原殿が、宰相様の御首をみすみす薩長土に差しだすつもりのはずがなかろう。そんなものは家中と世をよくわきまえぬ者らが勝手にめぐらせた下衆の勘ぐりにすぎない。惑わされるな、おちついて智恵をめぐらせよ。河原殿は公用方として公事奉行として京で七年も勤め、幕府や諸国、公卿の重役とわたりあい、鳥羽伏見でお義父上と旧友を亡くされた。その憤懣やるかたないお気持ちなど、お前らにはわかるまい。わからないことがわかったのなら、さっさと河原殿の奥方に非礼を侘びて病院で大人しくしているがいい。さきに前線へでて待っているから、癒えたときには出てきて存分にはたらけ。それこそ我ら武官の奉じるべき役目であって、同胞に疑いの矛先を向けることではない」
侍たちは目がさめたように丁重な詫びを述べて帰っていったが、あさ子は門前まで見送り、お大事にと言ったものである。
仲三郎が大きな体を小さく丸めて謝った。
「すまぬ、おあさ。あの二人はとくに激烈な部類で儂にも止めきれなかった。目を離したすきに病院をぬけだしていて、ここへ押しかけてしまった」
あさ子がクスリと笑って首を横にふる。
「いいえ、お気になさらず。もう慣れっこですから」
「なにっ、こうしたことはよくあるのか」
「ええ、これで河原に会わせろと訪ねてきたのは四組目、もうかれこれ九人目になります。話してもお引とりをいただけない場合は、今日のようにわざと挑発をして投げ飛ばしてきました。さすがに女相手に抜刀なさる方はなく、負けたとなれば恥じて他人には言えますまい」
「なるほど、そうか。ハハ、これは驚いた。そうだな、たしかに情けなくて人には言えなくなる。さすがは源さんゆずりの腕前だ、ガハハ」
源右衛門が亡くなってから、河原家のことを気にかけた宝蔵院流の猛者たちがたびたび訪ねてくるようになった。
日新館と家中に名をとどろかせた男たちが、あさ子のまえに来ると心をゆるして親しげに笑っている。
それが勝太郎にとっては不思議であり、母のことが誇らしくも思えるのだった。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
4
この作品の感想を投稿する
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる