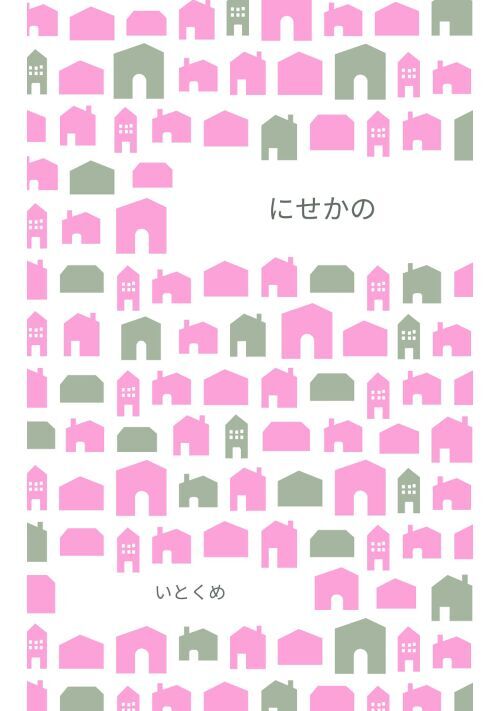56 / 145
本編第五章:宴会編
第八十三話「料理長の考え」
しおりを挟む
トーレス王国の王宮では魔王アンブロシウスら魔王国関係者、更にゴウとウィスティアを労う晩餐会が開かれていた。
宮廷料理長ユアン・ハドリーは国王アヴァディーンがゴウのことを“稀代の美食家”と言ったことに戦々恐々としながら、中華風の料理を出していく。
この料理は流れ人によって伝えられたものだが、気候風土が近い大陸の東にあるスールジア魔導王国で最も受け入れられていた。逆にトーレス王国を含む西側の国々では、食材や味付けの好みの違いから、あまり広まっていない。
但し、トーレス王国の王都ブルートンだけは事情が異なる。
元々トーレス王国は海路を通じ、スールジア魔導王国との交易が盛んで、王都には少ないながらも中華風の料理店があった。
王宮でも過去にスールジア魔導王国関係者が持ち込んだ料理に魅了された王がおり、スールジアの料理が積極的に取り入れられている。
そのため王宮にはスールジアから招聘した専属の料理人もおり、食材や調味料も常時取り揃えられていた。
宮廷での料理の総指揮を執るハドリー料理長も当然、中華風の料理に関する知識は十分に有している。
今回料理長が中華風の料理を晩餐に取り入れた理由は以下のようなものだ。
まず魔王たちが食べたことがない料理を提供することだ。ハイランドの王都ナレスフォードで魔王たちはハイランドやトーレスといった西側の料理を食べている。また、迷宮都市グリーフに赴いていることから、マシュー・ロスの和食を食べている可能性があると考えた。
中華風の料理はナレスフォードでもグリーフでも一般的ではなく、この料理を出せば魔王たちの興味を引けると考えたのだ。
二つ目の理由はゴウに対するものだ。彼の足跡をすべて把握しているわけではないが、少なくともトーレス王国に入ってから中華風の料理を食べる機会はなかった。
また、トーレスの料理や和食では既に迷宮産の高級食材を使ったものを食べている。腕で負けるつもりはなかったが、国王直々の命題である感動させるという点からすれば、同じ食材を使った二番煎じでは難しいと考えた。
今回、料理長は三皿目までの材料をあえて迷宮産のものにしなかった。
これは魔王国に輸出する食材を選んだためだが、それ以上にゴウに対し食材で勝負するより料理の腕や酒との相性、更には意外性といった要素で勝負したいと考えたからだ。
そして、その目論見の一部は成功していた。ゴウが満足げにそれらの料理を食べ、小籠包が好物であると知った時には内心で喜びを噛み締めている。
しかし、給仕が聞いた話から落胆もしていた。
カニ焼売を食べた時、日本酒がほしいと言ったと聞いたからだ。
(やはり白ワインではなく、サケにすべきだったか……)
料理長はその話を聞き、自分の選択に誤りがあったことを知った。実際、直前まで悩んでいたことだったのだ。
(小籠包には白ワインの方が確実に合う。しかし、カニ焼売はカニの風味が強い分、海産物に合うサケの方が合うことが多い。蒸し料理で二種類の酒を出すのは多いと思ったが、選択を誤ったようだな……)
料理の量に対し、ワインとサケの二種類を出すと多すぎると思い、より合うと考えた白ワインを出したが、それが裏目に出た形だ。
それでも気を取り直して三皿目の状況を部下に確認する。
「黄ハタの蒸し上りはあとどのくらいだ」
「一、二分です。既に油の準備も始めています」
蒸し器の横では油が熱せられ始めている。
「よろしい。既に次の酒が準備されているはずだ。蒸し上り次第、運び込むぞ」
料理長は演出も考えていた。
最後の仕上げを客に出す直前に行うことは香りを引き出すために必要なことだが、国王が主催の晩餐では厨房の中で仕上げ、取り分けてから運び込むことが多い。これは通常の晩餐では、主役はあくまで情報交換を目的とした会話であり、料理は脇役に過ぎないためだ。
しかし、今回の晩餐は料理が主役だ。特にゴウの知識がどの程度かを見極めつつ、喜ばせるには派手な演出もありだと考えたのだ。
料理を運び込んだ時、ゴウが蒸すという料理法について説明を行っていた。その説明を聞き、その知識の豊富さに舌を巻く。
(それにしてもこの知識量は恐ろしいほどだ。どうやら私の思惑も完全に読まれているようだな……)
次の料理の準備があるが、ゴウのコメントが気になり、彼が食べるまで待っていた。
そして、料理長自らが選んだ酒、フェニックスバイデンを絶賛したのを見て安堵する。
(スールジアでは白ワインを合わせることが多いと聞くが、地元の酒にして正解だった。しかし、シャーロックまで飲んでいるとはな……そうか! マシュー・ロスの店を貸し切りにしたという話だったな。彼ならシャーロックにはワイングラスを使ってくる。このやり方で驚きは得られなかったが、味で満足してくれたのでよかったと思うことにしよう……)
そんなことを考えるが、すぐに次の料理、メインディッシュのミノタウロスチャンピオンの石窯焼きの仕上げを確認しに厨房に戻る。
「最後の確認をお願いします」と部下が告げると、五本の細い串が放射状に打たれた肉の塊を確認する。
肉は一キログラムほどの塊で、最高級の木炭でじっくり火を通してある。もちろん、中は生ではなくギリギリのレアになるように調整しており、その確認を今から行うのだ。
一本の細い串を肉に刺す。そしてそれを引き抜き、唇に当てた。温度を確認した彼は小さく頷くと、
「これでいい。では、すぐに運ぶぞ」と命じた。
運び込むと既にワインの話で盛り上がっていた。
このブルートンのワインも料理長自らが選んだものだ。選んだ理由は単純に最も合うということもあるが、ハイランドにおいて、ゴウがミノタウロスチャンピオンの肉にビールを合わせ、“失敗した”と語ったことも理由の一つにある。
表面の焦げを丁寧に削ぎ落していく。石窯の中でじっくりと炭火で焼くため、どうしても表面の一部、特に角の部分は焦げてしまうためだ。
今回用意した調味料はシンプルなものばかりだ。通常の牛肉の場合、赤ワインや肉汁を使ったソースをかけることが多いが、肉本来の味を楽しむために焼き方だけでなく、調味料にも拘ったのだ。
そして、シンプルに肉の味で勝負するという今回の作戦は見事に決まった。
今までの料理では饒舌に解説していたゴウが無言になったのだ。
更にワインと合わせた時には自分にはこの組み合わせはできないと言わせることもできた。
この時、料理長は心の中で大きく安堵の息を吐き出していた。
最初の三皿は変化球と言えるものだが、メインの肉は素材、調理法、調味料、そして合わせる酒と、すべて直球で勝負している。これが認められなかったら、自分の腕に自信を無くすところだった。
最後のデザートまで好評で、料理長は肩の荷が下りたと表情を緩めた。
その時、ゴウから「一つ料理長に確認したいのですが」と質問されたが、油断していたため、「どのようなことでしょうか」と構えるように聞いてしまう。
「いえ、大したことではないんです」とゴウは苦笑し、
「今回の料理の意図と言いますか、最初の三皿を中華風の蒸し料理にした理由を聞かせていただきたいと思いまして」
その言葉に安堵するが、表情を引き締めて答えていく。
「三つ理由がございます。アンブロシウス陛下がご存じないであろう料理としたかったことが第一です。陛下にはいろいろな料理法があることを知っていただきたいと思ったのです」
「なるほど」
「二つ目は地元の素材をシンプルに味わっていただく方法として蒸すという方法を選びました。このことはエドガー殿が既に説明されている通りでございます」
「確かに素材の味をシンプルに味わうにはいい方法ですね。最初の理由と合わせれば、自然と中華風の蒸すという調理法になりますが、三つ目は何でしょうか?」
「エドガー殿に食べていただきたかったというものです」
「私に、ですか?」とゴウは驚く。
「はい。エドガー殿の噂はいろいろと耳にしております。我が国の料理、隣国のハイランド料理、ジン・キタヤマの広めたワショク、鉄板焼きといった庶民的なものまで、その知識は多岐に渡り、料理と酒に関する知識の豊富さは彼の天才、マシュー・ロス氏に“教えを請いたい”と言わしめるほどと。ですので、今回の料理が貴殿の満足いくものであったのか、率直な意見を伺いたいと思ったのです」
「つまり、私を試したと」と言って表情を硬くする。
「いいえ、それは違います!」と料理長は慌てて否定する。
「確かに今回の料理は変則的なものでした。ですが、私としては最高の料理を提供させていただいたと自負しております」
「その点は私も同じ意見ですよ」
「私は料理長として厨房の指揮を執っておりますが、専門はトーレス料理でございます。もちろん、宮廷料理長として様々な料理について日々研究し、研鑽を積んでいるつもりです。ですが、実際に様々な料理を食べておられる美食家の意見を聞いたことがございません」
「ブルートンにはアヴァディーン陛下を始め、多くの美食家がいらっしゃると思いますが?」
「もちろん、陛下を始めとした王家の方々の意見は参考にさせていただいております。ですが、私の料理を初めて食される美食家の方に、率直な意見を伺いたかったのです。私の今までの知識や考え方が正しかったのか、それを確かめるために」
料理長をフォローするようにアヴァディーンが発言する。
「エドガー殿を唸らせるような料理を頼むと余が頼んだのだ。本来であれば、自らの得意料理で勝負したかったのだろうが」
「なるほど。なので、メインがシンプルな石窯焼きの肉だったのですね」
「その通りです。石窯焼きはトーレス王国やハイランド連合王国でよく使われる手法でございます。火の入れ方次第では素材を殺してしまうことすらある調理法ですが、私の得意とする調理法でもあります」
そこでゴウの表情が緩む。
「分かりました。今回の料理は素晴らしいものでした。最初の三皿からメインへの連携も耳でこそ違和感を覚えましたが、食べてみたら全く違和感はありませんでした。それどころか、この流れが一番良いと思うほど感動しました。今度は是非とも料理長の自慢の料理をいただきたいものです」
料理長は「ありがとうございます」と大きく頭を下げ、そこで小さく安堵の息を吐き出した。
一時はゴウの不興を買ったと思ったからだ。
「うむ。我もユアンの料理をもう一度食べたいぞ」とウィスティアがいった。
「その折には同席させてもらいたいものだ。余も今回の料理には感動したのでな」
魔王がそう言うと料理長はもう一度大きく頭を下げる。
「次はミノタウロスエンペラーとレッドコカトリス、ブルーサンダーバードを頼むぞ。カールとマシューにも渡すつもりじゃが、そなたにも調理してもらいたいのじゃ」
ウィスティアの言葉に「「それはよい!」」とアヴァディーンと魔王が同時に声を上げる。
しかし、料理長は困惑の表情を浮かべていた。
「えっ? エンペラーとは? レッドコカトリス? ブルーサンダーバードとは何のことでしょうか?」
聞いたことがない魔物の名に混乱していたのだ。
「我らがスタンピードで狩った新たな魔物じゃ。いずれも変異種らしくての。上位種より美味いのではないかと思っておる」
ウィスティアの言葉に「変異種……」と絶句する。
今回使ったミノタウロスチャンピオンですら、数年に一度扱うかどうかという貴重な食材だ。ブラックコカトリスも滅多に入らない食材だが、それ以上にサンダーバードは宮廷料理長の彼ですらほとんど目にしたことがない幻の食材だ。
それよりも稀少である変異種と聞き、目の前が真っ暗になる。
「気にせずともよい。エンペラーも百キロ以上あるし、レッドもブルーも数十キロはあったはずじゃ。いろいろと試してから最高の料理を作ってくれればよいのじゃ」
「試してから……」と言葉を失う。
彼の常識ではミノタウロスチャンピオンの肉が一キロ一万ソル(日本円で百万円)でも買えず、サンダーバードは少なくともその数倍はすると言われている。それよりも高級な食材を一般の肉と同じような感覚で話しているウィスティアに返す言葉が見つからなかったのだ。
「彼女の言う通りですよ。こんな機会は滅多にないと楽しむくらいの気持ちでお願いしますね」
ゴウの言葉に「楽しむ、でございますか……」と答え、そこで気持ちを切り替えた。
「分かりました。私の持つすべての技量、知識で必ずやご満足いただける料理を作ってみせます」
パチパチという拍手の音が響く。
料理長の決意にアヴァディーンが拍手をし始めたのだ。
「その決意見事。余も期待しておるぞ」
その言葉に料理長は再び大きな課題を与えられたと気づいた。
宮廷料理長ユアン・ハドリーは国王アヴァディーンがゴウのことを“稀代の美食家”と言ったことに戦々恐々としながら、中華風の料理を出していく。
この料理は流れ人によって伝えられたものだが、気候風土が近い大陸の東にあるスールジア魔導王国で最も受け入れられていた。逆にトーレス王国を含む西側の国々では、食材や味付けの好みの違いから、あまり広まっていない。
但し、トーレス王国の王都ブルートンだけは事情が異なる。
元々トーレス王国は海路を通じ、スールジア魔導王国との交易が盛んで、王都には少ないながらも中華風の料理店があった。
王宮でも過去にスールジア魔導王国関係者が持ち込んだ料理に魅了された王がおり、スールジアの料理が積極的に取り入れられている。
そのため王宮にはスールジアから招聘した専属の料理人もおり、食材や調味料も常時取り揃えられていた。
宮廷での料理の総指揮を執るハドリー料理長も当然、中華風の料理に関する知識は十分に有している。
今回料理長が中華風の料理を晩餐に取り入れた理由は以下のようなものだ。
まず魔王たちが食べたことがない料理を提供することだ。ハイランドの王都ナレスフォードで魔王たちはハイランドやトーレスといった西側の料理を食べている。また、迷宮都市グリーフに赴いていることから、マシュー・ロスの和食を食べている可能性があると考えた。
中華風の料理はナレスフォードでもグリーフでも一般的ではなく、この料理を出せば魔王たちの興味を引けると考えたのだ。
二つ目の理由はゴウに対するものだ。彼の足跡をすべて把握しているわけではないが、少なくともトーレス王国に入ってから中華風の料理を食べる機会はなかった。
また、トーレスの料理や和食では既に迷宮産の高級食材を使ったものを食べている。腕で負けるつもりはなかったが、国王直々の命題である感動させるという点からすれば、同じ食材を使った二番煎じでは難しいと考えた。
今回、料理長は三皿目までの材料をあえて迷宮産のものにしなかった。
これは魔王国に輸出する食材を選んだためだが、それ以上にゴウに対し食材で勝負するより料理の腕や酒との相性、更には意外性といった要素で勝負したいと考えたからだ。
そして、その目論見の一部は成功していた。ゴウが満足げにそれらの料理を食べ、小籠包が好物であると知った時には内心で喜びを噛み締めている。
しかし、給仕が聞いた話から落胆もしていた。
カニ焼売を食べた時、日本酒がほしいと言ったと聞いたからだ。
(やはり白ワインではなく、サケにすべきだったか……)
料理長はその話を聞き、自分の選択に誤りがあったことを知った。実際、直前まで悩んでいたことだったのだ。
(小籠包には白ワインの方が確実に合う。しかし、カニ焼売はカニの風味が強い分、海産物に合うサケの方が合うことが多い。蒸し料理で二種類の酒を出すのは多いと思ったが、選択を誤ったようだな……)
料理の量に対し、ワインとサケの二種類を出すと多すぎると思い、より合うと考えた白ワインを出したが、それが裏目に出た形だ。
それでも気を取り直して三皿目の状況を部下に確認する。
「黄ハタの蒸し上りはあとどのくらいだ」
「一、二分です。既に油の準備も始めています」
蒸し器の横では油が熱せられ始めている。
「よろしい。既に次の酒が準備されているはずだ。蒸し上り次第、運び込むぞ」
料理長は演出も考えていた。
最後の仕上げを客に出す直前に行うことは香りを引き出すために必要なことだが、国王が主催の晩餐では厨房の中で仕上げ、取り分けてから運び込むことが多い。これは通常の晩餐では、主役はあくまで情報交換を目的とした会話であり、料理は脇役に過ぎないためだ。
しかし、今回の晩餐は料理が主役だ。特にゴウの知識がどの程度かを見極めつつ、喜ばせるには派手な演出もありだと考えたのだ。
料理を運び込んだ時、ゴウが蒸すという料理法について説明を行っていた。その説明を聞き、その知識の豊富さに舌を巻く。
(それにしてもこの知識量は恐ろしいほどだ。どうやら私の思惑も完全に読まれているようだな……)
次の料理の準備があるが、ゴウのコメントが気になり、彼が食べるまで待っていた。
そして、料理長自らが選んだ酒、フェニックスバイデンを絶賛したのを見て安堵する。
(スールジアでは白ワインを合わせることが多いと聞くが、地元の酒にして正解だった。しかし、シャーロックまで飲んでいるとはな……そうか! マシュー・ロスの店を貸し切りにしたという話だったな。彼ならシャーロックにはワイングラスを使ってくる。このやり方で驚きは得られなかったが、味で満足してくれたのでよかったと思うことにしよう……)
そんなことを考えるが、すぐに次の料理、メインディッシュのミノタウロスチャンピオンの石窯焼きの仕上げを確認しに厨房に戻る。
「最後の確認をお願いします」と部下が告げると、五本の細い串が放射状に打たれた肉の塊を確認する。
肉は一キログラムほどの塊で、最高級の木炭でじっくり火を通してある。もちろん、中は生ではなくギリギリのレアになるように調整しており、その確認を今から行うのだ。
一本の細い串を肉に刺す。そしてそれを引き抜き、唇に当てた。温度を確認した彼は小さく頷くと、
「これでいい。では、すぐに運ぶぞ」と命じた。
運び込むと既にワインの話で盛り上がっていた。
このブルートンのワインも料理長自らが選んだものだ。選んだ理由は単純に最も合うということもあるが、ハイランドにおいて、ゴウがミノタウロスチャンピオンの肉にビールを合わせ、“失敗した”と語ったことも理由の一つにある。
表面の焦げを丁寧に削ぎ落していく。石窯の中でじっくりと炭火で焼くため、どうしても表面の一部、特に角の部分は焦げてしまうためだ。
今回用意した調味料はシンプルなものばかりだ。通常の牛肉の場合、赤ワインや肉汁を使ったソースをかけることが多いが、肉本来の味を楽しむために焼き方だけでなく、調味料にも拘ったのだ。
そして、シンプルに肉の味で勝負するという今回の作戦は見事に決まった。
今までの料理では饒舌に解説していたゴウが無言になったのだ。
更にワインと合わせた時には自分にはこの組み合わせはできないと言わせることもできた。
この時、料理長は心の中で大きく安堵の息を吐き出していた。
最初の三皿は変化球と言えるものだが、メインの肉は素材、調理法、調味料、そして合わせる酒と、すべて直球で勝負している。これが認められなかったら、自分の腕に自信を無くすところだった。
最後のデザートまで好評で、料理長は肩の荷が下りたと表情を緩めた。
その時、ゴウから「一つ料理長に確認したいのですが」と質問されたが、油断していたため、「どのようなことでしょうか」と構えるように聞いてしまう。
「いえ、大したことではないんです」とゴウは苦笑し、
「今回の料理の意図と言いますか、最初の三皿を中華風の蒸し料理にした理由を聞かせていただきたいと思いまして」
その言葉に安堵するが、表情を引き締めて答えていく。
「三つ理由がございます。アンブロシウス陛下がご存じないであろう料理としたかったことが第一です。陛下にはいろいろな料理法があることを知っていただきたいと思ったのです」
「なるほど」
「二つ目は地元の素材をシンプルに味わっていただく方法として蒸すという方法を選びました。このことはエドガー殿が既に説明されている通りでございます」
「確かに素材の味をシンプルに味わうにはいい方法ですね。最初の理由と合わせれば、自然と中華風の蒸すという調理法になりますが、三つ目は何でしょうか?」
「エドガー殿に食べていただきたかったというものです」
「私に、ですか?」とゴウは驚く。
「はい。エドガー殿の噂はいろいろと耳にしております。我が国の料理、隣国のハイランド料理、ジン・キタヤマの広めたワショク、鉄板焼きといった庶民的なものまで、その知識は多岐に渡り、料理と酒に関する知識の豊富さは彼の天才、マシュー・ロス氏に“教えを請いたい”と言わしめるほどと。ですので、今回の料理が貴殿の満足いくものであったのか、率直な意見を伺いたいと思ったのです」
「つまり、私を試したと」と言って表情を硬くする。
「いいえ、それは違います!」と料理長は慌てて否定する。
「確かに今回の料理は変則的なものでした。ですが、私としては最高の料理を提供させていただいたと自負しております」
「その点は私も同じ意見ですよ」
「私は料理長として厨房の指揮を執っておりますが、専門はトーレス料理でございます。もちろん、宮廷料理長として様々な料理について日々研究し、研鑽を積んでいるつもりです。ですが、実際に様々な料理を食べておられる美食家の意見を聞いたことがございません」
「ブルートンにはアヴァディーン陛下を始め、多くの美食家がいらっしゃると思いますが?」
「もちろん、陛下を始めとした王家の方々の意見は参考にさせていただいております。ですが、私の料理を初めて食される美食家の方に、率直な意見を伺いたかったのです。私の今までの知識や考え方が正しかったのか、それを確かめるために」
料理長をフォローするようにアヴァディーンが発言する。
「エドガー殿を唸らせるような料理を頼むと余が頼んだのだ。本来であれば、自らの得意料理で勝負したかったのだろうが」
「なるほど。なので、メインがシンプルな石窯焼きの肉だったのですね」
「その通りです。石窯焼きはトーレス王国やハイランド連合王国でよく使われる手法でございます。火の入れ方次第では素材を殺してしまうことすらある調理法ですが、私の得意とする調理法でもあります」
そこでゴウの表情が緩む。
「分かりました。今回の料理は素晴らしいものでした。最初の三皿からメインへの連携も耳でこそ違和感を覚えましたが、食べてみたら全く違和感はありませんでした。それどころか、この流れが一番良いと思うほど感動しました。今度は是非とも料理長の自慢の料理をいただきたいものです」
料理長は「ありがとうございます」と大きく頭を下げ、そこで小さく安堵の息を吐き出した。
一時はゴウの不興を買ったと思ったからだ。
「うむ。我もユアンの料理をもう一度食べたいぞ」とウィスティアがいった。
「その折には同席させてもらいたいものだ。余も今回の料理には感動したのでな」
魔王がそう言うと料理長はもう一度大きく頭を下げる。
「次はミノタウロスエンペラーとレッドコカトリス、ブルーサンダーバードを頼むぞ。カールとマシューにも渡すつもりじゃが、そなたにも調理してもらいたいのじゃ」
ウィスティアの言葉に「「それはよい!」」とアヴァディーンと魔王が同時に声を上げる。
しかし、料理長は困惑の表情を浮かべていた。
「えっ? エンペラーとは? レッドコカトリス? ブルーサンダーバードとは何のことでしょうか?」
聞いたことがない魔物の名に混乱していたのだ。
「我らがスタンピードで狩った新たな魔物じゃ。いずれも変異種らしくての。上位種より美味いのではないかと思っておる」
ウィスティアの言葉に「変異種……」と絶句する。
今回使ったミノタウロスチャンピオンですら、数年に一度扱うかどうかという貴重な食材だ。ブラックコカトリスも滅多に入らない食材だが、それ以上にサンダーバードは宮廷料理長の彼ですらほとんど目にしたことがない幻の食材だ。
それよりも稀少である変異種と聞き、目の前が真っ暗になる。
「気にせずともよい。エンペラーも百キロ以上あるし、レッドもブルーも数十キロはあったはずじゃ。いろいろと試してから最高の料理を作ってくれればよいのじゃ」
「試してから……」と言葉を失う。
彼の常識ではミノタウロスチャンピオンの肉が一キロ一万ソル(日本円で百万円)でも買えず、サンダーバードは少なくともその数倍はすると言われている。それよりも高級な食材を一般の肉と同じような感覚で話しているウィスティアに返す言葉が見つからなかったのだ。
「彼女の言う通りですよ。こんな機会は滅多にないと楽しむくらいの気持ちでお願いしますね」
ゴウの言葉に「楽しむ、でございますか……」と答え、そこで気持ちを切り替えた。
「分かりました。私の持つすべての技量、知識で必ずやご満足いただける料理を作ってみせます」
パチパチという拍手の音が響く。
料理長の決意にアヴァディーンが拍手をし始めたのだ。
「その決意見事。余も期待しておるぞ」
その言葉に料理長は再び大きな課題を与えられたと気づいた。
応援ありがとうございます!
11
お気に入りに追加
3,539
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。