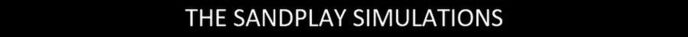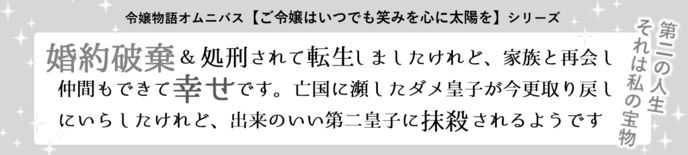10 / 35
Simulation Introduction
九、ムクロヒ領(2)
しおりを挟むこの世のすべての大地とすべての海をいだく強大なる「居神国」。
居神国はさる惑星における人類の平行世界。
最も近しい例を上げれば、日本国における弥生時代にも似た原始国家である。
大きく違うのは、徹底した女系王が管理する女性優位の社会であること。
政治的権力と社会的優位性を持つこと、また継承できるのは女のみ。
男は子種をもたらすだけの家畜である。……
居神国に属するムクロヒ領。
ここに生きるサレという男がこの物語の主人公である。
十七歳のサレは俊敏で運動能力にすこぶる恵まれていた。
とはいえ小柄であったため"宿"の男たちから下に見られ、少ない食料をさらに減らされることがしばしばあり、常に空腹だった。
腹が減ると、サレはこっそり柵を抜け出し、森に入って食べ物を探した。
柵を出ることは当然禁止されていて、兵士に見つかれば即刻殺されることはわかっていた。
それでも、若いサレは空腹の辛さには耐えられなかった。
森での散策に小柄な体系と俊敏さは大いに役立った。
「ねえ、もういいんじゃない? 残りはまた二、三日して取りに来ようよ」
「はあい、三久姉さん。ほら、木久ちゃん、行こう」
「あっ、待って、良久姉さん」
秋の森では自然の恵みを収穫する女たちを頻繁に見かける。
なんと、サレはこれまで一度も見つかったことがなかった。
今もこの三人の娘たちが去った後、クリを収穫しようと身を潜めて待っていた。
サレは女たちのきれいな髪や、明るい糸でつくられた腰紐、すらっとして健康的な手足に見とれることがある。
だが、近づいたりはしない。
見つかれば、兵士を呼ばれて殺される。
サレにとって、女は憧れであると同時に、敵であり畏怖の対象であった。
娘たちが去り、サレは早速クリの木の周りを物色した。
あの娘たちがあらかた採り尽くしていたので、木を揺らして実を落とそうと考えた。
手ごろな枝を取って木によじのぼり、届く枝をびしばしと叩きまくった。
枝が当たると、ぽとんぽとんといがが落ちる。
あのいがからクリの実を外すのは手間だが、それさえやりとげればほっくりと甘いクリの実が食べられる。
サレはその味を思い浮かべて、一生懸命に枝を振った。
そのときだ。
「あっ」
甲高い声に下を見ると、あの三姉妹のひとりが戻ってきていた。
「三久姉さん、木久ちゃん、来て! 男がクリを盗んでる!」
あまりに必死になっていたので気が付かなかった。
慌てて逃げようと駆けだしたが、一番大きい女、大きいといっても二十歳くらいだろうか。
女としては平均的な身長であったが、小柄なサレと比べると頭ひとつ分大きかった。
一番上の三久という娘に首根っこを掴まれ、びたんと大地にたたきつけられた。
「わあ、さすが三久姉さん!」
「あたりまえでしょ、ついこないだまで堀で土方やってたんだから。男の一人二人わけないわ」
サレは必死にもがいたが、今度は二番目の良久に棒で頭を殴られた。
「大人しくしろ! 兵士に突き出す前におまえの金玉つぶしてもいいんだぞ!」
「きゃははっ」
三番目の木久が口に手を当てて笑った。
「木久、ちょっと籠のなかに余分な縄がなかったかい」
「あるよ、はい」
三久から縄を受け取って三久がサレを手際よく縛り上げる。
サレは身動き取れずぶるぶると震えることしかできない。
ぐいっと顔を掴まれた。
「ふうん……」
「ねえ、三久姉さん、番所につき出したらご褒美もらえるんじゃない?」
「かもね。でもその前にちょっといいことを考えたよ」
「なになに? 金玉切り取る? 鉈ならここにあるよ」
ぞっとした。
見た目には愛らしくさえある女たちなのに、なんと残虐なのだろう。
男同士でさえ局部をつぶすだの切り取るだのと言う非道は口にもしない。
「ちがうよ。ちょっとあんたたら、泡草の生えてるところしらないかい?」
「んー、洗濯に使うやつだよね? 木久知ってる」
「じゃああるだけ摘んできておくれ。良久も」
「ええ~?」
「いいから」
「よっぽど面白いことじゃないと、良久は動きたくないなぁ」
「じゃあ、いいことがすんだら良久の好きにさせてあげるよ」
「ふ~ん、じゃあ取ってくる!」
良久と木久が駆け出していくと、三久はサレをぐいと引き上げ、川辺に向かって歩かせた。
しばらくすると、ふたりが泡草を摘んで抱えて戻ってきた。
「はい、これどうするの?」
「これでこの男を洗うのさ」
「あ、ら、う~っ!? 良久こんな汚いのに触りたくない!」
「いいから手伝っておくれ。うまくいったらわたしがあんたたちにご褒美をあげられるかもしれないよ」
「ほんとに~?」
サレはなにがなんだかわからないまま、三人の娘たちに泡草なる野草でごしごしと洗われた。
サレはときどき女たちが河辺べ着物を洗っているのを見たことがあったが、あれはこの草を使っていたのだと初めて分かった。
「さー、こんなもんかね」
頭から足の先までぐいぐいと洗われ、体中小さな擦り傷ができてぴりぴりとする。
だが、淡い花の香りがして心地よくもあった。
「さあこっちだよ」
サレは手を引かれて、森の茂みに連れていかれた。
突き倒されると、三久がその上に馬乗りになった。
「ねえ、三久姉さん、それをどうするの? まさか食べるの?」
「あはは、違うよ。うまくいくかどうか。良久はこいつの手押さえててくれるかい? 木久は誰も来ないように見張ってな」
「え~、木久も見たい」
「いいけど、周りにも気を配っててよ」
「はあい」
三久が突然腰紐を解き、衣を解いた。
「えっ、なにするの、三久姉さん!?」
「こいつから子種をもらうのさ」
「ええっ、こんなのから!?」
「ああ、うまくいけば、廓代が浮くだろう。今年はわたしの番だからね。さっさと妊娠しないと廓代もばかにならないよ」
「で、でも~……」
「いいかい、良久。わたしは子育てより本当はもっと働きたいんだ。でもこれは順番で回ってくる役目だからね。
だからさっさとやって、さっさと生んでしまうのが一番いいのさ」
「そっか~……。三久姉さん、はじめての順番だもんね」
「この前初めて廓に行ったときは、確かこんな感じに……」
三久がサレのいちもつを握った。
秋の冷たい水にさらされ、ふたりの女にとらわれ、サレは恐怖に震えた。
拙い摩擦が局部を刺激するが、とてもではないが立ちそうにない。
「三久姉さん、こいつだめなんじゃないの?」
「そうかなあ……。見た目は廓の"小種"とそんなに変わらないんだけど」
「もう殺す?」
「いや、ちょっと待って。寒すぎるのかもしれない」
そういうと、三久がサレの上に素肌で覆いかぶさってきた。
直に肌と肌から伝わるぬくもり、鼓動。
怯えていたのに、その温かさと重さにサレはまだ生きていることを実感した。
「くふふっ、こいつ泣いてるよ、三久姉さん」
「そりゃあ生き物だから泣くこともあるさ。そら、どうだい?
少しは体があったまってきたろう?」
その言葉に、サレはかつて幼い日に見た女たちの姿を思い出した。
宮殿の中で見たものは、"宿"で暮らすうちに幻だったのだと思うようになっていた。
だが、目の前にある柔らかな女体は、あのときの安心に包まれた日々を思い起こさせた。
「ほら、元気になって来たみたいだね」
「あ、本当だ……」
「その調子だよ。うまくできたらおまえを逃がしてやってもいいよ」
「ええ~?」
「いいだろ、良久。だってうまくいったら良久だってこいつから子種をもらえばいいじゃないか」
「あっ、そっか」
命が助かるかもしれないとわかって、サレはこくこくとうなづいた。
「お、おれ、じぶんで……」
「えっ、おまえしゃべれるの?」
「驚いた。男もしゃべれるなんて知らなかったよ。廓の"小種"もなんにも言わなかったから」
またこくこくとうなづいた
「いま、立たせてみせます……」
サレは自分のものをつかみ、感じやすいところを丹念に刺激した。
少し不安ではあったが、生き残るために、全神経を集中した。
冷え切った体が三久のおかげで熱を取り戻し、しだいに竿がむくむくと立ち上がる。
「はあっ、はあっ……」
「できるんじゃないか。よし」
そういうと、三久は着物のなかからなにかの入れ物を取り出し、それを空けた。
中にはとろみのついた軟膏のようななにかが入っていた。
「なにそれ、姉さん」
「廓通いをすることになって、母さんからもらったんだ。これがなくてもうまくいく人もいるらしいんだけど、慣れないうちはこれを塗るといいって」
「ふうん……」
三久は自分の局部それを塗り込め、さらにサレの竿にも軟膏を塗った。
その滑りの良さに、サレはびくびくと震える。
「あっ……、もう、出そうです……」
「えっ、ちょっと我慢だよ!」
あわてて三久が自らの穴にサレのいちもつを差し込む。
「ん、つ……っ」
「うっ、くっ」
ふたりの結合部に、熱いものが放たれる。
「あ、今のが種だね……?」
「は、はい」
三久が抜こうとすると、心地よい締め付けにあっという間に竿が張り詰める。
「あっ、まだ……っ」
「えっ、まだ? 今さっき」
「でも、まだ出そうで……」
「そうかい」
三久が体勢を整えると、サレにはたまらない刺激となって、全身に喜びが駆け巡る。
三久はまだ慣れていないのか、顔をしかめて発射を待っている。
「す、少し、動いてもいいですか?」
「変な真似をしたら許さないよ!」
良久がぎりっと睨みつけた。
「そうじゃなくて……。つまり、おれのものを差し込んだり抜いたりすると、その、よりうまくできるっていうか……」
「差したり抜いたり? なんだか痛そうだね。今だって結構……。でもそれでうまくいくならやってみて」
「はい。お、おれが上になってもいいですか?」
下の体位から腰を動かすのはかなり難しい。
良久はきわめて気にいらなそうな顔をしたが、三久は承知した。
上下を変えて体制を整える。
「あの、あ、脚をもっとひろげて……」
「こうかい?」
「はい……」
サレの前に広がった景色。
丸みを帯びた輪郭に、柔らかな肌。
男のものとは全く違う局部。
(こ、こんなふうになっているのか……)
その生々しい裂けめの中に、サレは自分を差し入れた。
「あっ……」
「う、うごきます」
「はっ、あっ」
サレが動くたびに、三久が甘い声を上げる。
どうやら、三久の形が今の体位と合っていたらしい。
さっきの体位では痛がって顔をしかめていた三久が、今はとろっと目を潤ませ始めている。
(感じている)
そうわかると、サレも気持ちが奮い立った。
何度も何度も三久の中に進入しては後退し、自分でも心地いい締め付けを甘受した。
放出されるまでの高まりは、今まで感じたことのない喜びであった。
「な、なかないいよ……」
「は、はい……」
これで命は助かったんだと、胸が軽くなる。
すると、脇で見ていた良久が急にぐいとサレの手首を掴んだ。
「次わたし」
「えっ!?」
「良久、あんたはまだ早いよ」
「だって、三久姉さんがあんまりにも気持ちよさそうなんだもん。
わたしだってもう十六だよ。お隣の晃ちゃんはもう妊娠してるもん」
「そうだけど、あんたの番は今年じゃないだろ?」
「わたしだって子どもじゃないよ。知ってるんだから。
妊娠しない薬があるんでしょ?」
「そうだけど……。まあしょうがないね……」
三久はまた着物を探り、紙で包まれた小さな薬を良久に渡す。
「これを飲めば妊娠しないよ。でもこの薬もただじゃないんだからね。
母さんには内緒だよ」
「わかった!」
薬を口に含むと、良久は生唾でグイッと飲み込んだ。
「うええ、まず……」
「ほら、これを自分で塗りこめて」
「うん」
軟膏を渡され、良久は自分の秘所に手探りで塗りこめた。
「よし、さあ、わたしにも入れて」
「は、はい……」
サレはどうしてこんなことにという思いであったが、断れれるはずもなかった。
それに、体格は違えど、この女の中でも同じように気持ちいい思いができるのかと思うと、自ら進んでやりたい気持ちも出てきた。
ころんと良久が横たわり、脚を広げた。
「あっ、姉さんは見ないで!」
「えっ、あんたはわたしの見てたでしょ」
「だってぇ」
「いいから、ほら、あんたやったげて」
三久がもはや自分のものであるかのように、サレのいちもつに軟膏を塗った。
次第に三久も要領を得て来たらしく、なかなかうまい愛撫である。
むくむくと亀頭が頭を突き上げ、サレは良久の割れ目に差し入れた。
だが、三久のものよりだいぶ固い。
体格の成長度合いというより、三久以上に良久の秘所はまだ開発が進んでいないようだった。
さっきのことからなんとなくわかりかけていたサレは、痛みをこらえるように顔をしかめる良久を見た。
「い、一度ぬきます」
「……ええっ、だめだよ! わざわざ薬まで飲んだんだから!」
「で、でも、このままじゃ痛いだけでは……」
「んんっ、じゃあどうするの?」
「その、ゆ、指で少し広げてみては……」
サレは強引"宿"での交わりの中でも、特別うまい指使いの男と体を合わせた記憶がある。
「じゃあ、やってみて」
「はい……」
いったん抜いて、サレは軟膏をたっぷりと取り、良久の秘所をゆっくりとなでた。
初めはおかしな顔をしていな良久だったが、次第に頬を染め、呼吸が乱れ始めた。
割目の中を探るように指を指し込むと、中は温かく柔らかく、まるでこの世の秘密がそこに隠されているかのような気がしてくる。
次第に軟膏とは粘度の違う液体が指に絡みつくようになった。
(これならいけそうだ)
生命の本能か、直感した。
サレは自分のものを奮い立たせると、良久の中に進入した。
「はあっ……!」
「だ、だいじょうぶ、ですか……?」
「あっ……、うん……、はあ……」
「すこし、うごきますね」
前後に腰を動かすと、良久がくねる。
「あっ、あ……、これが……、あ……」
初めは何が起こっているのか、探り確かめるようだった良久が、次第にその扉を開けていく。
「あっ、あっ、いいよ、いいっ」
「はあっ、はあっ」
「もっと奥まで来て、ねえ奥まで来てよ」
「え……」
良久が自分で手を添えて自分の脚を広げ、腰を突き出した。
サレのほうにもぐいっと刺激が高まる。
サレは恐る恐る、良久の尻に手を添えた。
嫌がる素振りをしなかったので、サレはぐいっと強く差し込んだ。
「はあっん、あっ、あっ」
「はあっ、はっ……」
サレは良久の中に快感を放った。
ふたりで果てて、折り重なるようになっていた。
ふたりとも、必死だった。
「……今度はわたしの番だよ」
腕を掴まれると、三久が欲情した目でサレを見下ろしていた。
サレは三久とそれから続けざまに三度達した。
体力のある三久はもっと欲しがったが、サレはもう疲れていた。
「今度はわたし」
いつの間にか回復して機会を待っていた良久がぱっとサレに馬乗りになった。
良久はへたったいちもつを掴むや、乱暴に擦り上げた。
「あっくっ!」
「良久、だめだよ。乱暴にやっても。こうだよ」
三久が軟膏を取ると、丁寧に愛撫をする。
さすがは年上というべきか、すでにすっかり心得たものだった。
おかげでもう果てたかと思っていたのに、もう一度よみがえった。
三久と良久に攻められ続け、ついにサレは気を失い寸前までになって倒れ込んだ。
三久も良久もなかなか満足したようであった。
「次、わたしの番?」
三人が振り返ると、一番若い木久が立っていた。
「あんた、いたの? びっくりするじゃないの」
「ねぇ三久姉さんと良久姉さん、なにやってたの? 木久もやりたい」
「だ、だめだよ、あんたはまだ小さすぎるよ」
「だって……」
「だめだめ。あんたの穴じゃまだ小さすぎるの」
「……じゃあ、みんなにばらしてもいいの?」
三久の言葉に姉たちもひきつった。
「しょうがない……」
「ねえ、あんた、さっきの良久にしてくれた指のやつやってあげてよ」
「は、はあ……」
そういって三久が軟膏の箱を開けると、中はすっかり空になっていた。
「あ……、だめだ、もうない」
「ええ~、木久、お母さんに言っちゃうよ?」
そのとき、三久が思い出したようにサレを見た。
「ねえ、あんたあれできる? 口でするやつ。廓で"小種"がやってくれたんだけど」
当然断れるわけがない。
サレは脚を広げた木久の前に伏した。
木久の局部はふたりの姉たちよりまだ未成熟で、陰毛もまばらであった。
「お姉さんたち、見ないで」
「見ないでって」
「あんたも見てたでしょ」
良久のときと同じ下りを耳にしながら、サレは割れ目を舌で舐め上げた。
男のものをしゃぶるのとはわけが違いそうだが、さっき指で良久の秘所を愛撫した時に、良久が強く反応するところがあった。
サレはそのピンク色の小さなつぼみを舌先で刺激してみる。
「あんっ」
やはりだ。
サレは集中的にそこを口でついばみ、舌で転がした。
「あんっ、やんっ、ああっそこばっかり!」
次第に、割れ目がてらてらと光ってくる。
幼いと思われたが、十分女であるようだ。
サレは指を使って、さらに愛撫し、割れ目の中に人差し指を出し入れした。
「はあっ、はあっ……!」
見ると訴えるような目つきでこちらを見る三久がいた。
そり幼くも欲望に従順な顔を見ているうちに、自分のものが起きだした。
「あ、あの……ぼくいけそうなんですけど……」
「木久はだめだぞ、薬もないしな」
「それはあたしがもらう。三久姉さんはわたしより一回多いでしょ」
「ああん、ずるい! 姉さんたちばっかり!」
ひと山超えて、もうひと山を越えた後、女たちは着物を着た。
「ねぇ、あんたよく抜け出してくるの?」
「……た、たまに……」
「見つかったら、即殺されちゃうよね」
言っていることは物騒だったが、もはや良久にそのつもりはなさそうだった。
木久が自分のおもちゃであることを主張するように、サレの腕を取った。
「ねえ、ここで飼おうよ」
「それは無理だよ。いくら森の中でも他の家族だってここのクリの林を利用しているんだよ。隠しきれない。それに木久に餌やりができるの?」
良久の問いに反論できない木久がサレの手を離した。
「あんたが廓の"小種"だったらよかったのにねぇ。あんただったら、わたしは指名するよ、
でも、"宿"に帰らなきゃいけないんだろ?」
「はい……」
「まあいいさ。またここで鉢合わせたらまた楽しませてよ
そうだ。わたしたちがいるときは、木にこの腰ひもを結んでおくよ。
それをもし見かけたら出てきてよ、ね?」
「はあ……」
女たちは、帰っていった。
採ったクリを少しおいて行ってくれた。
初めての女の肌をしり、もはやサレは"宿"の男たちと交わる気持ちが一糸たりとも失せていた。
死の恐怖が隣り合わせであったが、女たちと交わる快感は生きることそのものに思えた。
体中疲れてはいたが、気力なのかなんなのか体に力が満ちているのがわかった。
(これだ)
なにがこれなのか、サレは語る言葉を持たない。
でも、抑圧された人生の中で確かな確信がここにあった。
それでもサレは"宿"に戻られなればならない。
そこでなければ生きてはいけないからだ。
帰る道々、サレは体に土や泥をつけていった。
娘たちにすっかり洗われてしまったので、このまま帰ったら怪しまれることは違いなかった。
丹念に汚したつもりだったが、"宿"に入った瞬間すぐにばれた。
「なんだ、この匂い……」
「お前、どこでなにをしてきた?」
泡草の匂いだけでなく、女たちがつけていった匂い。
本能ともいうべく男たちのおそるべき嗅覚がかぎつけていた。
サレはすぐさま集団暴行にあい、なにもかもを白状した。
ぷんぷんとまき散らす女の匂いに欲情した男たちから手ひどい攻めにあった。
尻の穴は何人もの男に侵され、血で穢れた。
ぼろぼろになったサレを、男たちは兵士に突き出した。
既に顔かたちの確認できない状態であったため、サレはそのまま"滓穴"に葬られた。
後日、町の女たちの間にうわさが流れ始める。
「"宿"から男がひとり抜け出していたそうだよ。なんでも森で誰かと交わったらしいんだ。それも三人の姉妹」
「三姉妹? それだけじゃどこの誰か特定できっこないよ」
「特定したところでお咎めなんてありゃしないさ」
「そうなのかい? でも逃亡者を報告しなけりゃ罪になるだろ?」
「逃亡なんてしてないのさ。だって、男は"宿"にちゃんと帰ったんだよ」
「あ、そうか」
「兵士たちははなから交わった女たちの罪を咎めようなんて気はないのさ」
「ああ、そりゃそうだね」
「そうだよ」
「三人の女が、ばかな男ひとりのせいでなんで罪に問われなきゃなんないのさ」
「はは、そりゃそうだ」
噂が流れてから、三久、良久、木久はあのときの男が死んだことを知った。
「あーあ、こんなことならやっぱり森で飼えばよかった。木久まだ廓に行けるまで三年もあるのにな」
「あと何回かは見つからずに楽しめると思ったのにね。まあ、しょうがないわ」
「ねえ、三久姉さん、あいつのほかにも抜け出してくるやつがいるかもしれないよ。
今度、餅でも撒いてわなを仕掛けてみようか」
「そんな面倒くさいことするなら廓のほうがましよ」
「それもそっか」
彼女たちは結局サレの名前さえ知らなかったが、少しも気にかけることはなかった。
丹斗大巴(プロフィールリンク)で公開中!
こちらもぜひお楽しみください!
0
あなたにおすすめの小説

ちょっと大人な物語はこちらです
神崎未緒里
恋愛
本当にあった!?かもしれない
ちょっと大人な短編物語集です。
日常に突然訪れる刺激的な体験。
少し非日常を覗いてみませんか?
あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?
※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに
Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。
※不定期更新です。
※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――
のぞみ
恋愛
「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」
高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。
そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。
でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。
昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?
しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。
「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」
手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。
なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。
怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。
だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――
「…ほんとは、ずっと前から、私…」
ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。
恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。


どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。


ママと中学生の僕
キムラエス
大衆娯楽
「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

上司、快楽に沈むまで
赤林檎
BL
完璧な男――それが、営業部課長・**榊(さかき)**の社内での評判だった。
冷静沈着、部下にも厳しい。私生活の噂すら立たないほどの隙のなさ。
だが、その“完璧”が崩れる日がくるとは、誰も想像していなかった。
入社三年目の篠原は、榊の直属の部下。
真面目だが強気で、どこか挑発的な笑みを浮かべる青年。
ある夜、取引先とのトラブル対応で二人だけが残ったオフィスで、
篠原は上司に向かって、いつもの穏やかな口調を崩した。「……そんな顔、部下には見せないんですね」
疲労で僅かに緩んだ榊の表情。
その弱さを見逃さず、篠原はデスク越しに距離を詰める。
「強がらなくていいですよ。俺の前では、もう」
指先が榊のネクタイを掴む。
引き寄せられた瞬間、榊の理性は音を立てて崩れた。
拒むことも、許すこともできないまま、
彼は“部下”の手によって、ひとつずつ乱されていく。
言葉で支配され、触れられるたびに、自分の知らなかった感情と快楽を知る。それは、上司としての誇りを壊すほどに甘く、逃れられないほどに深い。
だが、篠原の視線の奥に宿るのは、ただの欲望ではなかった。
そこには、ずっと榊だけを見つめ続けてきた、静かな執着がある。
「俺、前から思ってたんです。
あなたが誰かに“支配される”ところ、きっと綺麗だろうなって」
支配する側だったはずの男が、
支配されることで初めて“生きている”と感じてしまう――。
上司と部下、立場も理性も、すべてが絡み合うオフィスの夜。
秘密の扉を開けた榊は、もう戻れない。
快楽に溺れるその瞬間まで、彼を待つのは破滅か、それとも救いか。
――これは、ひとりの上司が“愛”という名の支配に沈んでいく物語。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる