13 / 40
知らない香水
しおりを挟む
「ただいまー」
「おかえり、お父さん、今日は早いね」
「まだ起きてたのか?今日は取引先に行って、直帰だったんだよ」
そう言って、スーツを脱いで、真一は部屋に放った。
「?」
その時にそよいだ風に乗って、微かな香水の香りが、みのるの鼻腔に奥に届く。母親ではないその香りに少し戸惑いを覚えるが、気が付かないふりをした。お酒の臭いもしたが、それに混じって別の香りがすしたのだ。一瞬、父が遠い人のように感じて、少し寂しさを覚える。
よく真一の会社を訪れていた取引先の営業マンが、昇進して異動となった。そうしたら今度は逆に、こちらの営業マンが先方を訪問した時に面会してもらう担当者となった。
訪問してくる彼を担当していたのは真一だったから、営業担当者と西條を連れて挨拶に行ったのだ。西條が叫ぶ。
「わあ、営業って面白いですね、外の空気を吸うのって、なんか新鮮」
「西條さんは、勝手についてきたんでしょ?」
真一はあきれ顔だ。
内勤の2人は、基本的に自宅と会社の往復しかしない。真一も内心浮かれていたが、聖子はそれを隠さず、子供の様にはしゃいでいる。
もともと、真一と向こうの社員は仲が良かった。仕事で会う機会が多いのは当然だが、昼休みに外回り中の彼と偶然で食わせて、蕎麦を一緒に食べる機会もあったからだ。
挨拶は上々で、何事も無く進む。彼の直接の上司にも会う事が出来たし、挨拶だけとはいえ、親睦を深める良い機会となった。
初めて訪れたオフィスは広い。10階建ての3フロアを独占していて、自分の会社よりもだいぶ規模が大きいようだ。
「あの会社、ウチより大きかったんですね。
私、こっちを上に見ていたんですけど、ヤバッてちょっと思っちゃいました」
帰りに、西條が笑いながら言った。
「俺もだよ、ずっとタメ口で話していたけど、もう敬語だな」
「同じ課長じゃないですか、井上さんは、そのままで良いですよ。
それよりヒラの私は、態度を改めないと。
こんにちは位は言ってましたけど、お辞儀しなくちゃ、最敬礼かな?」
駅までの道のり、他愛も無い会話が続いた。
「そうだ、少し早いけど、ご飯食べていきませんか?」
「ご飯?良いけど、早すぎるでしょ?」
「良いじゃないですか、今日の仕事は終わったんですから、どうせ直帰だし。
3時だからおやつの時間も兼ねて、早めのお夕食にしましょう?みのる君にもお土産を買っていきましょう。
ほら、あの店なんて、雰囲気良くありませんか?」
丁度見つけたオセアニア料理のお店を指さした西條は、真一の手を取って店に入った。前に彼女の胸が肩に触れた事を思い出す。彼女と親しい関係になれたらと願う気持ちが強くて、何故この子がみのるの名を知っているかなど考えもしなかった。
昼の時間帯の品数はあまりないが、普段食べなれないオーストラリアやニュージーランドの料理がメニューに並ぶ。夕方以降の料理は豊富で、ディナーやお酒を楽しむことも出来そうだ。
「私、ワインと牛の串のヤツと、このケーキください」
「昼間から?」
「私お酒好きなんですよ、毎日飲むんですよ。
彼氏いないんで、1人寂しくですけどね。
あっ、でもいつも夜ですよ、飲むのは」
出てきた料理は、ワンプレート料理で、上半分にサラダがのっていて、一口サイズよりやや大きめの牛肉の串焼きが、下半分に2本のっている。真一が頼んだのは、キングサーモンだったが、盛り付けは西條の物とほとんど同じだ。
「あ、井上さんの豪華なんだ。
サラダにスモークサーモンがのってますよ」
2人は、それぞれの料理を少しずつ交換し合う。ニュージーランドといえば、羊のイメージが強かった真一は、記念にラムの串焼きを頼んでいた。少し野性味のある味であるが、そこそこ美味しい。西條は、やっぱり牛肉の方が美味しいと言っていた。
日本ではあまり有名でないが、グラスフェットビーフという牧草のみで育てた牛肉を使用しているらしい。牛は草食獣だし、牧草を食べているのが当たり前だと思っていた2人だが、よくよく考えると、穀物を食べている所しか思い浮かばない。
「ハーブばかりを食べさせたりする日本のブランド牛や、ドングリばかりを食べさせるイベリコ豚もいるし、風味が変わるのかもね」
「詳しいですね」
「全然、俺、スーパーのオージービーフしか食わないもん」
彼女が頼んだのは、グラスワインだった。本人がお酒好きだといっているのだから、強いのだろう。よってはいない様だが、それでもアルコールが入れば、微熱を帯びた様なしっとりとした魅力を見せるようになった。
もともと甘えるような口調ではにかんで話す彼女であるから、男はみんなムズムズとした感情変化に襲われる。真一も例外ではない。完全に素面であるにもかかわらず、西條に魅了されて、ほろ酔いの気分だ。
「ふふ、井上さんも飲みますか?」
おままごとで、赤ちゃんに何かを食べさせる様な素振りで、グラスを真一に勧めた。彼女に飲ませてもらった残りのワインを飲み干す。意を決した真一は、そのまま彼女に身を寄せて、瞳を見つめた。
指にそっと手を添えるが、西條は引っ込めない。左手で彼女の膝を撫でて静かに唇を重ねた。
2人が座っていた席は、観葉植物に囲まれていて、店員のいるレジや厨房からは死角になっている。昼の時間帯も終わっていたから、他もまばらだ。店は1面が全面ガラス張りになっていて、店内は外から丸見えだったが、人通りは無い。
1度のキスで済ませる気でいた真一だが、冷たい空気に触れた唇は、彼女の温もりが恋しいと、2度3度と求めた。
肩に触れた彼女の胸の柔らかさが忘れられない。真一の左手は、西條の胸を目指したが、ぎこちなく上手くいかない。
彼女は真一の右側に座っていた。L字型のソファだったから、真一が身を寄せるのは容易だったが、背もたれが邪魔で、右手が思うように使えない。だから、利きの右手を彼女の手に添えたまま、左手をモモから腰へ滑らせたのだが、結局、諦めてしまった。
少し見つめ合って、お互い照れ笑いを浮かべた後に、真一は言った。
「行こうか・・・」
「ん・・」
西條は、静かに頷いた。
「おかえり、お父さん、今日は早いね」
「まだ起きてたのか?今日は取引先に行って、直帰だったんだよ」
そう言って、スーツを脱いで、真一は部屋に放った。
「?」
その時にそよいだ風に乗って、微かな香水の香りが、みのるの鼻腔に奥に届く。母親ではないその香りに少し戸惑いを覚えるが、気が付かないふりをした。お酒の臭いもしたが、それに混じって別の香りがすしたのだ。一瞬、父が遠い人のように感じて、少し寂しさを覚える。
よく真一の会社を訪れていた取引先の営業マンが、昇進して異動となった。そうしたら今度は逆に、こちらの営業マンが先方を訪問した時に面会してもらう担当者となった。
訪問してくる彼を担当していたのは真一だったから、営業担当者と西條を連れて挨拶に行ったのだ。西條が叫ぶ。
「わあ、営業って面白いですね、外の空気を吸うのって、なんか新鮮」
「西條さんは、勝手についてきたんでしょ?」
真一はあきれ顔だ。
内勤の2人は、基本的に自宅と会社の往復しかしない。真一も内心浮かれていたが、聖子はそれを隠さず、子供の様にはしゃいでいる。
もともと、真一と向こうの社員は仲が良かった。仕事で会う機会が多いのは当然だが、昼休みに外回り中の彼と偶然で食わせて、蕎麦を一緒に食べる機会もあったからだ。
挨拶は上々で、何事も無く進む。彼の直接の上司にも会う事が出来たし、挨拶だけとはいえ、親睦を深める良い機会となった。
初めて訪れたオフィスは広い。10階建ての3フロアを独占していて、自分の会社よりもだいぶ規模が大きいようだ。
「あの会社、ウチより大きかったんですね。
私、こっちを上に見ていたんですけど、ヤバッてちょっと思っちゃいました」
帰りに、西條が笑いながら言った。
「俺もだよ、ずっとタメ口で話していたけど、もう敬語だな」
「同じ課長じゃないですか、井上さんは、そのままで良いですよ。
それよりヒラの私は、態度を改めないと。
こんにちは位は言ってましたけど、お辞儀しなくちゃ、最敬礼かな?」
駅までの道のり、他愛も無い会話が続いた。
「そうだ、少し早いけど、ご飯食べていきませんか?」
「ご飯?良いけど、早すぎるでしょ?」
「良いじゃないですか、今日の仕事は終わったんですから、どうせ直帰だし。
3時だからおやつの時間も兼ねて、早めのお夕食にしましょう?みのる君にもお土産を買っていきましょう。
ほら、あの店なんて、雰囲気良くありませんか?」
丁度見つけたオセアニア料理のお店を指さした西條は、真一の手を取って店に入った。前に彼女の胸が肩に触れた事を思い出す。彼女と親しい関係になれたらと願う気持ちが強くて、何故この子がみのるの名を知っているかなど考えもしなかった。
昼の時間帯の品数はあまりないが、普段食べなれないオーストラリアやニュージーランドの料理がメニューに並ぶ。夕方以降の料理は豊富で、ディナーやお酒を楽しむことも出来そうだ。
「私、ワインと牛の串のヤツと、このケーキください」
「昼間から?」
「私お酒好きなんですよ、毎日飲むんですよ。
彼氏いないんで、1人寂しくですけどね。
あっ、でもいつも夜ですよ、飲むのは」
出てきた料理は、ワンプレート料理で、上半分にサラダがのっていて、一口サイズよりやや大きめの牛肉の串焼きが、下半分に2本のっている。真一が頼んだのは、キングサーモンだったが、盛り付けは西條の物とほとんど同じだ。
「あ、井上さんの豪華なんだ。
サラダにスモークサーモンがのってますよ」
2人は、それぞれの料理を少しずつ交換し合う。ニュージーランドといえば、羊のイメージが強かった真一は、記念にラムの串焼きを頼んでいた。少し野性味のある味であるが、そこそこ美味しい。西條は、やっぱり牛肉の方が美味しいと言っていた。
日本ではあまり有名でないが、グラスフェットビーフという牧草のみで育てた牛肉を使用しているらしい。牛は草食獣だし、牧草を食べているのが当たり前だと思っていた2人だが、よくよく考えると、穀物を食べている所しか思い浮かばない。
「ハーブばかりを食べさせたりする日本のブランド牛や、ドングリばかりを食べさせるイベリコ豚もいるし、風味が変わるのかもね」
「詳しいですね」
「全然、俺、スーパーのオージービーフしか食わないもん」
彼女が頼んだのは、グラスワインだった。本人がお酒好きだといっているのだから、強いのだろう。よってはいない様だが、それでもアルコールが入れば、微熱を帯びた様なしっとりとした魅力を見せるようになった。
もともと甘えるような口調ではにかんで話す彼女であるから、男はみんなムズムズとした感情変化に襲われる。真一も例外ではない。完全に素面であるにもかかわらず、西條に魅了されて、ほろ酔いの気分だ。
「ふふ、井上さんも飲みますか?」
おままごとで、赤ちゃんに何かを食べさせる様な素振りで、グラスを真一に勧めた。彼女に飲ませてもらった残りのワインを飲み干す。意を決した真一は、そのまま彼女に身を寄せて、瞳を見つめた。
指にそっと手を添えるが、西條は引っ込めない。左手で彼女の膝を撫でて静かに唇を重ねた。
2人が座っていた席は、観葉植物に囲まれていて、店員のいるレジや厨房からは死角になっている。昼の時間帯も終わっていたから、他もまばらだ。店は1面が全面ガラス張りになっていて、店内は外から丸見えだったが、人通りは無い。
1度のキスで済ませる気でいた真一だが、冷たい空気に触れた唇は、彼女の温もりが恋しいと、2度3度と求めた。
肩に触れた彼女の胸の柔らかさが忘れられない。真一の左手は、西條の胸を目指したが、ぎこちなく上手くいかない。
彼女は真一の右側に座っていた。L字型のソファだったから、真一が身を寄せるのは容易だったが、背もたれが邪魔で、右手が思うように使えない。だから、利きの右手を彼女の手に添えたまま、左手をモモから腰へ滑らせたのだが、結局、諦めてしまった。
少し見つめ合って、お互い照れ笑いを浮かべた後に、真一は言った。
「行こうか・・・」
「ん・・」
西條は、静かに頷いた。
0
お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説
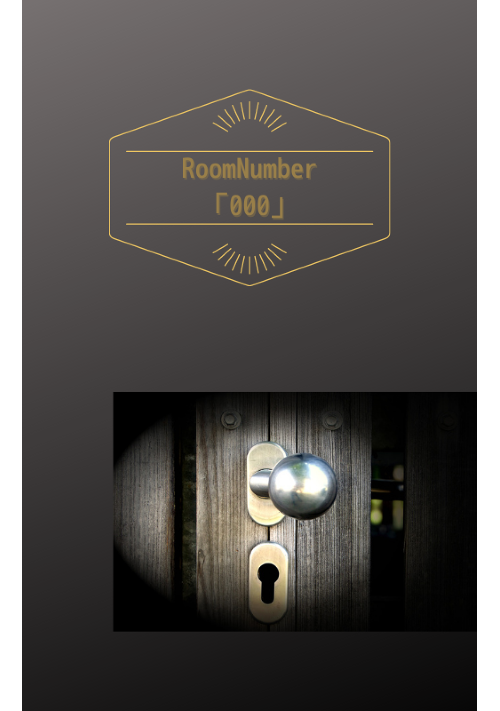
RoomNunmber「000」
誠奈
ミステリー
ある日突然届いた一通のメール。
そこには、報酬を与える代わりに、ある人物を誘拐するよう書かれていて……
丁度金に困っていた翔真は、訝しみつつも依頼を受け入れ、幼馴染の智樹を誘い、実行に移す……が、そこである事件に巻き込まれてしまう。
二人は密室となった部屋から出ることは出来るのだろうか?
※この作品は、以前別サイトにて公開していた物を、作者名及び、登場人物の名称等加筆修正を加えた上で公開しております。
※BL要素かなり薄いですが、匂わせ程度にはありますのでご注意を。

アナグラム
七海美桜
ミステリー
26歳で警視になった一条櫻子は、大阪の曽根崎警察署に新たに設立された「特別心理犯罪課」の課長として警視庁から転属してくる。彼女の目的は、関西に秘かに収監されている犯罪者「桐生蒼馬」に会う為だった。櫻子と蒼馬に隠された秘密、彼の助言により難解な事件を解決する。櫻子を助ける蒼馬の狙いとは?
※この作品はフィクションであり、登場する地名や団体や組織、全て事実とは異なる事をご理解よろしくお願いします。また、犯罪の内容がショッキングな場合があります。セルフレイティングに気を付けて下さい。
イラスト:カリカリ様
背景:由羅様(pixiv)

Springs -ハルタチ-
ささゆき細雪
ミステリー
――恋した少女は、呪われた人殺しの魔女。
ロシアからの帰国子女、上城春咲(かみじょうすざく)は謎めいた眠り姫に恋をした。真夏の学園の裏庭で。
金木犀咲き誇る秋、上城はあのときの少女、鈴代泉観(すずしろいずみ)と邂逅する。だが、彼女は眠り姫ではなく、クラスメイトたちに畏怖されている魔女だった。
ある放課後。上城は豊(ゆたか)という少女から、半年前に起きた転落事故の現場に鈴代が居合わせたことを知る。彼女は人殺しだから関わるなと憎らしげに言われ、上城は余計に鈴代のことが気になってしまう。
そして、鈴代の目の前で、父親の殺人未遂事件が起こる……
――呪いを解くのと、謎を解くのは似ている?
初々しく危うい恋人たちによる謎解きの物語、ここに開幕――!

孤島の洋館と死者の証言
葉羽
ミステリー
高校2年生の神藤葉羽は、学年トップの成績を誇る天才だが、恋愛には奥手な少年。彼の平穏な日常は、幼馴染の望月彩由美と過ごす時間によって色付けされていた。しかし、ある日、彼が大好きな推理小説のイベントに参加するため、二人は不気味な孤島にある古びた洋館に向かうことになる。
その洋館で、参加者の一人が不審死を遂げ、事件は急速に混沌と化す。葉羽は推理の腕を振るい、彩由美と共に事件の真相を追い求めるが、彼らは次第に精神的な恐怖に巻き込まれていく。死者の霊が語る過去の真実、参加者たちの隠された秘密、そして自らの心の中に潜む恐怖。果たして彼らは、事件の謎を解き明かし、無事にこの恐ろしい洋館から脱出できるのか?

ダブルネーム
しまおか
ミステリー
有名人となった藤子の弟が謎の死を遂げ、真相を探る内に事態が急変する!
四十五歳でうつ病により会社を退職した藤子は、五十歳で純文学の新人賞を獲得し白井真琴の筆名で芥山賞まで受賞し、人生が一気に変わる。容姿や珍しい経歴もあり、世間から注目を浴びテレビ出演した際、渡部亮と名乗る男の死についてコメント。それが後に別名義を使っていた弟の雄太と知らされ、騒動に巻き込まれる。さらに本人名義の土地建物を含めた多額の遺産は全て藤子にとの遺書も発見され、いくつもの謎を残して死んだ彼の過去を探り始めた。相続を巡り兄夫婦との確執が産まれる中、かつて雄太の同僚だったと名乗る同性愛者の女性が現れ、警察は事故と処理したが殺されたのではと言い出す。さらに刑事を紹介され裏で捜査すると告げられる。そうして真相を解明しようと動き出した藤子を待っていたのは、予想をはるかに超える事態だった。登場人物のそれぞれにおける人生や、藤子自身の過去を振り返りながら謎を解き明かす、どんでん返しありのミステリー&サスペンス&ヒューマンドラマ。


時の呪縛
葉羽
ミステリー
山間の孤立した村にある古びた時計塔。かつてこの村は繁栄していたが、失踪事件が連続して発生したことで、村人たちは恐れを抱き、時計塔は放置されたままとなった。17歳の天才高校生・神藤葉羽は、友人に誘われてこの村を訪れることになる。そこで彼は、幼馴染の望月彩由美と共に、村の秘密に迫ることになる。
葉羽と彩由美は、失踪事件に関する不気味な噂を耳にし、時計塔に隠された真実を解明しようとする。しかし、時計塔の内部には、過去の記憶を呼び起こす仕掛けが待ち受けていた。彼らは、時間が歪み、過去の失踪者たちの幻影に直面する中で、次第に自らの心の奥底に潜む恐怖と向き合わせることになる。
果たして、彼らは村の呪いを解き明かし、失踪事件の真相に辿り着けるのか?そして、彼らの友情と恋心は試される。緊迫感あふれる謎解きと心理的恐怖が交錯する本格推理小説。

「鏡像のイデア」 難解な推理小説
葉羽
ミステリー
豪邸に一人暮らしする天才高校生、神藤葉羽(しんどう はね)。幼馴染の望月彩由美との平穏な日常は、一枚の奇妙な鏡によって破られる。鏡に映る自分は、確かに自分自身なのに、どこか異質な存在感を放っていた。やがて葉羽は、鏡像と現実が融合する禁断の現象、「鏡像融合」に巻き込まれていく。時を同じくして街では異形の存在が目撃され、空間に歪みが生じ始める。鏡像、異次元、そして幼馴染の少女。複雑に絡み合う謎を解き明かそうとする葉羽の前に、想像を絶する恐怖が待ち受けていた。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















