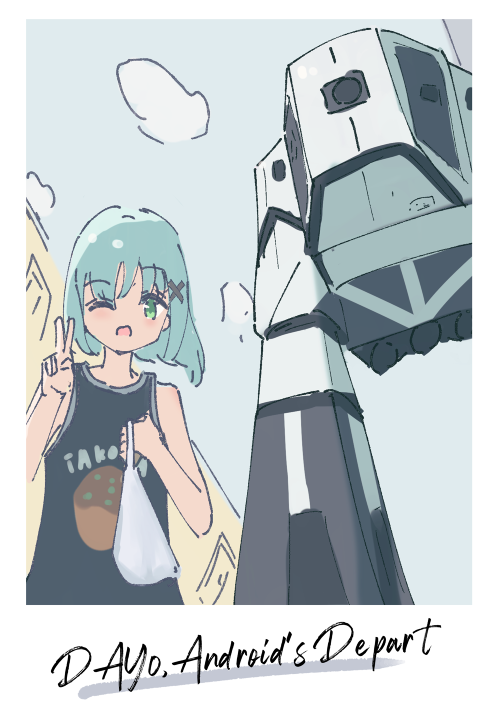43 / 63
十一月『羅刹女』
結
しおりを挟む
昼下がり――町から離れ、雑木林を抜けた野原で、修一郎は地べたに倒れていた。またしても、倒れていた。
「弱いねぇ」
修一郎を見下すその笑いには、嘲りを通り越して哀れみさえ含まれている。
「小生より弱いなんて、本当に剣の才能がないんだねえ。噂通りというか、噂以下というか」
反論はしない。したくても、乱れた呼吸を整えるのに精一杯で、反論すらままならないのである。後方から日を浴びながらにたにたといやらしく笑っている三八を、修一郎はただ仰ぐばかりであった。
「腕っぷしの弱い小生に攻撃ひとつ当てられないなんて、さすがに吃驚だよ。チャンバラで枝を振り回す子供の方がまだマシではないか?」
ボロクソに言われてもなお、修一郎は反論しない。呼吸が整って反論したところで、三八の言うことは全て真実だからである。現に修一郎は、その手に持った木刀で三八に一つも攻撃を加えられていない。ただ三八に向かって振り回しているだけで、一度もそれは攻撃として通らないのだ。
「お前がくねくねと動き回るからだ! なんだ、あのめちゃくちゃな動きは!」
三八はただただ修一郎の攻撃とも言えない攻撃を躱して受けて流すのみであったが、その動きは随分と変則的であった。剣を振ったことのない三八に対して居合の足さばきが通用しない分、同じく居合をやっている者に当てようとすることよりも難しいのだ。どころか、武術の中では暗黙の了解として存在する『こう来たらこう返す』という鉄則というものが、三八には全くない。ゆえに、居合の動きだけは染みついている修一郎とはまるで噛み合わないのである。
「だって小生、武術はからっきしだからねえ。だからこうして、避けて躱して受け流してるんだよ」
「ふざけるな! 実力を見るために相手をしてやろうなどと言っておきながら、お前は攻撃ひとつしてこないとはどういうことだ!」
修一郎は半ばムキになりながら、再び三八へ木刀を振りかざした。当然、そんな状態で振るわれる木刀に精度なんてものはあるわけもない。
「相手が君と同じ土俵で戦ってくれるとは限らない。増して相手が禁書なら尚更さ」
ただチャンバラのように振り回される木刀を、三八はひらりひらりと躱したり、木刀を手で受け流したりする。
「人を操る、心を操るなんて当たり前。戦えないのだって当たり前。君が将来的に相手しなきゃいけないのはそういう奴らだ。悔しかったら一撃でもあててごらん」
修一郎が必死に木刀を振り回すさなかで、三八は木刀を全てさばいて、余裕たっぷりに舌など出している。ますます腹を立てた修一郎は、その鼻っ面をへし折らんとばかりに力いっぱい振るう。
「はい、見えた」
三八はこともあろうに、剣筋ぶれぶれのまま振るわれた木刀をしっかと掴むと、自身の方へ強く引き寄せる。体勢を崩されて前のめりになった修一郎は、力学的な法則に従うまま前方に倒れ込んだ。三八の腕っぷしの弱さなど関係ない。物理的な力の流れを利用され、修一郎はまたしても地べたに手をつかされたのである。
「っ、木刀を掴むなんて反則だ!」
鼻を押さえた修一郎が不満たっぷりに喚く。寸前で木刀を離して手をついたとはいえ、高い鼻は地面の砂利で擦れてしまったようだった。
そもそも木刀を手でさばくこと自体が既に反則行為なのだが、素手対木刀なのだから多少は妥協していた部分はある。しかし、さばくどころか手でしっかりと握ってしまうのは、修一郎とていくらなんでも妥協しかねた。
「反則ではない。木刀を掴んじゃいけないなんて規則はここでは定めちゃいないんだから、木刀を掴んだところでそれは規則に反することではないよ」
しれっと屁理屈を垂れる三八に、修一郎は口を尖らせる。
「木刀を掴むなど、言うまでもなく禁止事項だ。常識だろう」
真剣が木刀に変わっただけ――そういった思考回路を持っていれば、そんな禁止事項は説明せずとも自明である。鍔から先は刃――刃に触れればその手は斬れるのだから、自傷を防ぐためという意味でも掴んではいけない。当たり前の常識、定義するまでもない常識。そう認識していたからこそ、そんな固定観念があったからこそ、その隙をついてこられた修一郎の不満も当然であった。
しかし、三八は喚かれてもにやにやと笑っていた。
「これは木でできた棒。木に触ったところで皮膚が切れるわけでもあるまいて。なあ?」
三八は身をかがめると、転がった木刀の刃先をこれみよがしとばかりにつんつんつついた。
「そもそもだ、修。禁書の【毒】はこんな木刀では斬れないし、真剣であっても結果は同じだ。禁書――元を辿るならば譚本――即ち、人が織り成す譚の結晶――そんなものが切り出した木の棒や鉄の塊なんぞで易々と斬れてしまったら形無しだろう」
「それくらい分かっている」
何を今更、それを論じるのだ。――思いはしたが、そこは言わずに抑えた。禁書には人間の武器が通用しないという常識を、あえて論じる理由があるのだろうと思ったからだ。
「そこを分かっているというなら、もう答えは目前じゃないか」
「どういうことだ、はっきり言え」
聡い修一郎ではあるが、あくまでその聡さが発揮されるのは推理であって、こういった謎かけじみた推測については別の話だ。第一、そんな勿体ぶったような物言いを元から好かないのが彼の性分である。三八は肩をすくめて言った。
「禁書に常識を求めるな。常識を当てはめるな。ただ、そこにあるものを見てみろ」
相手は人間の常識なんて持ち合わせてはくれない、人間ではないのだから。そんな言葉をつけ加えて、三八は修一郎を置き去りに、ぷらぷらと町の方へ歩き出した。
「それを理解しない限り、君は小生に打ち傷ひとつ負わせられないよ」
背を向けたまま手を振る三八に舌打ちしながらも、修一郎はその後を追いかけんと木刀を拾い上げた。――拾い上げてから、気づいた。
「ん?」
それはほんの僅かであったけれど、気のせいではないかと思ってしまうほど微細な変化であったけれど――木刀がところどころ黒ずんでいた。
まるで火の粉でもついて焼け焦げたかのように、点々と黒ずんでいた。
*****
並外れ。桁外れ。出鱈目。――世にはそういう存在が稀にいる。並があってこそ、凡庸があってこそ、平均値があってこそ、初めて『並外れた存在』になる。本を扱う者として出鱈目な才覚を持つ七本三八にしたって、居合術の使い手として桁外れの強さを持つ鍔倉真央にしたって、並があってこそ。
修一郎は、それらとは逆を行く出鱈目であった。つまり――出鱈目としか言いようのないほど、並外れた才覚のなさであった。彼に剣を持たせたところで、その素振りは子供が棒切れを振るうのと変わらない。居合の形を辛うじて保ってはいるけれど、逆に言えば形を保つのに精一杯で、結局はど素人の棒振りと同等である。
そんな棒振りも同然な居合術に意味などない。だから、修一郎は早々に剣を捨てた。居合剣術を誇りにする鍔倉家に長男として生まれながら、早々に剣を捨てる決断をした修一郎は、それだけ知恵の回る子供でもあった。家に蔓延していた価値観に縛られないその思考こそが、彼の並外れた才能の芽――萌芽の象徴であったと言っても過言ではない。知を深める方向へ舵を切った修一郎の判断は、この上なく正しかった。剣を崇拝し彼を影で馬鹿にしてさえいた家人たちを黙らせるほど、知性と思考力において立派な頭角を現したのである。彼は知性を身につけ思考することで、幾度も壁を乗り越えてきたのだ。
――ゆえに、修一郎はこの時も思考していた。しかして、今まで余分につけてきた常識を取り払って、思考していた。思考し、思考し、思考して。…………それを放棄してみることにした。
「七本、再戦だ」
遂には一度も攻撃を当てられずに稽古を終えたその翌日のことである。
「なにか対策を講じてきたのかな」
と聞く三八に対し、修一郎は
「そんなわけないだろう」
と返した。思考し知恵を回すことで壁を突破してきた彼にしては珍しい行動である。意外な答えに驚いた三八は、しかしそれを面白がって再戦に応じた。
そして所変わって、昨日と同じ昼下がりの野原にて。
「昨日と同じく一発でも攻撃を当てれば君の勝ちだ。いつでもおいで」
三八は特に身構えるわけでもなく、足を肩幅に開いて、ゆるりとそこに立っていた。ここも昨日と同じである。
さて、修一郎は昨日と同じく木刀を引き抜いて――その場に捨てた。
「?」
武器を手放した修一郎に、三八は「おや?」といったふうな、面食らった表情を浮かべる。まさか、素手で戦おうと言うのか? と思った、そのまさかで、修一郎は真正面から三八に殴りかかってきた。
「おっと!」
突き出される拳を横にずれることで躱した。なんの変哲もない、ど素人の拳である。修一郎の肉体についた年相応の筋肉による、特になんらかの修練を積んできたというわけでもない、喧嘩の真似事のような拳――それを避けるのに大した身体能力はいらない。
右の拳を左に逃げることで避け、左の拳は右に大きく身をよじることで避け、顔面を狙えば一歩大きく退き、蹴りを繰り出せばひょいと跳び上がる。
「よっ、ほっ」
身体能力の十割を防御に回していた三八にとって、修一郎の喧嘩もどきのような拳は脅威ではない。腑抜けた振りの木刀で殴られるよりもさらに弱そうだ。
――そのはずなのに。
「うおっ、と!」
三八の動きに、無駄がありすぎる。最低限の動作で木刀をいなしていた昨日よりも、明らかに動きが大きいのだ。大きな動きをするものだから次の動作への反応がその分遅れる――無才の修一郎がただ次々に、やたらめったらに放つ拳に、いっそ翻弄されていると言っても良かった。
「ちょ、危ない!」
再び顔面を狙った拳を、三八は上半身を大きく反らすことで避ける。髪の毛一本すら触らせたくないとでも言うかのような、じつに大袈裟な動きであった。
「触れられたくないのか? 私に」
「――!」
飛び退いた三八の反応で、修一郎は勘づいた。
無策で挑んだ再戦ではあったが、無謀に挑んだ再戦ではなかった。修一郎はやはり、拳を振るう中で思考していたのである。つまり、行き当たりばったりの策を講じていたのだ。
「てやぁぁぁッ!」
「ッ!?」
離れたところから助走をつけての突進。やはり振るわれる腑抜けた拳。しかし、自身に触れられること自体が脅威であった三八にとっては、恐ろしいことこの上ない攻撃であった。だから三八は、修一郎の進路から飛び退くことで避けた。――避けてしまった。
「なっ!?」
修一郎は殴り抜くままに、そのまま進路を変えることなく走り抜けた。対戦相手の三八を置いて、目もくれないで、走り抜けた。
「お、おい! 場外に出るのは反則だろ!」
「この場にそんな規則はない!」
焦って追いかけてくる三八に屁理屈を返して、修一郎は走った。
『何をしてるんだ』とか、『どこに行くんだ』とか、意味不明な相手の行動を訝るような反応ではなく、『反則だ』と――相手の行動を断定的に咎める反応である。修一郎のように勘のいい者ならば、この言い方の違和感には気づいたことだろう。
「場外に出られては困るんだな?」
「あっ」
咄嗟に飛び出てしまった迂闊な言葉で、修一郎は最初の勘が正しかったことを確信する。
修一郎は確信を持って走り、野原の傍にあった雑木林に潜り込んだ。雑木が入り乱れ、曲がりくねって方角がわからなくなりそうなその道を、なんの迷いもなく駆け抜け――そして、彼は
「捕まえた」
と言って――目の前にいた本物の三八の肩を叩いた。
「バレちゃったか。さすが、気づくのが早かったねえ」
三八は木の幹にもたれかかって、両手を上げた。降参の合図であった。
「常識を取り除いてもなお、論理的思考を武器に立ち向かう。いやはやお見事、ここまですんなりやられるとは思わなんだ。どこから気づいた?」
「最初からだ」
三八は木の根に腰を下ろすと、君も座りなさいと促す。修一郎は促されるまま木の根に腰をかけながら返答した。
「常識を捨てて見れば何のことはない。最初からおかしかったのだ。目の前にいた七本の影がな」
時分は昼下がり。太陽は高く昇り、そのため影は一日の中で最も短くなる、そんな時間である。修一郎から伸びる影もその例に漏れず、短い影を作っていた。そんなことは論じるまでもない常識だから、影の長さを気にしていちいち下を見る者などそうそういまい。
修一郎は常識を、固定観念を捨てて、だだっ広い野原という場内の全てを見回した。足元を見た時――すぐに気づいた。
「アレの足元の影が、私のものとは逆方向に伸びていた。それも異様に長く、この雑木林に続くようにな。だからあれが人間でない可能性にはすぐ行き着いた」
「じゃあなんでわざわざ殴ってきたんだい。すぐに影をたどってくれても良かったのに」
「それを易々と許すほど貴様も根性良しではないだろう」
それに、と修一郎は続ける。
「貴様、昨日の時点で解答を示唆していただろう。偽物に掴まれたりつつかれたりした木刀が黒ずんでいた。まるで火の粉で焦げたような跡だった」
勿論、そんな焦げ跡は対戦前にはなかった。あの時の『三八』に、妙な細工をされたということくらいは修一郎にも分かった。――この場合は、『三八』その人に細工があったというべきか。
「だから、私自ら素手で向かってきたらどう反応するかを確かめたかった」
結果――修一郎の予想した通り、『三八』は素手で触れられることを嫌がった。木刀には手で触れていたにもかかわらず、それよりも容易く触れられるはずの拳には一切触れようとしなかった。
「あの偽物には、触れたものを焦がす作用がある。私の肉体も、触れれば例外なく焦げる」
「その心は?」
「貴様、禁書で戦っていたな?」
「ご名答」
三八は懐から一冊の本を取り出した。黒い表紙の和綴じである。修一郎はそこに書かれていた文字を読み上げた。
「――『糜爛の処女』?」
「そう、これが小生の使う禁書。もっとも、現役時代にこいつは使ってなかったんだけどね」
三八の手が『糜爛の処女』を適当に開くと、それはすぐさま黒い糸のようにほつれた。ほつれた糸が三八の足元の影に吸い込まれていくと、そこから植物の芽がぬるりと生えてくるように、一匹の黒い蛇が這い出てきた。
「見ての通りだ、こいつは小生の影から生まれる【毒】でね。だから変幻自在なのさ。小生に化けることだって御茶の子さいさいだ」
触れたら焦げるような危険な【毒】なのに、三八だけが平然と蛇を撫でているのは、やはり使用者であるからだろうか。そんなふうに考えながら見ている修一郎に、三八は言った。
「これで人間の常識が禁書には通用しないと分かっただろう? 君はこれから禁書と戦っていくのだから、常にこれを忘れないようになさいね」
さて帰ろうか、と三八が立ち上がる。修一郎もまた立ち上がって、その背を追いかけた。
*****
意外なことに、七本三八は約束を律儀に守る男であった。修一郎にとって柄田家の教育方針は、全くもって役不足としか言いようがなかったが――彼の実力と弱点を考慮に入れた七本三八の、的確かつ容赦ない教育は、負けず嫌いの彼と実に相性が良かった。
その結果、彼は当初の目標である三年以内――およそ二年と二ヶ月で禁書士試験を突破した。年齢にして二十一歳、帝国史上最年少――とまでは残念ながらいかなかったが、それでも彼ほど短い期間で禁書士に成った若者はいないと言えよう。
そうして禁書士となった修一郎は、帝国司書隊図書資産管理部禁書回収課――第四部隊の一員として入隊し、間もなく第一部隊の隊長にまでのし上がった。
彼が因縁の相手――尾前一派、そして鍔倉真央と相対するのは、事件発生から十年後のことである。
十一月『羅刹女』・了
「弱いねぇ」
修一郎を見下すその笑いには、嘲りを通り越して哀れみさえ含まれている。
「小生より弱いなんて、本当に剣の才能がないんだねえ。噂通りというか、噂以下というか」
反論はしない。したくても、乱れた呼吸を整えるのに精一杯で、反論すらままならないのである。後方から日を浴びながらにたにたといやらしく笑っている三八を、修一郎はただ仰ぐばかりであった。
「腕っぷしの弱い小生に攻撃ひとつ当てられないなんて、さすがに吃驚だよ。チャンバラで枝を振り回す子供の方がまだマシではないか?」
ボロクソに言われてもなお、修一郎は反論しない。呼吸が整って反論したところで、三八の言うことは全て真実だからである。現に修一郎は、その手に持った木刀で三八に一つも攻撃を加えられていない。ただ三八に向かって振り回しているだけで、一度もそれは攻撃として通らないのだ。
「お前がくねくねと動き回るからだ! なんだ、あのめちゃくちゃな動きは!」
三八はただただ修一郎の攻撃とも言えない攻撃を躱して受けて流すのみであったが、その動きは随分と変則的であった。剣を振ったことのない三八に対して居合の足さばきが通用しない分、同じく居合をやっている者に当てようとすることよりも難しいのだ。どころか、武術の中では暗黙の了解として存在する『こう来たらこう返す』という鉄則というものが、三八には全くない。ゆえに、居合の動きだけは染みついている修一郎とはまるで噛み合わないのである。
「だって小生、武術はからっきしだからねえ。だからこうして、避けて躱して受け流してるんだよ」
「ふざけるな! 実力を見るために相手をしてやろうなどと言っておきながら、お前は攻撃ひとつしてこないとはどういうことだ!」
修一郎は半ばムキになりながら、再び三八へ木刀を振りかざした。当然、そんな状態で振るわれる木刀に精度なんてものはあるわけもない。
「相手が君と同じ土俵で戦ってくれるとは限らない。増して相手が禁書なら尚更さ」
ただチャンバラのように振り回される木刀を、三八はひらりひらりと躱したり、木刀を手で受け流したりする。
「人を操る、心を操るなんて当たり前。戦えないのだって当たり前。君が将来的に相手しなきゃいけないのはそういう奴らだ。悔しかったら一撃でもあててごらん」
修一郎が必死に木刀を振り回すさなかで、三八は木刀を全てさばいて、余裕たっぷりに舌など出している。ますます腹を立てた修一郎は、その鼻っ面をへし折らんとばかりに力いっぱい振るう。
「はい、見えた」
三八はこともあろうに、剣筋ぶれぶれのまま振るわれた木刀をしっかと掴むと、自身の方へ強く引き寄せる。体勢を崩されて前のめりになった修一郎は、力学的な法則に従うまま前方に倒れ込んだ。三八の腕っぷしの弱さなど関係ない。物理的な力の流れを利用され、修一郎はまたしても地べたに手をつかされたのである。
「っ、木刀を掴むなんて反則だ!」
鼻を押さえた修一郎が不満たっぷりに喚く。寸前で木刀を離して手をついたとはいえ、高い鼻は地面の砂利で擦れてしまったようだった。
そもそも木刀を手でさばくこと自体が既に反則行為なのだが、素手対木刀なのだから多少は妥協していた部分はある。しかし、さばくどころか手でしっかりと握ってしまうのは、修一郎とていくらなんでも妥協しかねた。
「反則ではない。木刀を掴んじゃいけないなんて規則はここでは定めちゃいないんだから、木刀を掴んだところでそれは規則に反することではないよ」
しれっと屁理屈を垂れる三八に、修一郎は口を尖らせる。
「木刀を掴むなど、言うまでもなく禁止事項だ。常識だろう」
真剣が木刀に変わっただけ――そういった思考回路を持っていれば、そんな禁止事項は説明せずとも自明である。鍔から先は刃――刃に触れればその手は斬れるのだから、自傷を防ぐためという意味でも掴んではいけない。当たり前の常識、定義するまでもない常識。そう認識していたからこそ、そんな固定観念があったからこそ、その隙をついてこられた修一郎の不満も当然であった。
しかし、三八は喚かれてもにやにやと笑っていた。
「これは木でできた棒。木に触ったところで皮膚が切れるわけでもあるまいて。なあ?」
三八は身をかがめると、転がった木刀の刃先をこれみよがしとばかりにつんつんつついた。
「そもそもだ、修。禁書の【毒】はこんな木刀では斬れないし、真剣であっても結果は同じだ。禁書――元を辿るならば譚本――即ち、人が織り成す譚の結晶――そんなものが切り出した木の棒や鉄の塊なんぞで易々と斬れてしまったら形無しだろう」
「それくらい分かっている」
何を今更、それを論じるのだ。――思いはしたが、そこは言わずに抑えた。禁書には人間の武器が通用しないという常識を、あえて論じる理由があるのだろうと思ったからだ。
「そこを分かっているというなら、もう答えは目前じゃないか」
「どういうことだ、はっきり言え」
聡い修一郎ではあるが、あくまでその聡さが発揮されるのは推理であって、こういった謎かけじみた推測については別の話だ。第一、そんな勿体ぶったような物言いを元から好かないのが彼の性分である。三八は肩をすくめて言った。
「禁書に常識を求めるな。常識を当てはめるな。ただ、そこにあるものを見てみろ」
相手は人間の常識なんて持ち合わせてはくれない、人間ではないのだから。そんな言葉をつけ加えて、三八は修一郎を置き去りに、ぷらぷらと町の方へ歩き出した。
「それを理解しない限り、君は小生に打ち傷ひとつ負わせられないよ」
背を向けたまま手を振る三八に舌打ちしながらも、修一郎はその後を追いかけんと木刀を拾い上げた。――拾い上げてから、気づいた。
「ん?」
それはほんの僅かであったけれど、気のせいではないかと思ってしまうほど微細な変化であったけれど――木刀がところどころ黒ずんでいた。
まるで火の粉でもついて焼け焦げたかのように、点々と黒ずんでいた。
*****
並外れ。桁外れ。出鱈目。――世にはそういう存在が稀にいる。並があってこそ、凡庸があってこそ、平均値があってこそ、初めて『並外れた存在』になる。本を扱う者として出鱈目な才覚を持つ七本三八にしたって、居合術の使い手として桁外れの強さを持つ鍔倉真央にしたって、並があってこそ。
修一郎は、それらとは逆を行く出鱈目であった。つまり――出鱈目としか言いようのないほど、並外れた才覚のなさであった。彼に剣を持たせたところで、その素振りは子供が棒切れを振るうのと変わらない。居合の形を辛うじて保ってはいるけれど、逆に言えば形を保つのに精一杯で、結局はど素人の棒振りと同等である。
そんな棒振りも同然な居合術に意味などない。だから、修一郎は早々に剣を捨てた。居合剣術を誇りにする鍔倉家に長男として生まれながら、早々に剣を捨てる決断をした修一郎は、それだけ知恵の回る子供でもあった。家に蔓延していた価値観に縛られないその思考こそが、彼の並外れた才能の芽――萌芽の象徴であったと言っても過言ではない。知を深める方向へ舵を切った修一郎の判断は、この上なく正しかった。剣を崇拝し彼を影で馬鹿にしてさえいた家人たちを黙らせるほど、知性と思考力において立派な頭角を現したのである。彼は知性を身につけ思考することで、幾度も壁を乗り越えてきたのだ。
――ゆえに、修一郎はこの時も思考していた。しかして、今まで余分につけてきた常識を取り払って、思考していた。思考し、思考し、思考して。…………それを放棄してみることにした。
「七本、再戦だ」
遂には一度も攻撃を当てられずに稽古を終えたその翌日のことである。
「なにか対策を講じてきたのかな」
と聞く三八に対し、修一郎は
「そんなわけないだろう」
と返した。思考し知恵を回すことで壁を突破してきた彼にしては珍しい行動である。意外な答えに驚いた三八は、しかしそれを面白がって再戦に応じた。
そして所変わって、昨日と同じ昼下がりの野原にて。
「昨日と同じく一発でも攻撃を当てれば君の勝ちだ。いつでもおいで」
三八は特に身構えるわけでもなく、足を肩幅に開いて、ゆるりとそこに立っていた。ここも昨日と同じである。
さて、修一郎は昨日と同じく木刀を引き抜いて――その場に捨てた。
「?」
武器を手放した修一郎に、三八は「おや?」といったふうな、面食らった表情を浮かべる。まさか、素手で戦おうと言うのか? と思った、そのまさかで、修一郎は真正面から三八に殴りかかってきた。
「おっと!」
突き出される拳を横にずれることで躱した。なんの変哲もない、ど素人の拳である。修一郎の肉体についた年相応の筋肉による、特になんらかの修練を積んできたというわけでもない、喧嘩の真似事のような拳――それを避けるのに大した身体能力はいらない。
右の拳を左に逃げることで避け、左の拳は右に大きく身をよじることで避け、顔面を狙えば一歩大きく退き、蹴りを繰り出せばひょいと跳び上がる。
「よっ、ほっ」
身体能力の十割を防御に回していた三八にとって、修一郎の喧嘩もどきのような拳は脅威ではない。腑抜けた振りの木刀で殴られるよりもさらに弱そうだ。
――そのはずなのに。
「うおっ、と!」
三八の動きに、無駄がありすぎる。最低限の動作で木刀をいなしていた昨日よりも、明らかに動きが大きいのだ。大きな動きをするものだから次の動作への反応がその分遅れる――無才の修一郎がただ次々に、やたらめったらに放つ拳に、いっそ翻弄されていると言っても良かった。
「ちょ、危ない!」
再び顔面を狙った拳を、三八は上半身を大きく反らすことで避ける。髪の毛一本すら触らせたくないとでも言うかのような、じつに大袈裟な動きであった。
「触れられたくないのか? 私に」
「――!」
飛び退いた三八の反応で、修一郎は勘づいた。
無策で挑んだ再戦ではあったが、無謀に挑んだ再戦ではなかった。修一郎はやはり、拳を振るう中で思考していたのである。つまり、行き当たりばったりの策を講じていたのだ。
「てやぁぁぁッ!」
「ッ!?」
離れたところから助走をつけての突進。やはり振るわれる腑抜けた拳。しかし、自身に触れられること自体が脅威であった三八にとっては、恐ろしいことこの上ない攻撃であった。だから三八は、修一郎の進路から飛び退くことで避けた。――避けてしまった。
「なっ!?」
修一郎は殴り抜くままに、そのまま進路を変えることなく走り抜けた。対戦相手の三八を置いて、目もくれないで、走り抜けた。
「お、おい! 場外に出るのは反則だろ!」
「この場にそんな規則はない!」
焦って追いかけてくる三八に屁理屈を返して、修一郎は走った。
『何をしてるんだ』とか、『どこに行くんだ』とか、意味不明な相手の行動を訝るような反応ではなく、『反則だ』と――相手の行動を断定的に咎める反応である。修一郎のように勘のいい者ならば、この言い方の違和感には気づいたことだろう。
「場外に出られては困るんだな?」
「あっ」
咄嗟に飛び出てしまった迂闊な言葉で、修一郎は最初の勘が正しかったことを確信する。
修一郎は確信を持って走り、野原の傍にあった雑木林に潜り込んだ。雑木が入り乱れ、曲がりくねって方角がわからなくなりそうなその道を、なんの迷いもなく駆け抜け――そして、彼は
「捕まえた」
と言って――目の前にいた本物の三八の肩を叩いた。
「バレちゃったか。さすが、気づくのが早かったねえ」
三八は木の幹にもたれかかって、両手を上げた。降参の合図であった。
「常識を取り除いてもなお、論理的思考を武器に立ち向かう。いやはやお見事、ここまですんなりやられるとは思わなんだ。どこから気づいた?」
「最初からだ」
三八は木の根に腰を下ろすと、君も座りなさいと促す。修一郎は促されるまま木の根に腰をかけながら返答した。
「常識を捨てて見れば何のことはない。最初からおかしかったのだ。目の前にいた七本の影がな」
時分は昼下がり。太陽は高く昇り、そのため影は一日の中で最も短くなる、そんな時間である。修一郎から伸びる影もその例に漏れず、短い影を作っていた。そんなことは論じるまでもない常識だから、影の長さを気にしていちいち下を見る者などそうそういまい。
修一郎は常識を、固定観念を捨てて、だだっ広い野原という場内の全てを見回した。足元を見た時――すぐに気づいた。
「アレの足元の影が、私のものとは逆方向に伸びていた。それも異様に長く、この雑木林に続くようにな。だからあれが人間でない可能性にはすぐ行き着いた」
「じゃあなんでわざわざ殴ってきたんだい。すぐに影をたどってくれても良かったのに」
「それを易々と許すほど貴様も根性良しではないだろう」
それに、と修一郎は続ける。
「貴様、昨日の時点で解答を示唆していただろう。偽物に掴まれたりつつかれたりした木刀が黒ずんでいた。まるで火の粉で焦げたような跡だった」
勿論、そんな焦げ跡は対戦前にはなかった。あの時の『三八』に、妙な細工をされたということくらいは修一郎にも分かった。――この場合は、『三八』その人に細工があったというべきか。
「だから、私自ら素手で向かってきたらどう反応するかを確かめたかった」
結果――修一郎の予想した通り、『三八』は素手で触れられることを嫌がった。木刀には手で触れていたにもかかわらず、それよりも容易く触れられるはずの拳には一切触れようとしなかった。
「あの偽物には、触れたものを焦がす作用がある。私の肉体も、触れれば例外なく焦げる」
「その心は?」
「貴様、禁書で戦っていたな?」
「ご名答」
三八は懐から一冊の本を取り出した。黒い表紙の和綴じである。修一郎はそこに書かれていた文字を読み上げた。
「――『糜爛の処女』?」
「そう、これが小生の使う禁書。もっとも、現役時代にこいつは使ってなかったんだけどね」
三八の手が『糜爛の処女』を適当に開くと、それはすぐさま黒い糸のようにほつれた。ほつれた糸が三八の足元の影に吸い込まれていくと、そこから植物の芽がぬるりと生えてくるように、一匹の黒い蛇が這い出てきた。
「見ての通りだ、こいつは小生の影から生まれる【毒】でね。だから変幻自在なのさ。小生に化けることだって御茶の子さいさいだ」
触れたら焦げるような危険な【毒】なのに、三八だけが平然と蛇を撫でているのは、やはり使用者であるからだろうか。そんなふうに考えながら見ている修一郎に、三八は言った。
「これで人間の常識が禁書には通用しないと分かっただろう? 君はこれから禁書と戦っていくのだから、常にこれを忘れないようになさいね」
さて帰ろうか、と三八が立ち上がる。修一郎もまた立ち上がって、その背を追いかけた。
*****
意外なことに、七本三八は約束を律儀に守る男であった。修一郎にとって柄田家の教育方針は、全くもって役不足としか言いようがなかったが――彼の実力と弱点を考慮に入れた七本三八の、的確かつ容赦ない教育は、負けず嫌いの彼と実に相性が良かった。
その結果、彼は当初の目標である三年以内――およそ二年と二ヶ月で禁書士試験を突破した。年齢にして二十一歳、帝国史上最年少――とまでは残念ながらいかなかったが、それでも彼ほど短い期間で禁書士に成った若者はいないと言えよう。
そうして禁書士となった修一郎は、帝国司書隊図書資産管理部禁書回収課――第四部隊の一員として入隊し、間もなく第一部隊の隊長にまでのし上がった。
彼が因縁の相手――尾前一派、そして鍔倉真央と相対するのは、事件発生から十年後のことである。
十一月『羅刹女』・了
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
387
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。