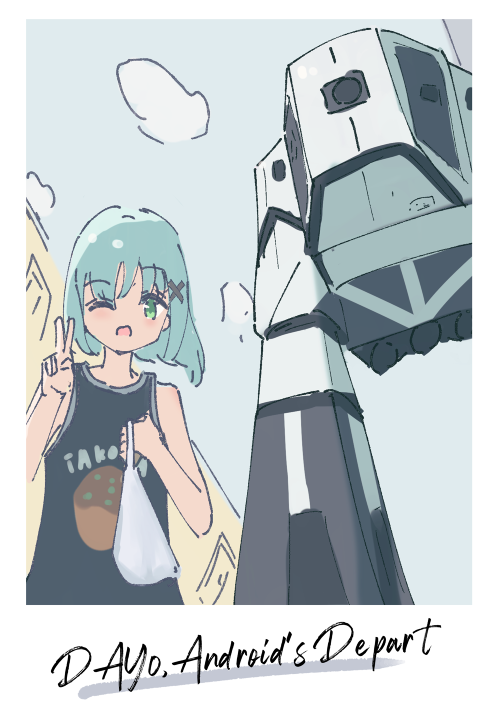22 / 63
八月『先生の匣庭』
その六
しおりを挟む
歌声が響き渡る朱色の空の下、村の中心で異変は起きていた。
「おかぁさん」「お姉ちゃん」「ユキちゃん」「おばあちゃん」「サヨちゃん」「かかさま」「ねぇね」
先ほどまで唯助や世助と戯れていた子供たちが、それぞれ思い思いの人の名前を口にしながら、消えていた。
ある子供は炎が燃え尽きるように。ある子供は星が瞬くように。ある子供は風に散っていくように。子供たちが思い思いに消えていた。
村の中心で歌っていた娘の鎮魂歌に導かれて、子供たちは次々に還っていく。どこの言葉かも分からないが、木々のさやめきのような歌声は、子供たちを在るべき場所に還していた。
「ほら、あの女の人!」
珱仙を連れてきた惣太郎と、その周りに集まった数名の子供たちが、一斉に娘を指さす。そこへ世助を引っ張ってきた唯助も到着した。
「姐さん! これは……」
子供をすべて還して、ようやく音音は歌うことをやめる。
その背後で、待ちわびていた男の声が独り言を呟いた。
「禁書『ある女』――まさか、こんな形で役に立つとは思わなんだ」
「旦那!」
ようやく迎えが来たことに安堵した唯助が、その喜びのままに世助を連れて駆け寄る。
「遅くなってすまない。よく我慢したな、唯助」
三八が駆け寄ってきた唯助の頭を撫でる。唯助ははぐれた飼い主を見つけたときの犬のようにそれを喜び、目を細めていた。
「……子供たちに、何をしたのですか?」
喜びもつかの間、唯助の背後で、子供たちを傍に連れた珱仙が三八に問いかける。自分を先生と慕い、自らもよほど愛情をかけてきたのであろう子供たちを突然消された彼が、三八に敵意を向けるのは当然であった。しかし、三八もまた、珱仙に対してぴりっと肌を焼くような敵意で返している。
「それはこちらの台詞だ、珱仙。子供たちを教え導く存在である貴方が、なにをしているのだ?」
「先に質問したのは私ですよ、ミツユキ様」
聞き慣れないその名前に、唯助は首を傾げる。珱仙は三八を誰かと勘違いしているのだろうか? とも考えたが──
「――その名前で呼ぶな。貴様の目の前にいる小生は、『七本三八』だ」
と三八は、前髪の下から睨んで返す。
まるで、かつて自らがそれを名乗っていたかのような物言い──今はそれを名乗っていないことを示す物言い。そもそもが謎だらけの三八だから、その謎が一つ暴かれたところで唯助は毎回驚いて終わりなのだが――今回ばかりはそれだけではない。よもや、自分に対して名乗っていた名が本当のものではないと判明し、なぜその呼び名を嫌がるのかという疑問が新たに浮上した。
しかし、状況は唯助の思ったこと感じたことに構うことなく進む。
「我が妻と禁書の力を借りて、子供たちを輪廻へ還した。この世界に染まってしまったがゆえにあの子たちが忘れていた、『元いた世界があったこと』を思い出させだけだ」
「……なるほど。解放したということですか」
「さて、質問には答えた。小生からも改めて問おう。貴様、なぜ子供たちを亡きものにすると分かっていながら、ここに連れ込んだのだ」
「――え?」
それに反応したのは、唯助に連れられるままにここまで来た世助であった。唯助も世助と同様に、三八の発言に反応した。
「どういうことですか? だって、あの口は、珱仙先生にも止められないって…! あの口は、禁書化してから子供たちを勝手に飲み込んでいるって」
あの時の珱仙の発言は、あくまで子供たちを連れ込んでいるのは『あの口』のせいであり、自分はそれを止めることができず嘆いている、といった意味合いのものであった。
しかし、三八の発言は珱仙が自らの意志であの口を操り、自分たちを含む子供を意図的にここに連れ込んだということを指摘している。
三八がこの状況で自分たちを惑わしてくるとは思えない──つまり、珱仙が双子を欺こうとしていたということになる。
おそらくは、双子よりも前にここに連れ込んだ子供たちにもまた同様に、「自分はこんなところに迷い込んでしまった子供たちの味方ですよ」というふうに見せかけ、さも自分が子供たちの味方であるかのように演じていたのだろう。
実際は、子供たちを禁書の中という異界に連れ込み、異界の存在に染め上げて――つまりは、現実世界に二度と戻ることのできない『亡きもの』にしているにもかかわらず――善良ぶっているのである。
「居場所を無くし、明日に怯える子供たちを救いたかっただけです」
珱仙は子供たちの前でそれを指摘されても、それを誤魔化そうとはしなかった。むしろ、堂々と認め、救いと言い切った。その態度に、三八はさらに不快感を示す。
「……人に危害を加えれば、自らが禁書になると分かっていたのに、か?」
「違いますよ、ミツユキ――いいえ、七本三八様」
珱仙はゆるゆると首を振って否定した。
「私は、子供たちを救いたくて禁書になったのですよ。譚本の【夢】はあくまで夢であって――『家』にはなりえないのですから」
同じ譚本の【夢】と言っても、通常の譚本の【夢】と、禁書の譚本の【夢】には雲泥の差がある。
通常の譚本が生み出す【夢】は無害でなくてはいけない。精神を蝕むものであってはいけない。読み手の現実を蝕むものであってはいけない。ゆえに、読み手には「なぁんだ、夢か」といったふうに思わせる必要がある。
禁書の譚本が生み出す【夢】は有害である。読み手の精神に確たる影響を及ぼし、現実を蝕むものである。それは『夢』と言うより、麻薬などによってもたらされる依存性を持った『幻覚』という表現の方が近い。
禁書になる前の譚本であった珱仙が、現実に居場所のない子供たちを救うのには、いっときの気休めのような『夢』では不十分であった。もっと大きくて、確固とした居所――『家』である必要があった。
だから、彼は無害であることを捨てた。あえて有害性――耐え難い現実に怯える子供たちのために、その現実を蝕む【毒】を持つことで、子供たちを救おうとした。禁書の中という異界に匿い、子供たちの恐怖を取り除き、幸せな『幻覚』を見せることで、子供たちを救おうとしたのである。
さて、これを慈悲深いと取るか、独善と取るかは――これもまた、読み手の解釈に拠るところ。
「彼らは何にも救われないまま死んでいく。私が納められていた祠へ救いを求めて手を合わせに、何人の子供たちが来たことか。現実世界の大人たちに見捨てられ、死にゆく運命をただ待つ子供たちの、なんと哀れなことか。――だから、私は間違ったことをしたとは思っていません」
そう言い切る珱仙に相対する三八は、それを独善と捉える方の読み手であった。
「同じ死なら救いのある死、か? 呆れる。それは貴様がやっている殺人の正当か――」
三八が侮蔑している間に、不意に。
――不意打ちに。
三八の体は真後ろに、民家の壁ごと吹っ飛ばされていた。
「みや様っ!?」
すぐ側にいた音音が、三八がいつの間にか攻撃を受けたのだと認識するその前に――彼女の二の句を、『手』が封じた。
「ですから、邪魔をしないでもらえますか?」
精神的に消沈していた世助はともかく、五感を鍛え抜かれていた唯助にすら目で追えない動きで、手は音音の首を絞めあげていた。
「う、く…っ!」
宙に浮いた音音の足が、地を求めて藻掻く。
唯助が目で追おうにも、実はそれは追えるはずもない。なぜなら、珱仙本人はそこから一歩も動いておらず、#指一本さえも動かしていないのだから。動いていたのは『手』だけ。どこからともなく生えた白い手が、彼の意志をそのまま実行するように動いていた。
遅れて唯助は気づく。彼の周りにいた子供たちが、忽然と姿を消している。三八と会話している時までいたはずの子供たちが、そっくり消えている。そして、音音を絞めあげているのその白い手は――子供の手がいくつも折り重なってできた、大きな手だった。
白い手が音音をそのまま放り投げる。武術の鍛錬を受けたことのない素人の音音は民家の壁に叩きつけられる。咄嗟に受け身も取れないまま、その場に倒れ込みうずくまった。
「姐さん!! てめえ、何しやがる!!」
「貴方もですよ、唯助くん」
わずか数秒で夫妻両方を攻撃した珱仙が、ちらりと唯助を見る。
珱仙の睨みは、睨みと表現できるほどむき出しであからさまではない。ただちらりと目を向けただけの、視線の移動だ。だが、そこには敵意と害意が滲み出ていた。
「あの夫婦と同類だと言うのなら、私は貴方も攻撃しなければいけません。元々私が狙ったのは世助くんのほうですから」
「な……っ!?」
「え……?」
力なく状況を見ているばかりだった世助本人も、この時ばかりは目を見開いた。珱仙は、自らの黒い目を指で示す。
「本当は、世助くんのことは大まかに見えていたんですよ。この『慧眼』こそが私の能力ですからね。貴方が歩んできた道も、居場所をなくしたことも、その経緯も、貴方が先ほどの祭で祠を訪れたときに分かっていました。それに」
言い終わる前に、また不意に。しかし、一瞬だけひやりとした気配を察知して。――敵意はますます鋭さを増して、唯助に向けられる。
「唯助くん。貴方が七本三八から大いに可愛がられているということも。あの男の教えを受けている最中だということも。幼少期にひどい喘息を患っていたことも――すべて見えています」
唯助の体が急に壁に押し付けられる。
「が、はっ……ぁ……っ!?」
「唯助っ!!」
無数の子供の手が唯助の体を押しつぶさんばかりに押さえつけ、肺と気道を圧迫する。駆け寄った世助がその手を剥がそうにも、手は無数にあるのでキリがない。
「やめてくれ、先生!! おれを狙ったっていうなら、こいつは関係ないだろ!?」
「関係ありませんよ。けれど、邪魔をするなら話は別です。貴方がこの人たちに連れられて現実に戻ったところで、居場所がないでしょう?」
戻ったところで、居場所がない。
珱仙の指摘は、まったくその通りであった。だからこそ、信心もなく祭のついでで祠に寄ってみたりなどした。三八と話していた時間、三八を待つまでの間、世助は迎えを素直に待とうという気にはなれなかった。それよりはいっそ、珱仙がそうしようとしていたように、そうもちかけようとしていたように――この世界に残る選択肢を取ろうかと世助は考えていた。
珱仙の本性が知れた今、都合よく訪れたこの展開のすべてが珱仙の掌の上だということは明らかであったが――それは行き先を失い、どこかに消えてしまおうかと考えていた世助にとっては渡りに船であった。
「よ、すけ……っ!」
呻く弟を見やる。
居場所のない自分だけがこの世界に残れば、弟は現実世界に帰ることができる。愛情をかけ、弟を幸せにしてくれた七本夫妻なら、世助も安心して弟を託すことができる。居場所がある唯助は、元の世界に帰るべきなのだ。
「頼む、こいつだけは──」
「よすけ……っ!」
なにがなんでも自分を連れて帰ろうともがく弟の制止を苦渋の思いで振り切り、世助は珱仙に乞い願った。
「おれはここに残る。こいつらがここから出れば、それで丸く収まるんだろ? ――頼む、たった一人の弟なんだ」
「だめ、だ……! 世助、そんなの……ッ!」
「――そんなの駄目!!」
途切れ途切れの唯助の声よりも確とした女の声が、空気を揺さぶる。
ある意味では、唯助よりも切々として。気迫を纏って。切迫して。──壁に打ちつけられて蹲っていたはずの音音が、珱仙の手を取りかけた世助を阻んでいた。
「たった一人の弟だと言うのなら、なぜそんなに大事な弟さんから目を背けようとするのですか!! 残される側がどんなに苦しくて悔しくて切ないか、分かりもしないで!!」
音音は過去に、たった一人の肉親を喪うという経験をしていたが為に――世助の軽率な判断を、叱咤していた。
「貴方にはまだ、唯助さんという心の拠り所があるのに! 自分と引き換えにするくらい大事にしているくせに! それくらい大事にしている弟さんが、貴方をこんなにも必死に止めているのに! どうしてその想いを振り切ろうとするのですか!」
三八のような大人の諭しではない。音音のそれは、子供が駄々をこねながら大人をぽかぽかと叩くような、ぶつけられるままの感情論。一歩間違えば、言葉の暴力であった。
「貴方にとって唯助さんがたった一人の弟であるように、唯助さんにとって世助さんはたった一人のお兄さんなんですよ!!」
幼稚な言葉の暴力となっていないのは、それがまだ世助の感情を揺さぶる力を持っていたから。それが世助を傷つけるには至っていないからか。
とにかく、音音の駄々にも似た説得は世助の心に少しだけ届いた。
――しかし、珱仙にとっては邪魔なことこの上ない。
「黙っていてもらえますか、お嬢さん」
唯助を押さえつけていた手の一部が、再び音音へと向かう。今度は文字通りの黙らせるだけというものではなく、確実に音音の声を息の根ごと止めようとする――殺意。
逃げろ、と叫ぼうにも、呼吸を封じられている唯助の肺には酸素がない。音音の首に手が触れる。
──触れたところで。
──バンッ!!
と、爆発的な音が響く。
反射的に目を閉じた音音に、傷は一つもつかなかった。
「……焼けた?」
珱仙の操っていた白い手を焼いた、黒い影。
続いて唯助を押さえつけていた手たちも喰い破るそれは。
「なるほど、『糜爛の処女』。噂以上にとんでもない毒性だ」
音音と唯助と世助、三者の所持していた栞に宿っていた、分身たちの本体。黒い蛇となって具現した『糜爛の処女』は、それを従える主人のもとへ這い寄る。
「小生の可愛い子らに、よくも無体を働いてくれたな。焼かれる覚悟はできたか、似非教師──!」
民家の瓦礫の中から現れた『糜爛の処女』の主――七本三八は、冷静に、冷酷に、怒り狂っていた。
「『糜爛の処女』の守りを無効化するためにあえて本体の貴方を最初に攻撃しましたが……私は貴方に対しては手加減しなかったはずですよ」
予想よりも圧倒的に早く意識を回復させた相手に、珱仙は首を傾げる。
三八は珱仙の疑問に答えることもせず、足元の蛇に命じた。
「『糜爛の処女』。――食い破れ!」
牙をむいた黒い蛇が、真正面に、一直線に珱仙に襲いかかる。
珱仙は白い手を再結集させ、黒い蛇を受け止めるべく、正面に突き出す。
しかし、先ほど白い手を食い破った黒い蛇の牙には当然叶うはずもなく。
蛇は妨害をものともせずに、手を次々に食い破り、全てを焼きながら、本体である珱仙の目前まで迫る。
「っ……く!!」
顔を食い破らんばかりに大口を開けた蛇。それを眼前に、珱仙はせめてもと腕で顔を庇う。
――だが、その目測は外れた。
黒い蛇は、咢を大きく、裂けるほど大きく広げたまま――本当に真っ二つに裂けた。
「うっ!?」
双頭になった蛇は珱仙の首元を、浅いながらも強い摩擦で掠め、後方へすり抜ける。
(――しまった)
すり抜けてから、珱仙は三八の本来の命令を悟るが、それはもう既に遅い。
蛇たちはそのまま後方を駆け抜け、何も無い【夢】の空間までも食い破った。
硝子が弾け飛ぶような爆音が響き渡り、朱色の風景に、夜闇を映す穴が空いた。
「唯助、音音! 世助を連れてその穴から脱出しろ!!」
「はいっ!」
茫然としていた唯助は三八の声に弾かれながら、膝をつきっぱなしの世助の手を引く。
「ほら、世助! ここから出るぞ!」
「……っで、も」
「ここにいたら死者になってしまいます! 早くお立ちになって!」
「――っ、待ちなさ……ぐっ!」
未だ躊躇う世助を連れ去ろうとする唯助と音音を、珱仙は阻もうとする。しかし、糜爛の処女につけられた傷は、例えかすり傷であろうと猛毒を発揮する。掠った首元の傷は、確実に珱仙を蝕んでおり、彼に激痛を与えていた。
二人に引きずられるように連れ出された世助は、未練がましく珱仙のほうへ振り返り、
「……先生」
と、未練がましい台詞の断片だけを残して、穴の奥に消えていった。
*****
棚葉町の祭は、既に終わっていた。
提灯の赤い光に煌々と照らされていた大通りは、いまや灯りひとつない。
朱色の世界から抜け出した彼らを照らすのは、頼りない星明かりだけであった。
「……なんで、連れ出した」
未練がましく。何かに引きずられたように。後ろ髪を引かれたように。まるで恨み言のように。世助は立ち尽くすような力もなくして、地面に膝をついていた。
「帰ってきたところで、どこに行けばいいんだよ」
無気力に。無活力に。無表情に脱力したように。脱魂したように。心ここに在らずといった面持ちで、世助は零す。
「何して、生きろってんだよ」
唯助の脳裏に、菜種梅雨の光景が浮かぶ。惨めな気持ちのまま雨に打たれ、捨て犬のようなみすぼらしい濡れ姿で無様に泣いていた、四月の記憶。
――同じではないか。
今の世助は、消えたいと願っていたかつての夏目唯助だ。そして、腰をかがめてそれを見ている自分は、きっとあの時の三八だ。
あの時の三八がやったように譚の結を問うのは――果たして今の世助にやって良いことなのだろうか?
唯助は自身に問いかけ、すぐさまそれを否定した。きっと、それはやってはいけないことだ。
世助の譚は、自分のような『大好きな兄に虐められた』譚ではない。『明らかな意志を持って無二の弟を蹴落とし、その結果天罰が下って転落した』という譚なのだ。
ずっと傍で生きてきた双子の弟である唯助には、彼の出すであろう結が問わずとも見えていた。
(――こいつ、死ぬ気だったんだ)
連れ出す時に音音が言った『死者になってしまう』という台詞――世助にとっては、それこそが『渡りに船』であったのだろう。
大事な弟を追い詰め、跡継ぎの座を奪い取った結果――これこそが因果応報だとでも突きつけられるように、世助は奈落の底へ落ちた。
実家に居場所をなくし、虐めてしまった唯一の弟を頼ることもできず、行く宛を完全に失った自分の譚の滑稽さを嘲笑って――死のうとしていたのだ。
珱仙のもとで暮らせば、苦痛もなく幸せに死ぬことができる。連れ込まれた子供たちのように、現実からは死人として消え、幸せな世界の中で生きていける。まさしく、世助にとってはこれ以上なく幸運な展開だったのだろう。
――ゆえに今、その展開を踏み倒してしまった唯助と音音に、恨み言を吐いているのである。結を聞いたところで、その答えは「死にたい」か「殺してくれ」のどちらかだろう。
「……なあ、世助」
けれど、それだけは止めなくては。そんな結を、世助から引き出す訳にはいかない。
「行くあてがないならさ、一緒に探そうよ」
「……探すって」
世助は、なおも自嘲する。唯助の言葉も嘲笑う。
「なんだよ、それ。んなこと言って、宛てなんかねえくせに。無責任な」
「無責任でもいいよ。お前が生きてくれるなら」
ぴくり、と。うなだれて脱力していた世助の指が動く。自嘲が止む。
「音音さんの言葉、聞いてなかったのか? 世助は、おれの兄ちゃんだろ。弟や妹たちと血が繋がってなかったなら尚更。おれの、たった一人の兄ちゃんだろ。なのに、お前がいなくなったら、おれ本当にひとりぼっちだよ」
──ひとりぼっち。
ひとりぼっちか。
世助はひとりぼっちという言葉を反芻して、再び嗤う。
「なにがひとりぼっちだ」
お前には『家』があるくせに──と世助は嗤う。
「夏目を捨てておれの前から去っていったお前がよく言うぜ。おれなんて会わない方が気が楽だろ」
「……同じ会えないでも、生きてるのと死んでるのとじゃ大違いなんだよ!」
ひねた反応しか返さない世助に、ここで初めて唯助が声を荒らげる。
「確かに、おれは兄貴に虐められたよ。死にたくなるほど傷ついたよ。悲しかったよ。でも、元から嫌いな奴ならこんなに苦しんでない。虐められても、それでも兄貴が好きだったから、余計に苦しかったんだよ!」
手荒い真似はすまいと抑えていたのを耐えきれず爆発させながら、唯助は世助の胸ぐらを掴む。
「好きな相手に向かって死んでいなくなっちまえなんて言える奴、この世のどこにもいねえよ!」
いきなり感情をむき出しにして怒鳴られた世助が動揺から立て直すよりも前に、唯助はその額を世助のそれに押し付ける。勢いを殺さなかったらあわや額が割れんばかりの頭突きである。
「兄貴の人生は、譚はまだ続いてんだろ! そりゃどうなるか分からないし不安だろうけど! おれみたいに幸せになれる可能性だってあるだろ!? なのにここで完結しちゃったらそんな展開も全部無かったことになるんだよ! こんなところで見切りつけて早々に死のうとしてんじゃねえよ、馬鹿野郎!!」
唯助はこれまで世助と喧嘩したことはあったが、憤怒に駆られるままブチ切れたのはこれが初めてであった。
世助からしてみても、弟にここまで怒られるのは初めてであったから、世助は言葉よりもまず、そこに動揺していたのだが。
そこへ憤慨した唯助とは異なる、ささやかな女の声が入り込む。
「世助さん。私も貴方と同じように、自ら命を絶とうとしたことがありました」
あらん限りの怒りをぶつけられて茫然としていた世助の耳に、音音の声はすっと浸透するように入り込んだ。
「大事な心の支えを失って、この先どうすればいいかも分からなくなって、いっそ死んでしまえと思いました。けれど、そうしようとしていたわたくしに『死なせたくない』と言ってくださった方がおりました。だから、わたくしは生きました。もう数年経ちましたが、こうしてわたくしは生きております。――生きていれば、それなりにどうにかなるものなのですよ」
音音とて、今の世助と同じなのである。
かつて実井寧々子のまま死のうとした彼女は、あの時の絶望を乗り越え、今に至っている。それまでの道のりは楽ではなかったけれど、七本音音として平穏な暮らしを得ているのだ。
世助は、そんな未来の可能性を見失っているのである。
「頼むから、そんな終わり方しないでくれよ。本に連れ込まれた子たちと違って、お前はまだ生きてるだろ。行き先がないなら、おれが旦那に頼むからさ。おれは、世助が死ぬなんてやだよ」
その状態で生きろというのは、あまりに無責任で残酷かもしれないが、生きていて欲しいと願う人がいるという事実まで見失わせるわけにはいかない。
唯助と音音のそんな想いは――ようやく届いた。
「……ばかじゃねーの……ばっっっかじゃねーの……」
世助は、今、この世で一番情けない表情を浮かべた自分の顔を隠すようにして、膝を抱え込んだ。
よりにもよって濡れた跡が目立ちやすい紫色に染められた浴衣を、大いに濡らしながら。
「おかぁさん」「お姉ちゃん」「ユキちゃん」「おばあちゃん」「サヨちゃん」「かかさま」「ねぇね」
先ほどまで唯助や世助と戯れていた子供たちが、それぞれ思い思いの人の名前を口にしながら、消えていた。
ある子供は炎が燃え尽きるように。ある子供は星が瞬くように。ある子供は風に散っていくように。子供たちが思い思いに消えていた。
村の中心で歌っていた娘の鎮魂歌に導かれて、子供たちは次々に還っていく。どこの言葉かも分からないが、木々のさやめきのような歌声は、子供たちを在るべき場所に還していた。
「ほら、あの女の人!」
珱仙を連れてきた惣太郎と、その周りに集まった数名の子供たちが、一斉に娘を指さす。そこへ世助を引っ張ってきた唯助も到着した。
「姐さん! これは……」
子供をすべて還して、ようやく音音は歌うことをやめる。
その背後で、待ちわびていた男の声が独り言を呟いた。
「禁書『ある女』――まさか、こんな形で役に立つとは思わなんだ」
「旦那!」
ようやく迎えが来たことに安堵した唯助が、その喜びのままに世助を連れて駆け寄る。
「遅くなってすまない。よく我慢したな、唯助」
三八が駆け寄ってきた唯助の頭を撫でる。唯助ははぐれた飼い主を見つけたときの犬のようにそれを喜び、目を細めていた。
「……子供たちに、何をしたのですか?」
喜びもつかの間、唯助の背後で、子供たちを傍に連れた珱仙が三八に問いかける。自分を先生と慕い、自らもよほど愛情をかけてきたのであろう子供たちを突然消された彼が、三八に敵意を向けるのは当然であった。しかし、三八もまた、珱仙に対してぴりっと肌を焼くような敵意で返している。
「それはこちらの台詞だ、珱仙。子供たちを教え導く存在である貴方が、なにをしているのだ?」
「先に質問したのは私ですよ、ミツユキ様」
聞き慣れないその名前に、唯助は首を傾げる。珱仙は三八を誰かと勘違いしているのだろうか? とも考えたが──
「――その名前で呼ぶな。貴様の目の前にいる小生は、『七本三八』だ」
と三八は、前髪の下から睨んで返す。
まるで、かつて自らがそれを名乗っていたかのような物言い──今はそれを名乗っていないことを示す物言い。そもそもが謎だらけの三八だから、その謎が一つ暴かれたところで唯助は毎回驚いて終わりなのだが――今回ばかりはそれだけではない。よもや、自分に対して名乗っていた名が本当のものではないと判明し、なぜその呼び名を嫌がるのかという疑問が新たに浮上した。
しかし、状況は唯助の思ったこと感じたことに構うことなく進む。
「我が妻と禁書の力を借りて、子供たちを輪廻へ還した。この世界に染まってしまったがゆえにあの子たちが忘れていた、『元いた世界があったこと』を思い出させだけだ」
「……なるほど。解放したということですか」
「さて、質問には答えた。小生からも改めて問おう。貴様、なぜ子供たちを亡きものにすると分かっていながら、ここに連れ込んだのだ」
「――え?」
それに反応したのは、唯助に連れられるままにここまで来た世助であった。唯助も世助と同様に、三八の発言に反応した。
「どういうことですか? だって、あの口は、珱仙先生にも止められないって…! あの口は、禁書化してから子供たちを勝手に飲み込んでいるって」
あの時の珱仙の発言は、あくまで子供たちを連れ込んでいるのは『あの口』のせいであり、自分はそれを止めることができず嘆いている、といった意味合いのものであった。
しかし、三八の発言は珱仙が自らの意志であの口を操り、自分たちを含む子供を意図的にここに連れ込んだということを指摘している。
三八がこの状況で自分たちを惑わしてくるとは思えない──つまり、珱仙が双子を欺こうとしていたということになる。
おそらくは、双子よりも前にここに連れ込んだ子供たちにもまた同様に、「自分はこんなところに迷い込んでしまった子供たちの味方ですよ」というふうに見せかけ、さも自分が子供たちの味方であるかのように演じていたのだろう。
実際は、子供たちを禁書の中という異界に連れ込み、異界の存在に染め上げて――つまりは、現実世界に二度と戻ることのできない『亡きもの』にしているにもかかわらず――善良ぶっているのである。
「居場所を無くし、明日に怯える子供たちを救いたかっただけです」
珱仙は子供たちの前でそれを指摘されても、それを誤魔化そうとはしなかった。むしろ、堂々と認め、救いと言い切った。その態度に、三八はさらに不快感を示す。
「……人に危害を加えれば、自らが禁書になると分かっていたのに、か?」
「違いますよ、ミツユキ――いいえ、七本三八様」
珱仙はゆるゆると首を振って否定した。
「私は、子供たちを救いたくて禁書になったのですよ。譚本の【夢】はあくまで夢であって――『家』にはなりえないのですから」
同じ譚本の【夢】と言っても、通常の譚本の【夢】と、禁書の譚本の【夢】には雲泥の差がある。
通常の譚本が生み出す【夢】は無害でなくてはいけない。精神を蝕むものであってはいけない。読み手の現実を蝕むものであってはいけない。ゆえに、読み手には「なぁんだ、夢か」といったふうに思わせる必要がある。
禁書の譚本が生み出す【夢】は有害である。読み手の精神に確たる影響を及ぼし、現実を蝕むものである。それは『夢』と言うより、麻薬などによってもたらされる依存性を持った『幻覚』という表現の方が近い。
禁書になる前の譚本であった珱仙が、現実に居場所のない子供たちを救うのには、いっときの気休めのような『夢』では不十分であった。もっと大きくて、確固とした居所――『家』である必要があった。
だから、彼は無害であることを捨てた。あえて有害性――耐え難い現実に怯える子供たちのために、その現実を蝕む【毒】を持つことで、子供たちを救おうとした。禁書の中という異界に匿い、子供たちの恐怖を取り除き、幸せな『幻覚』を見せることで、子供たちを救おうとしたのである。
さて、これを慈悲深いと取るか、独善と取るかは――これもまた、読み手の解釈に拠るところ。
「彼らは何にも救われないまま死んでいく。私が納められていた祠へ救いを求めて手を合わせに、何人の子供たちが来たことか。現実世界の大人たちに見捨てられ、死にゆく運命をただ待つ子供たちの、なんと哀れなことか。――だから、私は間違ったことをしたとは思っていません」
そう言い切る珱仙に相対する三八は、それを独善と捉える方の読み手であった。
「同じ死なら救いのある死、か? 呆れる。それは貴様がやっている殺人の正当か――」
三八が侮蔑している間に、不意に。
――不意打ちに。
三八の体は真後ろに、民家の壁ごと吹っ飛ばされていた。
「みや様っ!?」
すぐ側にいた音音が、三八がいつの間にか攻撃を受けたのだと認識するその前に――彼女の二の句を、『手』が封じた。
「ですから、邪魔をしないでもらえますか?」
精神的に消沈していた世助はともかく、五感を鍛え抜かれていた唯助にすら目で追えない動きで、手は音音の首を絞めあげていた。
「う、く…っ!」
宙に浮いた音音の足が、地を求めて藻掻く。
唯助が目で追おうにも、実はそれは追えるはずもない。なぜなら、珱仙本人はそこから一歩も動いておらず、#指一本さえも動かしていないのだから。動いていたのは『手』だけ。どこからともなく生えた白い手が、彼の意志をそのまま実行するように動いていた。
遅れて唯助は気づく。彼の周りにいた子供たちが、忽然と姿を消している。三八と会話している時までいたはずの子供たちが、そっくり消えている。そして、音音を絞めあげているのその白い手は――子供の手がいくつも折り重なってできた、大きな手だった。
白い手が音音をそのまま放り投げる。武術の鍛錬を受けたことのない素人の音音は民家の壁に叩きつけられる。咄嗟に受け身も取れないまま、その場に倒れ込みうずくまった。
「姐さん!! てめえ、何しやがる!!」
「貴方もですよ、唯助くん」
わずか数秒で夫妻両方を攻撃した珱仙が、ちらりと唯助を見る。
珱仙の睨みは、睨みと表現できるほどむき出しであからさまではない。ただちらりと目を向けただけの、視線の移動だ。だが、そこには敵意と害意が滲み出ていた。
「あの夫婦と同類だと言うのなら、私は貴方も攻撃しなければいけません。元々私が狙ったのは世助くんのほうですから」
「な……っ!?」
「え……?」
力なく状況を見ているばかりだった世助本人も、この時ばかりは目を見開いた。珱仙は、自らの黒い目を指で示す。
「本当は、世助くんのことは大まかに見えていたんですよ。この『慧眼』こそが私の能力ですからね。貴方が歩んできた道も、居場所をなくしたことも、その経緯も、貴方が先ほどの祭で祠を訪れたときに分かっていました。それに」
言い終わる前に、また不意に。しかし、一瞬だけひやりとした気配を察知して。――敵意はますます鋭さを増して、唯助に向けられる。
「唯助くん。貴方が七本三八から大いに可愛がられているということも。あの男の教えを受けている最中だということも。幼少期にひどい喘息を患っていたことも――すべて見えています」
唯助の体が急に壁に押し付けられる。
「が、はっ……ぁ……っ!?」
「唯助っ!!」
無数の子供の手が唯助の体を押しつぶさんばかりに押さえつけ、肺と気道を圧迫する。駆け寄った世助がその手を剥がそうにも、手は無数にあるのでキリがない。
「やめてくれ、先生!! おれを狙ったっていうなら、こいつは関係ないだろ!?」
「関係ありませんよ。けれど、邪魔をするなら話は別です。貴方がこの人たちに連れられて現実に戻ったところで、居場所がないでしょう?」
戻ったところで、居場所がない。
珱仙の指摘は、まったくその通りであった。だからこそ、信心もなく祭のついでで祠に寄ってみたりなどした。三八と話していた時間、三八を待つまでの間、世助は迎えを素直に待とうという気にはなれなかった。それよりはいっそ、珱仙がそうしようとしていたように、そうもちかけようとしていたように――この世界に残る選択肢を取ろうかと世助は考えていた。
珱仙の本性が知れた今、都合よく訪れたこの展開のすべてが珱仙の掌の上だということは明らかであったが――それは行き先を失い、どこかに消えてしまおうかと考えていた世助にとっては渡りに船であった。
「よ、すけ……っ!」
呻く弟を見やる。
居場所のない自分だけがこの世界に残れば、弟は現実世界に帰ることができる。愛情をかけ、弟を幸せにしてくれた七本夫妻なら、世助も安心して弟を託すことができる。居場所がある唯助は、元の世界に帰るべきなのだ。
「頼む、こいつだけは──」
「よすけ……っ!」
なにがなんでも自分を連れて帰ろうともがく弟の制止を苦渋の思いで振り切り、世助は珱仙に乞い願った。
「おれはここに残る。こいつらがここから出れば、それで丸く収まるんだろ? ――頼む、たった一人の弟なんだ」
「だめ、だ……! 世助、そんなの……ッ!」
「――そんなの駄目!!」
途切れ途切れの唯助の声よりも確とした女の声が、空気を揺さぶる。
ある意味では、唯助よりも切々として。気迫を纏って。切迫して。──壁に打ちつけられて蹲っていたはずの音音が、珱仙の手を取りかけた世助を阻んでいた。
「たった一人の弟だと言うのなら、なぜそんなに大事な弟さんから目を背けようとするのですか!! 残される側がどんなに苦しくて悔しくて切ないか、分かりもしないで!!」
音音は過去に、たった一人の肉親を喪うという経験をしていたが為に――世助の軽率な判断を、叱咤していた。
「貴方にはまだ、唯助さんという心の拠り所があるのに! 自分と引き換えにするくらい大事にしているくせに! それくらい大事にしている弟さんが、貴方をこんなにも必死に止めているのに! どうしてその想いを振り切ろうとするのですか!」
三八のような大人の諭しではない。音音のそれは、子供が駄々をこねながら大人をぽかぽかと叩くような、ぶつけられるままの感情論。一歩間違えば、言葉の暴力であった。
「貴方にとって唯助さんがたった一人の弟であるように、唯助さんにとって世助さんはたった一人のお兄さんなんですよ!!」
幼稚な言葉の暴力となっていないのは、それがまだ世助の感情を揺さぶる力を持っていたから。それが世助を傷つけるには至っていないからか。
とにかく、音音の駄々にも似た説得は世助の心に少しだけ届いた。
――しかし、珱仙にとっては邪魔なことこの上ない。
「黙っていてもらえますか、お嬢さん」
唯助を押さえつけていた手の一部が、再び音音へと向かう。今度は文字通りの黙らせるだけというものではなく、確実に音音の声を息の根ごと止めようとする――殺意。
逃げろ、と叫ぼうにも、呼吸を封じられている唯助の肺には酸素がない。音音の首に手が触れる。
──触れたところで。
──バンッ!!
と、爆発的な音が響く。
反射的に目を閉じた音音に、傷は一つもつかなかった。
「……焼けた?」
珱仙の操っていた白い手を焼いた、黒い影。
続いて唯助を押さえつけていた手たちも喰い破るそれは。
「なるほど、『糜爛の処女』。噂以上にとんでもない毒性だ」
音音と唯助と世助、三者の所持していた栞に宿っていた、分身たちの本体。黒い蛇となって具現した『糜爛の処女』は、それを従える主人のもとへ這い寄る。
「小生の可愛い子らに、よくも無体を働いてくれたな。焼かれる覚悟はできたか、似非教師──!」
民家の瓦礫の中から現れた『糜爛の処女』の主――七本三八は、冷静に、冷酷に、怒り狂っていた。
「『糜爛の処女』の守りを無効化するためにあえて本体の貴方を最初に攻撃しましたが……私は貴方に対しては手加減しなかったはずですよ」
予想よりも圧倒的に早く意識を回復させた相手に、珱仙は首を傾げる。
三八は珱仙の疑問に答えることもせず、足元の蛇に命じた。
「『糜爛の処女』。――食い破れ!」
牙をむいた黒い蛇が、真正面に、一直線に珱仙に襲いかかる。
珱仙は白い手を再結集させ、黒い蛇を受け止めるべく、正面に突き出す。
しかし、先ほど白い手を食い破った黒い蛇の牙には当然叶うはずもなく。
蛇は妨害をものともせずに、手を次々に食い破り、全てを焼きながら、本体である珱仙の目前まで迫る。
「っ……く!!」
顔を食い破らんばかりに大口を開けた蛇。それを眼前に、珱仙はせめてもと腕で顔を庇う。
――だが、その目測は外れた。
黒い蛇は、咢を大きく、裂けるほど大きく広げたまま――本当に真っ二つに裂けた。
「うっ!?」
双頭になった蛇は珱仙の首元を、浅いながらも強い摩擦で掠め、後方へすり抜ける。
(――しまった)
すり抜けてから、珱仙は三八の本来の命令を悟るが、それはもう既に遅い。
蛇たちはそのまま後方を駆け抜け、何も無い【夢】の空間までも食い破った。
硝子が弾け飛ぶような爆音が響き渡り、朱色の風景に、夜闇を映す穴が空いた。
「唯助、音音! 世助を連れてその穴から脱出しろ!!」
「はいっ!」
茫然としていた唯助は三八の声に弾かれながら、膝をつきっぱなしの世助の手を引く。
「ほら、世助! ここから出るぞ!」
「……っで、も」
「ここにいたら死者になってしまいます! 早くお立ちになって!」
「――っ、待ちなさ……ぐっ!」
未だ躊躇う世助を連れ去ろうとする唯助と音音を、珱仙は阻もうとする。しかし、糜爛の処女につけられた傷は、例えかすり傷であろうと猛毒を発揮する。掠った首元の傷は、確実に珱仙を蝕んでおり、彼に激痛を与えていた。
二人に引きずられるように連れ出された世助は、未練がましく珱仙のほうへ振り返り、
「……先生」
と、未練がましい台詞の断片だけを残して、穴の奥に消えていった。
*****
棚葉町の祭は、既に終わっていた。
提灯の赤い光に煌々と照らされていた大通りは、いまや灯りひとつない。
朱色の世界から抜け出した彼らを照らすのは、頼りない星明かりだけであった。
「……なんで、連れ出した」
未練がましく。何かに引きずられたように。後ろ髪を引かれたように。まるで恨み言のように。世助は立ち尽くすような力もなくして、地面に膝をついていた。
「帰ってきたところで、どこに行けばいいんだよ」
無気力に。無活力に。無表情に脱力したように。脱魂したように。心ここに在らずといった面持ちで、世助は零す。
「何して、生きろってんだよ」
唯助の脳裏に、菜種梅雨の光景が浮かぶ。惨めな気持ちのまま雨に打たれ、捨て犬のようなみすぼらしい濡れ姿で無様に泣いていた、四月の記憶。
――同じではないか。
今の世助は、消えたいと願っていたかつての夏目唯助だ。そして、腰をかがめてそれを見ている自分は、きっとあの時の三八だ。
あの時の三八がやったように譚の結を問うのは――果たして今の世助にやって良いことなのだろうか?
唯助は自身に問いかけ、すぐさまそれを否定した。きっと、それはやってはいけないことだ。
世助の譚は、自分のような『大好きな兄に虐められた』譚ではない。『明らかな意志を持って無二の弟を蹴落とし、その結果天罰が下って転落した』という譚なのだ。
ずっと傍で生きてきた双子の弟である唯助には、彼の出すであろう結が問わずとも見えていた。
(――こいつ、死ぬ気だったんだ)
連れ出す時に音音が言った『死者になってしまう』という台詞――世助にとっては、それこそが『渡りに船』であったのだろう。
大事な弟を追い詰め、跡継ぎの座を奪い取った結果――これこそが因果応報だとでも突きつけられるように、世助は奈落の底へ落ちた。
実家に居場所をなくし、虐めてしまった唯一の弟を頼ることもできず、行く宛を完全に失った自分の譚の滑稽さを嘲笑って――死のうとしていたのだ。
珱仙のもとで暮らせば、苦痛もなく幸せに死ぬことができる。連れ込まれた子供たちのように、現実からは死人として消え、幸せな世界の中で生きていける。まさしく、世助にとってはこれ以上なく幸運な展開だったのだろう。
――ゆえに今、その展開を踏み倒してしまった唯助と音音に、恨み言を吐いているのである。結を聞いたところで、その答えは「死にたい」か「殺してくれ」のどちらかだろう。
「……なあ、世助」
けれど、それだけは止めなくては。そんな結を、世助から引き出す訳にはいかない。
「行くあてがないならさ、一緒に探そうよ」
「……探すって」
世助は、なおも自嘲する。唯助の言葉も嘲笑う。
「なんだよ、それ。んなこと言って、宛てなんかねえくせに。無責任な」
「無責任でもいいよ。お前が生きてくれるなら」
ぴくり、と。うなだれて脱力していた世助の指が動く。自嘲が止む。
「音音さんの言葉、聞いてなかったのか? 世助は、おれの兄ちゃんだろ。弟や妹たちと血が繋がってなかったなら尚更。おれの、たった一人の兄ちゃんだろ。なのに、お前がいなくなったら、おれ本当にひとりぼっちだよ」
──ひとりぼっち。
ひとりぼっちか。
世助はひとりぼっちという言葉を反芻して、再び嗤う。
「なにがひとりぼっちだ」
お前には『家』があるくせに──と世助は嗤う。
「夏目を捨てておれの前から去っていったお前がよく言うぜ。おれなんて会わない方が気が楽だろ」
「……同じ会えないでも、生きてるのと死んでるのとじゃ大違いなんだよ!」
ひねた反応しか返さない世助に、ここで初めて唯助が声を荒らげる。
「確かに、おれは兄貴に虐められたよ。死にたくなるほど傷ついたよ。悲しかったよ。でも、元から嫌いな奴ならこんなに苦しんでない。虐められても、それでも兄貴が好きだったから、余計に苦しかったんだよ!」
手荒い真似はすまいと抑えていたのを耐えきれず爆発させながら、唯助は世助の胸ぐらを掴む。
「好きな相手に向かって死んでいなくなっちまえなんて言える奴、この世のどこにもいねえよ!」
いきなり感情をむき出しにして怒鳴られた世助が動揺から立て直すよりも前に、唯助はその額を世助のそれに押し付ける。勢いを殺さなかったらあわや額が割れんばかりの頭突きである。
「兄貴の人生は、譚はまだ続いてんだろ! そりゃどうなるか分からないし不安だろうけど! おれみたいに幸せになれる可能性だってあるだろ!? なのにここで完結しちゃったらそんな展開も全部無かったことになるんだよ! こんなところで見切りつけて早々に死のうとしてんじゃねえよ、馬鹿野郎!!」
唯助はこれまで世助と喧嘩したことはあったが、憤怒に駆られるままブチ切れたのはこれが初めてであった。
世助からしてみても、弟にここまで怒られるのは初めてであったから、世助は言葉よりもまず、そこに動揺していたのだが。
そこへ憤慨した唯助とは異なる、ささやかな女の声が入り込む。
「世助さん。私も貴方と同じように、自ら命を絶とうとしたことがありました」
あらん限りの怒りをぶつけられて茫然としていた世助の耳に、音音の声はすっと浸透するように入り込んだ。
「大事な心の支えを失って、この先どうすればいいかも分からなくなって、いっそ死んでしまえと思いました。けれど、そうしようとしていたわたくしに『死なせたくない』と言ってくださった方がおりました。だから、わたくしは生きました。もう数年経ちましたが、こうしてわたくしは生きております。――生きていれば、それなりにどうにかなるものなのですよ」
音音とて、今の世助と同じなのである。
かつて実井寧々子のまま死のうとした彼女は、あの時の絶望を乗り越え、今に至っている。それまでの道のりは楽ではなかったけれど、七本音音として平穏な暮らしを得ているのだ。
世助は、そんな未来の可能性を見失っているのである。
「頼むから、そんな終わり方しないでくれよ。本に連れ込まれた子たちと違って、お前はまだ生きてるだろ。行き先がないなら、おれが旦那に頼むからさ。おれは、世助が死ぬなんてやだよ」
その状態で生きろというのは、あまりに無責任で残酷かもしれないが、生きていて欲しいと願う人がいるという事実まで見失わせるわけにはいかない。
唯助と音音のそんな想いは――ようやく届いた。
「……ばかじゃねーの……ばっっっかじゃねーの……」
世助は、今、この世で一番情けない表情を浮かべた自分の顔を隠すようにして、膝を抱え込んだ。
よりにもよって濡れた跡が目立ちやすい紫色に染められた浴衣を、大いに濡らしながら。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
387
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。