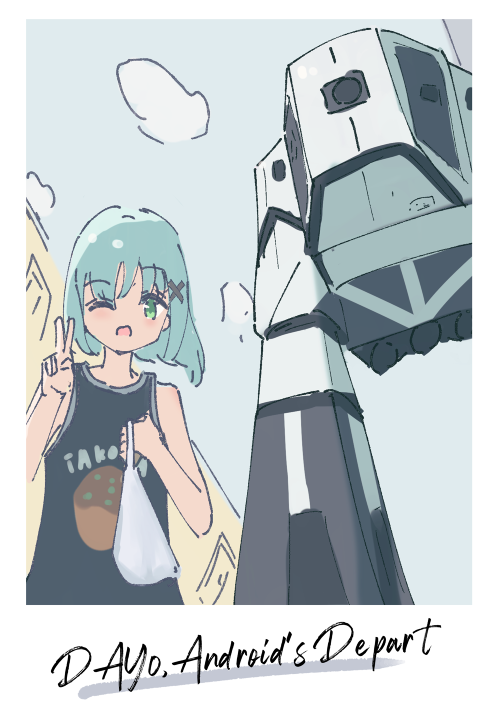21 / 63
八月『先生の匣庭』
その五
しおりを挟む
「……手をつけないのかい?」
珱仙が用意した食事にも、唯助は手をつけなかった。もちろん、世助もだった。
「すみません、今そんなに腹減ってなくて」
巨大な口に呑み込まれてから、体感的には二時間ほど。屋台の飯をこっそり食べているとはいえ、十八歳の食べ盛りな胃はその程度の飯では満ちるはずもなく。しかし、その誘惑に負けて飯を食えば戻って来れなくなってしまうので、唯助は腹の虫との我慢比べ状態であった。
「そうか……やはり心配事が多いから、食欲もそうわかないか」
「すみません、せっかく用意してくれてるのに」
「いいや、大丈夫だよ。気にすることはない」
珱仙はやはり、不快がる様子もなく、訝る様子もなく笑っている。珱仙とて善意で用意しているものであろうが、それを断り続けなければいけないことが、根性良しの唯助にとっては空腹よりなによりつらかった。
「正直、君たちのような子たちは初めてだね」
珱仙は自らも食事に手をつけないまま、おもむろに語り始める。
「出られないことを危惧し、何がなんでも出ようとし、そのために食事をとろうとしない。子供たちとの接触も避けているようだし。君たちは賢いね」
「え?」
「この世界に染まってしまわないように警戒しているんだろう? なんとなく予想はつくよ」
まさか、そんなところまで気づかれていたとは。この珱仙という男の目は、三八にも似ているように唯助には思えた。珱仙はふ、と笑う。
「あの口が狙う子供たちには共通点があってね。ここにくるのはみんな、現実世界には自分の居場所がないと思っている子供たちなんだ」
「「――!!」」
「戦災孤児や捨て子、虐待された子、貧困に喘ぐ子――みんな事情は違うけれど、ここに来た子は親や居場所を失っているんだ。みんな現実世界には戻りたくないと言う子たちでね」
もちろん来たばかりの子は戸惑ったり怖がったりするけれど。――珱仙はそう続ける。
「だから珍しいんだよ。君たちのようにこうやって何がなんでも外に出ようとする子たちに会うのは、私も初めてなんだ。けど、あの口が理由もなく君たちを呑み込んだとは思えない。何かあったんじゃないか?」
この世界が居場所のいない子供たちの拠り所だというならば、唯助はますますこの世界にはそぐわない存在である。夏目家にいられなくなった唯助は、幸運にも七本夫妻と出会い、住み込みで彼らの店を手伝っている。唯助はそこに居心地良さを感じているし、夏目家にいたときよりも充実した日々を送っているのだ。
――となれば、と唯助は隣を見やる。
「おれだよ。――つい先日に、居場所をなくした」
唯助がもしや、まさか、と予感していたものは、見事に的中したらしかった。
*****
唯助が夏目を出ていった後の五月から、世助は暫定的に夏目家の柔術道場の師範代となった。それまで大事にしてきた弟を蹴落とすことで、その座についた。
それを実行に移すまでに、葛藤がなかったわけでは決してない。弟と争わなければいけない展開は、できる限り避けようとした。唯助がいないところでも父に頼み込んだくらいだ。二人で師範代になることはできないのか? 二人でこの道場を引き継ぐことはどうしても無理なのか? と。しかし、この道場はあくまで、『分家』なのだ。宗家ではない。将来的に、一つの道場に二人の師範が生まれることを認める決定権は、父にはなかった。そして、決定権を持つ宗家はそれを認めなかった。
唯助から恋愛相談をされたのも、それと同じ頃である。世助が密かに慕っていた少女・ハルを、なんと唯助も慕っていたこと――そして、唯助がハルから告白を受けたらしいことを告げられた。なるほど、道理で最近唯助の拳が奮わないわけだと納得するのと同時に、世助は動揺した。
――相思相愛の二人の縁談が進んでしまったら、相手のいない自分は間違いなく不戦敗に終わる、と。
現在からしてみたら概念も古すぎる夏目家のことである。唯助に仲のいい娘がいると知れば、やれ嫁入りだの子を産めだの世継ぎだのと下世話なことを言ってくるに決まっている。
だから、世助はその展開に恐怖した。そして、思ってしまったのだ。
──唯助には女がいるのだから、自分が家をとっても不平ではないだろう。
唯助が恋に悩み試合に集中できていない状況につけ込み――世助はただひたすら集中し、鍛えた。当時、恋と家のことで揺れ動き、精神的に不安定であった唯助と、後がないため家を取ろうと集中していた世助。どちらが強くなるかは一目瞭然である。
世助は完膚なきまでに弟を負かしたが、幸いその弟は家を出たその後、七本屋という別の居場所を見つけていた。自分には道場の師範代という居場所がある。
弟に対して酷いことをしてしまった罪悪感は大いにあるものの、お互いに除け者にされる運命は避けられたのだから、世助はこの結果をとりあえずは良しとした。
しかし、先日。世助は、自分がしてきたことが――否、自分と弟がしてきたことが、端から無駄であったことを知らされてしまった。
*****
珱仙は黙して聞いていた。唯助もまた、懺悔にも似た世助の語りを聞いていた。
「無駄だったって……おれたちが、跡継ぎ争いをしてたことが、ってことか?」
唯助の問いに、世助が苦虫を噛み潰したような顔で頷く。
「あのクソ野郎――親戚たちの集まりで、おれと唯助が夏目の血を継いでないのをバラしやがった」
「―――え」
夏目の血を継いでいない。
そのひと言が、頭を強く殴られたような衝撃を唯助に与える。当然である──唯助はそもそも、自分たちは夏目家の夫婦から生まれた子であると、信じて疑っていなかったのだから。
「おれたちが夏目の婆さんに拾われたの、覚えてないのか? まあ、無理もないか。お前、あの時は喘息で苦しんでいた真っ只中だったからな」
――小児喘息。成長した今はほとんど治っていたが、唯助はその昔、病に苦しんでいた。発作が起きればまともに意識を保っていられないほどの重症例であり、激しい運動もひょいひょいとやってのける現在からは想像もできないほど病弱であった。
「おれらを拾った婆さんはな。息子夫婦に子供が産まれねえからって、そのへんをうろついてた孤児のおれらを夏目家の養子にしたんだ」
「うろついてた、孤児……?」
「本当になにも覚えてないんだな」
ふは、と世助から出た笑いは、力なく乾いている。
「婆さんにどんな考えがあったのかは今も分からねえ――夏目家の子供として振る舞うことを要求されたおれは、喘息で苦しんでる弟に医者を手配することを条件にして、それを呑んだ」
「じゃ、じゃあ! おれたちの弟や妹たちは何だったんだよ! あいつらは……!」
「あいつらも寄せ集めだよ。おれらと似たような経緯で集められた、身寄りのないガキどもだ。まさかお前、あいつらを本当の兄弟だと思ってたのか?」
「思、ってた……」
マジかよ、と世助は思わず漏らす。喘息で記憶が混濁していたとはいえ、そこまで夏目家にとって都合よく勘違いしていたとは思わなかったのである。
「医者の治療を受けられるようになって、成長とともにお前の喘息も良くなった。親父――いや、養父もおれらに才能を見出してたから、どちらかを師範代にして親戚に紹介しようとしてたんだ。けど、あの馬鹿、何を考えたんだか、親戚の奴らに俺が夏目家の子供じゃないってバラしたんだ。そっからの展開がもう笑えるくらい酷かった」
伝統ある血筋だの、優秀な夏目の遺伝子だの、この手のいわゆる『お高いところにとまっていたがる家』にはありがちな台詞を吐き散らかしていた親戚どもが、よもやその血をまったく引いていない人間を重役に置くという判断を受け入れるはずもなく。末端の分家の師範という親戚連中の中では弱い立場にあった父も反論はできず。
有り体に言って、世助は捨てられた。今までの努力や成果を鑑みられることもなく、ただ夏目の血が入ってないというだけのことで――失格の烙印を押されたのである。
世助は語りながら大いに自嘲する。
「笑えねえだろ? おれはなんのために必死に鍛えて、弟を蹴落とさなきゃいけなかったんだって話だよ。大事な弟を苦しめてまで掴んだものが、手を広げて見てみたらクソも同然でしたってさ。もう何も信用できなくなった。クソな親戚どもにも、馬鹿な養父にも付き合ってられなくなって、家を出た」
唯助は全て納得すると同時に、絶句した。夏目家が世助に対してとった行動にも呆然としたが、それ以上に。あれだけ努力していたのに、その努力とはまったく無関係なところで否定された世助の心境の計り知れなさに、慰めようもない深すぎる傷に、大きすぎる衝撃を受けた。
「お前が好きだったハルも、お前が七本屋にいった後に町を出ていった。掴んだはずの家督を失い、初恋も破れて――何よりも大事にしなきゃいけなかった弟を蹴落とした罰が当たったのかもしれねえな」
世助が非常にばつの悪い思いをしていたのも当然であった。惨めな結末に陥った直後に、幸運に恵まれ幸せに暮らしている弟との再会。しかも自分が苦しめたはずの弟は自分の異変を察知して後を追いかけてきたり、共に危機的状況に陥った自分を助けようとしたり、昔のことに素直に礼を言ったり、一切恨み言を吐かない。罵詈雑言の一つくらい言われた方が世助としてもスッキリするのだが、恨むことを筋違いとしていた唯助がそれをしなかったがために、世助は唯助に対して非常に後ろめたい思いをするはめになってしまった。
「……そうか。それは、つらい思いをしたね」
何の言葉もかけられなくなってしまった唯助の代わりのように、それまで世助の懺悔を聞いていた珱仙が言う。
「ずっとずっと、よく耐えてきたね。世助くん」
珱仙の手がするりと伸びると、百八十センチも越える巨漢の手のひらがそっと、世助の頭を撫でた。今まで堪えていた後悔や苦しみが、世助の目からぼたぼたと零れ始めた。
「ごめんな。ごめんな、唯助……お前に酷いことして、こんな、自分のことでいっぱいいっぱいになって、自分勝手な、自分のことばっかな兄貴で、ごめんな……」
胸の中に溜め込んでいたものを、世助は嗚咽とともに吐き出していく。唯助はそれに、大いに安堵した。
世助は、やはり自分の双子の兄であったのだ。師範代の座を奪うために双子で対立することを、最後まで厭っていた。跡継ぎをどちらにするか決めかねている父親を最後まで迷わせるために、わざと実力よりも弱いふりをして唯助に合わせていた。どちらにも優劣がつけられないように、ギリギリまで似ようとしていたのだ。
それにハルとの恋が絡んでしまい、波が立ってしまっただけ。それだけのことだったのだ。
「……そんなことねえよ。世助はちゃんと、おれのことも気にしてくれてたよ。ただ、今回のはさ。どうしようもなかったんだよ。色んなことが上手くいかなかっただけだからさ。おれはもう苦しくないから、お前が謝ることねえんだよ」
自分が苦しんでいたのと同じように苦しんでいた世助の背中を摩る。世助の嗚咽はますます大きくなる。
それまでずっと世助の頭を撫でていた珱仙が、
「……世助くん。もし、君が良ければ――」
と言いかけた時だった。
「珱仙先生!! 大変だよ!!」
沈みこんだ空気をぶち破るように、惣太郎が息せき切って庵へ駆け込んでくる。
「惣太郎? どうしたんだい?」
珱仙に背中をさすられながら、惣太郎は青ざめて叫んだ。
「みんなが、みんなが消えちゃったんだ!! 急に女の人が来て、歌を歌ったら――みんな消えちゃった!!」
「なんですって?」
「――!」
珱仙が惣太郎に連れられ、庵を飛び出していく。待機を命じられた唯助は、窓の方へ目をやり――微かに聞こえるその歌声とやらに、耳を澄ませた。
少しばかり掠れたような、遠慮がちに空気に混じるような歌声が、確かにする。音色は遠くから響いて聞こえるのに、そのささやかさは腕に抱いた赤子に聴かせる子守唄のようで。
その温もり溢れる声は、唯助が毎日のように聞いている“彼女”の声であった。
「……音音さん?」
「え?」
「世助! 迎えが来たぞ!」
唯助は世助の手を引き、外へと連れ出した。
珱仙が用意した食事にも、唯助は手をつけなかった。もちろん、世助もだった。
「すみません、今そんなに腹減ってなくて」
巨大な口に呑み込まれてから、体感的には二時間ほど。屋台の飯をこっそり食べているとはいえ、十八歳の食べ盛りな胃はその程度の飯では満ちるはずもなく。しかし、その誘惑に負けて飯を食えば戻って来れなくなってしまうので、唯助は腹の虫との我慢比べ状態であった。
「そうか……やはり心配事が多いから、食欲もそうわかないか」
「すみません、せっかく用意してくれてるのに」
「いいや、大丈夫だよ。気にすることはない」
珱仙はやはり、不快がる様子もなく、訝る様子もなく笑っている。珱仙とて善意で用意しているものであろうが、それを断り続けなければいけないことが、根性良しの唯助にとっては空腹よりなによりつらかった。
「正直、君たちのような子たちは初めてだね」
珱仙は自らも食事に手をつけないまま、おもむろに語り始める。
「出られないことを危惧し、何がなんでも出ようとし、そのために食事をとろうとしない。子供たちとの接触も避けているようだし。君たちは賢いね」
「え?」
「この世界に染まってしまわないように警戒しているんだろう? なんとなく予想はつくよ」
まさか、そんなところまで気づかれていたとは。この珱仙という男の目は、三八にも似ているように唯助には思えた。珱仙はふ、と笑う。
「あの口が狙う子供たちには共通点があってね。ここにくるのはみんな、現実世界には自分の居場所がないと思っている子供たちなんだ」
「「――!!」」
「戦災孤児や捨て子、虐待された子、貧困に喘ぐ子――みんな事情は違うけれど、ここに来た子は親や居場所を失っているんだ。みんな現実世界には戻りたくないと言う子たちでね」
もちろん来たばかりの子は戸惑ったり怖がったりするけれど。――珱仙はそう続ける。
「だから珍しいんだよ。君たちのようにこうやって何がなんでも外に出ようとする子たちに会うのは、私も初めてなんだ。けど、あの口が理由もなく君たちを呑み込んだとは思えない。何かあったんじゃないか?」
この世界が居場所のいない子供たちの拠り所だというならば、唯助はますますこの世界にはそぐわない存在である。夏目家にいられなくなった唯助は、幸運にも七本夫妻と出会い、住み込みで彼らの店を手伝っている。唯助はそこに居心地良さを感じているし、夏目家にいたときよりも充実した日々を送っているのだ。
――となれば、と唯助は隣を見やる。
「おれだよ。――つい先日に、居場所をなくした」
唯助がもしや、まさか、と予感していたものは、見事に的中したらしかった。
*****
唯助が夏目を出ていった後の五月から、世助は暫定的に夏目家の柔術道場の師範代となった。それまで大事にしてきた弟を蹴落とすことで、その座についた。
それを実行に移すまでに、葛藤がなかったわけでは決してない。弟と争わなければいけない展開は、できる限り避けようとした。唯助がいないところでも父に頼み込んだくらいだ。二人で師範代になることはできないのか? 二人でこの道場を引き継ぐことはどうしても無理なのか? と。しかし、この道場はあくまで、『分家』なのだ。宗家ではない。将来的に、一つの道場に二人の師範が生まれることを認める決定権は、父にはなかった。そして、決定権を持つ宗家はそれを認めなかった。
唯助から恋愛相談をされたのも、それと同じ頃である。世助が密かに慕っていた少女・ハルを、なんと唯助も慕っていたこと――そして、唯助がハルから告白を受けたらしいことを告げられた。なるほど、道理で最近唯助の拳が奮わないわけだと納得するのと同時に、世助は動揺した。
――相思相愛の二人の縁談が進んでしまったら、相手のいない自分は間違いなく不戦敗に終わる、と。
現在からしてみたら概念も古すぎる夏目家のことである。唯助に仲のいい娘がいると知れば、やれ嫁入りだの子を産めだの世継ぎだのと下世話なことを言ってくるに決まっている。
だから、世助はその展開に恐怖した。そして、思ってしまったのだ。
──唯助には女がいるのだから、自分が家をとっても不平ではないだろう。
唯助が恋に悩み試合に集中できていない状況につけ込み――世助はただひたすら集中し、鍛えた。当時、恋と家のことで揺れ動き、精神的に不安定であった唯助と、後がないため家を取ろうと集中していた世助。どちらが強くなるかは一目瞭然である。
世助は完膚なきまでに弟を負かしたが、幸いその弟は家を出たその後、七本屋という別の居場所を見つけていた。自分には道場の師範代という居場所がある。
弟に対して酷いことをしてしまった罪悪感は大いにあるものの、お互いに除け者にされる運命は避けられたのだから、世助はこの結果をとりあえずは良しとした。
しかし、先日。世助は、自分がしてきたことが――否、自分と弟がしてきたことが、端から無駄であったことを知らされてしまった。
*****
珱仙は黙して聞いていた。唯助もまた、懺悔にも似た世助の語りを聞いていた。
「無駄だったって……おれたちが、跡継ぎ争いをしてたことが、ってことか?」
唯助の問いに、世助が苦虫を噛み潰したような顔で頷く。
「あのクソ野郎――親戚たちの集まりで、おれと唯助が夏目の血を継いでないのをバラしやがった」
「―――え」
夏目の血を継いでいない。
そのひと言が、頭を強く殴られたような衝撃を唯助に与える。当然である──唯助はそもそも、自分たちは夏目家の夫婦から生まれた子であると、信じて疑っていなかったのだから。
「おれたちが夏目の婆さんに拾われたの、覚えてないのか? まあ、無理もないか。お前、あの時は喘息で苦しんでいた真っ只中だったからな」
――小児喘息。成長した今はほとんど治っていたが、唯助はその昔、病に苦しんでいた。発作が起きればまともに意識を保っていられないほどの重症例であり、激しい運動もひょいひょいとやってのける現在からは想像もできないほど病弱であった。
「おれらを拾った婆さんはな。息子夫婦に子供が産まれねえからって、そのへんをうろついてた孤児のおれらを夏目家の養子にしたんだ」
「うろついてた、孤児……?」
「本当になにも覚えてないんだな」
ふは、と世助から出た笑いは、力なく乾いている。
「婆さんにどんな考えがあったのかは今も分からねえ――夏目家の子供として振る舞うことを要求されたおれは、喘息で苦しんでる弟に医者を手配することを条件にして、それを呑んだ」
「じゃ、じゃあ! おれたちの弟や妹たちは何だったんだよ! あいつらは……!」
「あいつらも寄せ集めだよ。おれらと似たような経緯で集められた、身寄りのないガキどもだ。まさかお前、あいつらを本当の兄弟だと思ってたのか?」
「思、ってた……」
マジかよ、と世助は思わず漏らす。喘息で記憶が混濁していたとはいえ、そこまで夏目家にとって都合よく勘違いしていたとは思わなかったのである。
「医者の治療を受けられるようになって、成長とともにお前の喘息も良くなった。親父――いや、養父もおれらに才能を見出してたから、どちらかを師範代にして親戚に紹介しようとしてたんだ。けど、あの馬鹿、何を考えたんだか、親戚の奴らに俺が夏目家の子供じゃないってバラしたんだ。そっからの展開がもう笑えるくらい酷かった」
伝統ある血筋だの、優秀な夏目の遺伝子だの、この手のいわゆる『お高いところにとまっていたがる家』にはありがちな台詞を吐き散らかしていた親戚どもが、よもやその血をまったく引いていない人間を重役に置くという判断を受け入れるはずもなく。末端の分家の師範という親戚連中の中では弱い立場にあった父も反論はできず。
有り体に言って、世助は捨てられた。今までの努力や成果を鑑みられることもなく、ただ夏目の血が入ってないというだけのことで――失格の烙印を押されたのである。
世助は語りながら大いに自嘲する。
「笑えねえだろ? おれはなんのために必死に鍛えて、弟を蹴落とさなきゃいけなかったんだって話だよ。大事な弟を苦しめてまで掴んだものが、手を広げて見てみたらクソも同然でしたってさ。もう何も信用できなくなった。クソな親戚どもにも、馬鹿な養父にも付き合ってられなくなって、家を出た」
唯助は全て納得すると同時に、絶句した。夏目家が世助に対してとった行動にも呆然としたが、それ以上に。あれだけ努力していたのに、その努力とはまったく無関係なところで否定された世助の心境の計り知れなさに、慰めようもない深すぎる傷に、大きすぎる衝撃を受けた。
「お前が好きだったハルも、お前が七本屋にいった後に町を出ていった。掴んだはずの家督を失い、初恋も破れて――何よりも大事にしなきゃいけなかった弟を蹴落とした罰が当たったのかもしれねえな」
世助が非常にばつの悪い思いをしていたのも当然であった。惨めな結末に陥った直後に、幸運に恵まれ幸せに暮らしている弟との再会。しかも自分が苦しめたはずの弟は自分の異変を察知して後を追いかけてきたり、共に危機的状況に陥った自分を助けようとしたり、昔のことに素直に礼を言ったり、一切恨み言を吐かない。罵詈雑言の一つくらい言われた方が世助としてもスッキリするのだが、恨むことを筋違いとしていた唯助がそれをしなかったがために、世助は唯助に対して非常に後ろめたい思いをするはめになってしまった。
「……そうか。それは、つらい思いをしたね」
何の言葉もかけられなくなってしまった唯助の代わりのように、それまで世助の懺悔を聞いていた珱仙が言う。
「ずっとずっと、よく耐えてきたね。世助くん」
珱仙の手がするりと伸びると、百八十センチも越える巨漢の手のひらがそっと、世助の頭を撫でた。今まで堪えていた後悔や苦しみが、世助の目からぼたぼたと零れ始めた。
「ごめんな。ごめんな、唯助……お前に酷いことして、こんな、自分のことでいっぱいいっぱいになって、自分勝手な、自分のことばっかな兄貴で、ごめんな……」
胸の中に溜め込んでいたものを、世助は嗚咽とともに吐き出していく。唯助はそれに、大いに安堵した。
世助は、やはり自分の双子の兄であったのだ。師範代の座を奪うために双子で対立することを、最後まで厭っていた。跡継ぎをどちらにするか決めかねている父親を最後まで迷わせるために、わざと実力よりも弱いふりをして唯助に合わせていた。どちらにも優劣がつけられないように、ギリギリまで似ようとしていたのだ。
それにハルとの恋が絡んでしまい、波が立ってしまっただけ。それだけのことだったのだ。
「……そんなことねえよ。世助はちゃんと、おれのことも気にしてくれてたよ。ただ、今回のはさ。どうしようもなかったんだよ。色んなことが上手くいかなかっただけだからさ。おれはもう苦しくないから、お前が謝ることねえんだよ」
自分が苦しんでいたのと同じように苦しんでいた世助の背中を摩る。世助の嗚咽はますます大きくなる。
それまでずっと世助の頭を撫でていた珱仙が、
「……世助くん。もし、君が良ければ――」
と言いかけた時だった。
「珱仙先生!! 大変だよ!!」
沈みこんだ空気をぶち破るように、惣太郎が息せき切って庵へ駆け込んでくる。
「惣太郎? どうしたんだい?」
珱仙に背中をさすられながら、惣太郎は青ざめて叫んだ。
「みんなが、みんなが消えちゃったんだ!! 急に女の人が来て、歌を歌ったら――みんな消えちゃった!!」
「なんですって?」
「――!」
珱仙が惣太郎に連れられ、庵を飛び出していく。待機を命じられた唯助は、窓の方へ目をやり――微かに聞こえるその歌声とやらに、耳を澄ませた。
少しばかり掠れたような、遠慮がちに空気に混じるような歌声が、確かにする。音色は遠くから響いて聞こえるのに、そのささやかさは腕に抱いた赤子に聴かせる子守唄のようで。
その温もり溢れる声は、唯助が毎日のように聞いている“彼女”の声であった。
「……音音さん?」
「え?」
「世助! 迎えが来たぞ!」
唯助は世助の手を引き、外へと連れ出した。
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
387
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる
本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。
このユーザをミュートしますか?
※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。
※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。
※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。