あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~
さいとう みさき
恋愛
「ま、まさか!?」
あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。
弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。
弟とは凄く仲が良いの!
それはそれはものすごく‥‥‥
「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」
そんな関係のあたしたち。
でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥
「うそっ! お腹が出て来てる!?」
お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

至れり尽くせり!僕専用メイドの全員が溺愛してくる件
こうたろ
青春
普通の大学生・佐藤健太は目覚めると、自宅が豪華な洋館に変わり10人の美人メイドたちに「お目覚めですか、ご主人様?」と一斉に迎えられる。いつの間にか彼らの“専属主人”になっていた健太は戸惑う間もなく、朝から晩までメイドたちの超至れり尽くせりな奉仕を受け始める。

ヤンデレ美少女転校生と共に体育倉庫に閉じ込められ、大問題になりましたが『結婚しています!』で乗り切った嘘のような本当の話
桜井正宗@オートスキル第1巻発売中
青春
――結婚しています!
それは二人だけの秘密。
高校二年の遙と遥は結婚した。
近年法律が変わり、高校生(十六歳)からでも結婚できるようになっていた。だから、問題はなかった。
キッカケは、体育倉庫に閉じ込められた事件から始まった。校長先生に問い詰められ、とっさに誤魔化した。二人は退学の危機を乗り越える為に本当に結婚することにした。
ワケありヤンデレ美少女転校生の『小桜 遥』と”新婚生活”を開始する――。
*結婚要素あり
*ヤンデレ要素あり

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...
MisakiNonagase
青春
39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。
ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。
さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?
そのほかに外伝も綴りました。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件
桜井正宗@オートスキル第1巻発売中
青春
修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。
高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。
どうやら、漂流して流されていたようだった。
帰ろうにも島は『無人島』。
しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。
男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?
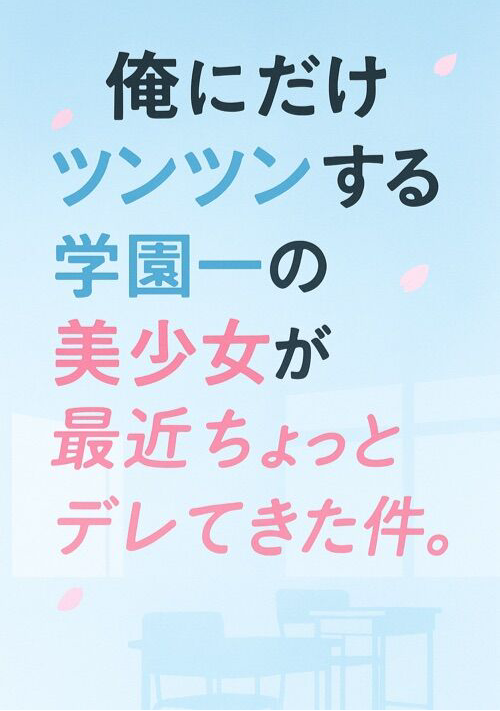
俺にだけツンツンする学園一の美少女が、最近ちょっとデレてきた件。
甘酢ニノ
恋愛
彼女いない歴=年齢の高校生・相沢蓮。
平凡な日々を送る彼の前に立ちはだかるのは──
学園一の美少女・黒瀬葵。
なぜか彼女は、俺にだけやたらとツンツンしてくる。
冷たくて、意地っ張りで、でも時々見せるその“素”が、どうしようもなく気になる。
最初はただの勘違いだったはずの関係。
けれど、小さな出来事の積み重ねが、少しずつ2人の距離を変えていく。
ツンデレな彼女と、不器用な俺がすれ違いながら少しずつ近づく、
焦れったくて甘酸っぱい、青春ラブコメディ。

意味が分かると怖い話(解説付き)
彦彦炎
ホラー
一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです
読みながら話に潜む違和感を探してみてください
最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください
実話も混ざっております
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















