9 / 56
第9話 それぞれの事情
しおりを挟む
(三人称視点)
Side ?????
奇妙な出で立ちの老人だ。
黒尽くめ。
まるで夜の闇をそのまま、纏ったような漆黒で統一された装束を着ていた。
中でも異様なのは顔半分を覆い隠さんとする大きな三角帽子である。
「ふむ」
老人の眼前にはチェック柄の遊戯盤が広げられていた。
縦八マス、横八マスの遊戯盤の上には白いピースと黒いピースがいくつか、置かれている。
老人が手にしていた白いピース――剣を持った騎士を模した駒――を盤上に置き、黒い大きなピースが一つ、砕け散った。
老人がその様子に満足したとでも言わんばかりに口角を上げると一陣の軽やかな風が吹いた。
ふと顔を上げた老人の向かいに純白のゴシックドレスを纏った少女が立っている。
「お祖父様。アレは事故。だから、今回は目を瞑ってくれません?」
「ああ。仕方なかろうよ。だが、必要以上の干渉はいかん」
「分かっているわ」
白金の色をした髪の少女が、大事そうに抱いている黒猫の喉を撫でると「みゃ」と一声鳴いて、黒猫は微睡んだ。
少女も黒猫もともに紅玉のように光で輝く、不思議な虹彩の瞳を持っていた。
「ルジェナが待っているから、帰るわね」
再び、一陣の風が吹くと少女の姿は幻のように消え失せていた。
「全く、相変わらず慌ただしい娘じゃのう」
老人のボヤキに答える者は誰もいない。
ただ、盤上の白いピースが二つ、燦然と輝きを見せるだけである。
Side マルチナ・ネドヴェト
その日、妹のユスティーナと登校したマルチナの心が晴れることはなかった。
数日前、末の妹アマーリエが二階から、転落して、怪我を負っていた。
幸いなことに目立った外傷はなかったものの意識が戻らないままである。
アマーリエはマルチナにとって、薬であり、毒だったと言える。
自分を慕ってくるまだ、あどけなさが残った可愛い妹であるのは間違いない。
だが、同時に貪欲に愛を求めようとするアマーリエのことをどこか、冷めた目線で見ているのも確かだったのだ。
それでなくてもデビュタントが間近に控えており、心身ともに疲れている時に起きたアマーリエの事故はマルチナにも暗い影を落とす。
長女として、母親がいない間は自分がしっかりしないといけないと思えば、思うほどに空回りする自分の気持ちに混乱していたのも大きかった。
仲の良い友人に「心配でしょうね」と声をかけられるたびに姉である自分がもっと何か、してあげるべきだったのではないかと言いようのない不安と罪悪感に襲われていた。
Side ユスティーナ・ネドヴェト
姉のマルチナと登校したユスティーナはその日、どこか不機嫌なままだった。
妹のアマーリエも含めた三人で登校し、元気でおしゃまなアマーリエのうるさいくらいなお喋りに付き合わされる。
それがユスティーナの日常であり、鬱陶しくも離れがたいという矛盾をはらんだ複雑な気持ちを抱いていた。
その日常が失われた。
行き場のない怒りを覚えているという自覚もない。
ユスティーナにとって、アマーリエが可愛い妹であるのに間違いない。
だが、どこか相容れないところがあり、事あるごとに衝突してたのも事実だった。
ユスティーナは怒りを憤りへと変換させた。
「あの子はまた、人の関心を引こうとしている」と憤慨することにした。
それがどれだけ、理不尽なことなのか、ユスティーナは分かっていなかった。
「あぁっ、もう! イライラする」
「ユナ! 集中しないと危ないぞ」
魔法科に比べて騎士科を選択する生徒も少数であり、騎士科の男女比は九対一で圧倒的に男子生徒しかいない。
これは将来、騎士を目指そうとする者しか、騎士科を選ばないことが大きく影響していた。
優秀な成績を収めた生徒は、優先的に騎士団への入団が認められるからだ。
だが、例え優秀ではなかったとしても卒業したという事実だけでも実力を認めてもらえる。
それほどに厳しいカリキュラムが組まれているのが騎士科なのである。
実技を伴った授業が多いのも特徴で実戦形式の組手が頻繁に行われる。
その日も騎士科の生徒数が少ないゆえ、学年や性別を問わず、木剣を使った組手での実習が行われていたのだ。
第二王子であるロベルトと侯爵令嬢であるユスティーナが、組手を行うのもさして、珍しいことではなかった。
「ロビーこそ、気が抜けてるんじゃないのっ!」
腹立ちまぎれに目を三角にしたユスティーナが、低い姿勢から繰り出した突きを払いで難なくいなしたロベルトだが、それ以上の反撃はせず、間合いを取る。
「ユナ。こういう時は落ち着かないと」
「うるさいっ」
困惑した表情を隠そうともしないロベルトと一方的にまくしたてるユスティーナの姿に周囲はいつもよりも酷いとは思いながらも誰も止めようとはしない。
結局、授業が終わるまで一方的に絡み続けるユスティーナだったが、腹立ちは収まるどころか、悪化の一途をたどっていた。
Side ユリアン・ポボルスキー
現在、十三歳のユリアンは宰相を務めるドゥシャン・ポボルスキーの三男として、この世に生を受けた。
既に成人しており、父親の補佐として活躍する長男。
騎士を目指し、実家を離れ、切磋琢磨している次男。
その二人からはやや年の離れた弟ということもあり、ある程度の自由と言えば、聞こえはいいが期待されることもなかった。
ユリアンとは年子で妹のサーラが生れると家族の興味と関心はサーラ一人が受けるものとなる。
しかし、ユリアンとサーラの仲が悪いということは決してなかった。
むしろ気が弱く、頼りない兄を引っ張る気が強く、しっかり者の妹としてうまくやっていたのである。
「ねぇ、お兄ちゃま」
「どうしたんだい?」
いつになく、元気のないサーラの声が心配になったユリアンが読んでいた書物から、目を上げると目を潤ませた妹の姿が視界に入った。
本を投げ出し、慌てて妹のもとに駆け寄ったユリアンは彼女が、傷だらけの黒猫を抱いていることに気が付いた。
「猫ちゃんが怪我してたの」
「そうか。うん。分かった。おとなしく待ってるんだよ」
ユリアンはべそをかく妹を椅子に座らせるとその頭を優しく、撫でてからどこかへと走っていく。
暫くすると応急処置を行うのに十分な包帯や消毒液を手にしたユリアンが現れた。
「こういうのは得意なんだ。お兄ちゃまに任せて」
「うん」
その言葉は嘘ではなく、手慣れた手つきで黒猫の傷を手当てし、器用に包帯を巻いていくユリアンの姿は普段、のんびりとした様子からは想像が出来ないほどにテキパキとしていた。
「ありがとう、お兄ちゃま」
サーラの満面の笑顔にユリアンはその日、満ち足りた気分のまま、夢の世界の住人となった。
そして、不思議な夢を見た。
サーラが連れてきたあの黒猫が元気な様子で駆け回り、ついてこいと言わんばかりにユリアンを促す。
首を傾げながらもユリアンが重い腰を上げ、黒猫の後についていくと黒猫が急に勢いよく、跳躍する。
跳躍した黒猫を受け止めたのは一人の少女だった。
ユリアンの記憶にはない少女だ。
折りからの風に靡く、やや色素の薄い白金色の長い髪に幻想的な美しさを感じ、ユリアンが息をするのも忘れ、見惚れていると紅玉のような輝きを放つ四つの瞳に見つめられていることに気付いた。
少女と黒猫の目だった。
ユリアンは人知れず、大事そうに黒猫を抱いた少女の浮かべる花笑みを呆けたように見つめるしかなかった。
「彼を助けてくれたお礼よ? あなたにも魔法をかけてあげるわ」
明くる朝、目を覚ましたユリアンは微かな頭痛を感じていた。
頭の奥の方に感じる針を刺されたような痛みだ。
しっかりと寝たはずなのに寝た気がしないのも不思議だった。
「『淑女への子守歌』って、なんだ? それじゃ、僕らは一体……」
ユリアンの呟きは誰の耳にも届くことなく、室内の静寂へと消えていった。
Side ?????
奇妙な出で立ちの老人だ。
黒尽くめ。
まるで夜の闇をそのまま、纏ったような漆黒で統一された装束を着ていた。
中でも異様なのは顔半分を覆い隠さんとする大きな三角帽子である。
「ふむ」
老人の眼前にはチェック柄の遊戯盤が広げられていた。
縦八マス、横八マスの遊戯盤の上には白いピースと黒いピースがいくつか、置かれている。
老人が手にしていた白いピース――剣を持った騎士を模した駒――を盤上に置き、黒い大きなピースが一つ、砕け散った。
老人がその様子に満足したとでも言わんばかりに口角を上げると一陣の軽やかな風が吹いた。
ふと顔を上げた老人の向かいに純白のゴシックドレスを纏った少女が立っている。
「お祖父様。アレは事故。だから、今回は目を瞑ってくれません?」
「ああ。仕方なかろうよ。だが、必要以上の干渉はいかん」
「分かっているわ」
白金の色をした髪の少女が、大事そうに抱いている黒猫の喉を撫でると「みゃ」と一声鳴いて、黒猫は微睡んだ。
少女も黒猫もともに紅玉のように光で輝く、不思議な虹彩の瞳を持っていた。
「ルジェナが待っているから、帰るわね」
再び、一陣の風が吹くと少女の姿は幻のように消え失せていた。
「全く、相変わらず慌ただしい娘じゃのう」
老人のボヤキに答える者は誰もいない。
ただ、盤上の白いピースが二つ、燦然と輝きを見せるだけである。
Side マルチナ・ネドヴェト
その日、妹のユスティーナと登校したマルチナの心が晴れることはなかった。
数日前、末の妹アマーリエが二階から、転落して、怪我を負っていた。
幸いなことに目立った外傷はなかったものの意識が戻らないままである。
アマーリエはマルチナにとって、薬であり、毒だったと言える。
自分を慕ってくるまだ、あどけなさが残った可愛い妹であるのは間違いない。
だが、同時に貪欲に愛を求めようとするアマーリエのことをどこか、冷めた目線で見ているのも確かだったのだ。
それでなくてもデビュタントが間近に控えており、心身ともに疲れている時に起きたアマーリエの事故はマルチナにも暗い影を落とす。
長女として、母親がいない間は自分がしっかりしないといけないと思えば、思うほどに空回りする自分の気持ちに混乱していたのも大きかった。
仲の良い友人に「心配でしょうね」と声をかけられるたびに姉である自分がもっと何か、してあげるべきだったのではないかと言いようのない不安と罪悪感に襲われていた。
Side ユスティーナ・ネドヴェト
姉のマルチナと登校したユスティーナはその日、どこか不機嫌なままだった。
妹のアマーリエも含めた三人で登校し、元気でおしゃまなアマーリエのうるさいくらいなお喋りに付き合わされる。
それがユスティーナの日常であり、鬱陶しくも離れがたいという矛盾をはらんだ複雑な気持ちを抱いていた。
その日常が失われた。
行き場のない怒りを覚えているという自覚もない。
ユスティーナにとって、アマーリエが可愛い妹であるのに間違いない。
だが、どこか相容れないところがあり、事あるごとに衝突してたのも事実だった。
ユスティーナは怒りを憤りへと変換させた。
「あの子はまた、人の関心を引こうとしている」と憤慨することにした。
それがどれだけ、理不尽なことなのか、ユスティーナは分かっていなかった。
「あぁっ、もう! イライラする」
「ユナ! 集中しないと危ないぞ」
魔法科に比べて騎士科を選択する生徒も少数であり、騎士科の男女比は九対一で圧倒的に男子生徒しかいない。
これは将来、騎士を目指そうとする者しか、騎士科を選ばないことが大きく影響していた。
優秀な成績を収めた生徒は、優先的に騎士団への入団が認められるからだ。
だが、例え優秀ではなかったとしても卒業したという事実だけでも実力を認めてもらえる。
それほどに厳しいカリキュラムが組まれているのが騎士科なのである。
実技を伴った授業が多いのも特徴で実戦形式の組手が頻繁に行われる。
その日も騎士科の生徒数が少ないゆえ、学年や性別を問わず、木剣を使った組手での実習が行われていたのだ。
第二王子であるロベルトと侯爵令嬢であるユスティーナが、組手を行うのもさして、珍しいことではなかった。
「ロビーこそ、気が抜けてるんじゃないのっ!」
腹立ちまぎれに目を三角にしたユスティーナが、低い姿勢から繰り出した突きを払いで難なくいなしたロベルトだが、それ以上の反撃はせず、間合いを取る。
「ユナ。こういう時は落ち着かないと」
「うるさいっ」
困惑した表情を隠そうともしないロベルトと一方的にまくしたてるユスティーナの姿に周囲はいつもよりも酷いとは思いながらも誰も止めようとはしない。
結局、授業が終わるまで一方的に絡み続けるユスティーナだったが、腹立ちは収まるどころか、悪化の一途をたどっていた。
Side ユリアン・ポボルスキー
現在、十三歳のユリアンは宰相を務めるドゥシャン・ポボルスキーの三男として、この世に生を受けた。
既に成人しており、父親の補佐として活躍する長男。
騎士を目指し、実家を離れ、切磋琢磨している次男。
その二人からはやや年の離れた弟ということもあり、ある程度の自由と言えば、聞こえはいいが期待されることもなかった。
ユリアンとは年子で妹のサーラが生れると家族の興味と関心はサーラ一人が受けるものとなる。
しかし、ユリアンとサーラの仲が悪いということは決してなかった。
むしろ気が弱く、頼りない兄を引っ張る気が強く、しっかり者の妹としてうまくやっていたのである。
「ねぇ、お兄ちゃま」
「どうしたんだい?」
いつになく、元気のないサーラの声が心配になったユリアンが読んでいた書物から、目を上げると目を潤ませた妹の姿が視界に入った。
本を投げ出し、慌てて妹のもとに駆け寄ったユリアンは彼女が、傷だらけの黒猫を抱いていることに気が付いた。
「猫ちゃんが怪我してたの」
「そうか。うん。分かった。おとなしく待ってるんだよ」
ユリアンはべそをかく妹を椅子に座らせるとその頭を優しく、撫でてからどこかへと走っていく。
暫くすると応急処置を行うのに十分な包帯や消毒液を手にしたユリアンが現れた。
「こういうのは得意なんだ。お兄ちゃまに任せて」
「うん」
その言葉は嘘ではなく、手慣れた手つきで黒猫の傷を手当てし、器用に包帯を巻いていくユリアンの姿は普段、のんびりとした様子からは想像が出来ないほどにテキパキとしていた。
「ありがとう、お兄ちゃま」
サーラの満面の笑顔にユリアンはその日、満ち足りた気分のまま、夢の世界の住人となった。
そして、不思議な夢を見た。
サーラが連れてきたあの黒猫が元気な様子で駆け回り、ついてこいと言わんばかりにユリアンを促す。
首を傾げながらもユリアンが重い腰を上げ、黒猫の後についていくと黒猫が急に勢いよく、跳躍する。
跳躍した黒猫を受け止めたのは一人の少女だった。
ユリアンの記憶にはない少女だ。
折りからの風に靡く、やや色素の薄い白金色の長い髪に幻想的な美しさを感じ、ユリアンが息をするのも忘れ、見惚れていると紅玉のような輝きを放つ四つの瞳に見つめられていることに気付いた。
少女と黒猫の目だった。
ユリアンは人知れず、大事そうに黒猫を抱いた少女の浮かべる花笑みを呆けたように見つめるしかなかった。
「彼を助けてくれたお礼よ? あなたにも魔法をかけてあげるわ」
明くる朝、目を覚ましたユリアンは微かな頭痛を感じていた。
頭の奥の方に感じる針を刺されたような痛みだ。
しっかりと寝たはずなのに寝た気がしないのも不思議だった。
「『淑女への子守歌』って、なんだ? それじゃ、僕らは一体……」
ユリアンの呟きは誰の耳にも届くことなく、室内の静寂へと消えていった。
182
あなたにおすすめの小説

地味で器量の悪い公爵令嬢は政略結婚を拒んでいたのだが
克全
恋愛
「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。
心優しいエヴァンズ公爵家の長女アマーリエは自ら王太子との婚約を辞退した。幼馴染でもある王太子の「ブスの癖に図々しく何時までも婚約者の座にいるんじゃない、絶世の美女である妹に婚約者の座を譲れ」という雄弁な視線に耐えられなかったのだ。それにアマーリエにも自覚があった。自分が社交界で悪口陰口を言われるほどブスであることを。だから王太子との婚約を辞退してからは、壁の花に徹していた。エヴァンズ公爵家てもつながりが欲しい貴族家からの政略結婚の申し込みも断り続けていた。このまま静かに領地に籠って暮らしていこうと思っていた。それなのに、常勝無敗、騎士の中の騎士と称えられる王弟で大将軍でもあるアラステアから結婚を申し込まれたのだ。

可愛い姉より、地味なわたしを選んでくれた王子様。と思っていたら、単に姉と間違えただけのようです。
ふまさ
恋愛
小さくて、可愛くて、庇護欲をそそられる姉。対し、身長も高くて、地味顔の妹のリネット。
ある日。愛らしい顔立ちで有名な第二王子に婚約を申し込まれ、舞い上がるリネットだったが──。
「あれ? きみ、誰?」
第二王子であるヒューゴーは、リネットを見ながら不思議そうに首を傾げるのだった。

「帰ったら、結婚しよう」と言った幼馴染みの勇者は、私ではなく王女と結婚するようです
しーしび
恋愛
「結婚しよう」
アリーチェにそう約束したアリーチェの幼馴染みで勇者のルッツ。
しかし、彼は旅の途中、激しい戦闘の中でアリーチェの記憶を失ってしまう。
それでも、アリーチェはルッツに会いたくて魔王討伐を果たした彼の帰還を祝う席に忍び込むも、そこでは彼と王女の婚約が発表されていた・・・
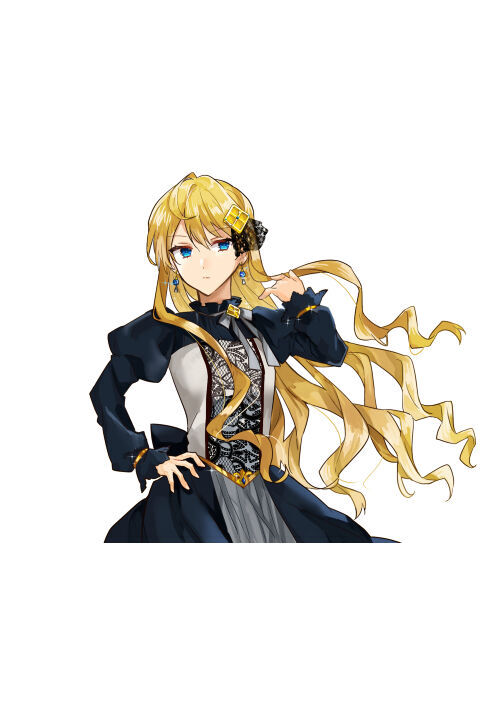
私はどうしようもない凡才なので、天才の妹に婚約者の王太子を譲ることにしました
克全
恋愛
「アルファポリス」「カクヨム」「小説家になろう」に同時投稿しています。
フレイザー公爵家の長女フローラは、自ら婚約者のウィリアム王太子に婚約解消を申し入れた。幼馴染でもあるウィリアム王太子は自分の事を嫌い、妹のエレノアの方が婚約者に相応しいと社交界で言いふらしていたからだ。寝食を忘れ、血の滲むほどの努力を重ねても、天才の妹に何一つ敵わないフローラは絶望していたのだ。一日でも早く他国に逃げ出したかったのだ。

永遠の誓いをあなたに ~何でも欲しがる妹がすべてを失ってからわたしが溺愛されるまで~
畔本グラヤノン
恋愛
両親に愛される妹エイミィと愛されない姉ジェシカ。ジェシカはひょんなことで公爵令息のオーウェンと知り合い、周囲から婚約を噂されるようになる。ある日ジェシカはオーウェンに王族の出席する式典に招待されるが、ジェシカの代わりに式典に出ることを目論んだエイミィは邪魔なジェシカを消そうと考えるのだった。

わたしの婚約者なんですけどね!
キムラましゅろう
恋愛
わたしの婚約者は王宮精霊騎士団所属の精霊騎士。
この度、第二王女殿下付きの騎士を拝命して誉れ高き近衛騎士に
昇進した。
でもそれにより、婚約期間の延長を彼の家から
告げられて……!
どうせ待つなら彼の側でとわたしは内緒で精霊魔術師団に
入団した。
そんなわたしが日々目にするのは彼を含めたイケメン騎士たちを
我がもの顔で侍らかす王女殿下の姿ばかり……。
彼はわたしの婚約者なんですけどね!
いつもながらの完全ご都合主義、
ノーリアリティのお話です。
少々(?)イライラ事例が発生します。血圧の上昇が心配な方は回れ右をお願いいたします。
小説家になろうさんの方でも投稿しています。

愛を知らないアレと呼ばれる私ですが……
ミィタソ
恋愛
伯爵家の次女——エミリア・ミーティアは、優秀な姉のマリーザと比較され、アレと呼ばれて馬鹿にされていた。
ある日のパーティで、両親に連れられて行った先で出会ったのは、アグナバル侯爵家の一人息子レオン。
そこで両親に告げられたのは、婚約という衝撃の二文字だった。

婚約破棄されたショックで前世の記憶を取り戻して料理人になったら、王太子殿下に溺愛されました。
克全
恋愛
「カクヨム」と「小説家になろう」にも投稿しています。
シンクレア伯爵家の令嬢ナウシカは両親を失い、伯爵家の相続人となっていた。伯爵家は莫大な資産となる聖銀鉱山を所有していたが、それを狙ってグレイ男爵父娘が罠を仕掛けた。ナウシカの婚約者ソルトーン侯爵家令息エーミールを籠絡して婚約破棄させ、そのショックで死んだように見せかけて領地と鉱山を奪おうとしたのだ。死にかけたナウシカだが奇跡的に助かったうえに、転生前の記憶まで取り戻したのだった。
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















