3 / 16
第三章
第三章
しおりを挟むわたしはてっきり中洲か天神あたりの店へ行くものと踏んでいたのだが、一歩先を行くお京は少し離れた商店や住宅が犇めき合う間の路地を暫し通って行く。
大分その辺を歩いた後、煙草を切らしたのをおもい出して目に止まった二十四時間営業の商店で購ったときである。店の向かい側にあった、おでん屋らしい暖簾をちょいと上げ、白い割烹着を着た女が「降ってくると」と空を見上げながら、中の誰かに言っている。
あたりは俄かに物気立つかと見る間もなく、吹落る疾風に葭簀や何やら倒れる音がすると、紙屑や塵芥などが丑三つ時の物の怪のように路の上を走っていく。すぐに稲妻が鋭く閃き、ゆるやかな雷の響につれてポツリポツリと大きな雨粒が落ちて来た。
吹き荒れる風と雨とに結った髪が乱れるのも構わず、片手で着物裾を持ち上げながら女が傘を差し出した。
「いや、わたしはいいから。お前は着物だろ」
「じゃ、よくって」
「ああ、いいから先へお出で。ついて行くから」
お京は路地へと入ると曲がるたび毎に、わたしが迷わぬかと振り返る。
やがて似たような高層の集合住宅が並ぶ、そのひとつに入った。
「あら、大変に濡れちまったわ」
傘をつぼめると、お京は自分のものよりも先に掌でわたしの上着の雫を払った。
「ここは、お前の家か?」
「拭いてあげるから、寄ってらっしゃい」
お京は玄関を開けると微笑んで見せた。
「いいのかな」
「拭いてあげるっていうのに。わたしだってお礼がしたいわよ」
「どんなお礼だ」
「だから、まぁ、お這入んなさいって」
雷の音は少し遠くなったが、雨は却って礫を打つように一層激しく降りそそぐのが、通路端にある踊り場のところでも伺える。跳ね上がる飛沫の烈しさに、わたしはとやかく言うのを止めて内に入った。
玄関には鈴とリボンのついた簾が下げてある。其の下にあった背の低い靴箱に腰をかけて靴を脱ぐ中に、お京は端折った裾も下ろさないまま自分とわたしの足を雑巾で拭いた。
「誰もいないから、お上がんなさい」
靴が傷まず乾くように立てかけて、居間へとわたしを案内してくれる。電燈を点けると、そこにはテーブルとソファがあった。
「一人暮らしなのかい?」
「ええ、昨夜まで、もう一人居たのよ。住替えしてね」
「お前さんが部屋を借りてるのかな」
「いいえ、お店がね。女の子たちのために用意している住まいなのよ」
「一人で居るなら暢気でいいや」
わたしはすすめられるがまま長椅子に座ると、ウヰスキーと氷やグラス水と酒の用意をする女の様子を見やった。
よく見ると童顔だが、年齢は二十三、四というところか。鼻筋の通った円顔に黒目勝ちの瞳も雲っていない、なかなかいい容貌である。
わたしは炊事場の方へちらりと目をやった。どういうわけか他のことはともかく、炊事場がかたづいてないと神経に障るところがわたしにはあった。食事後の食器が積み重ねられて放置されているような家を訪ねたときなどは、出されたお茶にも手を出したくない。ここの炊事場はすっかり清潔だった。
「上着を。ほんとに随分濡れたわね」
「ひどく降ったなぁ」
お京はわたしから上着を受け取ると形を整えて、桟のところに衣紋掛けで吊るした。
「わたし、雷さまが大嫌いなの」
懐紙で生え際の脂を拭きながら、お京は口を歪めるように尖らした。
「ちょっと着替えさせて。ね、あなた。お湯に入ります?」
そう言って隣の部屋に移ると薄い帳越しに両肌を脱ぐのが見えた。肌は白く、乳房は大きすぎず小さすぎず、形のよいものであった。
「何だかお前の檀那になったような気分だな」
「先に気兼ねなく呑んでらして」
「部屋はよく片づいてるね」
「毎日、掃除だけはちゃんとしますもの。こう見えても世帯持は上手よ」
「博多は長いのかい?」
「まだ、一年とちょっと……」
「商売は、こっちが初めてじゃないんだろう」
わたしは女の遊びをまんざら知らないわけではない。裾模様の単衣物に着替え、赤い弁慶縞の伊達締めを大きく前で結ぶ女の姿は、時空を超え明治年間の娼妓が現れたようである。
「いい趣向だね」
お京は衣紋を直しながら、わたしの側に坐ると空になったグラスを手にして酒を作り始めた。
「水割りでよろしいの?」
「そうだな、一対一で。で、朝までだといくらなるんだい、おぶ代は?」
お京は笑いながら話が早いと手を差し伸ばした。
「すみませんね。ほんとうに。御規則どおりだと、いまからなら四枚ってとこなんですけど…」
「縁起だから御祝儀をつけるよ」
紙入れから色をつけて福澤諭吉を五枚取り出し渡すと、女はそこから二枚だけ取り火を点けた煙草といっしょに残りは返してくれた。
「もう引けたあとだから。でも、何も受け取らないと気兼ねなく遊べないというものでしょう?」
わたしはそう仄めかす女の細く、さきほど覗いた肌よりなお白い手を取って身を引き寄せ耳元で囁いた。その言葉にお京は目を見張って睨み返しながら甘えた声を返した。
「馬鹿。知らないわよ……」
そう言いさま、わたしの肩を軽く撲るのだった。
続
0
お気に入りに追加
5
あなたにおすすめの小説

Last Mail
凛七星
現代文学
裏社会に足をつけて先の見えない暮らしぶりをしていた元バンドマンの三十路男と、身を売られて日本に密入国してきた中国女との間に、ほのかでかすかなやりとりから生まれる淡い関係。しかし、そんな二人は、やがておもわぬ出来事の中で、それぞれ不思議な感情にとらわれていくが……。

その男、人の人生を狂わせるので注意が必要
いちごみるく
現代文学
「あいつに関わると、人生が狂わされる」
「密室で二人きりになるのが禁止になった」
「関わった人みんな好きになる…」
こんな伝説を残した男が、ある中学にいた。
見知らぬ小グレ集団、警察官、幼馴染の年上、担任教師、部活の後輩に顧問まで……
関わる人すべてを夢中にさせ、頭の中を自分のことで支配させてしまう。
無意識に人を惹き込むその少年を、人は魔性の男と呼ぶ。
そんな彼に関わった人たちがどのように人生を壊していくのか……
地位や年齢、性別は関係ない。
抱える悩みや劣等感を少し刺激されるだけで、人の人生は呆気なく崩れていく。
色んな人物が、ある一人の男によって人生をジワジワと壊していく様子をリアルに描いた物語。
嫉妬、自己顕示欲、愛情不足、孤立、虚言……
現代に溢れる人間の醜い部分を自覚する者と自覚せずに目を背ける者…。
彼らの運命は、主人公・醍醐隼に翻弄される中で確実に分かれていく。
※なお、筆者の拙作『あんなに堅物だった俺を、解してくれたお前の腕が』に出てくる人物たちがこの作品でもメインになります。ご興味があれば、そちらも是非!
※長い作品ですが、1話が300〜1500字程度です。少しずつ読んで頂くことも可能です!

芙蓉の宴
蒲公英
現代文学
たくさんの事情を抱えて、人は生きていく。芙蓉の花が咲くのは一度ではなく、猛暑の夏も冷夏も、花の様子は違ってもやはり花開くのだ。
正しいとは言えない状況で出逢った男と女の、足掻きながら寄り添おうとするお話。
表紙絵はどらりぬ様からいただきました。

百合ランジェリーカフェにようこそ!
楠富 つかさ
青春
主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?
ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!
※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。
表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。
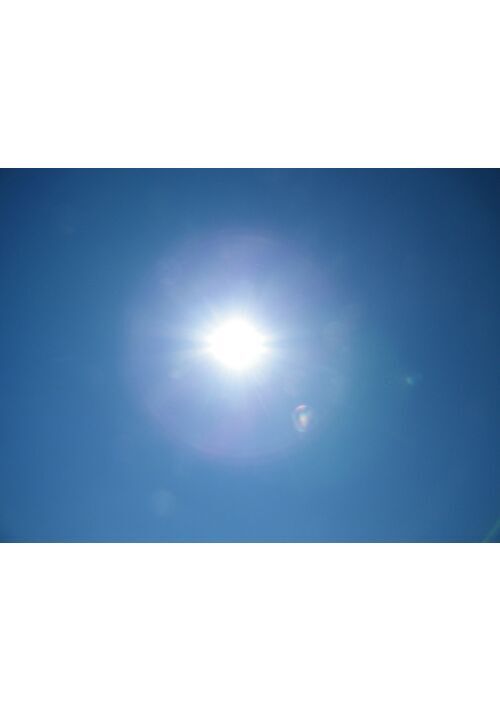
天穹は青く
梅林 冬実
現代文学
母親の無理解と叔父の存在に翻弄され、ある日とうとう限界を迎えてしまう。
気付けば傍に幼い男の子がいて、その子は尋ねる。「どうしたの?」と。
普通に生きたい。それだけだった。頼れる人なんて、誰もいなくて。
不意に訪れた現実に戸惑いつつも、自分を見つめ返す。その先に見えるものとは。


水神の棲む村
月詠世理
恋愛
辺境の閉鎖された村では伝統を大切にしていた。今までのしきたりなどを破るものは排除の対象。
ある女が小さな女の子を拾った。それまでは、村の人々と良い関係を築けていたのだろう。しかし、村の人々は子どもを拾った女を虐げた。
村の人々は女に言う。
「お前は、水神の供物だ。村の恵みのために、生贄になるのだ」
ある女はその言葉に蕩けるような笑みを浮かべた。
(※中編)
(※45話(最終話)で完結済)

読めない喫茶店
宇野片み緒
現代文学
生真面目な新卒営業マン・澤口、
うんちく好きで変わり者の店主・松虫、
ジャズロックバンド『シグ』の姉弟、
そして彼らを取り巻く人々。
読み間違いをきっかけに、
交流は広がってゆく──
カバーイラスト/間取り図:goto
装丁/作中字/本文:宇野片み緒
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる





















