3 / 8
第三話 水夫シルク
しおりを挟む
「イミシュ、開けるぜ」
掌砲長のイシュは船長室の扉を開けながら言った。
室内は広かったが、海賊船というよりは商船の船長室のようにシンプルな内装をしていた。本棚がいくつか天井から吊るされており、本が落ちないように前に棒を通し、留金をつけていた。船長イミシュはどうやら読書家らしい。
少年が辺りを見回していると、「彼が例の子供だな」と机越しの船長が話を始めた。少年の背中を押す水夫アクバルが応える。
「そうです、船長。ああそうだ。君、名前はなんだっけな」
少年は自分が名乗っていないことに気づくと慌てて船長の瞳を見上げて言った。
「僕はシルクと言います。シルク・トール」
「背が高い(トール)ねぇ……ふぅん」
掌砲長イシュの鼻で笑う声には、小さなシルク少年は応えなかった。その代わり、イシュの左足をアクバルが踏みつけ、彼は「ギャン」と悲鳴をあげた。
「二人とも、落ち着きなさい。それで、シルクくん。君はどうしたいのかね?」
船長イミシュは誰よりも落ち着いた声色でシルク少年に訊ねた。シルクは船長を見つめて再び口を開いた。
「僕は、一度命が消えたようなものです。それでも、生き抜きたいのです。海に突き落とされ、行方不明になった父は昔から言っていました。『生き抜いた者が正しいのだ』と。だから、僕も知りたい。生き抜いて、何が正しいのかを……!」
シルク少年の瞳は、部屋を照らす蝋燭の灯りよりも激しく燃えていた。船長イミシュは後ろで腕を組み少年の目の前へと歩く。向かい合い、瞳と瞳を合わせる。
「……良いでしょう。シルク・トール、君の覚悟は見せてもらった。君には後ろのアクバルと同じ水夫としてチャルチウィトリクエ号で働いてもらおう。アクバル、イシュ、船内を案内してやってくれ」
「アイアイサー」
船長室の扉を開けた途端、野次馬の船員たちが蜘蛛の子を散らすように持ち場へと戻っていった。どうも皆で盗み聞きをしていたらしい。全く、おかしな海賊たちだ。
シルク少年はまず、甲板掃除をする水夫キブとチュエンに挨拶をした。
「俺はキブ。戦うのと雑用が好きだから水夫をやっている」
クールに振る舞う、独特の髪飾りを付けた赤い瞳のキブはシルクの手を握った。
「うちはチュエンや。若いけえ水夫や。よろしくな」
女性のような高い声を持ち、青髪に青い瞳のチュエンもキブと同じように握手する。すると彼は甲高い悲鳴をあげた。「なんだなんだ」とアクバルとイシュがチュエンの顔を見る。
「シルク、あんためっちゃ肌スベスベやん!ええなあ、かわええなあ!」
そう、シルク少年の肌はそれこそ絹のように滑らかな触り心地なのである。すると、「かわいい」という言葉を聞きつけた男が息を切らしながら甲板に上がってきた。
「ハア、ハア……『かわいい』と聞いてすっ飛んできたぜ……」
茶色の跳ねた髪をした赤い瞳の変な男はシルク少年を見て真顔に戻った。
「子供への接触は俺の変態プライドに背くぜ……じゃあな」
彼は再び船内へと去っていく。
(なんだったんだ……)というシルク少年の表情を見てアクバルが説明した。
「あいつはラマト。変態だ。よし、次は俺たちの自己紹介をしておくか。俺はアクバル。同じ水夫だから仲良くしてくれよな」
アクバルの隣のイシュは、シルク少年の結んだ髪をぐしゃぐしゃに撫でながら言う。
「俺はイシュ。船長イミシュの弟なんかじゃねえぞ。火薬管理とか船員を鍛える掌砲長をやってる」
シルク少年は「よろしくお願いします」と応えるが、「この船の上ではもっとラフでいい」と言われた。
その後、船首から船尾、船底まで挨拶をしながら案内をしてもらった。シルク少年は二十人の船員の名前と顔をすぐに覚えることができた。皆個性的だからだ。
船長イミシュ、副船長キミ、海尉チクチャン、航海士カワク、掌帆長イク、掌砲長イシュ、主計長マニク、船医アハウ、操舵手メン、ベン、縫帆手カン、ラマト、音楽家カバン、船大工エブ、オク、料理人ムルク、エツナブ、水夫アクバル、キブ、チュエン、そしてシルクが加わり、ブリッグ船チャルチウィトリクエ号は総勢二十一人の命を乗せている。
この船はどこを目指しているのか、そして何を成すのか。シルク少年は胸元に隠した鍵を握りしめ、沈黙の海を眺めた。
掌砲長のイシュは船長室の扉を開けながら言った。
室内は広かったが、海賊船というよりは商船の船長室のようにシンプルな内装をしていた。本棚がいくつか天井から吊るされており、本が落ちないように前に棒を通し、留金をつけていた。船長イミシュはどうやら読書家らしい。
少年が辺りを見回していると、「彼が例の子供だな」と机越しの船長が話を始めた。少年の背中を押す水夫アクバルが応える。
「そうです、船長。ああそうだ。君、名前はなんだっけな」
少年は自分が名乗っていないことに気づくと慌てて船長の瞳を見上げて言った。
「僕はシルクと言います。シルク・トール」
「背が高い(トール)ねぇ……ふぅん」
掌砲長イシュの鼻で笑う声には、小さなシルク少年は応えなかった。その代わり、イシュの左足をアクバルが踏みつけ、彼は「ギャン」と悲鳴をあげた。
「二人とも、落ち着きなさい。それで、シルクくん。君はどうしたいのかね?」
船長イミシュは誰よりも落ち着いた声色でシルク少年に訊ねた。シルクは船長を見つめて再び口を開いた。
「僕は、一度命が消えたようなものです。それでも、生き抜きたいのです。海に突き落とされ、行方不明になった父は昔から言っていました。『生き抜いた者が正しいのだ』と。だから、僕も知りたい。生き抜いて、何が正しいのかを……!」
シルク少年の瞳は、部屋を照らす蝋燭の灯りよりも激しく燃えていた。船長イミシュは後ろで腕を組み少年の目の前へと歩く。向かい合い、瞳と瞳を合わせる。
「……良いでしょう。シルク・トール、君の覚悟は見せてもらった。君には後ろのアクバルと同じ水夫としてチャルチウィトリクエ号で働いてもらおう。アクバル、イシュ、船内を案内してやってくれ」
「アイアイサー」
船長室の扉を開けた途端、野次馬の船員たちが蜘蛛の子を散らすように持ち場へと戻っていった。どうも皆で盗み聞きをしていたらしい。全く、おかしな海賊たちだ。
シルク少年はまず、甲板掃除をする水夫キブとチュエンに挨拶をした。
「俺はキブ。戦うのと雑用が好きだから水夫をやっている」
クールに振る舞う、独特の髪飾りを付けた赤い瞳のキブはシルクの手を握った。
「うちはチュエンや。若いけえ水夫や。よろしくな」
女性のような高い声を持ち、青髪に青い瞳のチュエンもキブと同じように握手する。すると彼は甲高い悲鳴をあげた。「なんだなんだ」とアクバルとイシュがチュエンの顔を見る。
「シルク、あんためっちゃ肌スベスベやん!ええなあ、かわええなあ!」
そう、シルク少年の肌はそれこそ絹のように滑らかな触り心地なのである。すると、「かわいい」という言葉を聞きつけた男が息を切らしながら甲板に上がってきた。
「ハア、ハア……『かわいい』と聞いてすっ飛んできたぜ……」
茶色の跳ねた髪をした赤い瞳の変な男はシルク少年を見て真顔に戻った。
「子供への接触は俺の変態プライドに背くぜ……じゃあな」
彼は再び船内へと去っていく。
(なんだったんだ……)というシルク少年の表情を見てアクバルが説明した。
「あいつはラマト。変態だ。よし、次は俺たちの自己紹介をしておくか。俺はアクバル。同じ水夫だから仲良くしてくれよな」
アクバルの隣のイシュは、シルク少年の結んだ髪をぐしゃぐしゃに撫でながら言う。
「俺はイシュ。船長イミシュの弟なんかじゃねえぞ。火薬管理とか船員を鍛える掌砲長をやってる」
シルク少年は「よろしくお願いします」と応えるが、「この船の上ではもっとラフでいい」と言われた。
その後、船首から船尾、船底まで挨拶をしながら案内をしてもらった。シルク少年は二十人の船員の名前と顔をすぐに覚えることができた。皆個性的だからだ。
船長イミシュ、副船長キミ、海尉チクチャン、航海士カワク、掌帆長イク、掌砲長イシュ、主計長マニク、船医アハウ、操舵手メン、ベン、縫帆手カン、ラマト、音楽家カバン、船大工エブ、オク、料理人ムルク、エツナブ、水夫アクバル、キブ、チュエン、そしてシルクが加わり、ブリッグ船チャルチウィトリクエ号は総勢二十一人の命を乗せている。
この船はどこを目指しているのか、そして何を成すのか。シルク少年は胸元に隠した鍵を握りしめ、沈黙の海を眺めた。
0
あなたにおすすめの小説


【もふもふ手芸部】あみぐるみ作ってみる、だけのはずが勇者ってなんなの!?
釈 余白(しやく)
児童書・童話
網浜ナオは勉強もスポーツも中の下で無難にこなす平凡な少年だ。今年はいよいよ最高学年になったのだが過去5年間で100点を取ったことも運動会で1等を取ったこともない。もちろん習字や美術で賞をもらったこともなかった。
しかしそんなナオでも一つだけ特技を持っていた。それは編み物、それもあみぐるみを作らせたらおそらく学校で一番、もちろん家庭科の先生よりもうまく作れることだった。友達がいないわけではないが、人に合わせるのが苦手なナオにとっては一人でできる趣味としてもいい気晴らしになっていた。
そんなナオがあみぐるみのメイキング動画を動画サイトへ投稿したり動画配信を始めたりしているうちに奇妙な場所へ迷い込んだ夢を見る。それは現実とは思えないが夢と言うには不思議な感覚で、沢山のぬいぐるみが暮らす『もふもふの国』という場所だった。
そのもふもふの国で、元同級生の丸川亜矢と出会いもふもふの国が滅亡の危機にあると聞かされる。実はその国の王女だと言う亜美の願いにより、もふもふの国を救うべく、ナオは立ち上がった。
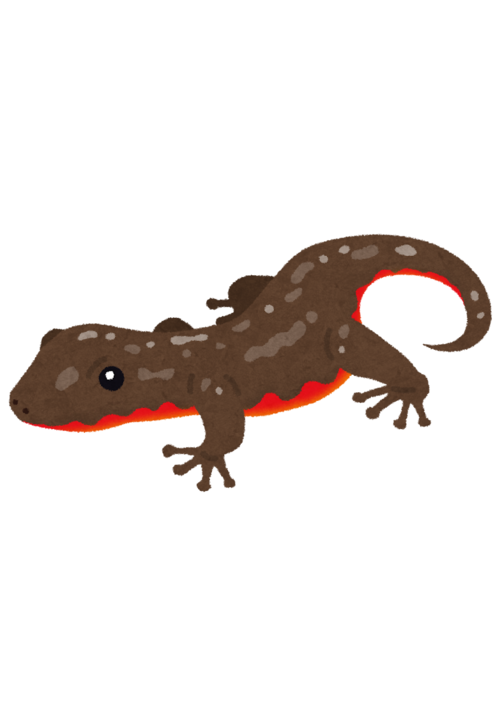

おっとりドンの童歌
花田 一劫
児童書・童話
いつもおっとりしているドン(道明寺僚) が、通学途中で暴走車に引かれてしまった。
意識を失い気が付くと、この世では見たことのない奇妙な部屋の中。
「どこ。どこ。ここはどこ?」と自問していたら、こっちに雀が近づいて来た。
なんと、その雀は歌をうたい狂ったように踊って(跳ねて)いた。
「チュン。チュン。はあ~。らっせーら。らっせいら。らせらせ、らせーら。」と。
その雀が言うことには、ドンが死んだことを(津軽弁や古いギャグを交えて)伝えに来た者だという。
道明寺が下の世界を覗くと、テレビのドラマで観た昔話の風景のようだった。
その中には、自分と瓜二つのドン助や同級生の瓜二つのハナちゃん、ヤーミ、イート、ヨウカイ、カトッぺがいた。
みんながいる村では、ヌエという妖怪がいた。
ヌエとは、顔は鬼、身体は熊、虎の手や足をもち、何とシッポの先に大蛇の頭がついてあり、人を食べる恐ろしい妖怪のことだった。
ある時、ハナちゃんがヌエに攫われて、ドン助とヤーミがヌエを退治に行くことになるが、天界からドラマを観るように楽しんで鑑賞していた道明寺だったが、道明寺の体は消え、意識はドン助の体と同化していった。
ドン助とヤーミは、ハナちゃんを救出できたのか?恐ろしいヌエは退治できたのか?

小さな歌姫と大きな騎士さまのねがいごと
石河 翠
児童書・童話
むかしむかしとある国で、戦いに疲れた騎士がいました。政争に敗れた彼は王都を離れ、辺境のとりでを守っています。そこで彼は、心優しい小さな歌姫に出会いました。
歌姫は彼の心を癒し、生きる意味を教えてくれました。彼らはお互いをかけがえのないものとしてみなすようになります。ところがある日、隣の国が攻めこんできたという知らせが届くのです。
大切な歌姫が傷つくことを恐れ、歌姫に急ぎ逃げるように告げる騎士。実は高貴な身分である彼は、ともに逃げることも叶わず、そのまま戦場へ向かいます。一方で、彼のことを諦められない歌姫は騎士の後を追いかけます。しかし、すでに騎士は敵に囲まれ、絶対絶命の危機に陥っていました。
愛するひとを傷つけさせたりはしない。騎士を救うべく、歌姫は命を賭けてある決断を下すのです。戦場に美しい花があふれたそのとき、騎士が目にしたものとは……。
恋した騎士にすべてを捧げた小さな歌姫と、彼女のことを最後まで待ちつづけた不器用な騎士の物語。
扉絵は、あっきコタロウさんのフリーイラストを使用しています。

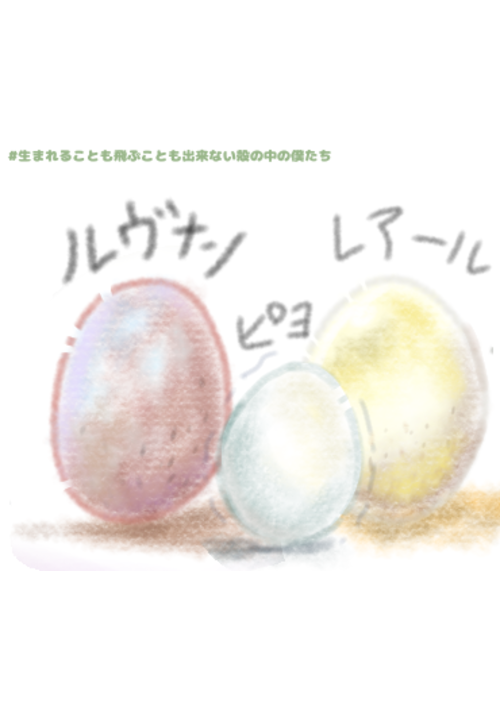
生まれることも飛ぶこともできない殻の中の僕たち
はるかず
児童書・童話
生まれることもできない卵の雛たち。
5匹の殻にこもる雛は、卵の中でそれぞれ悩みを抱えていた。
一歩生まれる勇気さえもてない悩み、美しくないかもしれない不安、現実の残酷さに打ちのめされた辛さ、頑張れば頑張るほど生まれることができない空回り、醜いことで傷つけ傷つけられる恐怖。
それぞれがそれぞれの悩みを卵の中で抱えながら、出会っていく。
彼らは世界の美しさを知ることができるのだろうか。

ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















