お気に入りに追加
3
あなたにおすすめの小説

忍者同心 服部文蔵
大澤伝兵衛
歴史・時代
八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。
服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。
忍者同心の誕生である。
だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。
それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

証なるもの
笹目いく子
歴史・時代
あれは、我が父と弟だった。天保11年夏、高家旗本の千川家が火付盗賊改方の襲撃を受け、当主と嫡子が殺害された−−。千川家に無実の罪を着せ、取り潰したのは誰の陰謀か?実は千川家庶子であり、わけあって豪商大鳥屋の若き店主となっていた紀堂は、悲嘆の中探索と復讐を密かに決意する。
片腕である大番頭や、許嫁、親友との間に広がる溝に苦しみ、孤独な戦いを続けながら、やがて紀堂は巨大な陰謀の渦中で、己が本当は何者であるのかを知る。
絡み合う過去、愛と葛藤と後悔の果てに、紀堂は何を選択するのか?(性描写はありませんが暴力表現あり)


紅花の煙
戸沢一平
歴史・時代
江戸期、紅花の商いで大儲けした、実在の紅花商人の豪快な逸話を元にした物語である。
出羽尾花沢で「島田屋」の看板を掲げて紅花商をしている鈴木七右衛門は、地元で紅花を仕入れて江戸や京で売り利益を得ていた。七右衛門には心を寄せる女がいた。吉原の遊女で、高尾太夫を襲名したたかである。
花を仕入れて江戸に来た七右衛門は、競を行ったが問屋は一人も来なかった。
七右衛門が吉原で遊ぶことを快く思わない問屋達が嫌がらせをして、示し合わせて行かなかったのだ。
事情を知った七右衛門は怒り、持って来た紅花を品川の海岸で燃やすと宣言する。

かくされた姫
葉月葵
歴史・時代
慶長二十年、大坂夏の陣により豊臣家は滅亡。秀頼と正室である千姫の間に子はなく、側室との間に成した息子は殺され娘は秀頼の正室・千姫の嘆願によって仏門に入ることを条件に助命された――それが、現代にまで伝わる通説である。
しかし。大坂夏の陣の折。大坂城から脱出した千姫は、秀頼の子を宿していた――これは、歴史上にその血筋を隠された姫君の物語である。

西涼女侠伝
水城洋臣
歴史・時代
無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超
舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。
役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。
家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。
ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。
荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。
主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。
三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)
涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

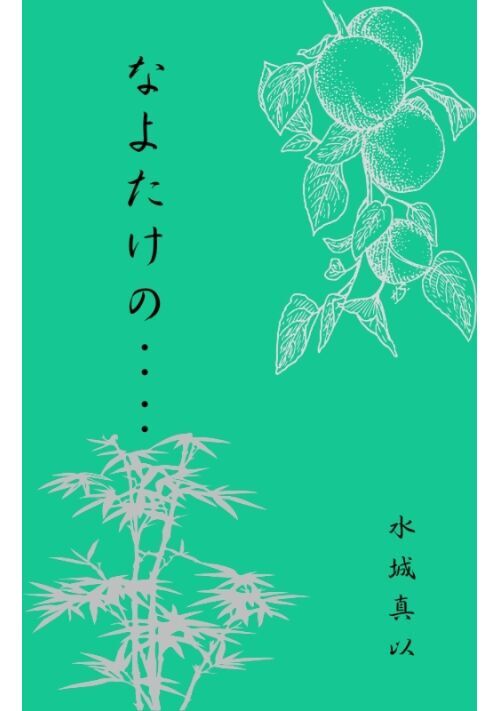
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















