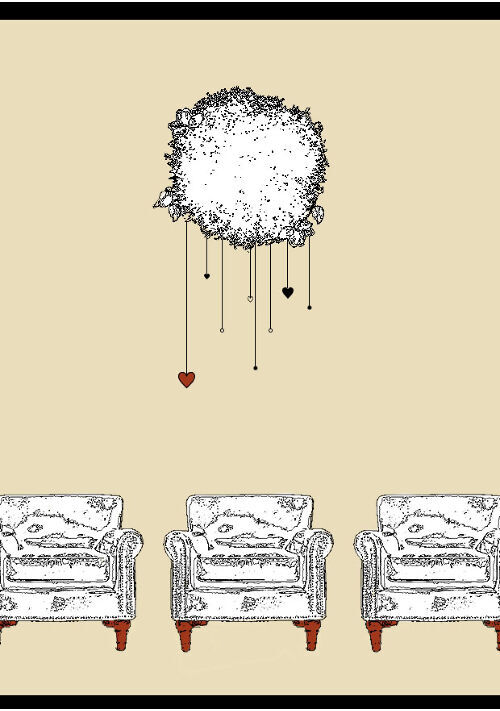6 / 16
第一章 第六節
表と裏
しおりを挟む
薄紫ノ僧に再び招集がかかったのは、世緒の儀式から一週間が経った日のことだった。午後の講義をすべて終わらせた澄史は、時間がないので講義でつかった書物や香道具を両腕に抱えたまま、急ぎ足で大広間へ向かった。
部屋に着くと、すでに薄紫ノ僧のほとんどが揃っていた。皆、興奮気味に今日の召集の理由について囁き合っている。
「あれから、天威皇子はどんな容態か知ってるか?」
「さあ。だから俺たちがここに呼ばれてるんだろ?」
「なあ聞いたか?あの世緒とやら、ここの薄墨ノ僧の棟に泊ってるらしいぜ。」
「本当か?なら……」
部屋を満たすざわめきと熱気に、澄史は何だかくらくらとしてきた。人が集まるところは嫌いだ。とくに薄紫ノ僧の間では、澄史は尊敬と羨望の的であり、要するに敬遠されている存在だ。自分をそんな風に見てくる人間の集団の中でじっとしていなければいけない時間は、澄史にとってはいつも耐え難いものだった。
(いや、今はみんな世緒や天威皇子のことを話していて、誰も俺のことなんか話してない。)
そう自分に言い聞かせ、一つ深呼吸すると、空いている場所を探そうと広間を見渡した。と、部屋の中央辺りに座っている僧と偶然目が合った。その瞬間、彼の目に何とも言えぬ気まずさのような、居心地の悪さのようなものが浮かぶのが見え、澄史は胸の中をざらざらした何かで撫でられているような不快感を覚えた。
(俺を見るだけで嫌なのか?何なんだ…。いや、まぁ俺が気にし過ぎているだけかもしれないけど。)
澄史は深く溜め息をつくと、部屋の左端に見つけた空いている座布団へ腰を下ろした。
しばらくすると、前方の御簾がするすると上がり、藤月和尚の姿が前にいる僧の肩越しに見えた。先ほどまで部屋を満たしていた囁き声が、引き波のように消えていく。部屋が完全に静まり返ると、藤月和尚はよく通る低い声で話しはじめた。
「今日は皆に重要な報告がありここに集まってもらった。私も多忙な皆の時間を取りたくないと思うておる故、手短にいきたい。今日皆を呼び出したのは、他でもない、天威皇子のご容態について報告があるからだ。」
一瞬にして部屋中に緊張が走る。
「喜ばしいことに、天威皇子は順調に回復に向かわれている。あの儀式の三日後に意識を取り戻され、そこから段々とお話しもされるようになり、昨日などは少しではあるが薬膳粥をお召し上がりになった。」
しんと静まり返った部屋に、声にならない驚きが広がった。
「世緒によれば、このまま何も問題がなければあと数日で完治は間違いないとのことだ。」
沈黙がさらに深まる。と、前列に座っていた僧が恐る恐る手を挙げた。
「…お、恐れながら、一つ、お尋ねしてもよろしいでしょうか、藤月和尚…。天威皇子が回復なされたのは、も、もちろん大変喜ばしい知らせでこざいます。し、しかし…我々忠清寺ではなく、世緒の儀式によって皇子が回復なされた今…我々はどうなってしまうのでしょうか…?」
これは、この大広間に集まる薄紫ノ僧全員が抱いている問いだった。雅真ノ国で帝に最も厚い信頼を寄せられているはずの忠清寺が、肝心な時に何もできず、どこの馬の骨とも分からない流れ者に功績を取られた今、その名声は地に落ちたも同然である。
「…うむ。皆には正直に話さねばなるまい。帝が我々に失望なさった、というのは否めない。…実際、帝は宮仕えの寺院の再編成をご検討されている。」
広間のここそこで息をのむ声が聞こえてきた。宮仕えの寺院とは、帝の政の補佐をするために選ばれた寺のことだ。複数の異なる寺院や宗派が指名されることもあるが、ここ数十年では、毎年宰相を輩出している忠清寺がその座を独占していた。忠清寺だけであっても、その中の限られた地位をめぐって激しい競争がなされているのに、新たな宗派や寺が加わればさらに厳しい戦いになる。
「落ち着け、皆の者。まだ『検討されている』に過ぎない。今回の件だけで、あの得体のしれない世緒とやらを我々忠清寺に代わって宮廷に置くのは尚早だと、紫ノ僧正様方が進言され、帝もそれを考慮されている。それに、まだ実際に再編成がなされたわけではないのだ。しかし、今回の件のために忠清寺の威信が揺らいだのも事実。今我々にできることは、ただ己の術を磨き霊力を高めることのみだ。わかるな。」
「し、しかし、それでは世緒に勝つことは…」
藤月和尚は、声のした方に氷のような冷たい視線を向けると、同じように冷たい口調で言い放った。
「雲月、そなた、桐和宗忠清寺があの流れ者に劣ると申すか。」
「い、いえ、もちろんそんなことはございません。違います…。私はただ…」
「世緒についてはこちらで出来る限りの調べをしている。そなたたちは余計な詮索をせずともよい。今はただ目の前の務めに励むことだ。よいか。」
有無を言わさぬ強い口調に、広間はしんと静まり返った。
「ほかに、少しでも忠清寺に疑いの心を持つ者はおるか。そのような者はいつでも薄墨ノ僧からやり直す許可を与えよう。」
辺りに凍り付いたような沈黙が流れる。澄史は俯いて、なぜかうるさいほど鳴っている自分の心臓の音を聞いていた。
「それではここで解散とする。澄史、そなたはここに残っているように。」
澄史はびくりとして顔を上げた。
(え、何だろう…。俺、何かしたかな。)
不安な面持ちで正座する澄史の横を、緊張の解けた他の僧たちががやがやと話しながらすり抜けていく。
「澄史だから……だろ。いつも修行ばっか……だよ。」
「知らね。また何か……『第二の神童』はやっぱり……」
「…あいつ見るとさ……もっと修行しないとって焦るし。……だから…」
途切れとぎれに聞こえてくる言葉と、時折感じる訝しげな視線が澄史の心をえぐる。
(もういい加減、こんなの慣れたはずなのにな。…心に瘡蓋はできないものなのかな。)
もしもできるのであれば、澄史の心の皮膚はとうの昔に分厚く硬くなっていて、このような冷たい目線にも言葉にも全く動じないようになっていただろう。
と、澄史は突然肩を叩かれて顔を上げた。すぐ目の前には、にやりと笑った緑雨が自分を見下ろしている。
「ついに澄史様もやらかしたか。何したんだ?」
「緑雨!びっくりさせないでくれよ。いや、俺は別に何もしてないはずだけど…。でも俺が自分で気づいてないだけで何かしたのかもしれない。」
不安そうにつぶやく澄史の肩に、緑雨は腕を回した。
「ま、怒られたら後で俺の部屋でも来いよ。俺特製の苦っが~い薬湯でも作って忘れさせてやるからさ。」
「それは感謝すればいいのか、怒られた俺へのさらなる嫌がらせと取ればいいのか、どっちなんだ…。」
「ま、とにかくだ。そんな暗い顔しないで藤月和尚んとこ行って来いよ。行ったら分かるんだし。」
そう言うと緑雨は澄史の腕を引っ張って立たせ、彼の背中をぽんぽんと叩いた。
「ありがとう。本当に後でお前の部屋に寄らせてもらうかも。」
緑雨はにっと笑うと、くるりと踵を返して部屋を出ていった。
少しして、最後の一人の僧が広間を出ていき、澄史は藤月と向かい合って正座していた。
「急に呼び出してすまぬな、澄史。」
「とんでもありません、藤月和尚。」
「そなたが何か良からぬことをしでかした、などという用件ではないから安心せよ。」
そこで藤月和尚は言葉を切った。罰せられるわけではないと分かったのは良かったが、全く見当がつかない分、澄史の緊張は高まる。
「実はそなたに、重大な任務を任せることになった。紫ノ僧正様全員からの直々のご命令だ。」
「!」
驚きと困惑で、澄史は目を見開いた。
「まだ大事にしたくないとの帝のご意向ゆえ、先ほどは皆に伝えなかったのだが、最近、白海部――門外へ出たことのないそなたでもこれくらいは知っておるな?この国で主に貧しい者たちが住まう海岸沿いの地域だ――で、天威皇子がかかられたものと同じ病にかかった者が十数名いるらしいのだ。そこで、帝は世緒を白海部へ遣わし、調査するよう命じられた。誠に遺憾だが、今のところ気奴しかあの病を治せる者がいないのでな。しかし、あれがどこからともなく突然現れた異人であるのも事実。加えて――」
和尚はここで一旦言葉を切ると、改めて澄史をじっと見据えた。
「世緒にこれ以上の功績をあげられては、忠清寺の立場が危うい。して、紫ノ僧正様方が何とか帝を説得し、気奴の監視という役目で忠清寺から僧を一人、奴に同行させる許しを得られた。高齢な紫ノ僧正様方や私のような者では、長旅になるであろうこの任務は務まらぬ。そこでだ、澄史、そなたに行ってもらいたい。」
あまりに突然のことで、澄史は返事をしようとしたが言葉がまったく出てこない。藤月和尚はそんな彼の様子など気にもとめず続けた。
「ここまで聞けば聡いそなたならばとうに読めているだろうが、当然『監視』というのは建前だ。そなたがせねばならぬのは、世緒の技を盗むこと――加えて、奴を消すことだ。」
澄史は呆気に取られた。
「け、消す、とは…」
「落ち着け、澄史。何もそなたに手を下してもらいたいわけではない。そなたは修行僧であって殺しの道を歩む者ではないし、そなたが返り討ちになることも考えられる。相手は力量の分からぬ流れ者だからな。万一のこともあり得る。して、実際に気奴を消すのは《飛影》だ。彼らには、そなたと気奴を常に監視し、そなたが奴の治癒の方法を会得した時点で奴を殺すよう命じてある。」
「《飛影》…?」
「そうか、次期宰相候補のそなたにはすでに話したと思うておったが。《飛影》というのは、忠清寺について秘密裡に動いておる刺客の集団のことだ。」
見開いた目をさらに大きくして、澄史は聞き返した。
「刺客…?!こ、殺し屋ですか。」
「そうだ、澄史。賢いそなたなら容易に想像がつくであろう。この国では政と法門が深く結びついている。そして忠清寺はその両方の面で大きな力を持っている寺なのだ。それほどの力を使い、保つには、必ず血生臭いものに手を出さねばならぬ。《飛影》は紫ノ僧の直属の集団だが、薄紫ノ僧の和尚にもその存在は知らされている。そなたは紫ノ僧になる見込みが最も高い修行僧であるし、今回の件もある。知っておくべきであろう。」
あまりのことに澄史は体中から冷や汗が吹き出すのを感じた。
「…お、恐れ入ります…。」
「して、そなたと《飛影》は随時連絡を取り合わねばならぬのだが、世緒に感づかれてはまずい。気奴の様子を見つつ、飛影の方からそなただけに分かるように接触を図らせるから、そなたはただ待っておればよい。このようなことは、手慣れた者に任せるのが一番だからな。最も肝要なのは、そなたが気奴の術を心得たことを飛影に知らせることだ。それさえ出来てしまえば、あとの始末は彼らが行う。よいか。」
(よっ、よいかって…。俺に、人を殺せと命じてるんだよな?!いや、人殺しの手助けか…。にしても、和尚はどうしてこんな命令を、表情一つ変えずに、当たり前のように言えるんだろうか…。)
藤月和尚は、澄史の心を見透かすような鋭い視線を向けると言った。
「澄史よ。そなた、上に立つ者には、表の務めと裏の務めがあることを存じているか。」
説明を求めるように、澄史は和尚を見つめ返す。
「輝かしい地位には、それだけ重い義務と責任が伴うのだ。とても表には出せぬような、後ろ暗い所業も務めのうち。その責を果たしてこそ、真に人の上に立つに相応しい人間になったと言える。澄史、そなたは私が今まで見てきた中でも屈指の優秀な僧だ。しかし、そなたはこの忠清寺でさらに上へ行くに相応しい、誠に比類なき存在か?その是非を決めるのは、このような命をやり遂げられるかどうかだ。つまり、これはそなたが紫ノ僧に、ひいては宰相の位に見合う者かどうかを見極める、重要な修行の一部なのだ。」
澄史はごくりと唾を飲みこんだ。
「して、澄史。この命、受けてくれるか。」
藤月和尚は、緊張した面持ちで俯く澄史をじっと見つめた。
「先ほども言うたが、これは内密の任務だ。他の者たちには、そなたは天啓を受けて山籠もりしているということにしておこう。これで誰も何の疑いもはさまないはずだ。」
確かにこれは良い口実だった。忠清寺では、位の高い僧の中に、数十年に一人いるかいないかの割合で、ある日突然天啓を受ける者がいる。こういった者たちは受けた啓示をより確実なものにするために山籠もりし、忠清寺の新たな教えという形で示すことができるようになるまで出てこない。その期間は人によって様々で、数十年かかる者もいれば、ほんの数日で出てくる者もいる。寺中にその名をとどろかせている澄史であれば、たしかに『天啓を受けて山籠もりしている』と言えば誰もがあっさりと信じるだろう。いつ帰ってきても怪しまれることもない、完璧な口実だ。
「して、事は急を要する。門に馬を二頭待たせておいたから、そなたらには明日の朝、日の出前に出発してもらいたい。」
「!」
澄史は驚きのあまり全身がこわばるのを感じた。
「…して澄史、もう一度尋ねよう。この命、受けるか。」
脂汗が額をつたい落ち、心臓が早鐘のようになっている。
(これは、今まで人一倍努力してきた俺だからこそ任されたことなんだ。俺だからできる、いや俺にしかできないことだ…。やり遂げれば忠清寺のさらなる繁栄、ひいては俺の確実な未来…もし失敗すれば……いや、考えるのはよそう。もう、行くしかないんだから。)
澄史はぎゅっと目を瞑って大きく息を吸い込むと、絞り出すような声で言った。
「謹んでお受けいたします。」
部屋に着くと、すでに薄紫ノ僧のほとんどが揃っていた。皆、興奮気味に今日の召集の理由について囁き合っている。
「あれから、天威皇子はどんな容態か知ってるか?」
「さあ。だから俺たちがここに呼ばれてるんだろ?」
「なあ聞いたか?あの世緒とやら、ここの薄墨ノ僧の棟に泊ってるらしいぜ。」
「本当か?なら……」
部屋を満たすざわめきと熱気に、澄史は何だかくらくらとしてきた。人が集まるところは嫌いだ。とくに薄紫ノ僧の間では、澄史は尊敬と羨望の的であり、要するに敬遠されている存在だ。自分をそんな風に見てくる人間の集団の中でじっとしていなければいけない時間は、澄史にとってはいつも耐え難いものだった。
(いや、今はみんな世緒や天威皇子のことを話していて、誰も俺のことなんか話してない。)
そう自分に言い聞かせ、一つ深呼吸すると、空いている場所を探そうと広間を見渡した。と、部屋の中央辺りに座っている僧と偶然目が合った。その瞬間、彼の目に何とも言えぬ気まずさのような、居心地の悪さのようなものが浮かぶのが見え、澄史は胸の中をざらざらした何かで撫でられているような不快感を覚えた。
(俺を見るだけで嫌なのか?何なんだ…。いや、まぁ俺が気にし過ぎているだけかもしれないけど。)
澄史は深く溜め息をつくと、部屋の左端に見つけた空いている座布団へ腰を下ろした。
しばらくすると、前方の御簾がするすると上がり、藤月和尚の姿が前にいる僧の肩越しに見えた。先ほどまで部屋を満たしていた囁き声が、引き波のように消えていく。部屋が完全に静まり返ると、藤月和尚はよく通る低い声で話しはじめた。
「今日は皆に重要な報告がありここに集まってもらった。私も多忙な皆の時間を取りたくないと思うておる故、手短にいきたい。今日皆を呼び出したのは、他でもない、天威皇子のご容態について報告があるからだ。」
一瞬にして部屋中に緊張が走る。
「喜ばしいことに、天威皇子は順調に回復に向かわれている。あの儀式の三日後に意識を取り戻され、そこから段々とお話しもされるようになり、昨日などは少しではあるが薬膳粥をお召し上がりになった。」
しんと静まり返った部屋に、声にならない驚きが広がった。
「世緒によれば、このまま何も問題がなければあと数日で完治は間違いないとのことだ。」
沈黙がさらに深まる。と、前列に座っていた僧が恐る恐る手を挙げた。
「…お、恐れながら、一つ、お尋ねしてもよろしいでしょうか、藤月和尚…。天威皇子が回復なされたのは、も、もちろん大変喜ばしい知らせでこざいます。し、しかし…我々忠清寺ではなく、世緒の儀式によって皇子が回復なされた今…我々はどうなってしまうのでしょうか…?」
これは、この大広間に集まる薄紫ノ僧全員が抱いている問いだった。雅真ノ国で帝に最も厚い信頼を寄せられているはずの忠清寺が、肝心な時に何もできず、どこの馬の骨とも分からない流れ者に功績を取られた今、その名声は地に落ちたも同然である。
「…うむ。皆には正直に話さねばなるまい。帝が我々に失望なさった、というのは否めない。…実際、帝は宮仕えの寺院の再編成をご検討されている。」
広間のここそこで息をのむ声が聞こえてきた。宮仕えの寺院とは、帝の政の補佐をするために選ばれた寺のことだ。複数の異なる寺院や宗派が指名されることもあるが、ここ数十年では、毎年宰相を輩出している忠清寺がその座を独占していた。忠清寺だけであっても、その中の限られた地位をめぐって激しい競争がなされているのに、新たな宗派や寺が加わればさらに厳しい戦いになる。
「落ち着け、皆の者。まだ『検討されている』に過ぎない。今回の件だけで、あの得体のしれない世緒とやらを我々忠清寺に代わって宮廷に置くのは尚早だと、紫ノ僧正様方が進言され、帝もそれを考慮されている。それに、まだ実際に再編成がなされたわけではないのだ。しかし、今回の件のために忠清寺の威信が揺らいだのも事実。今我々にできることは、ただ己の術を磨き霊力を高めることのみだ。わかるな。」
「し、しかし、それでは世緒に勝つことは…」
藤月和尚は、声のした方に氷のような冷たい視線を向けると、同じように冷たい口調で言い放った。
「雲月、そなた、桐和宗忠清寺があの流れ者に劣ると申すか。」
「い、いえ、もちろんそんなことはございません。違います…。私はただ…」
「世緒についてはこちらで出来る限りの調べをしている。そなたたちは余計な詮索をせずともよい。今はただ目の前の務めに励むことだ。よいか。」
有無を言わさぬ強い口調に、広間はしんと静まり返った。
「ほかに、少しでも忠清寺に疑いの心を持つ者はおるか。そのような者はいつでも薄墨ノ僧からやり直す許可を与えよう。」
辺りに凍り付いたような沈黙が流れる。澄史は俯いて、なぜかうるさいほど鳴っている自分の心臓の音を聞いていた。
「それではここで解散とする。澄史、そなたはここに残っているように。」
澄史はびくりとして顔を上げた。
(え、何だろう…。俺、何かしたかな。)
不安な面持ちで正座する澄史の横を、緊張の解けた他の僧たちががやがやと話しながらすり抜けていく。
「澄史だから……だろ。いつも修行ばっか……だよ。」
「知らね。また何か……『第二の神童』はやっぱり……」
「…あいつ見るとさ……もっと修行しないとって焦るし。……だから…」
途切れとぎれに聞こえてくる言葉と、時折感じる訝しげな視線が澄史の心をえぐる。
(もういい加減、こんなの慣れたはずなのにな。…心に瘡蓋はできないものなのかな。)
もしもできるのであれば、澄史の心の皮膚はとうの昔に分厚く硬くなっていて、このような冷たい目線にも言葉にも全く動じないようになっていただろう。
と、澄史は突然肩を叩かれて顔を上げた。すぐ目の前には、にやりと笑った緑雨が自分を見下ろしている。
「ついに澄史様もやらかしたか。何したんだ?」
「緑雨!びっくりさせないでくれよ。いや、俺は別に何もしてないはずだけど…。でも俺が自分で気づいてないだけで何かしたのかもしれない。」
不安そうにつぶやく澄史の肩に、緑雨は腕を回した。
「ま、怒られたら後で俺の部屋でも来いよ。俺特製の苦っが~い薬湯でも作って忘れさせてやるからさ。」
「それは感謝すればいいのか、怒られた俺へのさらなる嫌がらせと取ればいいのか、どっちなんだ…。」
「ま、とにかくだ。そんな暗い顔しないで藤月和尚んとこ行って来いよ。行ったら分かるんだし。」
そう言うと緑雨は澄史の腕を引っ張って立たせ、彼の背中をぽんぽんと叩いた。
「ありがとう。本当に後でお前の部屋に寄らせてもらうかも。」
緑雨はにっと笑うと、くるりと踵を返して部屋を出ていった。
少しして、最後の一人の僧が広間を出ていき、澄史は藤月と向かい合って正座していた。
「急に呼び出してすまぬな、澄史。」
「とんでもありません、藤月和尚。」
「そなたが何か良からぬことをしでかした、などという用件ではないから安心せよ。」
そこで藤月和尚は言葉を切った。罰せられるわけではないと分かったのは良かったが、全く見当がつかない分、澄史の緊張は高まる。
「実はそなたに、重大な任務を任せることになった。紫ノ僧正様全員からの直々のご命令だ。」
「!」
驚きと困惑で、澄史は目を見開いた。
「まだ大事にしたくないとの帝のご意向ゆえ、先ほどは皆に伝えなかったのだが、最近、白海部――門外へ出たことのないそなたでもこれくらいは知っておるな?この国で主に貧しい者たちが住まう海岸沿いの地域だ――で、天威皇子がかかられたものと同じ病にかかった者が十数名いるらしいのだ。そこで、帝は世緒を白海部へ遣わし、調査するよう命じられた。誠に遺憾だが、今のところ気奴しかあの病を治せる者がいないのでな。しかし、あれがどこからともなく突然現れた異人であるのも事実。加えて――」
和尚はここで一旦言葉を切ると、改めて澄史をじっと見据えた。
「世緒にこれ以上の功績をあげられては、忠清寺の立場が危うい。して、紫ノ僧正様方が何とか帝を説得し、気奴の監視という役目で忠清寺から僧を一人、奴に同行させる許しを得られた。高齢な紫ノ僧正様方や私のような者では、長旅になるであろうこの任務は務まらぬ。そこでだ、澄史、そなたに行ってもらいたい。」
あまりに突然のことで、澄史は返事をしようとしたが言葉がまったく出てこない。藤月和尚はそんな彼の様子など気にもとめず続けた。
「ここまで聞けば聡いそなたならばとうに読めているだろうが、当然『監視』というのは建前だ。そなたがせねばならぬのは、世緒の技を盗むこと――加えて、奴を消すことだ。」
澄史は呆気に取られた。
「け、消す、とは…」
「落ち着け、澄史。何もそなたに手を下してもらいたいわけではない。そなたは修行僧であって殺しの道を歩む者ではないし、そなたが返り討ちになることも考えられる。相手は力量の分からぬ流れ者だからな。万一のこともあり得る。して、実際に気奴を消すのは《飛影》だ。彼らには、そなたと気奴を常に監視し、そなたが奴の治癒の方法を会得した時点で奴を殺すよう命じてある。」
「《飛影》…?」
「そうか、次期宰相候補のそなたにはすでに話したと思うておったが。《飛影》というのは、忠清寺について秘密裡に動いておる刺客の集団のことだ。」
見開いた目をさらに大きくして、澄史は聞き返した。
「刺客…?!こ、殺し屋ですか。」
「そうだ、澄史。賢いそなたなら容易に想像がつくであろう。この国では政と法門が深く結びついている。そして忠清寺はその両方の面で大きな力を持っている寺なのだ。それほどの力を使い、保つには、必ず血生臭いものに手を出さねばならぬ。《飛影》は紫ノ僧の直属の集団だが、薄紫ノ僧の和尚にもその存在は知らされている。そなたは紫ノ僧になる見込みが最も高い修行僧であるし、今回の件もある。知っておくべきであろう。」
あまりのことに澄史は体中から冷や汗が吹き出すのを感じた。
「…お、恐れ入ります…。」
「して、そなたと《飛影》は随時連絡を取り合わねばならぬのだが、世緒に感づかれてはまずい。気奴の様子を見つつ、飛影の方からそなただけに分かるように接触を図らせるから、そなたはただ待っておればよい。このようなことは、手慣れた者に任せるのが一番だからな。最も肝要なのは、そなたが気奴の術を心得たことを飛影に知らせることだ。それさえ出来てしまえば、あとの始末は彼らが行う。よいか。」
(よっ、よいかって…。俺に、人を殺せと命じてるんだよな?!いや、人殺しの手助けか…。にしても、和尚はどうしてこんな命令を、表情一つ変えずに、当たり前のように言えるんだろうか…。)
藤月和尚は、澄史の心を見透かすような鋭い視線を向けると言った。
「澄史よ。そなた、上に立つ者には、表の務めと裏の務めがあることを存じているか。」
説明を求めるように、澄史は和尚を見つめ返す。
「輝かしい地位には、それだけ重い義務と責任が伴うのだ。とても表には出せぬような、後ろ暗い所業も務めのうち。その責を果たしてこそ、真に人の上に立つに相応しい人間になったと言える。澄史、そなたは私が今まで見てきた中でも屈指の優秀な僧だ。しかし、そなたはこの忠清寺でさらに上へ行くに相応しい、誠に比類なき存在か?その是非を決めるのは、このような命をやり遂げられるかどうかだ。つまり、これはそなたが紫ノ僧に、ひいては宰相の位に見合う者かどうかを見極める、重要な修行の一部なのだ。」
澄史はごくりと唾を飲みこんだ。
「して、澄史。この命、受けてくれるか。」
藤月和尚は、緊張した面持ちで俯く澄史をじっと見つめた。
「先ほども言うたが、これは内密の任務だ。他の者たちには、そなたは天啓を受けて山籠もりしているということにしておこう。これで誰も何の疑いもはさまないはずだ。」
確かにこれは良い口実だった。忠清寺では、位の高い僧の中に、数十年に一人いるかいないかの割合で、ある日突然天啓を受ける者がいる。こういった者たちは受けた啓示をより確実なものにするために山籠もりし、忠清寺の新たな教えという形で示すことができるようになるまで出てこない。その期間は人によって様々で、数十年かかる者もいれば、ほんの数日で出てくる者もいる。寺中にその名をとどろかせている澄史であれば、たしかに『天啓を受けて山籠もりしている』と言えば誰もがあっさりと信じるだろう。いつ帰ってきても怪しまれることもない、完璧な口実だ。
「して、事は急を要する。門に馬を二頭待たせておいたから、そなたらには明日の朝、日の出前に出発してもらいたい。」
「!」
澄史は驚きのあまり全身がこわばるのを感じた。
「…して澄史、もう一度尋ねよう。この命、受けるか。」
脂汗が額をつたい落ち、心臓が早鐘のようになっている。
(これは、今まで人一倍努力してきた俺だからこそ任されたことなんだ。俺だからできる、いや俺にしかできないことだ…。やり遂げれば忠清寺のさらなる繁栄、ひいては俺の確実な未来…もし失敗すれば……いや、考えるのはよそう。もう、行くしかないんだから。)
澄史はぎゅっと目を瞑って大きく息を吸い込むと、絞り出すような声で言った。
「謹んでお受けいたします。」
応援ありがとうございます!
0
お気に入りに追加
34
1 / 5
この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる