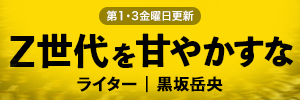データサイエンティスト「争奪戦」の虚妄…薄れる希少性、要求スキルへの誤解
2024.02.13
ビジネスジャーナル
単純化していえば、アメリカが『スーパーマン』のように一人で問題を全て解決してくれるヒーローを求めるとするなら、日本は『七人の侍(Magnificent 7)』のように、各分野のエキスパートを集めてチームで問題を解決しようとする。そんな日米の文化の違いは、「アメリカではデータサイエンティストに提示される年俸は日本円換算で最低でも1000万円台だが、日本では平均年俸500万円前後」という報酬のデータとも符合する。それを田中氏は「物価の違いもありますが、働き方の違い、企業文化の違いも大きいと思いますね」と指摘する。
日本企業では今、データサイエンティストも含めてDX人材の奪い合いが起きているが、その一方で、企業が講習会やオンライン学習により自前でデータサイエンティストを育成しようという動きも活発化している。経験者をスカウトできればそれに越したことはないが、現有の人材を長時間かけてじっくり育成しチーム化してもいい、ということだろう。なお、平均年収がたとえアメリカの半分の500万円でも、少なくとも若くしてハイレベルの報酬が約束される職種である、ということはできる。
データサイエンティストになるには
データサイエンティストへの転職を考えている人もいるだろう。では、どうすればなれるのだろうか。政府は19年6月に「AI戦略2019」を発表し、「25年までに全ての大学・高専生がデータサイエンスの初級レベルを習得する」という目標を掲げた。その時点で情報科学系でデータサイエンスの正規課程を持つのは滋賀大学、横浜国立大学、武蔵野大学の3校だけだったが、その後、東京大学、京都大学、名古屋市立大学、立正大学など多くの大学に開設され、21年8月に文部科学省が発表したデータでは59大学が認定されていた。そうやって人材供給源が増えれば、売り手市場は緩和される。
資格は「データサイエンティスト検定」のほか、統計分析スキルを証明する「統計検定」もある。専門学校などのプログラミングスクールの多くもデータサイエンティスト養成の専門コースに力を入れている。それらは近道なのだろうか。また、AIのプログラミング言語で現在の主流は「Python(パイソン)」だが、その習得は有利になるのだろうか。
「資格取得も、専門コースの受講も、Pythonの習得も、転職の際の決め手にはならない。むしろ、大きくものをいうのは業種、業界、業務の知識でしょう。その基盤があってデータ分析ができるデータサイエンティストは重宝されるはずです」(田中氏)
たとえば製造業なら生産現場、小売業なら販売現場で時間をかけて得る知識は、数理やデータ分析にいくら習熟していようと、一から学ぶ道は険しい。逆に、現場経験者がデータ分析やIT知識を学ぶほうが、現場の問題解決で活躍できる人材になれる可能性が高い。「現場の業務をよく知っているIT人材は強い」という声は、頻繁に聞かれる。
田中氏は、どんなに優秀なデータサイエンティストでも、従来の給与体系を崩して高額報酬で入社させるのは、日本企業の伝統的な風土になじまない問題もあると指摘する。そのため該当部門を別会社化したり、技術顧問に任じて対応している企業もあるという。
では、データサイエンティストの旺盛な需要は、今後も長く続くのだろうか。
「企業社会全体をみるとITのプロフェッショナル人材に対するニーズはヤマを越えたかなという印象です。少数の人材に高度なデータ分析をやらせなくても、今いる社員がデータを意識するようになればそれでいいという傾向もみられます。『データサイエンスの民主化』という言葉があり、経済産業省も一般のビジネスパーソンのための『デジタルリテラシー標準』を定義しました。リスキリングで学んだりして誰でもデータ分析ができるようになれば、専門人材の希少性はだんだんと薄れていくでしょう」(田中氏)
「データサイエンティスト」の看板だけで、セクシーでモテる時代はいずれ過ぎ去る。「このスキルに強い」「この業務に強い」といったように差別化しないと生き残れない時代がやって来るかもしれないことは、覚悟しておくべきだろう。
(文=寺尾淳/フリーライター、協力=田中健太/鶴見教育工学研究所所長)