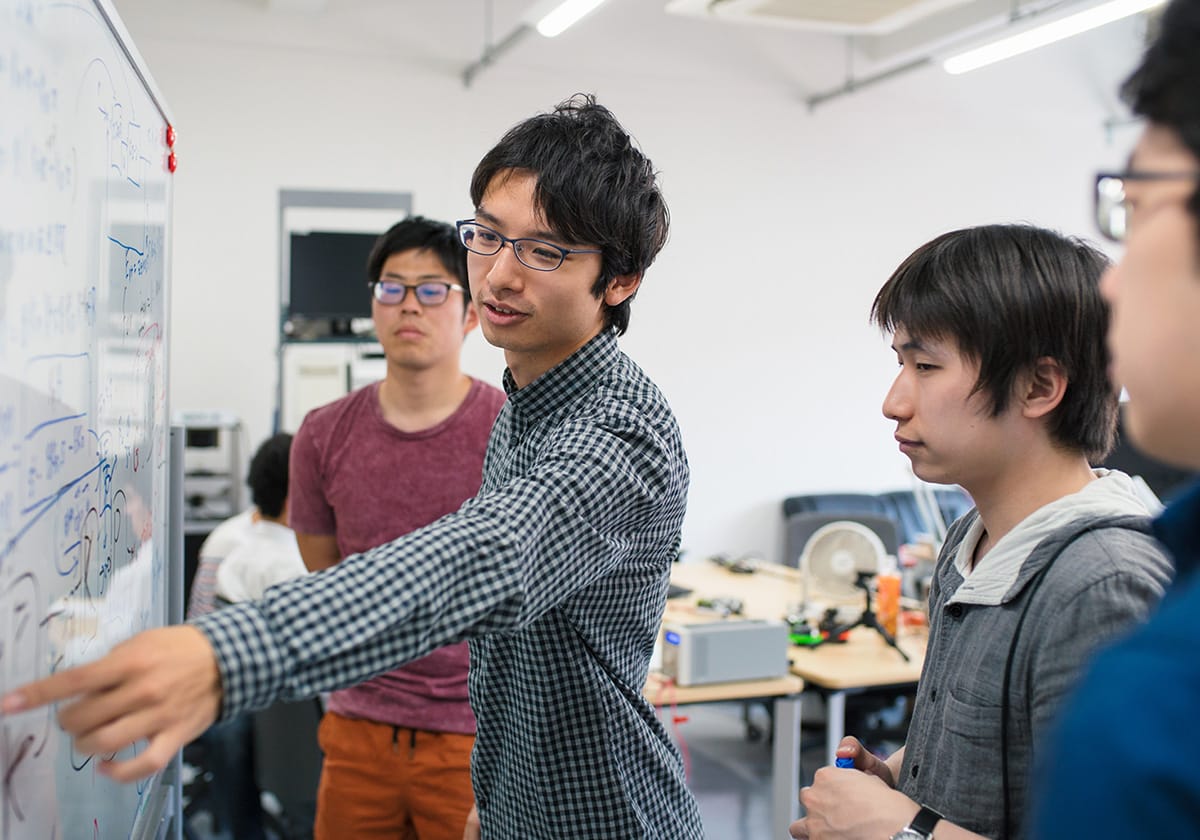「リベンジ退職」のリアル、会社を揺るがす報復劇
2025.03.17
東洋経済オンライン

「リベンジ退職」する社員が出てしまうと、会社は大きなダメージを受けてしまいます(写真:mits / PIXTA)
先日、中堅企業の人事部から、こんな相談を受けた。
「最近、当社の若手社員が退職するとき、わざと引き継ぎ資料を作らなかったり、会社の悪口をSNSに書き込んだりする例が増えています。リベンジするつもりなのか、退職時に問題を起こすケースが目立ちます」
「仕返し」目的の退職――いわゆる「リベンジ退職」が昨今増えているという。ただ単に転職するだけでなく、会社や上司に「痛い目に遭わせてやろう」という意図を持った退職だ。果たして、これは本当の意味での「報復」になっているのだろうか?
リベンジ退職、代表的な3パターン
"リベンジ退職"とは、一般的に「会社や上司への不満や怒りを晴らすために、意図的に組織に損害を与える形で退職すること」を指すようだ。典型的なパターンは以下の3つではないだろうか。
(1)繁忙期の突然退職
お客さまからの注文が殺到する年末商戦や、決算期の忙しい時期を狙って退職届を提出するケース。
ある小売業では、クリスマス商戦の直前に店長が退職し、代替要員が確保できないまま混乱に陥った。リベンジする側にとっては「会社が最も困るタイミング」を選ぶことで、組織に最大限の打撃を与えようとしたのだろう。
確定申告の時期にベテラン税理士が辞めてしまい、「地獄を味わった」税理士事務所の社長もいた。
(2)SNSなどでの暴露
次はSNSや口コミサイトに、社内の人間関係や職場の不満を暴露するパターンだ。
あるIT企業では、元社員が残業の実態や人間関係のトラブルを詳細に投稿した。その結果、採用活動に大きな影響が出たという。情報が拡散されやすい現代社会では、一度ネットに出た情報は取り返しがつかない。企業イメージを大きく損なう。
(3)引き継ぎの拒否
3つ目は、退職時に必要な引き継ぎをせず、業務に関する情報やノウハウを残さないパターンだ。
ある中堅メーカーの営業担当者は、重要なお客さまとの交渉プロセスや契約条件を一切残さずに退職。後任者は一から関係構築をやり直すことになり、お客さまとの信頼関係にも亀裂が入った。情報を隠すだけでなく、誤った情報をわざと残す、といった悪質なケースもあるようだ。
なぜリベンジ退職が増えているのか?
「会社が嫌なら黙って去ればいいのに」と思う人も多いだろう。しかし、リベンジ退職に至るまでには、必ず積み重なった不満や不信感がある。一夜にして「仕返し」を思いつくわけではない。
あくまでも推測だが、リベンジ退職が増加している背景には、大きく3つの要因があるのではないか。
(1)売り手市場の継続
深刻な人材不足が続いている現在、「辞めても次がある」という安心感が、退職者のいきすぎた行動を後押ししている。かつては「円満退職でないと次の就職に不利」と考えられていたが、今は転職のハードルが下がっている。
旅先で恥をかいてもその場限りで済むということわざ――「旅の恥はかき捨て」と同じ感覚で、退職を選んでいるのかもしれない。
(2)情報発信手段の多様化
SNSや口コミサイトなど、個人が情報を発信できるプラットフォームが充実した。「会社の実態を世間に知らしめる」という行為が、以前より格段に容易になったのも要因の1つだろう。
(3)組織への帰属意識の低下
昔なら会社に不満があっても、「世話になったから」と多少の理不尽さには耐えた。しかし「会社のために人生を捧げる」という価値観は完全に薄れている。このような帰属意識の低下が「我慢するのは損」という感覚を広めているのかもしれない。
リベンジ退職は、組織に深刻なダメージを与えることがある。