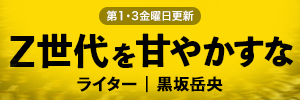ビジネス書に求められる作家の表現力 PART.1
ビジネス書にとっての作家性

ビジネス書でも、文芸書でも、コミックでも、本である以上は原稿のクオリティがすべてを決める。
ただ、原稿のクオリティといっても、ジャンルによって求められる質はやや異なる。
文芸書とは違い、ビジネス書では原稿が多少下手でも、使えるコンテンツを持った作家であればOKである。
この傾向は,いまも昔も変わりない。
かつて、ビジネス書は文章のうまい下手、すなわち作家の表現力は、あまりというより、ほとんど重視していないところがあった。それよりも、作家の持つ情報の有用性やユニークさのほうに軸足を置いていたのだ。
極端な言い方をすれば、ビジネス書の出版社では、原稿の調子など編集者が整えればよいと考えているふしもあった。
それが、ここ10年くらいのビジネス書を見ていると、作家の表現力は昔に比べるとずいぶん上がっている。作家の表現力によって、売れていると思える本も少なくない。
いまやビジネス書にも、読者は表現の面白さや斬新さを求めるようになってきているのだろう。
ビジネス書を書いている人のことを、出版社によっては作家と呼んだり、著者と呼んだりする。本稿では、作家と呼んでいるが、作家というと小説家みたいだと、私に違和感を訴える編集者はいまでも何人かいる。
しかし、いまや文芸書のように、ビジネス書作家にもファンのつく時代である。特に自己啓発ジャンルの本では、この傾向がはっきり表れている。
時代はビジネス書にも、文芸書に近い作家性が求められつつあるのかもしれない。
作家ということになれば、原稿の表現力は重要である。表現力とは、言葉を変えれば作家の個性である。
自己啓発書は、実務や経営など他のジャンルのビジネス書よりも、作家の個性が売れ行きに反映するように見える。
ビジネス書の表現スタイルで肝心なのは、「わかりやすさ」。これに尽きる。
わかりやすく、さらに文章が面白ければなおけっこうだが、文章は面白いが言って(書いて)いることが意味不明では、ビジネス書は成り立たない。
わかりやすいとは、結論がはっきりしているということである。
「なぜそうなのか?」よりも、「要するに何?」が大事なのだ。
それは、ビジネス書の持つ弱点、すなわち中身の浅さに通じることでもある。だが、それゆえにビジネス書はビジネス書であるのだ。
ビジネス書の読者は読者を大量生産する

そういうビジネス書ではあるが、実は表現スタイルには歴史がある。
ビジネス書もはじめから、結論重視の拙速を尊ぶスタイルではなかった。
ビジネス書が日本の出版界に登場したのはいつかというのは、恐らくいろいろな議論があると思われる。
ビジネス書という名称自体は、30年前にはすでにあったし、40年前にはまだなかったと思う。ただ、ビジネス書に相当するものは古くから存在する。
井原西鶴の『日本永代蔵』などは、江戸時代のビジネス書と言って差支えないだろう。
とはいえ、今日、ビジネス書といわれるジャンルの原形を遡ると、概ね昭和40年代、すなわち今から50年前に行き着く。
今から50年前は、それ以前から存在した経営学の書籍と、より実務的なビジネス書が、法経書というジャンルで括られ、まだ渾然としていた。
まさに昨今ブームでもある、ニューヨーク大学のドラッカー博士の本が、日本で続々と出版されるようになった時代である。
学問的な専門書籍とビジネス書が混在していた時代だけに、この時代のビジネス書は表現スタイルも学者的(実際書いているのも学者が多かった)で、わかりやすさを追求するというより、理論を教科書どおり忠実に記すものだった。
そうした制作姿勢では、作家が書きたいように書いたものをありがたく頂戴することとなり、どうしても読者目線は置き去りにされがちとなる。
わからないのは読者の勉強不足ということだから、知識と情報さえあればあまりあれこれ注文がつかない、作家としては恵まれた時代だった。
そうした中で、光文社のカッパブックスが編集サイドの企画意図を軸として、企画意図に沿った原稿を作家に要求したのは画期的だったといえよう。
昭和40年代は、年間のベストセラーに、今日でいうビジネス書が何冊も入ってくるが、それらのほとんどがカッパブックスであった。
年間のベストセラーにビジネス書がランキングされたのは、カッパブックスの貢献もあろうが、何より高度経済成長を経験した日本の産業社会が、それを必要としたのだろう。
ビジネス書の版元の多くは、この時代からスタートし、それ以前に創業していた会社もこのあたりから伸びはじめている。
この時代のビジネス書の表現スタイルは、ひと言で言えば、先に述べたとおり教科書的であった。
日本の高度経済成長はオイルショックまで続くが、ここでピークアウトし、その影響を受けビジネス書もやや趣を変えることになる。
それ以前がアメリカから輸入したマネージメント論の翻訳や学問的な論文が主流の、いわゆる総論だったのに対し、オイルショック以降は各論の時代に入る。
これが、およそ40年前、昭和50年代のことである。
高度経済成長の時代のように、読者が情報に飢えており、あまりつくり込まなくても売れた時代ではなくなったのだ。
本が売れなくなると、あれこれ工夫をはじめるのは、今も昔も同じ。
もはや学者的な表現では競争に勝てないため、次第に学者の作家は減っていき、より実務の現場に強い、現役のビジネスパーソンやコンサルタントが書き手に変わりはじめる。学者にとっても、ビジネス書の出版は、必ずしも学問的実績にカウントされないケースが出てきたことも、書き手の後退に拍車をかけた。
このあたりから、ビジネス書の表現スタイルは、間違いでなければ正しいというスタイルが定着をはじめる。精緻(せいち)であることよりも、実用性を重視した拙速さを尊ぶようになるのである。
次回に続く
オススメ記事
まだ記事はありません。「ビジネス書業界の裏話」 記事一覧
- 第50回 出版界の再編と作家の未来
- 第51回 ビジネス書作家の在り方とは
- 第9回 ビジネス書に求められる作家の表現力 PART.1
- 第8回 ビジネス書は賢い大人を相手に本をつくっている
- 第7回 ビジネス書の読者とはどんな人なのだろうか