5 / 6
夏の終わり
しおりを挟む
不思議なもので、カナメを意識するようになってからは学校に行くことがありがたいこともあった。
ずっと目で追っていたい。声を聞いていたい。すぐ隣で気配を感じていたいんだ。けれど、時々息ができなくなる。恋ってそういうものなんだろうか。そこにいるのがどんなに幸せなことかわからない。そのくせ目を合わせると苦しくなるなんて変なものだ。
「もう稲穂がずいぶん頭を垂れてきたねぇ」
ある日、キャットフードを買出しに行った車の中でカナメがのんびり言う。
「ふぅちゃん、帰りにいいとこ連れて行ってあげるね」
「どこ?」
期待に胸を膨らませる私に、彼はふっと笑う。
「さぁ、どこでしょう?」
あ、私、この笑い方好きだ。思わずにやにやしそうになって慌てて窓の方に顔を逸らした。
カナメの運転は流れるようにスムーズで、ブレーキも滑らか。あんまり丁寧に運転するから、大事にされているように感じて嬉しくなる。
カナメが連れて行ってくれたのは彼岸花の名所だった。林の合間に絨毯を敷き詰めたように緋色が広がっている。
「紅しょうがをぶちまけたみたいね」
「ふぅちゃん、もうちょっと情緒あるたとえないの?」
「そうだなぁ」
彼岸花の合間を縫うように整備された歩道に立ち尽くし、辺りを見回す。大地から湧き上がるような無数の緋色の炎。
「……怖い」
ぴくりとカナメの眉が上がる。
「どうして?」
「綺麗すぎるし、それに恨みとか妬みとかそういうものがこみ上げてるみたいに見える」
そう、あの子の目の中に見えた激昂を思い出す。
胸が狭くなった途端、カナメがすっと手を握ってくれた。ちょっと驚いたけれど、無性に安堵する。
「……そうかぁ。やっぱり従姉妹だなぁ」
「え?」
「俺も初めてばあちゃんに連れてこられたときは同じように見えたんだよ」
カナメがそのままゆっくりと私の手を引いて歩きだした。彼岸花を見渡しながら、彼はゆっくりと口を開く。
「今は単純に綺麗だと思うけど、あの頃は怖かった。ちょうど、ふぅちゃんと同じくらいの歳だったな」
彼が自分から過去の話をするのが珍しくて、それになんとなく嬉しくて、私はただただ黙って耳を傾けていた。
「ふぅちゃん、覚えてるかなぁ? 俺って中学のとき事故で死にかけたんだよね。母親と車に乗ってて、衝突してさ」
「そうだった?」
まったく記憶にない。目を丸くすると、彼は「うん」と背中を見せたまま頷いた。
「ふぅちゃん小学生だったしね。多分、叔母さんもあえて言わなかったのかな。幸いこうして元気になったけど、三日くらい意識なくて」
まるで世間話でもしているような、淡々とした声。
「そのとき、うちの母親が変な宗教に走ってさ。リハビリも時間かかったし、責任感じて辛かったんだろうけど。俺の父親って堅物だろ? 俺が元気になった頃にはお袋と離婚の話がまとまってた。せっかく生きて戻ってきたのに、すべてが壊れた。不器用な親父は俺と話すこともなく、そのうち俺は家に帰らなくなって」
カナメの声は静かだった。
「そんな俺を見かねたばあちゃんが、高校はこっちで過ごせって言ってくれたんだ。どこに行っても同じだと思ってた俺はここに来てもしばらくは黙ったまま、誰にも懐かなかった」
思わず「それって……」と呟くと、カナメがちょっと振り向いて口の端を吊り上げる。
「似てるでしょ、ふぅちゃんに」
カナメが私に向けた同情の目の理由が初めてちゃんとわかった。彼は多分、私の中に過去の自分を見たんだ。
「俺ねぇ、ばあちゃんに毎日を大切に暮らしなさいって言葉なしに教わったんだよ。丁寧にご飯を作って、きちんと味わって、気がつけば流れてる季節を追って、そうしているうちに今ここにいることに感謝できるって。そうなれるようになるまで一年はかかったけど」
いつか私はカナメに問いかけた。あさはんを『なんでいらないってのに用意するの?』と。その答えを今、口にしている。
思わず握った手に力をこめた。カナメは初めて自分の傷跡を晒そうとしてくれているんだ。他でもない私に。
どぎまぎするような、どことなくいたたまれないような気分で、木漏れ日を背負った後姿を見つめた。
「俺はここで人として大事なことを見つけたつもりで、東京に戻った。けど、大学での毎日も結局何か物足りなくて。叔母さんに夏休みをここで過ごさないかって提案されたとき、これだって思った」
「俺はここに確認しに来たんだ。もう一度、ここで何か見つけられるんじゃないかって思った。そしたら、昔の俺にそっくりな子がいたんだ」
ふふっと笑みをこぼし、彼は歩みを止めて私を見つめた。
「ねぇ、ふぅちゃん。季節が流れるように人の出逢いも戻せない。一度手離したらもう戻らないんだよね。不思議だね」
唇の隙間から、私のかすれ声が漏れる。
「カナメはここで何を見つけたの?」
「内緒だよ。でも、何をしなきゃいけないかはわかった気がする」
嗚呼。カナメの目は遠くを見ていた。私の手の届かないところを。なんとなく、彼が何を言いたいのかわかってしまった。
彼はもう東京へ帰るのだ。行ってしまう。夏が終わる。あさはんのある二人の夏が。
「どうして私に話すの?」
「なんだかね、知っておいて欲しかったんだよ。ここに置いていくべきものだからかもね」
……嫌だ。ふるっと涙があふれ出る。
「やっぱり、みんないなくなる」
ぐすっと鼻をすする。
「みんなって?」
静かに問い返すカナメに、私はぽつりぽつりと話し出した。
「中学のときね、好きな先輩がいたの。沼田先輩っていって、同じ部活で仲良くて。でも、親友も同じ人が好きで、二人で追っかけしてた」
前橋えりこ。自分を『明るいストーカー』と笑い飛ばしていた私の親友だった子だ。沼田先輩のことが大好きで雪山にうもれながら小一時間も彼の通う塾を覗き見したり、毎日同じ電車の車両に乗るために駅を駆け抜けたり。好きだってことを隠そうとしない、素直な性格。
最初は彼に興味もなかったけれど、えりこにつきあっているうちに次第に私まで惹かれていった。
けれど、言えなかった。堂々と「彼が大好き」と目を輝かせるえりこに「実は私も好き」だなんて。自分の気持ちに気づくまでは応援していたのは本当なの。でも、好きだと気づいてしまったら、言いようのない罪悪感に潰されそうで。苦しかった。
だけど、それが変わったのは先輩の卒業式の日。
床に伏せて泣くえりこを自分も泣きたい気分で慰め、私は、とぼとぼと家路についていた。
そこに、沼田先輩の親友に出くわした。彼は堂々と追っかけてくるえりことその傍にいる私を覚えてくれていたんだ。
「ご卒業おめでとうございます」
そう言った私に、彼は「ありがとう」とはにかんだが、すぐに眉をひそめた。
「そういえば君といつも一緒にいる沼田のファン、告白したの?」
「いえ、タイミングつかめなかったみたいですけど」
おずおずと答えると、彼は「そうか」とぼりぼり頭をかいた。
「良かったと思うよ。言っちゃ悪いけど、沼田って女いっぱいいるし」
「え?」
愕然とした。けれど、もっと私の息を止めたのは次の言葉だった。
「あのファンのこともさ『簡単にヤレそうな女』ってキープしてたし、君のことも……」
「私?」
彼は咄嗟に『口がすべった』という顔をしたが、ふっとため息をもらした。
「うん。教えたほうがいいなってずっと思ってたんだよね。君も沼田のこと好きでしょ? あいつそういうの鼻が利くんだけどさ、『ああいう女はちょっと優しくしたらすぐ抱ける』って得意になってて」
目の前が真っ暗になった気がした。確かに沼田先輩の本音なんてわからない。だって私もえりこも遠くから見つめたり、偶然を装って話しかけたりするだけだもの。それこそ、えりこが言うように『ストーカー』状態。まして、気持ちを隠してこっそり彼を思っていた私はまさしくだ。
ショックのあまり呆然とする私に、彼が歩み寄る。
「俺、沼田より君を大事にするけど?」
「へ?」
「ずっといいなって思ってたんだ。俺ら、付き合わない?」
手首をつかまれ、彼の顔が近づく。私は短く叫んでその場を走り出していた。
沼田先輩を悪く言って、私に取り込もうとしたの?
それとも本当に? 本当に先輩がそんなことを?
信じられない。どうしたらいいのかもわからない。
一番信じられなかったのは、その後。えりこからの一通のメール。そこには『沼田先輩に告白したら付き合うことになりました』って一文があった。足元から何かが崩れる音が聞こえた気がしたよ。
その後がさらに最悪だった。沼田先輩の友人はふられた腹いせにか、えりこに私も沼田先輩を好きだということをばらしてしまったんだ。
「私を陰で笑ってたってわけ? なんで言ってくれなかったの? 沼田先輩と付き合えたことも祝ってはくれないのね」
なんでもはっきりさせる性格の彼女が私につっかかってきた。
「あのねえりこ……」
言いたくない。本当は言いたくない。けれど、言わなくちゃ。傷つくのはえりこだ。
私は懸命に説明した。けれど、えりこは私を信じなかった。当たり前だよね。誰だってやっと付き合えた彼氏を信じるよね。
「なによそれ、何を根拠に言ってるの? 私が先輩と付き合うことになったから妬いてるんじゃないの?」
「ちが……」
「もういい、顔も見たくない。見損なったよ。フウカって最低。そんな人だと思わなかった。先輩を侮辱しないで!」
それで、結局私たちはそのままになった。あのとき彼女の瞳に宿った軽蔑の目を、私は忘れられない。
怒りと嫌悪感がまるで彼岸花のように咲いていたっけ。
話し終えたとき、私の涙は頬の上でひからびていた。ただただ虚しくて。この彼岸花が自分への戒めにしか見えなくて。
けれどそのとき、カナメがぎゅっと繋いだ手に力をこめてくれた。
「辛かったね」
その言葉はすとんと音をたて、私の中に落ちた気がした。
「……うん」
「その子が傷ついてないといいね」
「うん」
えりことの溝は埋まらないかもしれない。けれど、それでも私は彼女が笑っていてくれたらと願うんだ。
本当はわかってほしい。私ね、先輩をまっすぐ追いかける彼女が羨ましかった。好きだった。多分、先輩を好きになったのも、そんな彼女が好いた人だから惹かれたんだと思うの。
言葉にできたとき、私の中で何かが形を変えた気がした。そう、この足を絡めとっていたものがするりと抜け落ちたような。
それって左手で握り締めたトンボ玉と、右手のぬくもりのおかげなんだと知っている。私は『大丈夫』だから。私を無条件で大切に思ってくれる人がいるのを知った。だから、大丈夫。
帰りの車の中、カナメが呟く。
「ミドリさんをよろしくね」
彼女はここで生まれ育った子だから、ここに戻らなきゃね。彼は小さくそう言った。
「カナメがいなくて寂しがるよ」
ミドリさんも私も。すると、彼は「いいや」と笑う。
「猫は家につくんだよ」
「カナメはどこに戻るの?」
「俺は戻るために帰るんだよ」
そう力強く言う横顔を、じっと見つめた。彼の視線はもう遠くを見据えている。
ふと、私は自分の中に咲く彼岸花一輪に気がついて問いかけた。
「カナメ、あの女の人に連絡したの?」
「うん?」
「ほら、温泉で話してた同級生」
「うん、新婚ほやほやでのろけ話を一時間もされたよ」
そのとき、私の彼岸花が萎れるのを感じて、「そっか」と思わず笑う。
カナメは帰る。いつもそこにいるのが当たり前だった姿が、声が、匂いがなくなる。
そしてもう少しで母が帰ってくるだろう。今度は母と二人の暮らし。ゆっくりでいい。二人の形を築いていこう。カナメが前を見ているなら、私も同じ方を見ていたい。
えりこから手紙が届いたのは、それから数日後のことだった。私は嬉し泣きをし、カナメはずっと「よかったね」といつものようにぽんぽんと髪を撫でてくれたっけ。
風がどことなくひんやりした日曜日の朝。
「あさはん、できたよ」
カナメの声がする。いつものように二人で向かい合って座り、手を合わせて「いただきます」とかみ締めるように囁いた。
「ふぅちゃん、お醤油とって」
「うん」
納豆をかき混ぜる音。
「それじゃあね」
荷を積み終わったミニクーパーの前でカナメが振り返る。足を引きずるように歩み寄る私は、涙をこらえるので精一杯だ。
「また来るよ」
ふっとカナメが笑う。もうすっかり見慣れた眼鏡の奥で、いつものように目を穏やかに細めて。
「本当に?」
溢れる涙は既に視界をぼんやりさせている。カナメが滲んで見えなくなる。一瞬でも長く目に焼き付けたいのに。思わずこぼれた涙。
すると、彼は大きな手で私の頭にぽんと手を置いた。
「最初は嫌われてたのに、ずいぶん懐いたなぁ」
一度こぼれた涙は止めることができない。カナメは気づいているのだろうか。前に神社で泣いたときとは違う。子どもの泣き方じゃない。これは恋をする女の涙だってことに。
「……カナメのばかぁ。せっかく好きになれたのに」
静かに流れる涙に、カナメが苦笑していた。
「ふぅちゃん、俺、またここに来ていい?」
「絶対来て」
そう言う私の言葉は従姉妹のものではないんだよ。
今のはね、本当は従姉妹の『好き』じゃないんだよ。
「いつかと逆だねぇ」
カナメの手が私の髪を撫でた。
「神社のときは『帰ろう』って言ったけど、今日は『またね』だね」
ねぇ、カナメ。私がまたねって言葉の先に求めているもの、わかる?
髪に伝わる手の感触にぐっと唇を噛んだ。私はね、こんな風にあなたの目の前で泣いたとき、髪を撫でるより抱きしめて欲しいんだよ。従姉妹としてではなく、一人の女として見て欲しいんだよ。
でも、しゃくりあげながら両手で口を覆った。言えないというより、言っちゃいけない気がした。
すっと手が離れる。名残惜しさに声が漏れそうになる。
「……またね」
涙でぐしゃぐしゃの顔で何度も頷いた。眩しい秋晴れの日差しに輝くミニクーパーがエンジン音を響かせ、すうっと動き出す。小さくなる後姿が角を曲がってもその場から動くことができなかった。立ち尽くし、そして流れる涙をそのままに唇をきつく噛む。
『あさはん』の湯気みたいな人だった。
優しくあったかく心を満たして、笑顔にしてくれて、呆気なく消えてしまった。
思えばこのひと夏の間、私を笑わせるのも泣かすのも、全部『あさはん』と彼だったよ。
ずっと目で追っていたい。声を聞いていたい。すぐ隣で気配を感じていたいんだ。けれど、時々息ができなくなる。恋ってそういうものなんだろうか。そこにいるのがどんなに幸せなことかわからない。そのくせ目を合わせると苦しくなるなんて変なものだ。
「もう稲穂がずいぶん頭を垂れてきたねぇ」
ある日、キャットフードを買出しに行った車の中でカナメがのんびり言う。
「ふぅちゃん、帰りにいいとこ連れて行ってあげるね」
「どこ?」
期待に胸を膨らませる私に、彼はふっと笑う。
「さぁ、どこでしょう?」
あ、私、この笑い方好きだ。思わずにやにやしそうになって慌てて窓の方に顔を逸らした。
カナメの運転は流れるようにスムーズで、ブレーキも滑らか。あんまり丁寧に運転するから、大事にされているように感じて嬉しくなる。
カナメが連れて行ってくれたのは彼岸花の名所だった。林の合間に絨毯を敷き詰めたように緋色が広がっている。
「紅しょうがをぶちまけたみたいね」
「ふぅちゃん、もうちょっと情緒あるたとえないの?」
「そうだなぁ」
彼岸花の合間を縫うように整備された歩道に立ち尽くし、辺りを見回す。大地から湧き上がるような無数の緋色の炎。
「……怖い」
ぴくりとカナメの眉が上がる。
「どうして?」
「綺麗すぎるし、それに恨みとか妬みとかそういうものがこみ上げてるみたいに見える」
そう、あの子の目の中に見えた激昂を思い出す。
胸が狭くなった途端、カナメがすっと手を握ってくれた。ちょっと驚いたけれど、無性に安堵する。
「……そうかぁ。やっぱり従姉妹だなぁ」
「え?」
「俺も初めてばあちゃんに連れてこられたときは同じように見えたんだよ」
カナメがそのままゆっくりと私の手を引いて歩きだした。彼岸花を見渡しながら、彼はゆっくりと口を開く。
「今は単純に綺麗だと思うけど、あの頃は怖かった。ちょうど、ふぅちゃんと同じくらいの歳だったな」
彼が自分から過去の話をするのが珍しくて、それになんとなく嬉しくて、私はただただ黙って耳を傾けていた。
「ふぅちゃん、覚えてるかなぁ? 俺って中学のとき事故で死にかけたんだよね。母親と車に乗ってて、衝突してさ」
「そうだった?」
まったく記憶にない。目を丸くすると、彼は「うん」と背中を見せたまま頷いた。
「ふぅちゃん小学生だったしね。多分、叔母さんもあえて言わなかったのかな。幸いこうして元気になったけど、三日くらい意識なくて」
まるで世間話でもしているような、淡々とした声。
「そのとき、うちの母親が変な宗教に走ってさ。リハビリも時間かかったし、責任感じて辛かったんだろうけど。俺の父親って堅物だろ? 俺が元気になった頃にはお袋と離婚の話がまとまってた。せっかく生きて戻ってきたのに、すべてが壊れた。不器用な親父は俺と話すこともなく、そのうち俺は家に帰らなくなって」
カナメの声は静かだった。
「そんな俺を見かねたばあちゃんが、高校はこっちで過ごせって言ってくれたんだ。どこに行っても同じだと思ってた俺はここに来てもしばらくは黙ったまま、誰にも懐かなかった」
思わず「それって……」と呟くと、カナメがちょっと振り向いて口の端を吊り上げる。
「似てるでしょ、ふぅちゃんに」
カナメが私に向けた同情の目の理由が初めてちゃんとわかった。彼は多分、私の中に過去の自分を見たんだ。
「俺ねぇ、ばあちゃんに毎日を大切に暮らしなさいって言葉なしに教わったんだよ。丁寧にご飯を作って、きちんと味わって、気がつけば流れてる季節を追って、そうしているうちに今ここにいることに感謝できるって。そうなれるようになるまで一年はかかったけど」
いつか私はカナメに問いかけた。あさはんを『なんでいらないってのに用意するの?』と。その答えを今、口にしている。
思わず握った手に力をこめた。カナメは初めて自分の傷跡を晒そうとしてくれているんだ。他でもない私に。
どぎまぎするような、どことなくいたたまれないような気分で、木漏れ日を背負った後姿を見つめた。
「俺はここで人として大事なことを見つけたつもりで、東京に戻った。けど、大学での毎日も結局何か物足りなくて。叔母さんに夏休みをここで過ごさないかって提案されたとき、これだって思った」
「俺はここに確認しに来たんだ。もう一度、ここで何か見つけられるんじゃないかって思った。そしたら、昔の俺にそっくりな子がいたんだ」
ふふっと笑みをこぼし、彼は歩みを止めて私を見つめた。
「ねぇ、ふぅちゃん。季節が流れるように人の出逢いも戻せない。一度手離したらもう戻らないんだよね。不思議だね」
唇の隙間から、私のかすれ声が漏れる。
「カナメはここで何を見つけたの?」
「内緒だよ。でも、何をしなきゃいけないかはわかった気がする」
嗚呼。カナメの目は遠くを見ていた。私の手の届かないところを。なんとなく、彼が何を言いたいのかわかってしまった。
彼はもう東京へ帰るのだ。行ってしまう。夏が終わる。あさはんのある二人の夏が。
「どうして私に話すの?」
「なんだかね、知っておいて欲しかったんだよ。ここに置いていくべきものだからかもね」
……嫌だ。ふるっと涙があふれ出る。
「やっぱり、みんないなくなる」
ぐすっと鼻をすする。
「みんなって?」
静かに問い返すカナメに、私はぽつりぽつりと話し出した。
「中学のときね、好きな先輩がいたの。沼田先輩っていって、同じ部活で仲良くて。でも、親友も同じ人が好きで、二人で追っかけしてた」
前橋えりこ。自分を『明るいストーカー』と笑い飛ばしていた私の親友だった子だ。沼田先輩のことが大好きで雪山にうもれながら小一時間も彼の通う塾を覗き見したり、毎日同じ電車の車両に乗るために駅を駆け抜けたり。好きだってことを隠そうとしない、素直な性格。
最初は彼に興味もなかったけれど、えりこにつきあっているうちに次第に私まで惹かれていった。
けれど、言えなかった。堂々と「彼が大好き」と目を輝かせるえりこに「実は私も好き」だなんて。自分の気持ちに気づくまでは応援していたのは本当なの。でも、好きだと気づいてしまったら、言いようのない罪悪感に潰されそうで。苦しかった。
だけど、それが変わったのは先輩の卒業式の日。
床に伏せて泣くえりこを自分も泣きたい気分で慰め、私は、とぼとぼと家路についていた。
そこに、沼田先輩の親友に出くわした。彼は堂々と追っかけてくるえりことその傍にいる私を覚えてくれていたんだ。
「ご卒業おめでとうございます」
そう言った私に、彼は「ありがとう」とはにかんだが、すぐに眉をひそめた。
「そういえば君といつも一緒にいる沼田のファン、告白したの?」
「いえ、タイミングつかめなかったみたいですけど」
おずおずと答えると、彼は「そうか」とぼりぼり頭をかいた。
「良かったと思うよ。言っちゃ悪いけど、沼田って女いっぱいいるし」
「え?」
愕然とした。けれど、もっと私の息を止めたのは次の言葉だった。
「あのファンのこともさ『簡単にヤレそうな女』ってキープしてたし、君のことも……」
「私?」
彼は咄嗟に『口がすべった』という顔をしたが、ふっとため息をもらした。
「うん。教えたほうがいいなってずっと思ってたんだよね。君も沼田のこと好きでしょ? あいつそういうの鼻が利くんだけどさ、『ああいう女はちょっと優しくしたらすぐ抱ける』って得意になってて」
目の前が真っ暗になった気がした。確かに沼田先輩の本音なんてわからない。だって私もえりこも遠くから見つめたり、偶然を装って話しかけたりするだけだもの。それこそ、えりこが言うように『ストーカー』状態。まして、気持ちを隠してこっそり彼を思っていた私はまさしくだ。
ショックのあまり呆然とする私に、彼が歩み寄る。
「俺、沼田より君を大事にするけど?」
「へ?」
「ずっといいなって思ってたんだ。俺ら、付き合わない?」
手首をつかまれ、彼の顔が近づく。私は短く叫んでその場を走り出していた。
沼田先輩を悪く言って、私に取り込もうとしたの?
それとも本当に? 本当に先輩がそんなことを?
信じられない。どうしたらいいのかもわからない。
一番信じられなかったのは、その後。えりこからの一通のメール。そこには『沼田先輩に告白したら付き合うことになりました』って一文があった。足元から何かが崩れる音が聞こえた気がしたよ。
その後がさらに最悪だった。沼田先輩の友人はふられた腹いせにか、えりこに私も沼田先輩を好きだということをばらしてしまったんだ。
「私を陰で笑ってたってわけ? なんで言ってくれなかったの? 沼田先輩と付き合えたことも祝ってはくれないのね」
なんでもはっきりさせる性格の彼女が私につっかかってきた。
「あのねえりこ……」
言いたくない。本当は言いたくない。けれど、言わなくちゃ。傷つくのはえりこだ。
私は懸命に説明した。けれど、えりこは私を信じなかった。当たり前だよね。誰だってやっと付き合えた彼氏を信じるよね。
「なによそれ、何を根拠に言ってるの? 私が先輩と付き合うことになったから妬いてるんじゃないの?」
「ちが……」
「もういい、顔も見たくない。見損なったよ。フウカって最低。そんな人だと思わなかった。先輩を侮辱しないで!」
それで、結局私たちはそのままになった。あのとき彼女の瞳に宿った軽蔑の目を、私は忘れられない。
怒りと嫌悪感がまるで彼岸花のように咲いていたっけ。
話し終えたとき、私の涙は頬の上でひからびていた。ただただ虚しくて。この彼岸花が自分への戒めにしか見えなくて。
けれどそのとき、カナメがぎゅっと繋いだ手に力をこめてくれた。
「辛かったね」
その言葉はすとんと音をたて、私の中に落ちた気がした。
「……うん」
「その子が傷ついてないといいね」
「うん」
えりことの溝は埋まらないかもしれない。けれど、それでも私は彼女が笑っていてくれたらと願うんだ。
本当はわかってほしい。私ね、先輩をまっすぐ追いかける彼女が羨ましかった。好きだった。多分、先輩を好きになったのも、そんな彼女が好いた人だから惹かれたんだと思うの。
言葉にできたとき、私の中で何かが形を変えた気がした。そう、この足を絡めとっていたものがするりと抜け落ちたような。
それって左手で握り締めたトンボ玉と、右手のぬくもりのおかげなんだと知っている。私は『大丈夫』だから。私を無条件で大切に思ってくれる人がいるのを知った。だから、大丈夫。
帰りの車の中、カナメが呟く。
「ミドリさんをよろしくね」
彼女はここで生まれ育った子だから、ここに戻らなきゃね。彼は小さくそう言った。
「カナメがいなくて寂しがるよ」
ミドリさんも私も。すると、彼は「いいや」と笑う。
「猫は家につくんだよ」
「カナメはどこに戻るの?」
「俺は戻るために帰るんだよ」
そう力強く言う横顔を、じっと見つめた。彼の視線はもう遠くを見据えている。
ふと、私は自分の中に咲く彼岸花一輪に気がついて問いかけた。
「カナメ、あの女の人に連絡したの?」
「うん?」
「ほら、温泉で話してた同級生」
「うん、新婚ほやほやでのろけ話を一時間もされたよ」
そのとき、私の彼岸花が萎れるのを感じて、「そっか」と思わず笑う。
カナメは帰る。いつもそこにいるのが当たり前だった姿が、声が、匂いがなくなる。
そしてもう少しで母が帰ってくるだろう。今度は母と二人の暮らし。ゆっくりでいい。二人の形を築いていこう。カナメが前を見ているなら、私も同じ方を見ていたい。
えりこから手紙が届いたのは、それから数日後のことだった。私は嬉し泣きをし、カナメはずっと「よかったね」といつものようにぽんぽんと髪を撫でてくれたっけ。
風がどことなくひんやりした日曜日の朝。
「あさはん、できたよ」
カナメの声がする。いつものように二人で向かい合って座り、手を合わせて「いただきます」とかみ締めるように囁いた。
「ふぅちゃん、お醤油とって」
「うん」
納豆をかき混ぜる音。
「それじゃあね」
荷を積み終わったミニクーパーの前でカナメが振り返る。足を引きずるように歩み寄る私は、涙をこらえるので精一杯だ。
「また来るよ」
ふっとカナメが笑う。もうすっかり見慣れた眼鏡の奥で、いつものように目を穏やかに細めて。
「本当に?」
溢れる涙は既に視界をぼんやりさせている。カナメが滲んで見えなくなる。一瞬でも長く目に焼き付けたいのに。思わずこぼれた涙。
すると、彼は大きな手で私の頭にぽんと手を置いた。
「最初は嫌われてたのに、ずいぶん懐いたなぁ」
一度こぼれた涙は止めることができない。カナメは気づいているのだろうか。前に神社で泣いたときとは違う。子どもの泣き方じゃない。これは恋をする女の涙だってことに。
「……カナメのばかぁ。せっかく好きになれたのに」
静かに流れる涙に、カナメが苦笑していた。
「ふぅちゃん、俺、またここに来ていい?」
「絶対来て」
そう言う私の言葉は従姉妹のものではないんだよ。
今のはね、本当は従姉妹の『好き』じゃないんだよ。
「いつかと逆だねぇ」
カナメの手が私の髪を撫でた。
「神社のときは『帰ろう』って言ったけど、今日は『またね』だね」
ねぇ、カナメ。私がまたねって言葉の先に求めているもの、わかる?
髪に伝わる手の感触にぐっと唇を噛んだ。私はね、こんな風にあなたの目の前で泣いたとき、髪を撫でるより抱きしめて欲しいんだよ。従姉妹としてではなく、一人の女として見て欲しいんだよ。
でも、しゃくりあげながら両手で口を覆った。言えないというより、言っちゃいけない気がした。
すっと手が離れる。名残惜しさに声が漏れそうになる。
「……またね」
涙でぐしゃぐしゃの顔で何度も頷いた。眩しい秋晴れの日差しに輝くミニクーパーがエンジン音を響かせ、すうっと動き出す。小さくなる後姿が角を曲がってもその場から動くことができなかった。立ち尽くし、そして流れる涙をそのままに唇をきつく噛む。
『あさはん』の湯気みたいな人だった。
優しくあったかく心を満たして、笑顔にしてくれて、呆気なく消えてしまった。
思えばこのひと夏の間、私を笑わせるのも泣かすのも、全部『あさはん』と彼だったよ。
0
お気に入りに追加
0
あなたにおすすめの小説


児童絵本館のオオカミ
火隆丸
児童書・童話
閉鎖した児童絵本館に放置されたオオカミの着ぐるみが語る、数々の思い出。ボロボロの着ぐるみの中には、たくさんの人の想いが詰まっています。着ぐるみと人との間に生まれた、切なくも美しい物語です。

フツーさがしの旅
雨ノ川からもも
児童書・童話
フツーじゃない白猫と、頼れるアニキ猫の成長物語
「お前、フツーじゃないんだよ」
兄弟たちにそうからかわれ、家族のもとを飛び出した子猫は、森の中で、先輩ノラ猫「ドライト」と出会う。
ドライトに名前をもらい、一緒に生活するようになったふたり。
狩りの練習に、町へのお出かけ、そして、新しい出会い。
二匹のノラ猫を中心に描かれる、成長物語。

イケメン男子とドキドキ同居!? ~ぽっちゃりさんの学園リデビュー計画~
友野紅子
児童書・童話
ぽっちゃりヒロインがイケメン男子と同居しながらダイエットして綺麗になって、学園リデビューと恋、さらには将来の夢までゲットする成長の物語。
全編通し、基本的にドタバタのラブコメディ。時々、シリアス。

RICE WORK
フィッシュナツミ
経済・企業
近未来の日本、長時間労働と低賃金に苦しむ社会で、国民全員に月額11万円を支給するベーシックインカムが導入され、誰もが「生活のために働かなくても良い」自由を手にしたかに見えました。希望に満ちた時代が到来する中、人々は仕事から解放され、家族との時間や自分の夢に専念できるようになります。しかし、時が経つにつれ、社会には次第に違和感が漂い始めます。
『RICE WORK』は、経済的安定と引き換えに失われた「働くことの意味」や「人間としての尊厳」を問いかける物語。理想と現実の狭間で揺れる人々の姿を通して、私たちに社会の未来を考えさせるディストピア小説です。
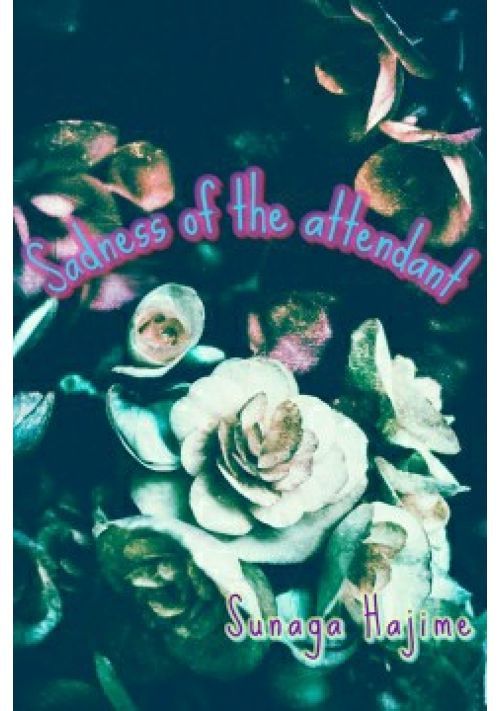
Sadness of the attendant
砂詠 飛来
児童書・童話
王子がまだ生熟れであるように、姫もまだまだ小娘でありました。
醜いカエルの姿に変えられてしまった王子を嘆く従者ハインリヒ。彼の強い憎しみの先に居たのは、王子を救ってくれた姫だった。

月神山の不気味な洋館
ひろみ透夏
児童書・童話
初めての夜は不気味な洋館で?!
満月の夜、級友サトミの家の裏庭上空でおこる怪現象を見せられたケンヂは、正体を確かめようと登った木の上で奇妙な物体と遭遇。足を踏み外し落下してしまう……。
話は昼間にさかのぼる。
両親が泊まりがけの旅行へ出かけた日、ケンヂは友人から『旅行中の両親が深夜に帰ってきて、あの世に連れて行く』という怪談を聞かされる。
その日の放課後、ふだん男子と会話などしない、おとなしい性格の級友サトミから、とつぜん話があると呼び出されたケンヂ。その話とは『今夜、私のうちに泊りにきて』という、とんでもない要求だった。

佐藤さんの四重奏
makoto(木城まこと)
児童書・童話
佐藤千里は小学5年生の女の子。昔から好きになるものは大抵男子が好きになるもので、女子らしくないといじめられたことを機に、本当の自分をさらけ出せなくなってしまう。そんな中、男子と偽って出会った佐藤陽がとなりのクラスに転校してきて、千里の本当の性別がバレてしまい――?
弦楽器を通じて自分らしさを見つける、小学生たちの物語。
第2回きずな児童書大賞で奨励賞をいただきました。ありがとうございます!
ユーザ登録のメリット
- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!
- お気に入り登録で最新話を見逃さない!
- しおり機能で小説の続きが読みやすい!
1~3分で完了!
無料でユーザ登録する
すでにユーザの方はログイン
閉じる




















